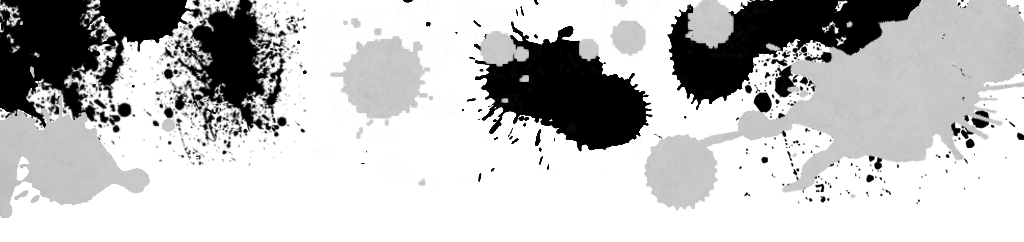マルとバツ
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
海賊の争いに巻き込まれた私は眼に怪我をし、そのせいで視力が落ちた。
まったく見えないという訳ではないけど、今まで見えてた景色がぼやけて見えるようになった。
リーン……。
鈴の音を響かせながら歩く一人の女性。
その音に慣れた街の人達は、特に気にする事もなく通り過ぎる。
「おはようございます!」
女性の仕事場なのだろう。
酒場へと入れば、元気良くあいさつした。
「おはよう!リラちゃん、今日も鈴を付けてるのかい?」
酒場の女将に、チョーカーに付いてる鈴の事を聞かれれば笑顔で返事をした。
「鈴の反響音で、障害物とか分かりやすいですから」
リラと呼ばれた女性は、見え辛くなった眼を頼りにするのではなく、耳を頼りにするようになったら、音の反響音で状況が分かるようになった。
元々、鈴付きのチョーカーは眼に怪我をする前からのお気に入りで、両親からのプレゼントだった。
そっと鈴に触れる。
「バツさんにお礼が言いたいな……」
リラの呟きをたまたま聞いてた女将は、不思議そうな顔をした。
「バツさん?初めて聞く名前だね」
女将の言葉に慌てて訂正した。
「違うの!名前が分からないからバツさんって呼んでるだけで、名前じゃないの!」
「誰なんだい、そのバツさんとやらは」
リラは少し目線を下げると、助けてくれた人……と、頬を染めながら答えた。
あれは二年前。
見え辛い眼に慣れてなくて、とにかく一人でも歩けるようにと練習してた時の事……。
リラは近くの森を、散歩するように歩いていた。
相変わらず、鈴の音を響かせて……。
この時はまだ音を利用する事が出来なくて、眼を凝らしていた。
早く見え辛いのに慣れないと、仕事も満足に出来ない……と、意気込んでいたせいもあって気が付かなかった。
鈴の音に引き寄せられ、近づいてくる不穏な気配に……。
「お嬢さん!」
声をかけられた事で、ようやく誰かいる事に気が付いたリラ。
眼を凝らしても、人の影しか見えない事に不安を感じた。
「……何か?」
「いけないねぇ、こんな所に一人でいるなんて。送ってあげるよ?」
耳障りな笑いをする男に、眉間に皺を寄せた。
「結構です。一人で帰れますので!」
直ぐに、その場から離れようと反対を向けば、肩を掴まれた。
「離して!」
「人の親切を何だと思ってる!!」
抵抗するも、男の力には敵わないし、何より見えない事に恐怖すら感じた。
男はどんどん人気のない……更に森の奥へとリラを引きずる。
見え辛いリラも、何処に連れて行かれようとしてるのか、男の雰囲気で分かる。
このままでは……っと、あらん限りの声で、助けを呼ぶ。
それに焦った男はリラの頬を叩き、大人しくしろと怒鳴った。
当たりどころが良かったのか、叩かれた衝撃で意識が朦朧としてきた事に、諦めるしかないのかと思った時だった。
「そこの男、何をしてる」
別のところからする男の声に、リラはどうするべきかと、朦朧とする意識で考えていた。
「なんだぁ?こっちは取り込み中だ!」
男はリラを担ぎ上げ、森の奥へと行こうとして遮られた。
「邪魔すんな!この女はオレによろしくされたいらしくてなぁ!!」
冗談じゃないと、声に出して否定したいのに、朦朧とする意識の中では首を振る事も出来ない。
悔しくて眼に涙を浮かべた。
「……お前のような男に言っても仕方なかったな」
瞬間的に身体が浮遊感を感じたと思った時には、殴る音と男のうめき声が聞こえた。
そして、自分が誰かに抱きかかえられてる事に気が付く。
「や……離して」
力なく抵抗すれば、男は慌てた。
「待て。お前を連れ去ろうとした男とは違う。落ち着け」
優しく声をかけてきた男に、リラは抵抗を止めた。
「意識が定まってないだろ。木陰で休もう」
リラを気遣うように抱え直した男は、ゆっくりとした足取りで木陰に移動した。
男はリラを抱きかかえたまま木に寄りかかり、自分の膝の上に座らせた。
寄りかかった男の胸の逞しさに思わず俯いたリラだったが、助けてもらったお礼を言ってないと思い顔を上げた。
その時、リラの眼にはバツ印が微かに見えた事に、バツ……と心で呟いた。
「……バツ?」
筈だったが、どうやら微かに声に出していたらしく、聞き返されてしまった。
直ぐに視線を外したが、男はリラの視線が自分の顎の傷にあったのを見逃さなかった。
「あぁ……この傷か」
「……ごめん……なさい」
「気にしてない」
微かに、フッと笑う声に安心感すら覚えるリラ。
……安心したら、意識が遠くなってきた……。
意識がなくなる前にお礼は言わないと……リラは既に眼を閉じた状態で、言葉を放つ。
ありがとう……バツさん……助けて……くれて……。
聞こえたのか、最後に聞こえた男の言葉に微笑みを浮かべ、意識を放棄した。
「……これがバツさんとの出会いです」
次に眼を覚ました時は、病院の上だった。
自分を連れてきた人の事を医者に聞いても、名乗らずに去ったと言われた。
「青春だねぇ」
「はい?」
「私ももう少し若ければ、そんな運命的な出会いを望めたのに」
女将の言葉に、顔を真っ赤にするリラ。
「そういえば、そのバツさんとやらは、最後なんて言ってたんだい?」
それを聞いたリラは、顔を手で覆った。
『お前は特徴的な丸い鈴を付けてるな……。オレがバツならお前はマルだな』
思い出したリラは鈴に触れて、自然と頬が緩んだ。
それを見た女将はからかいながら、教えろと言っては、くすぐってきたのだった。
バツさんとの大事な思い出だから内緒と言えば、更にからかわれてしまった。
「若いって良いわねぇ!」
「でも、あの一回きりだけの出会いでしたし、私もこんな眼だから……顔も分からなくて。声も……あの状況だから覚えてなくて……」
言って落ち込むリラに、女将は屈託ない笑顔で言い放った。
「それだけ運命的な出会いをしたんだ!また会えるさ!!」
運命的かどうかリラには分からないが、また会えると良いなと思うのであった。
顔も名前も知らない人に、恋い焦がれるなんて、人はバカみたいと言うかもしれない。
でも、芽生えてしまった気持ちを消す事など出来ないでいた。
日も暮れて、酒場も賑わってきた。
リラも忙しそうに動き回る。
そして、その度に鈴の音を響かせる。
慣れた常連だと、聞こえる鈴の音に笑みを浮かべる程だ。
「相変わらず、綺麗な音だね」
常連のおじいさんに話しかけられれば、リラは嬉しそうに返事をする。
「特注で作ってもらった鈴らしいです」
幼い頃に、よく迷子になる私を見つけやすいようにと、両親からプレゼントされたもの。
心地良い音でしょと聞けば、穏やかな顔で頷いてくれたのだった。
鈴の音を聞く度に、バツさんの事を思い出して頬が緩んでしまう。
いやいや……今は仕事中。
切り変えなきゃ……。
仕事に戻れば、今度は別の人から話しかけられた。
「ねぇ、仕事が落ち着いたらオレと飲もうよ!良いっしょ、女将!」
リラにではなく、女将に許可を取る……。
此処では、女将の許可なしではリラにお酌さえしてもらえないと、ちょっとした話題となり、お遊び感覚になってしまった。
「駄目よ!リラちゃんは恋する乙女なんだから!今後は、その質問すら受け付けないわよ!」
女将の言葉に、店にいた男達は嘆きの声を上げた。
リラは持っていたトレーを食器諸共落としそうになった。
「ちょっと女将さん!何を言うの!!」
「そんな真っ赤な顔で何を言っても、説得力ないわよ!」
照れるリラを見て、可愛いぞ!とか、いったい誰だ!?などと色んな声が飛び交った。
そんな和やかな雰囲気をぶち壊す声が飛んできた。
「顔に傷のある女なんぞ、誰も相手にしねぇよ!鏡で顔を見てから、恋なんて言葉を口にすんだな!」
声を放った男とその周りにいる男達が、けたたましく笑い声を上げた。
男達はたまたま立ち寄った海賊らしく、女将や常連の者達は文句を言いたかったが、反抗出来なかった。
リラは泣きそうになるのを耐えて、トレーを厨房へと運ぼうとすれば腕を引っ張られ、持っていたトレーは食器と共に床に落ちて、綺麗な音を立てて割れた。
「このネェちゃん、良く見れば可愛い顔してんじゃん」
厭らしい顔をしながら近寄る男。
別の男もリラに近寄れば、顔をまじまじと見る。
「確かに!傷があっても、それも味のある魅力だ!」
海賊達が、逃げようとするリラの逃げ道を塞ぎながら囲んでいった。
リラ自身も絶体絶命という言葉が頭に浮かんだ。
逃げ道はない。
女将さんも常連さんも、みんな海賊が怖いのは当たり前。
助けは望めない。
また、あの時のように諦めるか……そう考えが頭を掠めた時、リィンと鈴の音でハッとした。
掴まれてる手を払えば海賊達は逆上し、リラを押し倒した。
「もう泣いても許してやらねぇ」
此処でマワしてやる!と一人が覆い被さり、それぞれ手足を別の海賊達に抑え込まれてしまった。
何人もの男達に抑え込まれてしまえば、抵抗出来る訳もなく、どうしようもなかった。
上着を破かれ、更にキャミソールに男の手が掛かった時、何処からか声がした。
「そこの海賊共。何をしてる」
デジャブ……。
リラはあの時と似たような感覚に、眼から涙が溢れ……零れた。
「なんだぁ!?……てめぇも海賊じゃねぇか!だったら分かんだろ!どっか別の酒場を探すんだな」
海賊達はそう言い放つと、またリラの方を向いた。
「さて……邪魔が入ったが続きをしようか、ネェちゃんよぉ」
その言葉に首を振るしか出来なかった。
「泣いても止めないと言わなかったか?」
そう言いながら、男が最後の服に手をかけ破いた瞬間、男達の叫び声が響いた。
抑えられていた手が解放されれば、誰かに抱きかかえられた。
この感触に覚えのあるリラは涙腺が緩んだ。
「おい!!こいつ、あの赤旗のドレークじゃないか!?」
一人が叫べば、一斉にその場を去った海賊達。
訳の分からないリラは、茫然とするしかなかった。
フッと、自分を抱きかかえてる人の顔を見れば、あるものが眼に入った。
ぼやけた視界でも忘れる訳がない。
また会いたいと願っていた人……。
「バツ……さん?」
「また鈴の音に引き寄せられたよ、マル」
「マルって……覚えてくれてたんですか?もう二年も前の話しなのに……」
「お前こそ、あの意識の中でよくオレがマルと言ったのを覚えていたな」
リラは涙を止める方法など分かる筈もなく、抱き付いて大泣きしてしまった。
その場にいた女将や常連は、リラが助かった事に安堵しつつ、助けに入った男が誰なのかと思案顔になった。
その時、女将だけはピンときた。
今日、話に聞いたばかりのバツさんだという事に気が付いた。
そうと分かれば、女将の行動は早かった。
「……ドレークさんと言ったね?ウチの従業員を助けてくれて、本当にありがとう」
女将が何度も頭を下げる事に、ドレークと呼ばれた男は、構わないと微笑んだ。
「……バツさん、ドレークさんって言うの?」
「あぁ。そういえば、あの時はお互いに名乗ってなかったな」
苦笑いをするドレークに、リラは顔を上げようとすれば、背中を強く押さえつけられた。
いや……強く抱きしめられたという言い方が正しいだろうか。
「あの……バツさん?」
「……少し待て」
動揺を隠せないリラは気が付かなかった。
ドレークの耳が真っ赤に染まっている事を……。
状況が分かってると言わんばかりの女将は、リラを二階に連れて行ってくれないかとドレークに申し出た。
それを聞き入れたドレークは、足早にその場を後にし、酒場の二階へと進んだ。
二階の空き部屋に行けば、リラを下ろさず抱きかかえたまま、ドレークが口を開いた。
「すまなかった」
謝られた意味がよく分からないリラは聞き返した。
すると、ドレークは顔を真っ赤にさせながら、服……と答えた。
「あのまま上半身を上げれば、あの場にいる者達に見えてしまうと思ってな……」
手で自分の服を確認すれば破れてる。
ドレークの服は前がはだけてるのか……肌の感触がする?
服の感触がしない事に、思わず上半身をドレークから離し、胸に手を置いた。
「な、何をしてるんだ!?」
ドレークからすれば、リラの柔らかい胸の感触が分かる程に密着し(これは状況的に仕方ない)しかも、眼の前で揺れるモノを見てしまえば、もうノックアウト寸前。
挙句、どう言った理由で、自分の胸に手を置いてるのか……最終的にフリーズした。
そして、リラはようやく事の状況に気が付けば、今更に顔を真っ赤にさせた。
結果……二人して固まった。
直ぐに、気を持ち直したリラは下ろしてもらうよう言えば、ドレークは何も言わずリラを下ろした。
そして、羽織ってるマントをリラに掛けた。
「……二度も助けて頂きました。本当に何と言って良いか……ありがとうございます」
リラは頭を下げた。
ドレークは頭を上げさせると、徐にリラのチョーカーに付いてる鈴に触れた。
「あの時も、そして今回も……この鈴の音に引き寄せられた」
「……鈴の音に?」
「綺麗な音だ」
リラは嬉しくて仕方なかった。
この鈴は幸運を運んでくれた。
ドレークと出会わせてくれただけでなく、再び会わせてくれた。
両手で顔を覆えば、止まった筈の涙がまた溢れてきた。
少し動揺する気配がしたが、何も言わず泣きやむのを待ってくれた。
ドレークの優しさに甘えて、今はとことん泣こう……。
ようやく気持ちが落ち着いてきた頃、リラは顔を上げた。
「名乗るのが遅れてごめんなさい。私はリラと申します」
「リラか……オレはドレークだ。X・ドレーク」
「フフ……何か変な感じですね」
「何がだ?」
「今までバツさんと呼んでいたので……」
すると、ドレークもフッと笑みを零した。
「それなら、オレも同じだな」
「マル……ですか?」
返事の代わりに、苦笑いで返されてしまった。
そんなドレークに、リラは嬉しくなった。
「なら、マルと呼んで下さい!特別ですよ!」
少しからかうように言えば、ドレークもからかうように、オレもバツで良いと返してきた。
クスクスと笑う二人。
「そういえば、バツさんは海賊だったんですね」
「今はな」
今はという言葉に、不思議そうにすれば、初めて会った時は海軍にいたと説明された。
「あの時は、たまたま休暇中でな。私服を着てたし、分からなかったと思うが」
その言葉に、リラは苦笑いしか出なかった。
「私……殆ど眼が見えてないので……どっちにしろ分からなかったと思います」
刹那、息を呑む気配がした。
驚かせてしまっただろうか……心配になったが、顔を上げる事が出来なかった。
何も言わないドレークに、ポツリポツリと経緯を話した。
話し終えて、暫くは沈黙がその場を支配した。
どうすれば良いのか分からないリラは、手に力が入るのを感じた。
すると、不意にドレークが何かを話そうとする気配を感じて、少しだけ顔を上げた。
「……そんな風には見えなかった」
「……え?」
「海賊が怖くないのか?そんな目に合って……」
その問いに首を振った。
失ったものがあれば、得たものもあると答えれば、強い女だと返ってきた。
「……いつまでも、そんな格好させてる訳にもいかないな」
そう言って部屋を出ようとするドレーク。
リラは慌てて引き止めれば、言葉を遮るように、マルと呼ばれた。
「また、鈴の音が聞こえたら……会おう」
バタンと音を立て、ドアが閉まった。
残されたリラは悲しそうな顔をして、暫くその場から動けなかった。
結局その日は女将の言葉もあり、それ以上店に出る事なく帰路に着いた。
翌朝……。
朝早くに起きて、借りたマントを洗った。
そして、助けてくれたお礼に、何か贈り物をしたいと考えたリラは仕事前に、色々と店を回ってみる事にした。
リーン……。
リィン。
まだ店も開いたばかりで、人もちらほらとしかいない街中で、鈴の音が鮮明に響く。
リィーン……。
「リラちゃん、昨日の今日だし……休みかしら?」
酒場では、未だに来ないリラを心配する女将の声は、誰の耳にも届く事なく消えた。
暗い……。
冷たい場所……。
痛い……。
リラは、だんだんと覚醒する意識の中、周りが暗い事に気が付いた。
窓辺を見ても暗い……暗い!?
確かに、朝早くに街にいた筈なのに、いつの間にか夜になってる!?
動こうとすれば、自分が床に横たわってる事……縛られてる事にも気が付いた。
ようやく、冷たいと感じる理由……そして、痛いと感じた理由が分かった。
(……此処は何処?)
周りを把握しようにも、この眼では把握出来ない。
必死に耳を澄ませようにも、風の音で聞き取れない。
縛られてる状態では、起き上がるのも一苦労だと感じれば、横たわったまま身体の力を抜いた。
「いらっしゃい!!」
店に女将の声が響いた。
客を迎え入れようと振り返り、誰か分かれば笑みが零れた。
「あんたは昨日の……バツさん!」
「……ドレークだ」
「その呼び方はリラちゃん限定かしら?」
クスクス笑う女将に、バツの悪そうな顔をした。
「リラちゃん目当てかしら?」
「……いるか?」
すると困ったように、女将が溜め息を吐いた。
「まだ……来てないのよね」
「休みなのか?」
「違うけど……昨日の今日だし、塞ぎ込んでなきゃ良いけど……」
その時、女将を呼ぶ客の声に、その場を離れていってしまった。
「ドレーク船長!」
呼び声と共に店に入って来たクルー達。
一人のクルーがドレークに何かを渡してきた。
「これ、昨日の子が身に付けていたものじゃないですか!?」
見れば、鈴付きのチョーカーだった。
この特徴的な鈴……間違いない。
「これを何処で?」
「海辺の方です」
海辺……何故、そんなところに。
嫌な予感がしたドレークは、直ぐに船へ戻ろうと身を翻す。
その道中、道を阻む影が現れた。
「よう、赤旗」
現れたのは、昨日の海賊達だった。
視線を鋭くしたドレークに、海賊達は不敵な笑みを浮かべた。
「良いのか?オレ達に手を出せば、大事なものを失う事になるぞ」
その言葉で、リラが脳裏に浮かんだ。
店に来なかったのではなく、来れなかったんだとすれば……行き着いた考えに、ドレークは殺気を放った。
「……何処にいる?」
海賊達は慌てる事なく、武器に手をかけた。
「お前の首を取れば、オレ達の名が上がる。お前はただ黙って、オレ達に殺られれば良い」
抵抗すれば、女の命はない。
その言葉を合図に、両者の武器がぶつかり合った。
「バツさん……助けて……」
「口ほどにもない」
武器をしまいながら、地に伏してる海賊達を冷たい眼で見た。
「てめぇ……女を無事……返す……と……」
最後まで言葉を紡げず、意識がなくなった。
「……居場所の見当などついてる」
残りの海賊達をクルー達に任せ、ドレークは一人その場を去った。
どれぐらい経ったのか。
相変わらず人の気配はしないし、自力で抜け出そうにも紐を固く結ばれているのか解けない。
このまま誰にも気付かれず、訳の分からないまま死ぬのか……絶望を感じた時、初めて人の気配がした。
(……誰?)
こちらに足音が近付いてる。
リラは何とか上体を起こして、ドアの方を凝視する。
すると足音はドアの前で止まった。
緊張からか息が詰まりそうになるのを耐え、身体を強張らせる。
ドアが開き、誰かが入ってきたのは分かったが、こうも暗くては誰だか判別出来なかった。
声を出そうにも、恐怖のせいなのか出なかった。
「……お前も運のない女だ」
覚えのない声だった。
「だが、ドレークの女なら覚悟は出来てんだろ」
「……ドレーク……さん?」
振り絞って出た言葉は、自分で分かる程に震えていた。
「今頃、オレ達海賊団が潰し終えてる頃だな」
つまりは、自分が人質になったと理解した。
足手まといになってしまった。
悔しくて涙が出た。
「泣いてるのか。そりゃあ、そうだろうな」
男の笑いに虫唾が走った。
「オレが慰めてやる」
男は持っていたナイフで素早く服を斬り裂いた。
リラが抵抗出来ないよう、ナイフを向けた状態で肌に触れてきた。
気持ち悪い……。
そう思っても、縛られた上にナイフを向けられてては抗う事が出来なかった。
お腹辺りを触られていたと思えば、だんだん上へとくる。
胸の突起を指で弾かれ、声が出そうになる。
そんな微かな反応を示した事に男の機嫌が良くなったのか、首元に顔を近付けてくればチクリとした痛みが走った。
これ以上は我慢の限界だ!
怪我しようが構わない!
リラは抵抗しようとした時、けたたましい音と共にドアが破壊された。
「マル!?此処にいるか!?」
聞いた事がない程、焦ったドレークの声が聞こえた。
助けに来てくれた……?
「バツさん!!」
ドレークは眼の前の状況に息を呑んだ。
リラの服は剥ぎ取られ、あられもない姿になっている事に怒りが抑えられなかった。
男はリラの上体を起こし、首元にナイフを当てた。
「女をこれ以上、傷モンにしたかねぇだろ?」
ドレークの気迫に圧されながらも抵抗を見せる。
リラは、何とか隙を作れば、後はドレークが絶対助けてくれると信じ、浅く呼吸した。
気持ちを落ち着かせ、男に頭突きを食らわせた。
瞬間、怯んだ男を見逃す筈のないドレークは、リラを抱き上げ、男に蹴りを食らわせた。
腹に入った蹴りの威力で、男は壁に叩き付けられ、そのまま床に倒れ動かなくなった。
やっぱり助けてくれた。
何の確証もないのに、確信があった。
「……何て無茶をしたんだ」
ドレークの言葉に、何の事だとポカンとした。
そんなリラの顔を見たドレークは、溜め息を吐いた。
「あの状態で、頭突きをする女なんて初めて見た」
「…………」
「相手は刃物を持ってたんだぞ。一つ間違えば、自分から刺されにいったようなもんだ」
「……返す言葉もございません……」
「とにかく無事で……」
言いかけて止めたドレークに、今度は何だと首を傾げた。
リラを抱き上げたまま、スタスタと少し歩けば、ぅぐっと声が聞こえた事に、気を失った男を蹴っ飛ばした事が窺えた。
無抵抗な相手に攻撃するような人には見えないのに……何で、と困惑した。
周りは暗いし、元々眼も見え辛いリラは、ドレークの眼が何処を見たのか分からなかった。
……酒場の時よりも派手に服が引き裂かれ、挙句の果てには首元にある赤い印。
これを見たドレークは、蹴り飛ばすだけでは気が治まらなかったが、今はリラを優先と考え、その場にあったシーツをリラに巻き付ければ、その場を後にした。
「海の音……此処は船だったんですね」
部屋を出た後、聞こえてきた音にリラは口を開いた。
ようやく、自分があの海賊達の船に監禁されてたと分かった。
「……あの船を沈めておけ」
「え?」
「分かりました」
バタバタと何人もの足音が聞こえる。
「あの……今の人達は?」
「オレのクルー達だ」
なるほど……と思いながら、ある事に気が付いた。
「あの……バツさん!」
「話は後だ」
「……え?」
抱きかかえられたままのリラは、ドレークの足が何処に向かってるのか分からないままだった。
「此処は?」
「オレの船だ」
今、凄い事を聞いた気がするぞ?
私の聞き間違い?
オレの船と言った?
何で、船に連れてこられた?
疑問に思うも、ドレークの足は止まらない。
とりあえず、されるがままのリラ。
そして、行き着いた場所はお風呂だった。
「バツさん?」
「身体が汚れている。洗い流せ」
確かに、監禁されてた場所は掃除をしてなかったのか埃だらけだった。
「服なら用意する。何も気にせず入れ」
その言葉に甘えて、お風呂に入る事にした。
この状態で家に戻っても両親にはビックリさせちゃうし、お風呂が借りられて良かったと安心した。
ただ、気掛かりなのは鈴……。
気が付いた時にはなかった。
もしかしたら、あの海賊船の何処かに……。
そう思ったら居ても立ってもいられないリラは、直ぐに身体の汚れを落とし、お風呂から出た。
用意されてたタオルで拭いて、これまた用意してくれた服に手を掛けて気が付いた。
ワンピース?
この船に、女物の服がある事に驚いた。
(もしかしてバツさんの……)
申し訳ない気持ちもあったけど、このままの姿でいる訳にもいかず、袖を通した。
脱衣所から出れば、入口に誰か人の影があった。
誰だろうと思っていれば、その人物に声をかけられた。
「随分と早かったな」
聞こえた声が、ドレークのものであった事に安心した。
「えぇ、気になる事がありまして……。お風呂ありがとうございました」
頭を下げてお礼を言い、服のお礼も言うのだった。
「それで……この服を貸して下さった方にも、お礼を言いたいのですが……」
「いや。この服はマルの為に用意したもので、誰のものでもない」
「……私の?」
聞けば、昨日の事で服を駄目にしてしまったのを見て、今日たまたまリラに似合いそうだと思った服を見かけて購入したとか……。
それを聞いたリラは、顔を真っ赤にする事しか出来なかった。
私の為にわざわざ……バツさんの彼女のではなかったと、安心と嬉しい気持ちが溢れた。
「……此処へ来る時と、今気になってる事とは、これの事だろ?」
リィン……と音を鳴らし、リラの手に渡した。
「鈴……気付いたら、無くなってたのに……何処にあったんですか?」
「あいつらの船の近くに落ちてたのを、クルーが見つけてな」
それで、リラの監禁場所も分かったのだと教えてくれた。
「やっぱり、この鈴は幸運を運んでくれる、特別な鈴です」
「そうだな。これを見つけてなきゃ、分からなかったかもな」
「それだけじゃないです」
リラは、ぼんやりと影しか見えないドレークを見て、微笑んだ。
「私とバツさんを、引き合わせてくれました」
初めて会った時。
二回目に再会した昨日。
そして、今回……鈴のお陰で助けられた。
愛おしそうに鈴を握りしめ、ドレークにそう言えば、チョーカーを貸してほしいと言われ、素直に渡した。
勇気を出して言った言葉に、何も言わないドレークに、薄っすら涙を浮かべそうになった。
すると、眼の前に影が出来たと思えば、首に慣れた感触が触れた。
どうやら、チョーカーを着けてくれたらしい。
「……初めて会った時。再会した時……この鈴の音に導かれるように音を辿った。そこにマルがいた」
突然、語り出したドレークに、黙って耳を傾けた。
「マルを見た時、この鈴のようだと……二年前のあの日から、忘れられなくなった」
「それって……」
「危険からは絶対に守る。だから、オレと一緒に来ないか?」
嬉しくて、声が出なかった。
着いて行きたいと、必死に頷いて答えた。
フッと笑うドレークに、離れたくないと言わんばかり抱き付けば、抱き締め返された。
眼が見えなくても良いと言ってくれた。
その分、鈴の音が二人を繋いでくれる。
リィーン……。
今日も海では、鈴の音が響き渡る。
「マル」
「バツさん」
あとがき
此処まで読んでいただき、ありがとうございます。
今回はドレークを書いてみました。
若干、薄っぺらい微裏的な場面もありましたが……何処からが微裏になるのでしょうか?
難しいです。
毎度の事ながら、読みづらい文を読んで頂いてる皆様には感謝です!
そして、ぜひとも別の作品も読んで頂けると嬉しいです!
皆様に素敵な夢が訪れますように☆