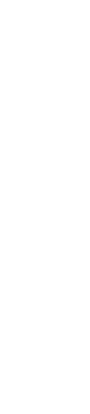✩.*˚哀とコナンと……②✩.*˚
私は、工藤君に手を引かれ…お兄さんの家に来た。チャイムを鳴らすと、蘭さんが出迎えてくれた。
「あら、いらっしゃい…哀ちゃんも、久しぶりね」
「ご無沙汰しています」
「上がって待ってて~」
そう頭を下げると私達はリビングに通された。
「ごめんね~新一まだ仕事で…帰ってきてないのよ~座って待っててくれる?」
「うん」
「はい」
四人座りのテーブルに、キッチンが見える側に私達は腰掛けた。待ってる間、蘭さんは夕食の支度を続けながら私に声を掛けてきた。
「所で哀ちゃん、留学は順調!?」
「ええ、何とかやってます。この調子なら来年の卒業式終えたら帰って来れそうです。」
その私の言葉に、蘭さんよりも早く工藤君は反応していた。
「本当か!?灰原っ!」
目を輝かせて聞いてくる工藤君の顔がとてつもなく面白くて、喜んでくれる工藤君が凄く嬉しかった。
「ええ、今の所順調だから安心して」
そう話す私の顔を満面の笑みで見てくる。そんな彼に教えてあげると、"よかった"と言って安心するかの様に微笑んでいた。
そんな私達を見ながら蘭さんも笑顔を向けてくれる。
しばらくして、玄関を開ける音と共に"ただいまー"と言ってお兄さんが帰ってきた。
「あ、兄ちゃん!」
「お邪魔してます」
「おかえりなさい」
「おう、お前ら来てたのか」
そう言って、私達の方を見ると笑顔を向けてくれた。特に私がいる事で隣にいる工藤君が嬉しそうな面持ちで座っているのを見て安心している様子にも見えた。
お兄さんは席に着くなり不思議になりながら聞いてくる。
「所でお前ら、今日はどうしたんだ?二人揃って来て…久しぶりに二人会えたんだ、明日でもよかったんだぜ?」
そんなお兄さんは蘭さんから何も聞いてないらしく、今日私達が来た事に不思議に思い聞いてくる。
「私が呼んだの…ちょっと、大事な話があって。」
「大事な話!?」
そう言って話す蘭さんは嬉しそうにしていた。食事の用意が出来上がり…席に着く蘭さん。"それじゃ、頂きましょう"という蘭さんの声を合図に手を合わせて食べ始めた。
「食事しながらでも聞いて欲しいの。私ね、今日病院行ったら、出来たみたいなの…」
その言葉に私と工藤くんは目をぱちぱちすると顔を見合わせあーっと言って微笑む。その一方でお兄さんは蘭さんの作った食事を口に放り込みながら聞いてきた。
「何が?」
「…もうっ!」
そう言って、何の事か分かってないお兄さんに不満になる蘭さん。
「まったく…お兄さんだけね、分かってないの…」
「え!?」
「赤ちゃん…だよね?」
分かってないお兄さんに教えてあげるように…工藤君がぽつりと言う。その言葉にお兄さんは驚いてゴホゴホと食べていた物を詰まらせていた。
「ほ、ほんとか!?」
「ええ、2ヶ月だって…」
蘭さんの肩を掴みながらまじまじと蘭さんの顔を見るお兄さん。その視線はだんだんと蘭さんのお腹へと移っていった。
「よかったなあ~」
「ほんと」
そんな微笑ましい2人を目にして、私と工藤君も嬉しくなっていた。
「でも、二人目って感じよね?」
「あ、ああ…そうだな」
そうクスッと笑いながら工藤君の方に目線を移す二人に、私も納得する部分があった。
「なんで?」
二人の言葉に今度は工藤君が不思議になっていた。隣にいた私は呆れるように工藤君に言う。
「もうっ!あなたは産まれた頃から面倒見てもらったんじゃない…」
そう教えると"そっか"と言って、頭をかいていた。
「でも、お兄さんに任せない方がいいわよ、蘭さん…また甘ったれに育っちゃうと思いますから」
そう話す私の意見に賛同し横目でちらっとお兄さんを見ながら"そうね~"と納得する蘭さんに何も言えなくなったお兄さんは絶句していた。
その一方で、工藤君はクスッと笑っていたから私は肩を小突いて文句を言う。
「もう、あなたの事言ってるんだからね…」
「え…うん」
「でも、いいのよコナン君は…可愛かったから。」
「そうだな、お前は産まれたばかりのころとにかくちっちゃかったからな…未熟児で産まれたせいもあってな、よく風邪ひいてたし…すげー心配していたんだよ。まあ、手が掛かってたけどな…」
「僕、そんなに手が掛かってたの?」
「まあな」
「うん」
ひとしきりお兄さんが説明し終わった後、工藤君はぽつりと聞くとお兄さんや蘭さんは二人同時に答えていた。
「なんだよ、二人して…」
「手がかかるのは今もじゃない…」
「灰原まで…」
そんな反応に不貞腐れながら文句を言う工藤君に私は今も手がかかってる事にフッと笑って言うと、工藤君は口を尖らせながら黙々と食事をしていた。
そんな私達を見て、お兄さんは静かに口を開いて工藤君に諭す様に話しかけた。
「でもな、コナン…いいんだよ、それが子供の性(さが)さ。お前が大人になって、あの頃を思うと懐かしくなって思い出に浸るくらい、手がかかっても可愛かったんだよ、お前は…」
「そうね~コナン君が私に懐いちゃって、新一が私に嫉妬するくらいにねー」
「してねーだろーが…」
「本当に~?」
そう言って笑い出す私達の中には、とても小さくて心配で堪らない気持ちで作り上げた有希子さんの思いがあのアルバムに記されていた事、改めて思い出す。滅多に見せてくれなくなった工藤君だけど、いつかまたこっそりと見たいと密かに思っていた。
「でも、よくわかったわね、コナン君…赤ちゃんの事」
「だって、灰原を向かいに行く前に置いてあったから…母子手帳……」
「ああ…置きっぱなしにしてたんだった……」
そう言うと、まだ何も書かれてない貰ってきたばかりの母子手帳を手に取ると、嬉しそうにめくっていた。
「これから、色々書かなきゃな…」
「そうね、新一のお母さんのようにたくさんね…」
そう言う蘭さんに工藤君はあっと言って思い出した様に言う。
「あのさ、蘭ねーちゃん…風邪引いた日まで書かなくてもいいと、思うよ…」
そう言った工藤君に私達は笑い出す。きっとあの記録が恥ずかしかったんだろうとそれを聞いて隣で照れてる工藤君に私は微笑みを掛けていた。
「まあ、あの母子手帳とアルバムは、俺達にとって大切な宝物だ。あの家で育って成長してきた証なんだぜ?ちょっと、母さんのコレクターは変わってるけどな…お前が未熟児で産まれた時はどうなるか分からなかったけど、そんなお前がこんなにでっかくなった事は、母さんや父さんだって嬉しい事なんだよ、だから将来お前に子供が出来たら見せてやれよ、お前の有志をな!」
そう言ってニッと笑うお兄さんの言葉に、工藤君は赤くなって慌てていた。
「な、な、何言ってるんだよ、兄ちゃん」
お兄さんはイタズラな笑顔でそんな慌てる弟を笑ってみてるのを見て、私はわざとやってる様に思えてならなかった。
「あんまり弟を虐めないでくれる?お兄さん…」
「ああ、わり…」
そう言うお兄さんだけど、悪いなんて思ってないくせにと思いながら…私は、蘭さんのお腹に宿る赤ちゃんを見て、私もいつか……なんて、そんな事を思うと、少しばかり照れくさくなって、慌ててコーヒーを飲みながら顔を隠していた。
日本に一時帰国して、私はお兄さんと蘭さんの家で子供の頃の工藤君の思い出に浸り、とても暖かいものを感じた。一年ぶりに会う私達の傍らでとても幸せそうな二人を見て、私はもっと嬉しくなった。
いつか、お兄さんや蘭さんみたいに幸せな家族を持ちたいと私は思っている。私が産まれた時、物心ついた頃には家族はみんな亡くなっていたから…幼少時代はそんな寂しい思いしか家族に対してはなかった私だから…。
そんな二人から子供の頃の工藤君の話を話続けられ、恥ずかしくて堪らない工藤君は照れながら言う。
「もういいよ、僕の話は…」
「いいえ、もっと聞かせてください」
そう言う私の言葉に工藤君はまた頬を赤らめていた。一年経ってもこういう所は変わらない工藤君に、私は…私達は、とても穏やかな気持ちになっていた。
いつまで経ってもお兄さんの事が大好きな工藤君に、私は少し心配になるけど…きっと工藤君自身も少しづつ、私達の知らない所で…未来へ踏み出そうとしてる事、何となくだけど感じていた。
「あら、いらっしゃい…哀ちゃんも、久しぶりね」
「ご無沙汰しています」
「上がって待ってて~」
そう頭を下げると私達はリビングに通された。
「ごめんね~新一まだ仕事で…帰ってきてないのよ~座って待っててくれる?」
「うん」
「はい」
四人座りのテーブルに、キッチンが見える側に私達は腰掛けた。待ってる間、蘭さんは夕食の支度を続けながら私に声を掛けてきた。
「所で哀ちゃん、留学は順調!?」
「ええ、何とかやってます。この調子なら来年の卒業式終えたら帰って来れそうです。」
その私の言葉に、蘭さんよりも早く工藤君は反応していた。
「本当か!?灰原っ!」
目を輝かせて聞いてくる工藤君の顔がとてつもなく面白くて、喜んでくれる工藤君が凄く嬉しかった。
「ええ、今の所順調だから安心して」
そう話す私の顔を満面の笑みで見てくる。そんな彼に教えてあげると、"よかった"と言って安心するかの様に微笑んでいた。
そんな私達を見ながら蘭さんも笑顔を向けてくれる。
しばらくして、玄関を開ける音と共に"ただいまー"と言ってお兄さんが帰ってきた。
「あ、兄ちゃん!」
「お邪魔してます」
「おかえりなさい」
「おう、お前ら来てたのか」
そう言って、私達の方を見ると笑顔を向けてくれた。特に私がいる事で隣にいる工藤君が嬉しそうな面持ちで座っているのを見て安心している様子にも見えた。
お兄さんは席に着くなり不思議になりながら聞いてくる。
「所でお前ら、今日はどうしたんだ?二人揃って来て…久しぶりに二人会えたんだ、明日でもよかったんだぜ?」
そんなお兄さんは蘭さんから何も聞いてないらしく、今日私達が来た事に不思議に思い聞いてくる。
「私が呼んだの…ちょっと、大事な話があって。」
「大事な話!?」
そう言って話す蘭さんは嬉しそうにしていた。食事の用意が出来上がり…席に着く蘭さん。"それじゃ、頂きましょう"という蘭さんの声を合図に手を合わせて食べ始めた。
「食事しながらでも聞いて欲しいの。私ね、今日病院行ったら、出来たみたいなの…」
その言葉に私と工藤くんは目をぱちぱちすると顔を見合わせあーっと言って微笑む。その一方でお兄さんは蘭さんの作った食事を口に放り込みながら聞いてきた。
「何が?」
「…もうっ!」
そう言って、何の事か分かってないお兄さんに不満になる蘭さん。
「まったく…お兄さんだけね、分かってないの…」
「え!?」
「赤ちゃん…だよね?」
分かってないお兄さんに教えてあげるように…工藤君がぽつりと言う。その言葉にお兄さんは驚いてゴホゴホと食べていた物を詰まらせていた。
「ほ、ほんとか!?」
「ええ、2ヶ月だって…」
蘭さんの肩を掴みながらまじまじと蘭さんの顔を見るお兄さん。その視線はだんだんと蘭さんのお腹へと移っていった。
「よかったなあ~」
「ほんと」
そんな微笑ましい2人を目にして、私と工藤君も嬉しくなっていた。
「でも、二人目って感じよね?」
「あ、ああ…そうだな」
そうクスッと笑いながら工藤君の方に目線を移す二人に、私も納得する部分があった。
「なんで?」
二人の言葉に今度は工藤君が不思議になっていた。隣にいた私は呆れるように工藤君に言う。
「もうっ!あなたは産まれた頃から面倒見てもらったんじゃない…」
そう教えると"そっか"と言って、頭をかいていた。
「でも、お兄さんに任せない方がいいわよ、蘭さん…また甘ったれに育っちゃうと思いますから」
そう話す私の意見に賛同し横目でちらっとお兄さんを見ながら"そうね~"と納得する蘭さんに何も言えなくなったお兄さんは絶句していた。
その一方で、工藤君はクスッと笑っていたから私は肩を小突いて文句を言う。
「もう、あなたの事言ってるんだからね…」
「え…うん」
「でも、いいのよコナン君は…可愛かったから。」
「そうだな、お前は産まれたばかりのころとにかくちっちゃかったからな…未熟児で産まれたせいもあってな、よく風邪ひいてたし…すげー心配していたんだよ。まあ、手が掛かってたけどな…」
「僕、そんなに手が掛かってたの?」
「まあな」
「うん」
ひとしきりお兄さんが説明し終わった後、工藤君はぽつりと聞くとお兄さんや蘭さんは二人同時に答えていた。
「なんだよ、二人して…」
「手がかかるのは今もじゃない…」
「灰原まで…」
そんな反応に不貞腐れながら文句を言う工藤君に私は今も手がかかってる事にフッと笑って言うと、工藤君は口を尖らせながら黙々と食事をしていた。
そんな私達を見て、お兄さんは静かに口を開いて工藤君に諭す様に話しかけた。
「でもな、コナン…いいんだよ、それが子供の性(さが)さ。お前が大人になって、あの頃を思うと懐かしくなって思い出に浸るくらい、手がかかっても可愛かったんだよ、お前は…」
「そうね~コナン君が私に懐いちゃって、新一が私に嫉妬するくらいにねー」
「してねーだろーが…」
「本当に~?」
そう言って笑い出す私達の中には、とても小さくて心配で堪らない気持ちで作り上げた有希子さんの思いがあのアルバムに記されていた事、改めて思い出す。滅多に見せてくれなくなった工藤君だけど、いつかまたこっそりと見たいと密かに思っていた。
「でも、よくわかったわね、コナン君…赤ちゃんの事」
「だって、灰原を向かいに行く前に置いてあったから…母子手帳……」
「ああ…置きっぱなしにしてたんだった……」
そう言うと、まだ何も書かれてない貰ってきたばかりの母子手帳を手に取ると、嬉しそうにめくっていた。
「これから、色々書かなきゃな…」
「そうね、新一のお母さんのようにたくさんね…」
そう言う蘭さんに工藤君はあっと言って思い出した様に言う。
「あのさ、蘭ねーちゃん…風邪引いた日まで書かなくてもいいと、思うよ…」
そう言った工藤君に私達は笑い出す。きっとあの記録が恥ずかしかったんだろうとそれを聞いて隣で照れてる工藤君に私は微笑みを掛けていた。
「まあ、あの母子手帳とアルバムは、俺達にとって大切な宝物だ。あの家で育って成長してきた証なんだぜ?ちょっと、母さんのコレクターは変わってるけどな…お前が未熟児で産まれた時はどうなるか分からなかったけど、そんなお前がこんなにでっかくなった事は、母さんや父さんだって嬉しい事なんだよ、だから将来お前に子供が出来たら見せてやれよ、お前の有志をな!」
そう言ってニッと笑うお兄さんの言葉に、工藤君は赤くなって慌てていた。
「な、な、何言ってるんだよ、兄ちゃん」
お兄さんはイタズラな笑顔でそんな慌てる弟を笑ってみてるのを見て、私はわざとやってる様に思えてならなかった。
「あんまり弟を虐めないでくれる?お兄さん…」
「ああ、わり…」
そう言うお兄さんだけど、悪いなんて思ってないくせにと思いながら…私は、蘭さんのお腹に宿る赤ちゃんを見て、私もいつか……なんて、そんな事を思うと、少しばかり照れくさくなって、慌ててコーヒーを飲みながら顔を隠していた。
日本に一時帰国して、私はお兄さんと蘭さんの家で子供の頃の工藤君の思い出に浸り、とても暖かいものを感じた。一年ぶりに会う私達の傍らでとても幸せそうな二人を見て、私はもっと嬉しくなった。
いつか、お兄さんや蘭さんみたいに幸せな家族を持ちたいと私は思っている。私が産まれた時、物心ついた頃には家族はみんな亡くなっていたから…幼少時代はそんな寂しい思いしか家族に対してはなかった私だから…。
そんな二人から子供の頃の工藤君の話を話続けられ、恥ずかしくて堪らない工藤君は照れながら言う。
「もういいよ、僕の話は…」
「いいえ、もっと聞かせてください」
そう言う私の言葉に工藤君はまた頬を赤らめていた。一年経ってもこういう所は変わらない工藤君に、私は…私達は、とても穏やかな気持ちになっていた。
いつまで経ってもお兄さんの事が大好きな工藤君に、私は少し心配になるけど…きっと工藤君自身も少しづつ、私達の知らない所で…未来へ踏み出そうとしてる事、何となくだけど感じていた。