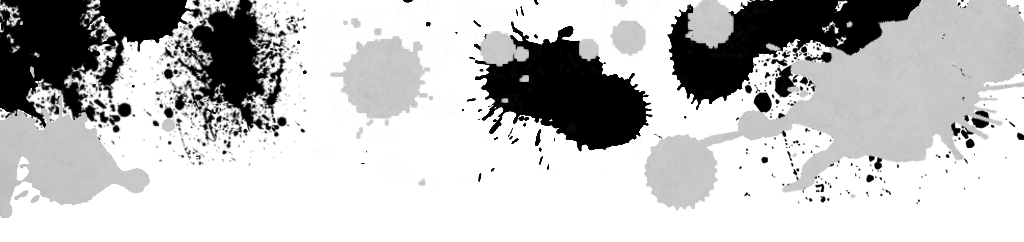帰路
祖父に連れられてやってきた、世界の終わりのような光の中にあった場所。そこは今では大勢の人が生活していた関東の都市部とは思えないくらい何も無かった。祖父がなにやら黙り込んで居座っている場所に至る道には、再興という言葉さえも考えられないようなコンクリートの塊やこんなものまで吹き飛んだのかと疑うほどの大きな鉄骨が転がっていた。
かつては陸だった、と祖父が連れてきた場所を見て普段動じることの無い少年も、僅かだが目を見張った。凪いだ風が揺らす穏やかな水面しか視界に入ってこなかったからだ。かつてコンクリートで覆われ無数のビルが建っていたと言われた場所はもう遠くに水平線が望めるほど、見晴らしが良くなっていた。
陸だった、という祖父の言葉が俄には信じがたく、少年は水中に潜り水底を確かめてみた。夏休みに近所の子らと訪れた川や、家族と訪れた遙か遠い記憶の海の水底ともまるで違っていた。
―――なるほど。
少年が普段過ごしている風景とは明らかに異質な風景を納得する形で受け入れたのも、この世の風景とは思えないあの光の柱を目撃したからだろうか。
肺の空気を全て出し切って、少年は水底の異世界から陽の当たる陸地に上がった。
纏わり付いた異世界の空気を払うように、身体中の水滴を振るい落とした。湿った塩の味がする自分の唇を舐めながら、祖父の座っている場所を見上げると、自分と同い年くらいの頭に乗せている麦わら帽だけが風景の中で浮いていた。
帰り道。行きの道より何故だかはっきりと周りの様子が見えた。そしてここで何ら変わらない日常を送っていた人々が存在した、という証拠だと主張するように無数の家具や日用品が目につく。ふと、目を向けた先に瓦礫の中に埋もれた写真のようなものを見つけた。どこかから流されてきたのだろう。塩水と泥でぐちゃぐちゃになったその写真は誰が映っているのかも分からない。だがなんとなく家族写真の様に目の端では見て取れた。行きと同じように祖父の二歩後ろをついて行きながら、
「こいつの世界は終わったんかな」
と、2日後に11歳の誕生日を迎える少年は感慨も無く、そう思った。
かつては陸だった、と祖父が連れてきた場所を見て普段動じることの無い少年も、僅かだが目を見張った。凪いだ風が揺らす穏やかな水面しか視界に入ってこなかったからだ。かつてコンクリートで覆われ無数のビルが建っていたと言われた場所はもう遠くに水平線が望めるほど、見晴らしが良くなっていた。
陸だった、という祖父の言葉が俄には信じがたく、少年は水中に潜り水底を確かめてみた。夏休みに近所の子らと訪れた川や、家族と訪れた遙か遠い記憶の海の水底ともまるで違っていた。
―――なるほど。
少年が普段過ごしている風景とは明らかに異質な風景を納得する形で受け入れたのも、この世の風景とは思えないあの光の柱を目撃したからだろうか。
肺の空気を全て出し切って、少年は水底の異世界から陽の当たる陸地に上がった。
纏わり付いた異世界の空気を払うように、身体中の水滴を振るい落とした。湿った塩の味がする自分の唇を舐めながら、祖父の座っている場所を見上げると、自分と同い年くらいの頭に乗せている麦わら帽だけが風景の中で浮いていた。
帰り道。行きの道より何故だかはっきりと周りの様子が見えた。そしてここで何ら変わらない日常を送っていた人々が存在した、という証拠だと主張するように無数の家具や日用品が目につく。ふと、目を向けた先に瓦礫の中に埋もれた写真のようなものを見つけた。どこかから流されてきたのだろう。塩水と泥でぐちゃぐちゃになったその写真は誰が映っているのかも分からない。だがなんとなく家族写真の様に目の端では見て取れた。行きと同じように祖父の二歩後ろをついて行きながら、
「こいつの世界は終わったんかな」
と、2日後に11歳の誕生日を迎える少年は感慨も無く、そう思った。
1/1ページ