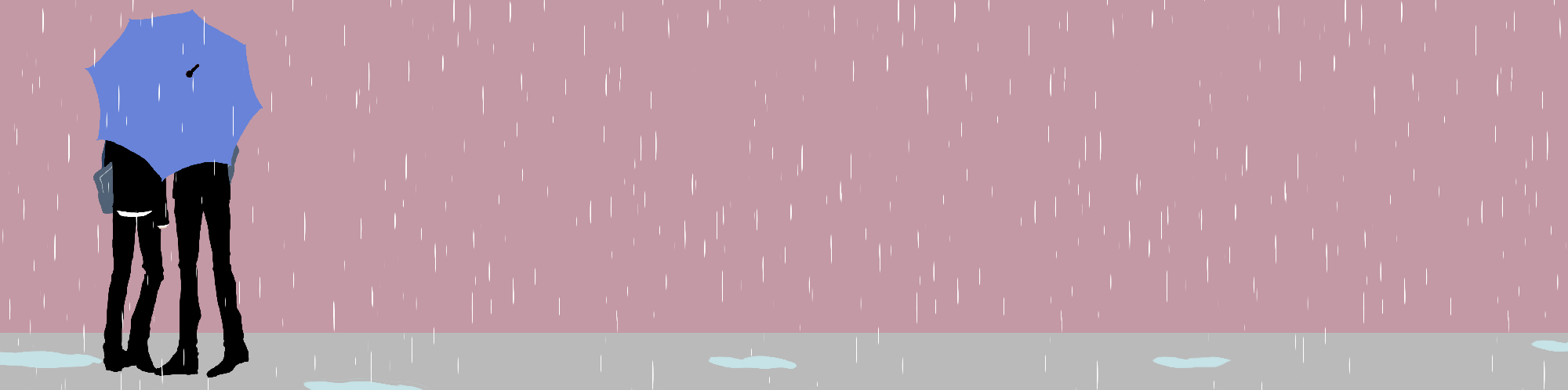ヒバ山
真夏のとある日
パタパタパタ。
廊下から足音が近づいてくる。
…走るなって言ってるのに…。
うとうとと夢の世界をまどろんでいた僕は、現実の世界へと引き戻されていく。
世間は夏休み。
暑い日が続き、日頃の疲れもたまっていたのか今日は体がずしりと重い。僕は仕事を一段落させ応接室のソファーで横になる事にした。
それからどれ程経ったのか。
もうあの子が来る時間だなんて、よほど深く眠ってしまったらしい。
コンコンとノックが聞こえたかと思えば、「ヒバリいる~?」と声とともにドアがあく。
彼はいつも返事など待たずに入ってくる。
…いつかしつけよう。
そう思いながら僕は眉根を寄せた。
「あ……寝てんのか」
まだ目を開けずにいると、ポツリと声がした。
……そんなうるさくされてこの僕が起きない訳ないだろう、と、思う。
しかし、山本は静々と僕から離れた。
どこに行くのかと思えば、ゴオォと音をたて部屋の空気が流れ始める。
そういえば体にうっすら汗が滲んでいる。エアコンがいつの間にか切れていたようだ。空気が少しずつ快適になり、呼吸も軽くなる。
へぇ、気が利くね。
僕は大きく息を吸った。
仕方ないから起きようか。
そう思った時だった。
ふわり。
柔らかな布が額に軽く押し当てられる。
……?
心地よいそれは、額を数回撫でると、僕の首元に移動した。
…汗を拭いてるのか。
きちんと洗われ日の光を浴びたタオルは気持ちが良く。
部活のある日はタオルは二枚用意すると言っていた。それは今日使わなかった方なのだろう。なぜだか献身的に世話をする山本が、つい可愛く感じてしまい、しばらくされるがままにしてみる事にした。
放っておくと、何を思ったのか山本は僕のネクタイを緩め始めた。
……何してんの?
スルスルとネクタイは抜き取られ、山本はボタンへと手にかける。
そして再びタオルを首元に優しく押し当てた。
…あぁ。汗、ね。
あと5秒遅かったらうっかり殴ってしまうところだった。
「ネクタイとって寝た方が絶対楽なのに」
山本は小さく笑った。
…余計なお世話だよ。
山本の気配が遠ざかる。
がちゃりと隣の部屋に続くドアの音がして、再び気配が近づいた。ゴクゴクと何かを勢いよく飲む音がする。
冷蔵庫にあった牛乳は昨日空になったから、水でも飲んでいるのだろう。山本がこの部屋に通うようになり約3ヶ月。すっかり勝手知ったる応接室だ。気がつけば山本の好きな牛乳が常備されていたり、夏休みの宿題が本棚に置かれていたり。
まぁ別に、好きに使えばいいけど。
山本はプハーと息をはいた。水分補給して満足したらしい。そして退屈になったのか、ものすごく視線を感じる…。
この眠ったフリはいつまで続けよう。
なんとなく起きるタイミングを逃してしまった。
「ヒバリ」
不意に耳元で囁くような声。
続いてそっと耳たぶに指が添えられ、やんわりと動く。
「まだ起きねぇの?」
その言葉と共に、生暖かいものが降りた。
「……!?」
突然の出来事にピクリと体が揺れてしまった。
そのまま耳の裏や中を舌が這う。その濡れた感触がくすぐったくて、ぞくりとする。僕は息を飲んだ。
山本はそのまま唇を首筋へとうつす。先程開けられたボタンをさらにもう一つ外され、首元はがら空きだった。
何これ……。
思わず顔を背けたせいで余計首をあらわにしてしまった。
それを逃さず這う舌が、吐息が、唇が熱くて。
「……っ」
殺していた息が、漏れてしまった。
この子…何を…してるわけ………!!
バキッ!
乾いた音が部屋に響く。
僕は目を開けると、寝たまま力任せに山本を殴っていた。
「ってぇ…何だよヒバリ~」
山本は額をさすりながら僕を見上げる。
そんなに痛くないだろう。不覚にもうまく力が入らなかった。
そう思うと僕はムカついてしまい、ギロリと睨んだ。手をつき、体を起こす。
「君こそ何してるの。寝込みを襲うなんて悪趣味だね」
「…寝てなかったじゃん」
山本はぷぅっと唇を尖らせた。
僕は頬がヒクリとひきつる。
「……あぁそう。気付いてたんだ?」
「はは、途中から」
「それでこの行動?いい度胸してるじゃない」
「へへ、まーな」
「褒めてないんだけど」
あはは、と、山本は頬を緩ませ、ソファに腰掛けると僕の首に腕を回した。
「…何なの暑苦しい」
近づく山本に睨みをきかせる。
山本はいたずらっぽく目を輝かせた。
「ヒバリもさ、耳とか首、弱ぇのな」
「………は?」
「寝顔見てて、ヒバリはどこが弱いのかなあって考えてたら、ムラッとしちゃった」
「………」
「…ヒバリ?聞いてる?」
言葉も出ない。漫画なら、血管の一本や二本は額に浮き出ているんじゃないだろうか。
僕が弱い?よく言うよ。別に僕はそんなトコ弱くなんかない。ただ、いきなりでびっくりしただけだ。
「ヒバ…ぅんっ…!?」
おもむろに目の前の唇を奪う。後ろに逃げようと引く頭を押さえ、深く深く舐めあげれば、首に回されている山本の腕がだらりと重くなる。唇を啄み、ゆっくりと離れると、山本は耳まで真っ赤になっていた。
「は…ぁ…っ…いきなり何だよ」
弱々しく発せられる声に、僕の中で何かが弾けた。
「君が弱いトコ、教えてあげようか?」
にまりと目を細めると、何かを感じたのか山本は手をすすっと引き、目を泳がせた。
「あ、いや…大丈夫。間に合ってっから」
「遠慮しなくていいんだよ?」
「うわ!!」
逃がしはしない。僕は山本の上へと転がるように体を移した。
後ずさりしてソファからずり落ちた山本は、そのまま仰向けに倒れる。僕はその両腕を頭の上で床に縫い止めた。
「ちょっ、ヒバリ!怒ってんのか?」
「何で?怒られるような事した訳?」
「えっと……睡眠を邪魔したから」
「君が来た時はとっくに起きてたよ」
「あ、じゃあ弱いって言った事?」
「……!」
「え、違ったか?じゃあその…殴る力も奪っちゃうくらい、その……」
「……っ!」
「もが!」
それ以上言わせないようにと山本の口を手で塞ぐ。山本は目を丸くした。
僕は口角を吊り上げる。
さぁて、十分頭にきたわけだけど、どうしてくれようか。
気付けば、少し暴れたせいかそれとも冷や汗なのか、うっすら額が濡れている。
僕は顔を寄せ、それを舐めた。
「ん…!」
僕の手の下から、山本のくぐもった声が漏れる。
「さっきは僕の汗を拭いてくれたからね。お礼だよ」
「ちょ…ひあり…」
「何?聞こえない。あぁ、首も拭いてくれたっけ」
さすがにやりづらいので、腕を封じていた方の手を離し、口は塞いでいるその手で少し上を向かせる。
そうやって首筋に噛み付けば、山本の体はピクリと跳ね、鎖骨から顎下へと舌で濡らせば、塞いだ手に熱い息がかかった。
「……っ、待っ」
手は自由だというのに、山本は僕を引き離そうとはしない。シャツをひっぱるその力は弱々しくて、したくてもできないのだと訴えている。
「…僕の事弱いなんて言ったけど、君は弱い所が多過ぎだよね」
「ふは…!何だよやっぱその事?そんなに怒んなくてもいいだろ」
口から手を離せば、眉を下げて頬は真っ赤なくせして言葉だけは荒げてみせる。
拗ねた子供みたいだ。
「別に怒ってないよ」
「じゃあ何だよ」
「だから、僕より君の方が弱いって教えてあげてるだけ」
「だから何だよそれ」
「例えば…」
ちょっと脇腹をつつくだけで
「ぎゃ!」
ちょっと腰を撫でるだけで
「…っ」
ちょっと臍周りに触れるだけで
「ふは、くすぐった…」
そのまま、ちょっと胸に手を滑らすだけで、
「……っ!」
―――本当弱い。
「そんなんで、よく僕の事弱いなんて言えたよねぇ…」
「ん、あ、だっ…て」
「だって、何?」
呼吸を乱す山本に問い掛ける。答える時間をあげる間、僕は山本のシャツのボタンを外す事にした。山本はされるがままに、僕を見上げた。
「弱いっつーけど、ヒバリだから、だぜ?」
「?」
「ヒバリが触るから、あっちこっちくすぐってぇの」
「……」
「だから、オレが触ったら、ヒバリもくすぐってぇのかなって思っただけ」
「……」
さっきまであった怒りの熱は、瞬時に別な熱へと変わる。
ああ、成る程。
確かに、山本が相手じゃなかったらあんなにぞくりとはしない。
そもそも指一本触れさせる気は無いし、そんな事考える小動物がいたなら二度と立てないほど咬み殺してやるだろう。
でも相手が、山本だから。
「分かった。じゃあ、仕返しにたっぷり可愛いがってあげるよ」
「え…何で!?」
「君だから」
「は?どーゆー事?」
「もう黙れば」
「ぅむ…ン…!」
君だから、この部屋を自由に使っても許してあげる。
君だから、僕に触れても許してあげる。
君だから、
その可愛い声を、
聞きたいと思う。
「ヒバリ…今日ちょっと意地悪ぃ…」
熱く息を吐いた山本は、恥ずかしそうに瞳を麗せて僕を見た。僕は胸を高鳴らせ、ふっと笑った。
「君が相手だと、つい、ね」
そういう気持ちを僕に気付かせた、君のせいでしょ。
end
パタパタパタ。
廊下から足音が近づいてくる。
…走るなって言ってるのに…。
うとうとと夢の世界をまどろんでいた僕は、現実の世界へと引き戻されていく。
世間は夏休み。
暑い日が続き、日頃の疲れもたまっていたのか今日は体がずしりと重い。僕は仕事を一段落させ応接室のソファーで横になる事にした。
それからどれ程経ったのか。
もうあの子が来る時間だなんて、よほど深く眠ってしまったらしい。
コンコンとノックが聞こえたかと思えば、「ヒバリいる~?」と声とともにドアがあく。
彼はいつも返事など待たずに入ってくる。
…いつかしつけよう。
そう思いながら僕は眉根を寄せた。
「あ……寝てんのか」
まだ目を開けずにいると、ポツリと声がした。
……そんなうるさくされてこの僕が起きない訳ないだろう、と、思う。
しかし、山本は静々と僕から離れた。
どこに行くのかと思えば、ゴオォと音をたて部屋の空気が流れ始める。
そういえば体にうっすら汗が滲んでいる。エアコンがいつの間にか切れていたようだ。空気が少しずつ快適になり、呼吸も軽くなる。
へぇ、気が利くね。
僕は大きく息を吸った。
仕方ないから起きようか。
そう思った時だった。
ふわり。
柔らかな布が額に軽く押し当てられる。
……?
心地よいそれは、額を数回撫でると、僕の首元に移動した。
…汗を拭いてるのか。
きちんと洗われ日の光を浴びたタオルは気持ちが良く。
部活のある日はタオルは二枚用意すると言っていた。それは今日使わなかった方なのだろう。なぜだか献身的に世話をする山本が、つい可愛く感じてしまい、しばらくされるがままにしてみる事にした。
放っておくと、何を思ったのか山本は僕のネクタイを緩め始めた。
……何してんの?
スルスルとネクタイは抜き取られ、山本はボタンへと手にかける。
そして再びタオルを首元に優しく押し当てた。
…あぁ。汗、ね。
あと5秒遅かったらうっかり殴ってしまうところだった。
「ネクタイとって寝た方が絶対楽なのに」
山本は小さく笑った。
…余計なお世話だよ。
山本の気配が遠ざかる。
がちゃりと隣の部屋に続くドアの音がして、再び気配が近づいた。ゴクゴクと何かを勢いよく飲む音がする。
冷蔵庫にあった牛乳は昨日空になったから、水でも飲んでいるのだろう。山本がこの部屋に通うようになり約3ヶ月。すっかり勝手知ったる応接室だ。気がつけば山本の好きな牛乳が常備されていたり、夏休みの宿題が本棚に置かれていたり。
まぁ別に、好きに使えばいいけど。
山本はプハーと息をはいた。水分補給して満足したらしい。そして退屈になったのか、ものすごく視線を感じる…。
この眠ったフリはいつまで続けよう。
なんとなく起きるタイミングを逃してしまった。
「ヒバリ」
不意に耳元で囁くような声。
続いてそっと耳たぶに指が添えられ、やんわりと動く。
「まだ起きねぇの?」
その言葉と共に、生暖かいものが降りた。
「……!?」
突然の出来事にピクリと体が揺れてしまった。
そのまま耳の裏や中を舌が這う。その濡れた感触がくすぐったくて、ぞくりとする。僕は息を飲んだ。
山本はそのまま唇を首筋へとうつす。先程開けられたボタンをさらにもう一つ外され、首元はがら空きだった。
何これ……。
思わず顔を背けたせいで余計首をあらわにしてしまった。
それを逃さず這う舌が、吐息が、唇が熱くて。
「……っ」
殺していた息が、漏れてしまった。
この子…何を…してるわけ………!!
バキッ!
乾いた音が部屋に響く。
僕は目を開けると、寝たまま力任せに山本を殴っていた。
「ってぇ…何だよヒバリ~」
山本は額をさすりながら僕を見上げる。
そんなに痛くないだろう。不覚にもうまく力が入らなかった。
そう思うと僕はムカついてしまい、ギロリと睨んだ。手をつき、体を起こす。
「君こそ何してるの。寝込みを襲うなんて悪趣味だね」
「…寝てなかったじゃん」
山本はぷぅっと唇を尖らせた。
僕は頬がヒクリとひきつる。
「……あぁそう。気付いてたんだ?」
「はは、途中から」
「それでこの行動?いい度胸してるじゃない」
「へへ、まーな」
「褒めてないんだけど」
あはは、と、山本は頬を緩ませ、ソファに腰掛けると僕の首に腕を回した。
「…何なの暑苦しい」
近づく山本に睨みをきかせる。
山本はいたずらっぽく目を輝かせた。
「ヒバリもさ、耳とか首、弱ぇのな」
「………は?」
「寝顔見てて、ヒバリはどこが弱いのかなあって考えてたら、ムラッとしちゃった」
「………」
「…ヒバリ?聞いてる?」
言葉も出ない。漫画なら、血管の一本や二本は額に浮き出ているんじゃないだろうか。
僕が弱い?よく言うよ。別に僕はそんなトコ弱くなんかない。ただ、いきなりでびっくりしただけだ。
「ヒバ…ぅんっ…!?」
おもむろに目の前の唇を奪う。後ろに逃げようと引く頭を押さえ、深く深く舐めあげれば、首に回されている山本の腕がだらりと重くなる。唇を啄み、ゆっくりと離れると、山本は耳まで真っ赤になっていた。
「は…ぁ…っ…いきなり何だよ」
弱々しく発せられる声に、僕の中で何かが弾けた。
「君が弱いトコ、教えてあげようか?」
にまりと目を細めると、何かを感じたのか山本は手をすすっと引き、目を泳がせた。
「あ、いや…大丈夫。間に合ってっから」
「遠慮しなくていいんだよ?」
「うわ!!」
逃がしはしない。僕は山本の上へと転がるように体を移した。
後ずさりしてソファからずり落ちた山本は、そのまま仰向けに倒れる。僕はその両腕を頭の上で床に縫い止めた。
「ちょっ、ヒバリ!怒ってんのか?」
「何で?怒られるような事した訳?」
「えっと……睡眠を邪魔したから」
「君が来た時はとっくに起きてたよ」
「あ、じゃあ弱いって言った事?」
「……!」
「え、違ったか?じゃあその…殴る力も奪っちゃうくらい、その……」
「……っ!」
「もが!」
それ以上言わせないようにと山本の口を手で塞ぐ。山本は目を丸くした。
僕は口角を吊り上げる。
さぁて、十分頭にきたわけだけど、どうしてくれようか。
気付けば、少し暴れたせいかそれとも冷や汗なのか、うっすら額が濡れている。
僕は顔を寄せ、それを舐めた。
「ん…!」
僕の手の下から、山本のくぐもった声が漏れる。
「さっきは僕の汗を拭いてくれたからね。お礼だよ」
「ちょ…ひあり…」
「何?聞こえない。あぁ、首も拭いてくれたっけ」
さすがにやりづらいので、腕を封じていた方の手を離し、口は塞いでいるその手で少し上を向かせる。
そうやって首筋に噛み付けば、山本の体はピクリと跳ね、鎖骨から顎下へと舌で濡らせば、塞いだ手に熱い息がかかった。
「……っ、待っ」
手は自由だというのに、山本は僕を引き離そうとはしない。シャツをひっぱるその力は弱々しくて、したくてもできないのだと訴えている。
「…僕の事弱いなんて言ったけど、君は弱い所が多過ぎだよね」
「ふは…!何だよやっぱその事?そんなに怒んなくてもいいだろ」
口から手を離せば、眉を下げて頬は真っ赤なくせして言葉だけは荒げてみせる。
拗ねた子供みたいだ。
「別に怒ってないよ」
「じゃあ何だよ」
「だから、僕より君の方が弱いって教えてあげてるだけ」
「だから何だよそれ」
「例えば…」
ちょっと脇腹をつつくだけで
「ぎゃ!」
ちょっと腰を撫でるだけで
「…っ」
ちょっと臍周りに触れるだけで
「ふは、くすぐった…」
そのまま、ちょっと胸に手を滑らすだけで、
「……っ!」
―――本当弱い。
「そんなんで、よく僕の事弱いなんて言えたよねぇ…」
「ん、あ、だっ…て」
「だって、何?」
呼吸を乱す山本に問い掛ける。答える時間をあげる間、僕は山本のシャツのボタンを外す事にした。山本はされるがままに、僕を見上げた。
「弱いっつーけど、ヒバリだから、だぜ?」
「?」
「ヒバリが触るから、あっちこっちくすぐってぇの」
「……」
「だから、オレが触ったら、ヒバリもくすぐってぇのかなって思っただけ」
「……」
さっきまであった怒りの熱は、瞬時に別な熱へと変わる。
ああ、成る程。
確かに、山本が相手じゃなかったらあんなにぞくりとはしない。
そもそも指一本触れさせる気は無いし、そんな事考える小動物がいたなら二度と立てないほど咬み殺してやるだろう。
でも相手が、山本だから。
「分かった。じゃあ、仕返しにたっぷり可愛いがってあげるよ」
「え…何で!?」
「君だから」
「は?どーゆー事?」
「もう黙れば」
「ぅむ…ン…!」
君だから、この部屋を自由に使っても許してあげる。
君だから、僕に触れても許してあげる。
君だから、
その可愛い声を、
聞きたいと思う。
「ヒバリ…今日ちょっと意地悪ぃ…」
熱く息を吐いた山本は、恥ずかしそうに瞳を麗せて僕を見た。僕は胸を高鳴らせ、ふっと笑った。
「君が相手だと、つい、ね」
そういう気持ちを僕に気付かせた、君のせいでしょ。
end