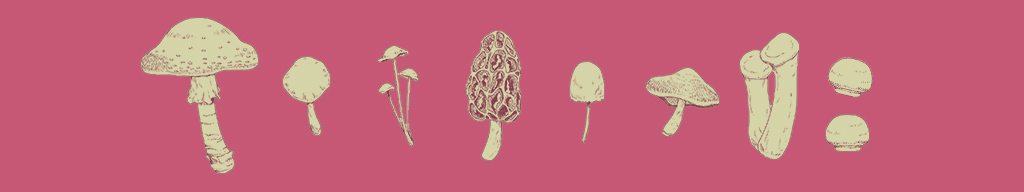New life
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
※左馬刻妹捏造※
「んで、……さっきの話、詳しく聞かせろ」
「っ…、わ、分かりました…」
私がソファに腰を下ろして数十秒も経たないうちに確信をついてくる左馬刻様。
正直とぼけようとも思ったが、射抜くような左馬刻様の鋭い視線に嘘をつくことも出来ず…。私は気味悪がられるのも承知で腹をくくり、ゆっくりと口を開けた。
「じ、実は……_______」
*
「まぁ、確かに現実離れした話だなそりゃ」
「…………はい。信じてもらえないのは、当然です」
取り敢えず今まであった事全てを洗いざらい左馬刻様に話す。一つの嘘をも吐く事無く、事実だけを彼に話した。信じてもらえないのは当然だ、けれど信じてほしい。そんな矛盾した願いを込めて、話している途中決して彼から視線を外すことはなかった。
左馬刻様もそんな私の想いを汲み取ったのか、それとも気まぐれなのか、真剣な表情のまま黙って耳を傾けてくれていた。
「バァカ、そんな顔する奴が嘘なんかつけっかよ。あんま俺様を見くびんじゃねぇぞ」
「っ……、し、信じてくれるんですか…?」
半分諦めた気持ちでいた私に投げかけられた言葉は思いもよらないもので。ゆっくりと視線を左馬刻様へと向ければ、少しだけ口角を上げた彼を鮮明に視界のど真ん中で捉える。
初めて見る彼の微笑み?とはいかないけれど笑った表情があまりにも綺麗なものだからつい見惚れてしまいそうになった。それと同時に耳に響く出会った時よりも数倍柔らかな声が、私の張り詰めてい心をゆっくりと解いていく。
ここに来てからロクに精神を休められずにいたものだから、久々の心からの安堵感に自然と体の力が抜けていく。
「よかった………絶対気味悪がられるって、」
「俺の反応を予想するなんざ100万年早ぇよクソガキ」
「…ごめんなさい、……それと、ありがとうございます」
胸に手を当てて呼吸を整える私の頭上から、左馬刻様の優しい悪態が降ってくる。やっぱり彼は優しい。本当に人情味に溢れている。
私はそんな彼に感謝の気持ちを覚え、今日何度目か分からないけれど頭を深々と下げながらお礼の言葉を並べた。
「けどよ、お前これからどうするつもりだ。帰る場所ねぇんだろ」
「……それは、今から考えます。何とか元の世界に戻らないと……」
暫くは幸せに満ちた空間だったが、左馬刻様のある一言で一気に現実に引き戻される。そうだ、私には家がない。現実の世界に戻ると行っても住む場所がなければすぐにのたれ死んでしまうだろう。それだけは御免だ。だって私にはたった一人の姉を残して来ているのだから。大切な姉を。
膝の上で拳を強く握りしめながら、何とか解決策を見つけようと思考を張り巡らせる。
どうする?中央区に行くべきか?幾ら自分が嫌でもこれはやむを得ない。死ぬよりは全然マシだ。
「あの、私中央区に_________…」
「だったら、ここに住めばいいじゃねぇか」
「……え?」
俯いた顔を勢い良く上げて左馬刻様に自身の思いを告げようとした瞬間、彼から飛び出したのはとんでもない爆弾発言だった。
自然と私の口は閉口し、ぐるぐると脳内を駆け巡っていた思考も停止する。とんでもないアホ面を晒していたとは思うが、これは仕方ないだろう。体を静止させ黙り込んでしまった私を聞こえていなかったのだと勘違いした左馬刻様は、今度は自分に顔をぐっと近づけて再度口を開けた。
「だから、俺様がここに置いてやるっつってんだよ」
「えっ!?う、うそ!?……え、えええ」
「あ"?なんか文句あんのかよ。金も飯も全部俺が用意してやるっつってんだ、こんなウマい話滅多にねぇだろうが」
「で、でもっ……」
半分錯乱状態で慌てふためく私にイラついたのか、左馬刻が不機嫌そうに眉を潜める。だって畏れ多いんだよぉぉ!!!流石にそんな事までしてもらうなんて……!まず私の心臓がもたない!!!!
てか、何でこんなに私を気にかけてくるの…?逆に疑問だよ…!
「……でも、あ、あの、お気持ちは大変嬉しいのですが……何でそこまでしてくれるのでしょうか…?」
「………」
取り敢えずその疑問を解消しようと、左馬刻様の顔色を伺いながら恐る恐る言葉を紡ぐ。
すると彼は一瞬言葉に詰まらせて黙り込んだと思うと、今度は酷く静かな口調で開口した。
「…お前見てると、妹思い出すんだよ」
「い、妹さん…?そ、そんな畏れ多い!私白髪でも美形でもないのに!」
「容姿なわけねぇだろーが!丁度テメェと変わらねぇ年でよ。今年の春この家を出てって、今は中央区で一人暮らし中」
ポツリと溢された言葉にすかさず反応すれば、鋭いツッコミが荒い口調と共に飛んでくる。左馬刻様に妹がいるのは知っていたけど容姿までは分からなかった。だって公式でも妹がいるって事くらいしか情報がなかったし。
まぁ、左馬刻様と兄妹なだけあってきっと物凄い美人だって事くらいは大体予想つくけれど。
しかし容姿抜きにしても左馬刻様の妹さんと似ているなんて、全く検討がつかない。
未だ疑問を残している私の脳内を見透かす様にこちらに視線を送る左馬刻様は、再度口を開けそのまま話を続けた。
「彼奴も何つーか、いつまでもほっておけねぇくらいのビビリでよォ。何でも怖い怖いって、すぐ俺に泣きついてくんだよ」
「………」
「その癖肝心な時にはちゃんと芯を持った強い奴でよ、下手すりゃ俺でも負けちまうくらいのな。………誰に似たんだか」
「……あ、の」
「今日俺を睨みつけたテメェの目があまりにも彼奴と重なって見えて、柄にもなく情が湧いちまったみてぇだな」
そう言って口角を上げた左馬刻様の表情が少し寂しげに見えたのは、私の勘違いだったのだろうか。けれどそのルビーの瞳が切なげに揺れていたのは、それだけは分かった。その中に移る私がどんな表情をしていたのかも。
ああ、左馬刻様は私に妹さんを重ねて見てるんだ。寂しいんだ、きっと。心配なんだ、中央区に行ってしまったたった一人の家族の事が。
ドラマCDだけでは見えてこなかった彼の心情が今ハッキリ分かる気がして、心臓が鷲掴みされたように痛くなる。
左馬刻様の心に近くで触れてみて、やっと、やっとこの世界にいる事を実感する。
次元が違うと引いていた境界線が少しずつ消えていくのが分かった。
目の前の酷く綺麗で、強くて、強欲で、自己中で、誰よりも脆く儚い存在に、私の心は段々と支配されていくのが分かる。
守ってあげなきゃ、この人を。妹さんの代わりに今度は私が。
何て偉そうに、私に何が出来るのか。アニメの主人公でもヒーローでもない私に、平凡でビビリのごく普通の高校生に何が出来ると言うのか。私より断然強い人だというのに。むしろ私が邪魔をしてしまうくらいかも知れないのに。
けれど、いいじゃないか。ヒーローじゃなくたって、主人公じゃなくたって、弱くたってビビリだって守りたいものくらいあるものだ。それを否定する権利は誰にもない。
今この世界で、私は確かに碧棺左馬刻という存在を守りたい、そう直感的に思ったのだ。
「んで、どーすんだよ。ここに住むのか住まねぇのか、ハッキリしろや」
「…………あ、あの……じゃあ。ご迷惑で無ければ、よろしくお願いします……!」
中々返事をしない私に痺れを切らしたのか、左馬刻様が俯いていた私の顔を覗き込んでくる。
同時に伏せていた顔をゆっくりと上げ、目を固く瞑りながら精一杯の言葉を紡けば不意に頭に優しい体温が乗っかった。
閉じていた瞼をゆっくりと浮上させると、視界には緩く口角を上げた左馬刻様だけが映る。それと共に髪を優しい手つきに撫でられ、私は体の体温が一気に上昇するのが分かる。きっと私の頬っぺたは茹でたこのように真っ赤なんだろうな。
「そう言えば聞いてなかったよな。名前は?」
「山田……山田花子です、」
「……じゃあ花子。お前とは長い付き合いになりそうだわ」
「ふ、不束者ですが、よろしくお願いします………左馬刻様」
手をソファにつけ土下座するように頭を下げれば、頭上で左馬刻様が喉を鳴らしながら笑い声をあげたのが分かる。
俺達夫婦じゃねぇだろうが、なんて心底楽しそうな声が聞こえたものだから、自然と私の胸も優しい熱に飲み込まれた。
「…てか、何で様呼びなんだよ」
「ああ、恥ずかしながら自分の世界ではそう呼んでいたもので……」
「ふーん、まぁ別に良いけどよ」
「(ラップの時に自分で様をつけろって言ってるんだけどね……一郎に!!!!!)」
まぁ、それは内緒にしておこう。この世界がどこまで進んでいるのかなんて分からないから。それに左馬刻様の前で一郎の名前を出せばどうなるか…ドラマCDでのワンシーンを思い出して一人身震いした。
山田花子、18歳。暫くこの世界で生きていくみたいです。
(…あ、和子へ連絡しなきゃ…!!これは大変な事になったぞ…)
「んで、……さっきの話、詳しく聞かせろ」
「っ…、わ、分かりました…」
私がソファに腰を下ろして数十秒も経たないうちに確信をついてくる左馬刻様。
正直とぼけようとも思ったが、射抜くような左馬刻様の鋭い視線に嘘をつくことも出来ず…。私は気味悪がられるのも承知で腹をくくり、ゆっくりと口を開けた。
「じ、実は……_______」
*
「まぁ、確かに現実離れした話だなそりゃ」
「…………はい。信じてもらえないのは、当然です」
取り敢えず今まであった事全てを洗いざらい左馬刻様に話す。一つの嘘をも吐く事無く、事実だけを彼に話した。信じてもらえないのは当然だ、けれど信じてほしい。そんな矛盾した願いを込めて、話している途中決して彼から視線を外すことはなかった。
左馬刻様もそんな私の想いを汲み取ったのか、それとも気まぐれなのか、真剣な表情のまま黙って耳を傾けてくれていた。
「バァカ、そんな顔する奴が嘘なんかつけっかよ。あんま俺様を見くびんじゃねぇぞ」
「っ……、し、信じてくれるんですか…?」
半分諦めた気持ちでいた私に投げかけられた言葉は思いもよらないもので。ゆっくりと視線を左馬刻様へと向ければ、少しだけ口角を上げた彼を鮮明に視界のど真ん中で捉える。
初めて見る彼の微笑み?とはいかないけれど笑った表情があまりにも綺麗なものだからつい見惚れてしまいそうになった。それと同時に耳に響く出会った時よりも数倍柔らかな声が、私の張り詰めてい心をゆっくりと解いていく。
ここに来てからロクに精神を休められずにいたものだから、久々の心からの安堵感に自然と体の力が抜けていく。
「よかった………絶対気味悪がられるって、」
「俺の反応を予想するなんざ100万年早ぇよクソガキ」
「…ごめんなさい、……それと、ありがとうございます」
胸に手を当てて呼吸を整える私の頭上から、左馬刻様の優しい悪態が降ってくる。やっぱり彼は優しい。本当に人情味に溢れている。
私はそんな彼に感謝の気持ちを覚え、今日何度目か分からないけれど頭を深々と下げながらお礼の言葉を並べた。
「けどよ、お前これからどうするつもりだ。帰る場所ねぇんだろ」
「……それは、今から考えます。何とか元の世界に戻らないと……」
暫くは幸せに満ちた空間だったが、左馬刻様のある一言で一気に現実に引き戻される。そうだ、私には家がない。現実の世界に戻ると行っても住む場所がなければすぐにのたれ死んでしまうだろう。それだけは御免だ。だって私にはたった一人の姉を残して来ているのだから。大切な姉を。
膝の上で拳を強く握りしめながら、何とか解決策を見つけようと思考を張り巡らせる。
どうする?中央区に行くべきか?幾ら自分が嫌でもこれはやむを得ない。死ぬよりは全然マシだ。
「あの、私中央区に_________…」
「だったら、ここに住めばいいじゃねぇか」
「……え?」
俯いた顔を勢い良く上げて左馬刻様に自身の思いを告げようとした瞬間、彼から飛び出したのはとんでもない爆弾発言だった。
自然と私の口は閉口し、ぐるぐると脳内を駆け巡っていた思考も停止する。とんでもないアホ面を晒していたとは思うが、これは仕方ないだろう。体を静止させ黙り込んでしまった私を聞こえていなかったのだと勘違いした左馬刻様は、今度は自分に顔をぐっと近づけて再度口を開けた。
「だから、俺様がここに置いてやるっつってんだよ」
「えっ!?う、うそ!?……え、えええ」
「あ"?なんか文句あんのかよ。金も飯も全部俺が用意してやるっつってんだ、こんなウマい話滅多にねぇだろうが」
「で、でもっ……」
半分錯乱状態で慌てふためく私にイラついたのか、左馬刻が不機嫌そうに眉を潜める。だって畏れ多いんだよぉぉ!!!流石にそんな事までしてもらうなんて……!まず私の心臓がもたない!!!!
てか、何でこんなに私を気にかけてくるの…?逆に疑問だよ…!
「……でも、あ、あの、お気持ちは大変嬉しいのですが……何でそこまでしてくれるのでしょうか…?」
「………」
取り敢えずその疑問を解消しようと、左馬刻様の顔色を伺いながら恐る恐る言葉を紡ぐ。
すると彼は一瞬言葉に詰まらせて黙り込んだと思うと、今度は酷く静かな口調で開口した。
「…お前見てると、妹思い出すんだよ」
「い、妹さん…?そ、そんな畏れ多い!私白髪でも美形でもないのに!」
「容姿なわけねぇだろーが!丁度テメェと変わらねぇ年でよ。今年の春この家を出てって、今は中央区で一人暮らし中」
ポツリと溢された言葉にすかさず反応すれば、鋭いツッコミが荒い口調と共に飛んでくる。左馬刻様に妹がいるのは知っていたけど容姿までは分からなかった。だって公式でも妹がいるって事くらいしか情報がなかったし。
まぁ、左馬刻様と兄妹なだけあってきっと物凄い美人だって事くらいは大体予想つくけれど。
しかし容姿抜きにしても左馬刻様の妹さんと似ているなんて、全く検討がつかない。
未だ疑問を残している私の脳内を見透かす様にこちらに視線を送る左馬刻様は、再度口を開けそのまま話を続けた。
「彼奴も何つーか、いつまでもほっておけねぇくらいのビビリでよォ。何でも怖い怖いって、すぐ俺に泣きついてくんだよ」
「………」
「その癖肝心な時にはちゃんと芯を持った強い奴でよ、下手すりゃ俺でも負けちまうくらいのな。………誰に似たんだか」
「……あ、の」
「今日俺を睨みつけたテメェの目があまりにも彼奴と重なって見えて、柄にもなく情が湧いちまったみてぇだな」
そう言って口角を上げた左馬刻様の表情が少し寂しげに見えたのは、私の勘違いだったのだろうか。けれどそのルビーの瞳が切なげに揺れていたのは、それだけは分かった。その中に移る私がどんな表情をしていたのかも。
ああ、左馬刻様は私に妹さんを重ねて見てるんだ。寂しいんだ、きっと。心配なんだ、中央区に行ってしまったたった一人の家族の事が。
ドラマCDだけでは見えてこなかった彼の心情が今ハッキリ分かる気がして、心臓が鷲掴みされたように痛くなる。
左馬刻様の心に近くで触れてみて、やっと、やっとこの世界にいる事を実感する。
次元が違うと引いていた境界線が少しずつ消えていくのが分かった。
目の前の酷く綺麗で、強くて、強欲で、自己中で、誰よりも脆く儚い存在に、私の心は段々と支配されていくのが分かる。
守ってあげなきゃ、この人を。妹さんの代わりに今度は私が。
何て偉そうに、私に何が出来るのか。アニメの主人公でもヒーローでもない私に、平凡でビビリのごく普通の高校生に何が出来ると言うのか。私より断然強い人だというのに。むしろ私が邪魔をしてしまうくらいかも知れないのに。
けれど、いいじゃないか。ヒーローじゃなくたって、主人公じゃなくたって、弱くたってビビリだって守りたいものくらいあるものだ。それを否定する権利は誰にもない。
今この世界で、私は確かに碧棺左馬刻という存在を守りたい、そう直感的に思ったのだ。
「んで、どーすんだよ。ここに住むのか住まねぇのか、ハッキリしろや」
「…………あ、あの……じゃあ。ご迷惑で無ければ、よろしくお願いします……!」
中々返事をしない私に痺れを切らしたのか、左馬刻様が俯いていた私の顔を覗き込んでくる。
同時に伏せていた顔をゆっくりと上げ、目を固く瞑りながら精一杯の言葉を紡けば不意に頭に優しい体温が乗っかった。
閉じていた瞼をゆっくりと浮上させると、視界には緩く口角を上げた左馬刻様だけが映る。それと共に髪を優しい手つきに撫でられ、私は体の体温が一気に上昇するのが分かる。きっと私の頬っぺたは茹でたこのように真っ赤なんだろうな。
「そう言えば聞いてなかったよな。名前は?」
「山田……山田花子です、」
「……じゃあ花子。お前とは長い付き合いになりそうだわ」
「ふ、不束者ですが、よろしくお願いします………左馬刻様」
手をソファにつけ土下座するように頭を下げれば、頭上で左馬刻様が喉を鳴らしながら笑い声をあげたのが分かる。
俺達夫婦じゃねぇだろうが、なんて心底楽しそうな声が聞こえたものだから、自然と私の胸も優しい熱に飲み込まれた。
「…てか、何で様呼びなんだよ」
「ああ、恥ずかしながら自分の世界ではそう呼んでいたもので……」
「ふーん、まぁ別に良いけどよ」
「(ラップの時に自分で様をつけろって言ってるんだけどね……一郎に!!!!!)」
まぁ、それは内緒にしておこう。この世界がどこまで進んでいるのかなんて分からないから。それに左馬刻様の前で一郎の名前を出せばどうなるか…ドラマCDでのワンシーンを思い出して一人身震いした。
山田花子、18歳。暫くこの世界で生きていくみたいです。
(…あ、和子へ連絡しなきゃ…!!これは大変な事になったぞ…)