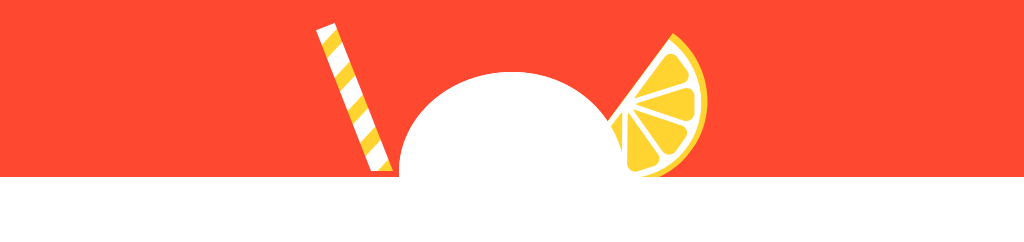1️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
誕生日、断れなかった急な依頼。
電話越しに悲しそうな声を上げる弟達。
家を出る前に夕食は盛大に祝うから!期待しててね、と言っていた彼女と弟達の顔が浮かぶ。
やっとの思いで帰宅したのは日付が越えるギリギリの時間だった。
電気の消えた真っ暗な自宅。
冷蔵庫の中には綺麗に大皿に盛られた料理がラップの膜に包まれて眠っている。
《にいちゃんへ お疲れ様!食べてもいいよ》と二郎の字で書かれたメモが貼り付けられている。
美味そうな料理に一瞬心が揺らぐが折角の料理だ。
「みんなで食いてえな…」
大量の料理を見て、腹の虫が空腹を訴え出す。
育ち盛りの胃袋は二十歳になったからといって大人しくなる事はない様だ。
仕方なく夜食用に買い置きしてあるカップラーメンをキッチンの小さなあかりを頼りに漁っていると、リビングの電気がついて急に明るくなる。
「いちろ…?」
「おぉ、悪い。起こしたか?」
「んーん、おかえり」
眠たそうに瞼をこする彼女が擦り寄ってくる。
「お夜食?」
「まあな、夕飯は食ったんだけど腹減っちまって」
「…ラーメンの気分?」
「いや、そういう訳じゃねぇけど…」
「じゃあ、私がとっておきの夜食を用意してあげましょう!」
自信ありげに勝ち誇った顔をする彼女が可愛くて、無意識に笑顔で首を縦に振っていた。
深夜のキッチンで黙々と玉ねぎを刻み出す彼女。
「…簡単なのでいいぞ?」
「だいじょぶ、だいじょぶ!簡単だから」
見てて?と笑う彼女。
そのゆるい笑顔に心が洗われる。
「さて、今晩の主役はぁ…?」
刻み終えた玉ねぎをボウルに移して缶詰などが置かれた棚の中を漁りだす彼女。
「じゃ〜んッ!コンビーフさんです!」
深夜テンションというヤツか、いつもよりご機嫌な彼女は誇らし気に見つけ出したコンビーフの缶を掲げている。
「特別にお誕生日さんにこの缶を開けさせてあげます」
「じゃ、ありがたく…」
嬉々としてその姿に拍手を送り、大げさに改まってその缶を受け取った。
ネジ巻きの様に缶を開けていく。これがコンビーフの醍醐味といってもいいだろう。
「開いたぞ」
「ありがと。それではこれと先程の玉ねぎを混ぜます!」
「おお!」
「そしてここに黒胡椒と…マヨネーズを入れます!」
「マジか!」
これはぜってぇ美味いヤツだ!と腹の虫が期待の声を上げる。
「そして、この具をチーズと一緒に食パンに挟んでホットサンドメーカーで焼きます」
「悪魔の食い物だな…」
待つこと数分。
こんがり焼きあがったホットサンドとインスタントのオニオンスープで贅沢過ぎる夜食が完成した。
食卓にのった料理を羨ましそうに見詰める彼女がぽつりと呟く。
「あ〜、私もちょっと食べたいなぁ…」
「食わないのか?」
「だって…ぜったい太るもん」
そう言いつつ唸る彼女の手は食パンにチーズをのせている。欲望に抗えない可愛い可愛い俺の彼女なのである。
「じゃあ、これ半分にしようぜ」
皿の上のホットサンドを指すと、瞳を輝かせる彼女。
2人っきりの食卓に並んでホットサンドにかぶり付く。
「うまッ!」
「おいひ〜〜ぃ」
深夜に食べる罪深きジャンキーな食べ物。
これに合わせる飲み物はコーラ…いや、きっと…
「…ビールだな」
「あ〜それはサイコ〜」
飲んだことないけど、と彼女が笑う。
あいにく昨日まで未成年だった俺の家の冷蔵庫にはビールは常備されていないのでいつものコーラで我慢する事にする。
炭酸の泡が喉を強く刺激するように弾ける。
結局残り1枚も2人で分け合ってペロリと完食して落ち着いた腹の虫。
眠気も相まって彼女の肩にもたれかかって瞼を閉じる。
「なぁに?今日の一郎くんは甘えん坊さんだね」
「ン、」
「ねるの?お風呂は?」
「行くけど…ちょっとだけ…」
誕生日特権ってヤツ?
今日くらいは、甘えさせてくれよ。
「一郎、お誕生日おめでとう」
微睡みに落ちる俺の髪を撫でる彼女の手がとても暖かかった。
電話越しに悲しそうな声を上げる弟達。
家を出る前に夕食は盛大に祝うから!期待しててね、と言っていた彼女と弟達の顔が浮かぶ。
やっとの思いで帰宅したのは日付が越えるギリギリの時間だった。
電気の消えた真っ暗な自宅。
冷蔵庫の中には綺麗に大皿に盛られた料理がラップの膜に包まれて眠っている。
《にいちゃんへ お疲れ様!食べてもいいよ》と二郎の字で書かれたメモが貼り付けられている。
美味そうな料理に一瞬心が揺らぐが折角の料理だ。
「みんなで食いてえな…」
大量の料理を見て、腹の虫が空腹を訴え出す。
育ち盛りの胃袋は二十歳になったからといって大人しくなる事はない様だ。
仕方なく夜食用に買い置きしてあるカップラーメンをキッチンの小さなあかりを頼りに漁っていると、リビングの電気がついて急に明るくなる。
「いちろ…?」
「おぉ、悪い。起こしたか?」
「んーん、おかえり」
眠たそうに瞼をこする彼女が擦り寄ってくる。
「お夜食?」
「まあな、夕飯は食ったんだけど腹減っちまって」
「…ラーメンの気分?」
「いや、そういう訳じゃねぇけど…」
「じゃあ、私がとっておきの夜食を用意してあげましょう!」
自信ありげに勝ち誇った顔をする彼女が可愛くて、無意識に笑顔で首を縦に振っていた。
深夜のキッチンで黙々と玉ねぎを刻み出す彼女。
「…簡単なのでいいぞ?」
「だいじょぶ、だいじょぶ!簡単だから」
見てて?と笑う彼女。
そのゆるい笑顔に心が洗われる。
「さて、今晩の主役はぁ…?」
刻み終えた玉ねぎをボウルに移して缶詰などが置かれた棚の中を漁りだす彼女。
「じゃ〜んッ!コンビーフさんです!」
深夜テンションというヤツか、いつもよりご機嫌な彼女は誇らし気に見つけ出したコンビーフの缶を掲げている。
「特別にお誕生日さんにこの缶を開けさせてあげます」
「じゃ、ありがたく…」
嬉々としてその姿に拍手を送り、大げさに改まってその缶を受け取った。
ネジ巻きの様に缶を開けていく。これがコンビーフの醍醐味といってもいいだろう。
「開いたぞ」
「ありがと。それではこれと先程の玉ねぎを混ぜます!」
「おお!」
「そしてここに黒胡椒と…マヨネーズを入れます!」
「マジか!」
これはぜってぇ美味いヤツだ!と腹の虫が期待の声を上げる。
「そして、この具をチーズと一緒に食パンに挟んでホットサンドメーカーで焼きます」
「悪魔の食い物だな…」
待つこと数分。
こんがり焼きあがったホットサンドとインスタントのオニオンスープで贅沢過ぎる夜食が完成した。
食卓にのった料理を羨ましそうに見詰める彼女がぽつりと呟く。
「あ〜、私もちょっと食べたいなぁ…」
「食わないのか?」
「だって…ぜったい太るもん」
そう言いつつ唸る彼女の手は食パンにチーズをのせている。欲望に抗えない可愛い可愛い俺の彼女なのである。
「じゃあ、これ半分にしようぜ」
皿の上のホットサンドを指すと、瞳を輝かせる彼女。
2人っきりの食卓に並んでホットサンドにかぶり付く。
「うまッ!」
「おいひ〜〜ぃ」
深夜に食べる罪深きジャンキーな食べ物。
これに合わせる飲み物はコーラ…いや、きっと…
「…ビールだな」
「あ〜それはサイコ〜」
飲んだことないけど、と彼女が笑う。
あいにく昨日まで未成年だった俺の家の冷蔵庫にはビールは常備されていないのでいつものコーラで我慢する事にする。
炭酸の泡が喉を強く刺激するように弾ける。
結局残り1枚も2人で分け合ってペロリと完食して落ち着いた腹の虫。
眠気も相まって彼女の肩にもたれかかって瞼を閉じる。
「なぁに?今日の一郎くんは甘えん坊さんだね」
「ン、」
「ねるの?お風呂は?」
「行くけど…ちょっとだけ…」
誕生日特権ってヤツ?
今日くらいは、甘えさせてくれよ。
「一郎、お誕生日おめでとう」
微睡みに落ちる俺の髪を撫でる彼女の手がとても暖かかった。