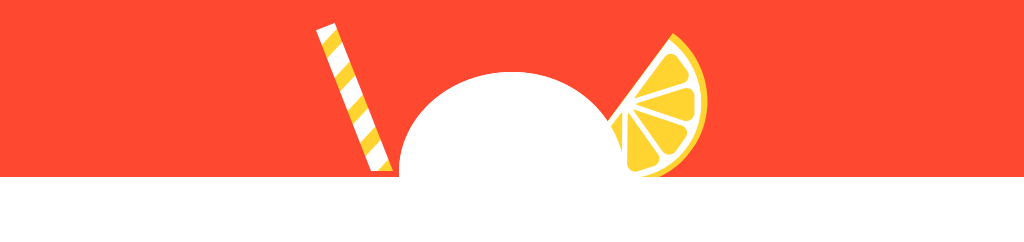1️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「これ、知ってるか?《ポルボロン》っつうお菓子らしいんだが」
お得意さんから貰ったというお菓子を差し出しながら彼が私の横に座る。
「へぇ〜、初めて見た」
受け取ったそれを物珍しそうに見詰める私は今より少しだけ幼くて、まだ彼の彼女になる少し前の唯の女友達だった頃の姿をしていて、これが夢だとすぐに気付いた。
ポルボロンを巡る会話をしている自分たちを私は部屋の少し上の方から見ている。
「これを口に入れて崩れる前に《ポルボロン》って三回唱えられたら願いが叶うんだと」
「えー、ほんとぉ?」
可愛らしい洋風のパッケージから取り出したお菓子をほぼ同時に口の中に放り込めばその瞬間から崩れ出す。二人は口をもぐもぐとさせたまま顔を見合わせて苦笑いを浮かべる。
「…むりでしょ」
「…むりだな」
口の中に広がる甘さをふたりで笑ったっけ。
夢の中とは不思議なものでその出来事を体感している自分とそれを冷静にこれは夢だと理解して傍観している自分の感情がごちゃ混ぜになる。
夢から覚める方法は知っている。
目を閉じて深呼吸をする。
そうすれば次に目を覚ます時はベッドの上だ。
「おい、〇〇聞いてるか?」
暖かな陽射しに照らされる窓際のボックス席。
運ばれてきたコーヒーが目の前に置かれて、店員さんはすぅっと消えていく。
やけに静かな店内。
「えっと、ごめん。何の話だっけ」
「会うの久し振りだなって話だよ」
「ごめんごめん、ちょっとぼぅっとしてた。うん、そうだね…!」
混乱する頭で次になんて話を切り出したらいいのか迷いながらコーヒーにミルクと砂糖を入れる。
ぐるぐると黒い渦に飲み込まれるミルクを見詰めていると、相変わらず柔らかくて暖かな声の彼が「元気だったか?」と私に問う。
「まぁ、それなりに。一郎は?」
「俺もぼちぼちかなぁ」
「そっか」
しばらくすれば緊張は解けて、彼の兄弟の話や仕事の話、毎年行っている記念日の旅行を今年はどこにしようかなんていつもと変わらない会話が弾んだ。
「この間は軽井沢だったろ?今回は南のほうってのはどうだ?」
「あ〜、いいねぇ九州とか?でも沖縄とかも捨て難い…!」
「いいな、沖縄」
俺、行ったことねぇんだよなぁ…、と呟く彼は手元の旅行雑誌をペラペラと捲る。
「いっそのこと二郎くんと三郎くんも誘ってみんなで行くのはどう?絶対楽しいよ」
「あ〜、いいなぁ…でもそれじゃあほとんど家族旅行みたいなもんになっちまうぞ?いいのか?」
「勿論!みんな一緒の方が楽しいでしょ?」
コーヒーに口を付けるとそれはまだ随分と熱くて、猫舌な私は舌を少し火傷してしまった。
「熱っ」
「おい、大丈夫か?」
おっちょこちょいだなぁ、と笑う彼。
美味しそうにコーヒーを飲む彼のカップはいつまでも満たされたままで、ふと冷静な自分が戻ってくる。
私たち以外に誰も居ない店内。
いつまで経っても減らない、冷めないコーヒー。
都合良く現れる旅行雑誌。
目の前で楽しそうに笑う一郎。
ずっと気付かないフリをしていたけれど、それももう限界だろう。
「嗚呼、そっか」
「ん?」
雑誌から視線を上げた彼。
私の大好きな赤と緑のオッドアイと可愛い泣き黒子。
強くてどこまでも真っ直ぐな瞳が私を見詰める。
この暖かな陽だまりにいつまでも居たいけれど、そろそろ起きないと。
愛おしい彼の名を呼ぶ。
「一郎、」
「これ、夢…なんだね」
綺麗な色違いの瞳をまぁるくした彼。
数秒の沈黙の後、彼が静かに口を開く。
「…まぁ、な」
「私のこと、心配して出てきてくれたの?」
優しく悲しい顔をした彼が曖昧に、どこか寂しそうに笑う。
「私はもう大丈夫だよ」
「そっか。お前は強いなぁ、流石俺の彼女だな!」
私の髪を撫でる温かな彼の手。太陽みたいな彼の笑顔が眩し過ぎて思わず泣きそうになってしまう。
「本当に大丈夫か?」
「…うん、まだ何回も思い出すかもしれないけどちゃんと前を向くから」
本当は優しい彼の手に包まれたままで居たいけれど、大丈夫、そう自分に言い聞かせた。
「また、思い出したら会いに来てもいい?」
「嗚呼、ずっと待ってるからいつでも来いよ」
「おばあちゃんになっても笑わないで居てくれる?」
「お前はきっと婆ちゃんになっても可愛いよ」
「自分が若いままだからって他の子に余所見なんてしないでね?」
「お前以外なんて考えらんねぇから安心しろよ」
「言ったね?約束だよ?」
「嗚呼、約束だ」
この夢から覚める方法は知っている。
いつまでも冷めないままのコーヒーに添えられた洋風な赤いパッケージのお菓子に手を伸ばす。
「一郎、ありがとね。バイバイ」
まだ沢山伝えたい事はあるけれど、上手く言葉に出来そうにないから崩れそうなお菓子を口の中に放り込んで君が教えてくれた魔法の言葉を唱える。
あの時、一瞬で解けたお菓子の形は夢の中では少しだけ長く形を留めていてくれる。
ポルボロン ポルボロン ポルボロン、
どうか君が健やかに眠れますように、
どうか君がしあわせでありますように、
君の居ない世界なんて私には要らないから
どうか明日世界が終わりますように、
「〇〇、しあわせになれよ」
溢れる涙でボヤけてしまいそうな彼の優しい笑顔を瞼の裏に焼き付けて、目を閉じる。
次に目を覚ました私の世界、
何処を探しても君はもういない。
お得意さんから貰ったというお菓子を差し出しながら彼が私の横に座る。
「へぇ〜、初めて見た」
受け取ったそれを物珍しそうに見詰める私は今より少しだけ幼くて、まだ彼の彼女になる少し前の唯の女友達だった頃の姿をしていて、これが夢だとすぐに気付いた。
ポルボロンを巡る会話をしている自分たちを私は部屋の少し上の方から見ている。
「これを口に入れて崩れる前に《ポルボロン》って三回唱えられたら願いが叶うんだと」
「えー、ほんとぉ?」
可愛らしい洋風のパッケージから取り出したお菓子をほぼ同時に口の中に放り込めばその瞬間から崩れ出す。二人は口をもぐもぐとさせたまま顔を見合わせて苦笑いを浮かべる。
「…むりでしょ」
「…むりだな」
口の中に広がる甘さをふたりで笑ったっけ。
夢の中とは不思議なものでその出来事を体感している自分とそれを冷静にこれは夢だと理解して傍観している自分の感情がごちゃ混ぜになる。
夢から覚める方法は知っている。
目を閉じて深呼吸をする。
そうすれば次に目を覚ます時はベッドの上だ。
「おい、〇〇聞いてるか?」
暖かな陽射しに照らされる窓際のボックス席。
運ばれてきたコーヒーが目の前に置かれて、店員さんはすぅっと消えていく。
やけに静かな店内。
「えっと、ごめん。何の話だっけ」
「会うの久し振りだなって話だよ」
「ごめんごめん、ちょっとぼぅっとしてた。うん、そうだね…!」
混乱する頭で次になんて話を切り出したらいいのか迷いながらコーヒーにミルクと砂糖を入れる。
ぐるぐると黒い渦に飲み込まれるミルクを見詰めていると、相変わらず柔らかくて暖かな声の彼が「元気だったか?」と私に問う。
「まぁ、それなりに。一郎は?」
「俺もぼちぼちかなぁ」
「そっか」
しばらくすれば緊張は解けて、彼の兄弟の話や仕事の話、毎年行っている記念日の旅行を今年はどこにしようかなんていつもと変わらない会話が弾んだ。
「この間は軽井沢だったろ?今回は南のほうってのはどうだ?」
「あ〜、いいねぇ九州とか?でも沖縄とかも捨て難い…!」
「いいな、沖縄」
俺、行ったことねぇんだよなぁ…、と呟く彼は手元の旅行雑誌をペラペラと捲る。
「いっそのこと二郎くんと三郎くんも誘ってみんなで行くのはどう?絶対楽しいよ」
「あ〜、いいなぁ…でもそれじゃあほとんど家族旅行みたいなもんになっちまうぞ?いいのか?」
「勿論!みんな一緒の方が楽しいでしょ?」
コーヒーに口を付けるとそれはまだ随分と熱くて、猫舌な私は舌を少し火傷してしまった。
「熱っ」
「おい、大丈夫か?」
おっちょこちょいだなぁ、と笑う彼。
美味しそうにコーヒーを飲む彼のカップはいつまでも満たされたままで、ふと冷静な自分が戻ってくる。
私たち以外に誰も居ない店内。
いつまで経っても減らない、冷めないコーヒー。
都合良く現れる旅行雑誌。
目の前で楽しそうに笑う一郎。
ずっと気付かないフリをしていたけれど、それももう限界だろう。
「嗚呼、そっか」
「ん?」
雑誌から視線を上げた彼。
私の大好きな赤と緑のオッドアイと可愛い泣き黒子。
強くてどこまでも真っ直ぐな瞳が私を見詰める。
この暖かな陽だまりにいつまでも居たいけれど、そろそろ起きないと。
愛おしい彼の名を呼ぶ。
「一郎、」
「これ、夢…なんだね」
綺麗な色違いの瞳をまぁるくした彼。
数秒の沈黙の後、彼が静かに口を開く。
「…まぁ、な」
「私のこと、心配して出てきてくれたの?」
優しく悲しい顔をした彼が曖昧に、どこか寂しそうに笑う。
「私はもう大丈夫だよ」
「そっか。お前は強いなぁ、流石俺の彼女だな!」
私の髪を撫でる温かな彼の手。太陽みたいな彼の笑顔が眩し過ぎて思わず泣きそうになってしまう。
「本当に大丈夫か?」
「…うん、まだ何回も思い出すかもしれないけどちゃんと前を向くから」
本当は優しい彼の手に包まれたままで居たいけれど、大丈夫、そう自分に言い聞かせた。
「また、思い出したら会いに来てもいい?」
「嗚呼、ずっと待ってるからいつでも来いよ」
「おばあちゃんになっても笑わないで居てくれる?」
「お前はきっと婆ちゃんになっても可愛いよ」
「自分が若いままだからって他の子に余所見なんてしないでね?」
「お前以外なんて考えらんねぇから安心しろよ」
「言ったね?約束だよ?」
「嗚呼、約束だ」
この夢から覚める方法は知っている。
いつまでも冷めないままのコーヒーに添えられた洋風な赤いパッケージのお菓子に手を伸ばす。
「一郎、ありがとね。バイバイ」
まだ沢山伝えたい事はあるけれど、上手く言葉に出来そうにないから崩れそうなお菓子を口の中に放り込んで君が教えてくれた魔法の言葉を唱える。
あの時、一瞬で解けたお菓子の形は夢の中では少しだけ長く形を留めていてくれる。
ポルボロン ポルボロン ポルボロン、
どうか君が健やかに眠れますように、
どうか君がしあわせでありますように、
君の居ない世界なんて私には要らないから
どうか明日世界が終わりますように、
「〇〇、しあわせになれよ」
溢れる涙でボヤけてしまいそうな彼の優しい笑顔を瞼の裏に焼き付けて、目を閉じる。
次に目を覚ました私の世界、
何処を探しても君はもういない。