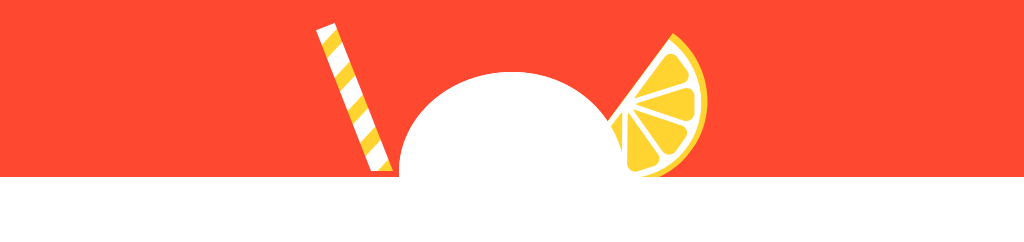2️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
『うわ、冷てぇ!』
「何、大丈夫?」
『雪の塊落ちて来たわ』
服の中入った!、と電話の向こうで騒ぐ彼の声。
「ちょっと、大丈夫?」
バイト先の裏口を開けた瞬間、ビル風に煽られチラチラと舞う雪が顔に降りかかる。
「うわっ、寒い!」
『足元気を付けろよ』
「わかってるよ」
バイト終わりの帰り道にどちらともなく電話をして駅に着くまでだったり、家に着くまでの間電話をするのが日課になっている。
学校でも出来るような他愛も無い話をして、おやすみまた明日。と中々電話を切れずにせーので切るのがきまりになりつつある。
裏口から大通りまでの細い道はまだ誰の足跡もついていなかった。
真っ白な雪を踏む。
慣れない雪に歩き方が覚束無い。
このまま行くと明日は何年振りの大雪なんてニュースが流れるだろう。
明日は早く家を出た方が良さそうだ。
《 雪がふっている
さびしいから 何か食べよう 》
『あ?なんだよそれ』
サクサクと心地いい音を立てる雪に気を取られて思わず零れた言葉。
電話ごし、彼の不思議そうな顔が思い浮かぶ。
「え?嗚呼、詩。この間読んだの」
もう一度、ゆっくりと噛みしめるように詩を暗唱する。
池袋の街はいつもの喧騒は何処へやら。すれ違う人は足早に通り過ぎ、降り積もる雪に世界がモノクロに見えた。
『へー。なんで寂しいんだろーな』
「うーん、雪が降るとさ、何となく世界がゆっくりに見えたりするじゃん?」
『そうかぁ?』
「さむいなぁ、寂しいなぁ、早く帰りたいなぁとか思うでしょう?」
『あー、それは分かるかも』
「私は二郎に会いたいなぁって思うけど…なんて」
水溜りに張った薄氷を踏むと、パキリ、と心地の良い音がする。
静かな街の中で電話越しの彼の声が大きく聴こえた。
「俺だっていつでもお前に会いたいけど?」
「え、二郎⁉︎ぎゃっ⁉︎」
電話の向こうに居るはずの彼が目の前に立っていた。驚きのあまり氷に足を取られてつるりと滑ってしまった私の腕を二郎が掴む。
「あっぶねぇ!足元気を付けろって言っただろ」
「あはは、ごめん…」
しょうがねぇな、と言いたげに彼が溜め息を吐きながら私のコートに付いた雪を払って、繋がれた手は彼のジャケットのポケットへと向かう。
「何か食ってくか」
「え、二郎の奢り?あったかいものがいいな〜」
「あったかいものってなんだよ」
「うーん、お鍋とか?」
「いや、コンビニとかじゃねぇのかよ!…あ、今日確かウチ鍋だけど、来る?」
「え、いいの⁉︎」
他愛も無い会話をしながら彼の家へと向かう。池袋の街にゆっくりと降り積もる雪。
不思議と寂しさは感じなかった。
「何、大丈夫?」
『雪の塊落ちて来たわ』
服の中入った!、と電話の向こうで騒ぐ彼の声。
「ちょっと、大丈夫?」
バイト先の裏口を開けた瞬間、ビル風に煽られチラチラと舞う雪が顔に降りかかる。
「うわっ、寒い!」
『足元気を付けろよ』
「わかってるよ」
バイト終わりの帰り道にどちらともなく電話をして駅に着くまでだったり、家に着くまでの間電話をするのが日課になっている。
学校でも出来るような他愛も無い話をして、おやすみまた明日。と中々電話を切れずにせーので切るのがきまりになりつつある。
裏口から大通りまでの細い道はまだ誰の足跡もついていなかった。
真っ白な雪を踏む。
慣れない雪に歩き方が覚束無い。
このまま行くと明日は何年振りの大雪なんてニュースが流れるだろう。
明日は早く家を出た方が良さそうだ。
《 雪がふっている
さびしいから 何か食べよう 》
『あ?なんだよそれ』
サクサクと心地いい音を立てる雪に気を取られて思わず零れた言葉。
電話ごし、彼の不思議そうな顔が思い浮かぶ。
「え?嗚呼、詩。この間読んだの」
もう一度、ゆっくりと噛みしめるように詩を暗唱する。
池袋の街はいつもの喧騒は何処へやら。すれ違う人は足早に通り過ぎ、降り積もる雪に世界がモノクロに見えた。
『へー。なんで寂しいんだろーな』
「うーん、雪が降るとさ、何となく世界がゆっくりに見えたりするじゃん?」
『そうかぁ?』
「さむいなぁ、寂しいなぁ、早く帰りたいなぁとか思うでしょう?」
『あー、それは分かるかも』
「私は二郎に会いたいなぁって思うけど…なんて」
水溜りに張った薄氷を踏むと、パキリ、と心地の良い音がする。
静かな街の中で電話越しの彼の声が大きく聴こえた。
「俺だっていつでもお前に会いたいけど?」
「え、二郎⁉︎ぎゃっ⁉︎」
電話の向こうに居るはずの彼が目の前に立っていた。驚きのあまり氷に足を取られてつるりと滑ってしまった私の腕を二郎が掴む。
「あっぶねぇ!足元気を付けろって言っただろ」
「あはは、ごめん…」
しょうがねぇな、と言いたげに彼が溜め息を吐きながら私のコートに付いた雪を払って、繋がれた手は彼のジャケットのポケットへと向かう。
「何か食ってくか」
「え、二郎の奢り?あったかいものがいいな〜」
「あったかいものってなんだよ」
「うーん、お鍋とか?」
「いや、コンビニとかじゃねぇのかよ!…あ、今日確かウチ鍋だけど、来る?」
「え、いいの⁉︎」
他愛も無い会話をしながら彼の家へと向かう。池袋の街にゆっくりと降り積もる雪。
不思議と寂しさは感じなかった。