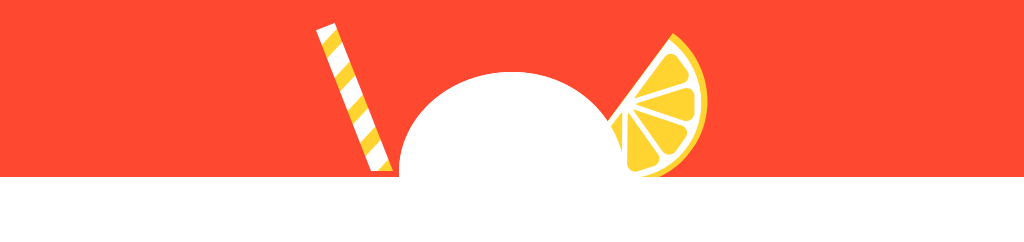3️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
昨晩から兄達がコソコソと準備をしているのを気付いていて気付かない振りをしていた。しかし、今日は日曜だ。
学校も無いしこれといった用事もないので必然的に自宅で過ごす事になる。そうなると僕に秘密で準備をしたい兄達には不都合になる。
「三郎〜、今日は出掛けないのか?」
「いちにいは出掛けないんですか?」
「ん〜〜、まぁ色々やる事があってだなぁ…!」
なぁ、二郎!とぎこちなく二郎に視線を向けるいちにいを見て、「僕、図書館に行ってきます。夕方には帰りますから…!」そう嘘を吐いて、ぎこちない笑顔で僕を見送る二人を背に家を出た。
さぁ、どこへ行こうか。
「三郎くん!」
最寄駅の階段で背後から腕を引かれた。
振り返るとそこには三兄弟が実の姉のように慕う、隣の家の彼女が居た。
「何?」
「今日学校は?おやすみ?」
「〇〇姉、今日は日曜ですよ」
「嗚呼、そうか!お出掛け?」
「なんでもいいでしょ、ついてこないで」
「え〜〜」
曜日感覚すら朧げな彼女(社畜)は休日通勤の途中なのだろう。シンプルなデザインのコートと首元にワインレッドのマフラーを巻いて、僕の隣を並走して駅構内までついて来る。
彼女を撒くために歩いていたが埒があかないのでホームへと向かう階段を下る。
発車のアナウンスが鳴り響き、やんわりと掴まれていた腕を払って今にも締まりそうなドアに駆け込む。
ドアが締まり、やっと彼女を振り払った。
はずだった。
「や〜!ギリギリだったね!」
にこりと笑う彼女。
「なんで!ついて来るんだよ‼︎」
「まぁまぁ、今更引き返せないし座ろうよ」
そう言った癖に彼女は動こうとしない。
「ねぇ、座らないの?」
「さぶくん…」
「何、」
「コート挟まっちゃった…」
今にも泣きそうな顔に今日何度目かの溜息を吐いた瞬間、車体がぐらりと揺れて彼女がバランスを崩す。
「きゃっ!」
「うわっ、」
咄嗟に掴んだ腕はコートを着込んでいても分かるくらいに華奢だった。
「大丈夫…?」
「う、うん。ありがと」
「ねぇ、あの子達カップルかなぁ?めっちゃくっついてる」「可愛い〜〜」少し離れた座席に座っていた女子大生達が囃し立てる。
その声が彼女にも聞こえたのか俯いた彼女の耳が赤く染まっていく。それに気付いてしまった僕も段々と恥ずかしくなってしまって、新宿までの数分の無言が永遠にさえ感じていた。
無事、新宿で挟まったコートが解放されて空いた席に並んで座った。
「はぁ、ビックリしたぁ!」
「驚いたのは僕の方なんだけど?」
「ごめんね」
「まぁ、別にいいけど。…それよりついて来ちゃっていいの?」
「ん?そうだねぇ、私もお休みしちゃおっかなぁ?」
歳上の女性とは思えないくらい無邪気に笑うものだから彼女の頭を無言で小突く。
「いてっ」
「馬鹿」
「馬鹿って言う方が馬鹿なんですぅ〜」
「二郎みたいな事言わないでよ」
「しーらないっ!」
「みて!海!」
結局、その後二回の乗り換えでも彼女を振り切る事は出来なくて、僕らは一緒に熱海まで来てしまった。
十二月の海は人気もなく静かだった。
何を思ったのかパンプスとストッキングを脱いで波打ち際を裸足で歩く彼女。
「うわっ!冷たい!」
迫り来る波を避けきれずに脚を濡らしていた。
「…さぶろぉくん」
「馬鹿じゃないの?」
濡れたスカートの裾を握り締める彼女の手を引いて、近くにあった水道で脚を洗ってやる。
「水道、水抜きされてなくて良かったね」
「…冷たい」
「自業自得」
「うぅ…っ」
体育用に持っていたスポーツタオルで彼女の脚を拭いて、ヒールのついた淡いピンクのパンプスを履かせてやる。
「なんでさ、熱海なの?」
優しい声がしゃがみ込んだままの僕の頭上に降ってくる。
「…ずっと昔に家族でここに来たんだ。いちにいと二郎と、父さんと母さんで」
まぁ、僕は覚えてないんだけどね。目を合わせずに立ち上がって彼女の横に座る。
「その写真を見てさ、僕には両親の思い出がないんだなぁって実感したんだ。何にもない。」
波が激しく、静かに砂浜に打ち付けている。
黙っていた彼女が急に立ち上がって僕の方を見て笑う。
「じゃあさ、次の夏はレンタカーでも借りてさ!一郎と二郎くんと四人で来よう?いっぱい写真撮って思い出いっぱい作ろう!」
「何それ」
「過去は変えられないけど、未来なら変えられるでしょ?楽しい思い出たくさん作ろう?」
「まず、手始めに海鮮丼‼︎食べてもう少し観光してからお土産買って帰ろう?一郎も二郎くんもきっと待ってるよ?」
それからお昼に彼女の奢りで海鮮丼を食べて、2時間半の時間を掛けて僕らの街へと帰った。
2回目の乗り換えを終えて、運良く空いた席に並んで座った。
「ねぇ、三郎くん。お誕生日おめでとう」
「知ってたんだ」
「勿論、これから思い出たくさん作ろうね」
ふにゃりと眠そうに笑った彼女はしばらくすると僕の肩を枕にして夢の世界へと行ってしまった。
「ありがとう」
片道1438円の逃避行は僕の気持ちを少しだけ軽くしてくれた。
日がどっぷり沈んでから家に帰ると兄が迎えてくれた。どうやら彼女が連絡を入れていたらしい。
「おかえり。海楽しかったか?次はみんなで揃って行こうな!」
太陽みたいな兄の笑顔に僕の涙腺がちょっとだけ緩んだのは髪を撫でてくれた彼女だけが知っている。