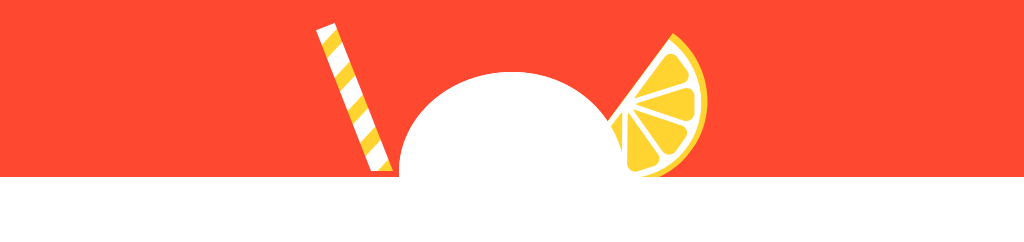3️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
雨の音で目が覚めた。
布団に入った頃から降り出した雨。
日付が変わった今も屋根を叩く雨音はやまない。
この雨では明日の朝、家を早く出なければならないかもしれない。
足元が濡れるのも、湿度の高い教室に詰め込まれて授業を受けるのも億劫だ…
様々な不安が三郎の心を曇らせて眠りを妨げる。
( 何か飲んでからもう一度寝よう… )
スマートフォンの灯りを頼りに所々軋む冷たいフローリングの廊下を抜けて辿り着いたリビング。
電気を点けようとしたところでソファーの上で何かがもぞもぞと動いた。
それに驚いた三郎が電気を点け、いきなりの明転に驚いたのかソファーの上の何かが小さく呻く。
「ぅんん…」
「うわっ!」
「ん…眩しい…。あれ、三郎くん?」
「へ、〇〇姉?居たんですか」
「うん、雨降ってきて帰れなくなったから今日はお泊り」
毛布に包まり寝惚け眼でへらりと笑う彼女は近所に住んでいる若い女性で、幼い頃からよく三兄弟の面倒をみてくれていて三兄弟が本当の姉の様に慕う人だ。
「寝れないの?」
「ちょっと、雨の音が気になってしまって…」
「手冷たいね」
ひたり、触れた彼女の手は暖かくて少しほっとした。
ちょっと待ってて、と彼女が台所へと向かい
水場の小さな蛍光灯をつけて戸棚から小鍋を取り出した。
「何するの?」
「ん〜?」
背伸びをして戸棚の上のカゴを取り出そうとしている彼女に近付いて代わりにカゴを取ってやる。
「ありがとう、三郎くん大きくなったねぇ」
しんみりとした表情で彼女がそういうから、おばさんみたいだよと笑えば脇腹を軽く小突かれた。
「あった、あった!」
カゴの中から取り出したのは製菓に使う様な無糖のココアだった。
少し前に僕が加糖タイプと間違えて買っちゃったやつ。
使い道がわからなくて戸棚に仕舞い込んでいたものだ。
「ココアならここにあるよ?」
来客用のインスタントコーヒーや茶葉が置かれた棚から加糖タイプのココアの袋を出してみせる。すると彼女はにんまりと笑って言う。
「今晩は特別なココアを淹れてあげる」
簡単だから三郎くんも作れるよ。
そう言った彼女はココアの缶を開けてティースプーン二杯分のココアと同じ量の砂糖を小鍋に入れた。
「お水を少し、」
「お水…」
「弱火にかけて、ペースト状になるまで練る!」
「こう?」
渡された小さな泡立て器を握る僕の手に彼女の手が重なって僕を導く様に鍋底を混ぜる。
「うん、上手。そこにバターを一欠片」
「バター、ひとかけ…」
「あと、秘密のスパイス」
微笑む彼女が鍋の上で摘んだ指先を擦り合わせる。
いつの間にか離された手は彼女が導いたのと同じ様に鍋底を恐る恐る掻き回して、放り込まれたバターは黄金色に溶けて黒い渦に飲み込まれて消える。
「しっかり練って…、ペースト状になったら牛乳を入れて…フチがふつふつしたら完成」
そうしてあっという間にマグカップ二つ分のココアが出来上がった。
暖かな湯気を立てるマグカップを両手で持って、ココアをひとくち。
今まで飲んでいたモノが偽物なのかと疑うくらい、それは暖かくて優しい味がした。
「美味しい…!」
「二郎くんには内緒だよ?」
「はい、…ところで秘密のスパイスって?」
「それはね、愛情だよ。食べる人を想ってすこーし。そうすれば何でも美味しくなるの。今度二郎くんや一郎に作ってあげなね?きっと喜ぶよ」
優しく微笑む彼女の表情が少しだけ一にいに似ていて、暫く顔を合わせていない長男の事を思った。
「いちにいは大丈夫かな…」
この雨の中どこに居るんだろう。
ちゃんと休めているだろうか、元気でいるだろうか。
僕らが子供だから嫌になってしまったのだろうか。
もう、帰ってきてはくれないのだろうか…。
「一郎ならきっとお友達のお家に泊まってるだろうから大丈夫だよ」
不安で泣き出しそうな僕の頭を暖かい手が優しく撫でる。
「きっと雨で服も靴も濡れただろうから、明日には帰ってくるはずだよ?私が保証する」
にこりと笑う彼女の姿がやけに心強くて本当に明日にはいちにいが帰ってくる様な気がした。
「それも魔法ですか?」
「ふふ、どうだろうね。ほら、早く飲まないとココア冷めちゃうよ。」
彼女は魔法使いだ。
彼女の笑顔はいちにいと同じくらい心強くて胸が暖かくなる。
彼女の言う事は必ず本当になるし、一度も外れた事は無い。
最後の一口を飲み干して、マグカップを洗っているうちに瞼が重くなるのを感じた。
「〇〇姉ありがとうございました。おかげで良く眠れそうです」
「そう、良かった」
僕の髪に微笑んだ彼女の唇が触れる。
「おやすみ、良い夢を…」
心臓がトクトクと脈を撃つ。
顔が赤くなっているのを悟られない様に少しだけ俯いて彼女におやすみをした。
「〇〇姉も、良い夢を」
その晩、夢にいちにいが出て来て僕の髪を撫でて笑っていた。
この夢も、この手の暖かさも明日の朝まで覚えていられたらいいのに。
そう思いながら僕はまた微睡みに沈んでいった。
布団に入った頃から降り出した雨。
日付が変わった今も屋根を叩く雨音はやまない。
この雨では明日の朝、家を早く出なければならないかもしれない。
足元が濡れるのも、湿度の高い教室に詰め込まれて授業を受けるのも億劫だ…
様々な不安が三郎の心を曇らせて眠りを妨げる。
( 何か飲んでからもう一度寝よう… )
スマートフォンの灯りを頼りに所々軋む冷たいフローリングの廊下を抜けて辿り着いたリビング。
電気を点けようとしたところでソファーの上で何かがもぞもぞと動いた。
それに驚いた三郎が電気を点け、いきなりの明転に驚いたのかソファーの上の何かが小さく呻く。
「ぅんん…」
「うわっ!」
「ん…眩しい…。あれ、三郎くん?」
「へ、〇〇姉?居たんですか」
「うん、雨降ってきて帰れなくなったから今日はお泊り」
毛布に包まり寝惚け眼でへらりと笑う彼女は近所に住んでいる若い女性で、幼い頃からよく三兄弟の面倒をみてくれていて三兄弟が本当の姉の様に慕う人だ。
「寝れないの?」
「ちょっと、雨の音が気になってしまって…」
「手冷たいね」
ひたり、触れた彼女の手は暖かくて少しほっとした。
ちょっと待ってて、と彼女が台所へと向かい
水場の小さな蛍光灯をつけて戸棚から小鍋を取り出した。
「何するの?」
「ん〜?」
背伸びをして戸棚の上のカゴを取り出そうとしている彼女に近付いて代わりにカゴを取ってやる。
「ありがとう、三郎くん大きくなったねぇ」
しんみりとした表情で彼女がそういうから、おばさんみたいだよと笑えば脇腹を軽く小突かれた。
「あった、あった!」
カゴの中から取り出したのは製菓に使う様な無糖のココアだった。
少し前に僕が加糖タイプと間違えて買っちゃったやつ。
使い道がわからなくて戸棚に仕舞い込んでいたものだ。
「ココアならここにあるよ?」
来客用のインスタントコーヒーや茶葉が置かれた棚から加糖タイプのココアの袋を出してみせる。すると彼女はにんまりと笑って言う。
「今晩は特別なココアを淹れてあげる」
簡単だから三郎くんも作れるよ。
そう言った彼女はココアの缶を開けてティースプーン二杯分のココアと同じ量の砂糖を小鍋に入れた。
「お水を少し、」
「お水…」
「弱火にかけて、ペースト状になるまで練る!」
「こう?」
渡された小さな泡立て器を握る僕の手に彼女の手が重なって僕を導く様に鍋底を混ぜる。
「うん、上手。そこにバターを一欠片」
「バター、ひとかけ…」
「あと、秘密のスパイス」
微笑む彼女が鍋の上で摘んだ指先を擦り合わせる。
いつの間にか離された手は彼女が導いたのと同じ様に鍋底を恐る恐る掻き回して、放り込まれたバターは黄金色に溶けて黒い渦に飲み込まれて消える。
「しっかり練って…、ペースト状になったら牛乳を入れて…フチがふつふつしたら完成」
そうしてあっという間にマグカップ二つ分のココアが出来上がった。
暖かな湯気を立てるマグカップを両手で持って、ココアをひとくち。
今まで飲んでいたモノが偽物なのかと疑うくらい、それは暖かくて優しい味がした。
「美味しい…!」
「二郎くんには内緒だよ?」
「はい、…ところで秘密のスパイスって?」
「それはね、愛情だよ。食べる人を想ってすこーし。そうすれば何でも美味しくなるの。今度二郎くんや一郎に作ってあげなね?きっと喜ぶよ」
優しく微笑む彼女の表情が少しだけ一にいに似ていて、暫く顔を合わせていない長男の事を思った。
「いちにいは大丈夫かな…」
この雨の中どこに居るんだろう。
ちゃんと休めているだろうか、元気でいるだろうか。
僕らが子供だから嫌になってしまったのだろうか。
もう、帰ってきてはくれないのだろうか…。
「一郎ならきっとお友達のお家に泊まってるだろうから大丈夫だよ」
不安で泣き出しそうな僕の頭を暖かい手が優しく撫でる。
「きっと雨で服も靴も濡れただろうから、明日には帰ってくるはずだよ?私が保証する」
にこりと笑う彼女の姿がやけに心強くて本当に明日にはいちにいが帰ってくる様な気がした。
「それも魔法ですか?」
「ふふ、どうだろうね。ほら、早く飲まないとココア冷めちゃうよ。」
彼女は魔法使いだ。
彼女の笑顔はいちにいと同じくらい心強くて胸が暖かくなる。
彼女の言う事は必ず本当になるし、一度も外れた事は無い。
最後の一口を飲み干して、マグカップを洗っているうちに瞼が重くなるのを感じた。
「〇〇姉ありがとうございました。おかげで良く眠れそうです」
「そう、良かった」
僕の髪に微笑んだ彼女の唇が触れる。
「おやすみ、良い夢を…」
心臓がトクトクと脈を撃つ。
顔が赤くなっているのを悟られない様に少しだけ俯いて彼女におやすみをした。
「〇〇姉も、良い夢を」
その晩、夢にいちにいが出て来て僕の髪を撫でて笑っていた。
この夢も、この手の暖かさも明日の朝まで覚えていられたらいいのに。
そう思いながら僕はまた微睡みに沈んでいった。