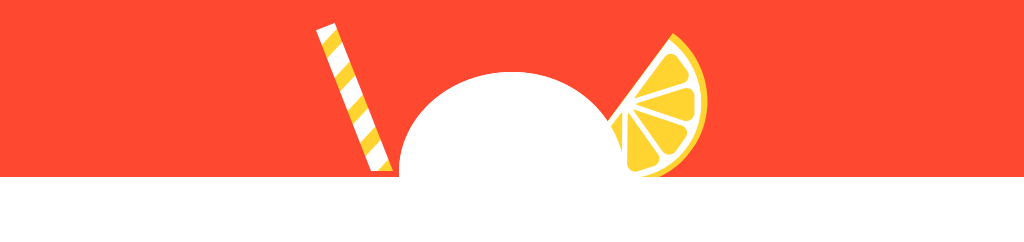2️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「じろちゃん、ごめんね」
『しょーがねぇよ』
電話越しの彼の声は優しくて思わず涙が溢れる。
彼のテスト期間や文化祭が重なって中々会うことが出来なかった私達の約1ヶ月振りのデートを前に私は風邪を引いてしまった。
とても楽しみにしていたのに…
季節の変わり目のせいか、はたまた日頃の行いのせいか…自分の体調管理の甘さにぽろぽろと涙が出る。
「久々に会えるはずだったのに…」
『また、熱が下がったらな』
「うん」
電話の向こうの彼の声が優しく私を心配してくれる。
『飯食ったか?』
「…食欲ない」
『食って薬飲まねぇと治らねえぞ?』
『俺が看病しに行こうか…?』
伺いを立てて甘えるみたいな彼の声。
垂れ目を潤ませて小首を傾げる子犬みたいな彼の姿が脳裏に浮かんだ。
「ううん、大丈夫だよ」
『…そう言うと思った。』
「ごめんね」
しょんぼりと萎んだ語尾に彼の優しさを無下にした申し訳なさを感じ、会いたい気持ちを抑えて電話越しに謝罪する。
『ゼリーとか必要そうな物、買ってドアの前に置いといたから、食えそうなら食って』
「え、」
ベッドから起き上がって玄関のドアを開けるとドアの前には近所のスーパーのビニール袋。
私の好きなゼリーとプリン。スポーツドリンクにレトルトのおかゆ。
袋の中のゼリーはまだひんやりと冷たい。
「ありがと」
『おぉ』
彼の優しさに触れて思わず涙が溢れた。
涙腺の緩さに自分の体調が優れないことを自覚して、さっきまでの強い心は何処へやら…独りぼっちの状況が急に寂しくなる。
「ねぇ、二郎。やっぱり傍に居て欲しい…」
電話口から聴こえる彼の笑い声。
『「最初っから素直にそう言えよな〜」』
彼の声が重なって聞こえる。
「二郎!なんで!?」
電話で話していたはずの彼が私の目の前に現れて、熱に浮かされて幻覚でも見ているのかと少し混乱してしまった。
「いや、お前が傍に居て♡って言うんじゃねぇかなって思って階段に座ってた…」
恥ずかしそうに笑う彼の姿を見て、嬉しさと混乱でキャパオーバーを迎えた私が泣き崩れ、慌てた彼が私を抱き抱えて部屋まで運んでくれた。
私が泣き止むまで彼はずっと「びっくりさせてごめんな」と抱き締めていてくれた。
キッチンから心地いい包丁の音。
泣き疲れて空腹を覚えた私に彼がおかゆを作ってくれた。
「ほら、出来たぞ食えるか?」
「ありがと」
鼻が詰まっていて匂いが分からないのがとても悲しかったけれど、湯気だけでも美味しいのが見て取れる。
「あーんとかしてくれるの?」
「自分で食えるだろっ」
「看病の定番じゃん」
冗談を真に受けて顔を耳まで赤くした彼が「しょうがねぇなぁ」と照れくさそうに笑う。
掬ったひと匙に息を吹きかけた彼がそれをこちらに差し出す。
ぱくりと頬張れば口に広がる、まろやかで優しいたまごの味。
「おいしい」
食欲がなかった事なんてすっかり忘れてぺろりとおかゆを平らげた。
空っぽのお皿を嬉しそうに見詰める彼。
身体の内側が暖かくて眠たくなってしまう。
「早く良くなれよ」
そう言って優しく頭を撫でてくる彼の穏やかな表情を見て、この人のこういう所がが好きだなぁと心から思った。
『しょーがねぇよ』
電話越しの彼の声は優しくて思わず涙が溢れる。
彼のテスト期間や文化祭が重なって中々会うことが出来なかった私達の約1ヶ月振りのデートを前に私は風邪を引いてしまった。
とても楽しみにしていたのに…
季節の変わり目のせいか、はたまた日頃の行いのせいか…自分の体調管理の甘さにぽろぽろと涙が出る。
「久々に会えるはずだったのに…」
『また、熱が下がったらな』
「うん」
電話の向こうの彼の声が優しく私を心配してくれる。
『飯食ったか?』
「…食欲ない」
『食って薬飲まねぇと治らねえぞ?』
『俺が看病しに行こうか…?』
伺いを立てて甘えるみたいな彼の声。
垂れ目を潤ませて小首を傾げる子犬みたいな彼の姿が脳裏に浮かんだ。
「ううん、大丈夫だよ」
『…そう言うと思った。』
「ごめんね」
しょんぼりと萎んだ語尾に彼の優しさを無下にした申し訳なさを感じ、会いたい気持ちを抑えて電話越しに謝罪する。
『ゼリーとか必要そうな物、買ってドアの前に置いといたから、食えそうなら食って』
「え、」
ベッドから起き上がって玄関のドアを開けるとドアの前には近所のスーパーのビニール袋。
私の好きなゼリーとプリン。スポーツドリンクにレトルトのおかゆ。
袋の中のゼリーはまだひんやりと冷たい。
「ありがと」
『おぉ』
彼の優しさに触れて思わず涙が溢れた。
涙腺の緩さに自分の体調が優れないことを自覚して、さっきまでの強い心は何処へやら…独りぼっちの状況が急に寂しくなる。
「ねぇ、二郎。やっぱり傍に居て欲しい…」
電話口から聴こえる彼の笑い声。
『「最初っから素直にそう言えよな〜」』
彼の声が重なって聞こえる。
「二郎!なんで!?」
電話で話していたはずの彼が私の目の前に現れて、熱に浮かされて幻覚でも見ているのかと少し混乱してしまった。
「いや、お前が傍に居て♡って言うんじゃねぇかなって思って階段に座ってた…」
恥ずかしそうに笑う彼の姿を見て、嬉しさと混乱でキャパオーバーを迎えた私が泣き崩れ、慌てた彼が私を抱き抱えて部屋まで運んでくれた。
私が泣き止むまで彼はずっと「びっくりさせてごめんな」と抱き締めていてくれた。
キッチンから心地いい包丁の音。
泣き疲れて空腹を覚えた私に彼がおかゆを作ってくれた。
「ほら、出来たぞ食えるか?」
「ありがと」
鼻が詰まっていて匂いが分からないのがとても悲しかったけれど、湯気だけでも美味しいのが見て取れる。
「あーんとかしてくれるの?」
「自分で食えるだろっ」
「看病の定番じゃん」
冗談を真に受けて顔を耳まで赤くした彼が「しょうがねぇなぁ」と照れくさそうに笑う。
掬ったひと匙に息を吹きかけた彼がそれをこちらに差し出す。
ぱくりと頬張れば口に広がる、まろやかで優しいたまごの味。
「おいしい」
食欲がなかった事なんてすっかり忘れてぺろりとおかゆを平らげた。
空っぽのお皿を嬉しそうに見詰める彼。
身体の内側が暖かくて眠たくなってしまう。
「早く良くなれよ」
そう言って優しく頭を撫でてくる彼の穏やかな表情を見て、この人のこういう所がが好きだなぁと心から思った。