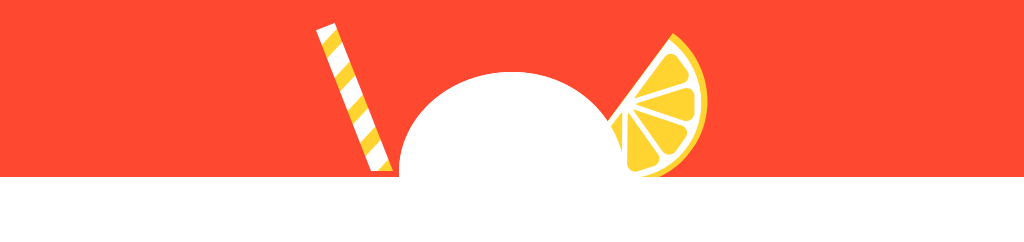1️⃣2️⃣3️⃣
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
朝早くに眠そうな顔をした彼女がふらりとやって来た。
「いちろー、おはよ」
「おぉ、どうした?」
TDD時代の古い馴染みで同業者。
俺に萬屋のいろはを教えてくれた師匠だ。
(ちなみに師匠といっても歳はそんなに離れていない。)
「また危ない事してたんじゃねーよなぁ?危ない仕事は俺に頼ってくれって言ってるだろ?」
するりと俺の横を抜けて、まるで我が家の如くソファーに座った彼女の前に麦茶を置く。
「…一郎くん、男だから出来る仕事もあるけど、女じゃなきゃ出来ない仕事もあるんだよ」
俺の問いに鋭く目を煌らせた彼女が冷たく笑う。その目の冷たさに怯みそうになりながら彼女の目を見詰める。
次の瞬間。
今までの視線が嘘のようにふぁ、と気の抜けた欠伸をしてみせる。
「いやぁ、情報の裏取るに張り込んでたらこの時間だよ」
参っちゃうよもう。なんて彼女がぼやく。
寝不足であまり頭が回っていないのだろう。喋りが少しふわふわとしている。
彼女の表情はコロコロと変わる。
まるで猫のような人だ。
俺は呆れながら冷蔵庫の中身を思い浮かべていた。
「メシ、食うか?」
「食べる」
トーストに目玉焼きとウインナー、それにサラダ。冷蔵庫の有り合わせで作った朝食を彼女は嬉しそうに食べる。
「ご馳走さまでした」
満足そうに手を合わせる彼女の瞳はさっきよりもトロンとしていて眠さが伺える。
「寝てけよ、どうせそんなんじゃ帰れないだろ?」
「うーん、食べた後に寝たら牛になっちゃうよ…」
そう言いながら着ていたパーカーを脱ぎ捨ててソファーに横になる。
直ぐにすうすうと規則正しい寝息が聞こえる。
「ったく、結局寝るんじゃねぇか…」
自室からタオルケットを持ってきてかけてやる。不健康な程白く透き通った肌。その白さを際立たせる無防備な黒のキャミソール。体はとても薄く力を込めたらすぐに折れてしまいそうだった。
「ふ、〜〜ッ!」
「魘されてる」
唯一エアコンが入るリビングに夏場は三兄弟全員が入り浸る。
彼女が眠るソファーの前にあるテーブルで宿題をしていた三郎が呟く。
「ん?嗚呼、本当だな」
彼女の額にはじんわりと汗が滲んで、眉間に皺が寄っていた。
「おい、〇〇大丈夫か?」
触れたら折れてしまいそうな肩にそっと手を置いて出来るだけ優しく揺らす。
「ん…、あれ…?」
眠りから覚めたまだ寝惚けた瞳がふわふわと辺りを見回す。
「そっか、一郎の家だ。」
「魘されてたぞ」
「うん、ごめん。大丈夫」
「そうか、」
定まった瞳は冷たい色をしていて、どこか少しだけ遠くを見ているように思えた。
「あれ、二郎くん?」
少し離れた所に居る三郎に向かってふわふわとした足取りで近づく。
「さ、三郎だッ!」
「ごめん、ごめん!え、三郎くん!?嘘!大きくなったねぇ〜!」
お姉ちゃんのこと覚えてないよね〜?前に会ったのこんな小さい時だもんね!
なんて、嬉しそうに三郎に抱きつく。
「ちょっと、離してください!!一兄笑ってないで助けて下さい!」
彼女の腕を振り解けずにいる三郎から無理矢理彼女を引き剥がす。
「ただいま〜〜」
買い出しに行っていた二郎が帰って来た。
ヤバイ。
そう思った時にはもう遅く、俺の腕からするりと抜けだして二郎の元へと駆け寄っていった。
「じろちゃん!?」
「へ?」
拍子抜けするような二郎の声。
抱き着かれた衝撃で二郎の手から買い物袋が滑り落ちる。
あれ、玉子入ってねぇよなぁ…。
「え〜〜!じろちゃん!!大きくなったねぇ!」
「ちょっ、え?!〇〇姉!?」
バランスを崩した二郎がソファーに躓いて背中から倒れた。そして彼女が二郎の上に伸し掛かる形で倒れ込む。
「俺、今汗だくだから抱きつくなって!兄ちゃん助けて!!!」
悪化する状況と恥ずかしさで耳まで真っ赤にした二郎から彼女を引き剥がす。
「こらいい加減にしろ。弟達が困ってるだろ、誰彼構わず抱きつく癖なんとかした方がいいぞ?」
「えー、だって嬉しいんだもん。」
二郎から引き剥がした細い腕がするりと俺の首にまわされる。
「一郎が大きくなったのも嬉しいよ」
あんなに意気がってた高校生がねぇ…なんてしんみりとした空気を醸し出す彼女を再び引き離して、手繰り寄せたタオルを放り投げる。
「昔話はもういいから風呂でも入って来いよ。二郎着替え出してやってくれ」
はぁい、と間延びした声が2つ廊下へと消えて行く。
溜め息を1つ吐いて、二郎が落とした買い物袋を確認する。
お一人様2パック限り本日の目玉商品が謳い文句のアイツが変わり果てた姿で顔を出す。
「二郎ォ!お前!玉子割れてるじゃねえか‼︎」
一郎の悲痛な叫びが山田家に響き渡った。
「いちろー、おはよ」
「おぉ、どうした?」
TDD時代の古い馴染みで同業者。
俺に萬屋のいろはを教えてくれた師匠だ。
(ちなみに師匠といっても歳はそんなに離れていない。)
「また危ない事してたんじゃねーよなぁ?危ない仕事は俺に頼ってくれって言ってるだろ?」
するりと俺の横を抜けて、まるで我が家の如くソファーに座った彼女の前に麦茶を置く。
「…一郎くん、男だから出来る仕事もあるけど、女じゃなきゃ出来ない仕事もあるんだよ」
俺の問いに鋭く目を煌らせた彼女が冷たく笑う。その目の冷たさに怯みそうになりながら彼女の目を見詰める。
次の瞬間。
今までの視線が嘘のようにふぁ、と気の抜けた欠伸をしてみせる。
「いやぁ、情報の裏取るに張り込んでたらこの時間だよ」
参っちゃうよもう。なんて彼女がぼやく。
寝不足であまり頭が回っていないのだろう。喋りが少しふわふわとしている。
彼女の表情はコロコロと変わる。
まるで猫のような人だ。
俺は呆れながら冷蔵庫の中身を思い浮かべていた。
「メシ、食うか?」
「食べる」
トーストに目玉焼きとウインナー、それにサラダ。冷蔵庫の有り合わせで作った朝食を彼女は嬉しそうに食べる。
「ご馳走さまでした」
満足そうに手を合わせる彼女の瞳はさっきよりもトロンとしていて眠さが伺える。
「寝てけよ、どうせそんなんじゃ帰れないだろ?」
「うーん、食べた後に寝たら牛になっちゃうよ…」
そう言いながら着ていたパーカーを脱ぎ捨ててソファーに横になる。
直ぐにすうすうと規則正しい寝息が聞こえる。
「ったく、結局寝るんじゃねぇか…」
自室からタオルケットを持ってきてかけてやる。不健康な程白く透き通った肌。その白さを際立たせる無防備な黒のキャミソール。体はとても薄く力を込めたらすぐに折れてしまいそうだった。
「ふ、〜〜ッ!」
「魘されてる」
唯一エアコンが入るリビングに夏場は三兄弟全員が入り浸る。
彼女が眠るソファーの前にあるテーブルで宿題をしていた三郎が呟く。
「ん?嗚呼、本当だな」
彼女の額にはじんわりと汗が滲んで、眉間に皺が寄っていた。
「おい、〇〇大丈夫か?」
触れたら折れてしまいそうな肩にそっと手を置いて出来るだけ優しく揺らす。
「ん…、あれ…?」
眠りから覚めたまだ寝惚けた瞳がふわふわと辺りを見回す。
「そっか、一郎の家だ。」
「魘されてたぞ」
「うん、ごめん。大丈夫」
「そうか、」
定まった瞳は冷たい色をしていて、どこか少しだけ遠くを見ているように思えた。
「あれ、二郎くん?」
少し離れた所に居る三郎に向かってふわふわとした足取りで近づく。
「さ、三郎だッ!」
「ごめん、ごめん!え、三郎くん!?嘘!大きくなったねぇ〜!」
お姉ちゃんのこと覚えてないよね〜?前に会ったのこんな小さい時だもんね!
なんて、嬉しそうに三郎に抱きつく。
「ちょっと、離してください!!一兄笑ってないで助けて下さい!」
彼女の腕を振り解けずにいる三郎から無理矢理彼女を引き剥がす。
「ただいま〜〜」
買い出しに行っていた二郎が帰って来た。
ヤバイ。
そう思った時にはもう遅く、俺の腕からするりと抜けだして二郎の元へと駆け寄っていった。
「じろちゃん!?」
「へ?」
拍子抜けするような二郎の声。
抱き着かれた衝撃で二郎の手から買い物袋が滑り落ちる。
あれ、玉子入ってねぇよなぁ…。
「え〜〜!じろちゃん!!大きくなったねぇ!」
「ちょっ、え?!〇〇姉!?」
バランスを崩した二郎がソファーに躓いて背中から倒れた。そして彼女が二郎の上に伸し掛かる形で倒れ込む。
「俺、今汗だくだから抱きつくなって!兄ちゃん助けて!!!」
悪化する状況と恥ずかしさで耳まで真っ赤にした二郎から彼女を引き剥がす。
「こらいい加減にしろ。弟達が困ってるだろ、誰彼構わず抱きつく癖なんとかした方がいいぞ?」
「えー、だって嬉しいんだもん。」
二郎から引き剥がした細い腕がするりと俺の首にまわされる。
「一郎が大きくなったのも嬉しいよ」
あんなに意気がってた高校生がねぇ…なんてしんみりとした空気を醸し出す彼女を再び引き離して、手繰り寄せたタオルを放り投げる。
「昔話はもういいから風呂でも入って来いよ。二郎着替え出してやってくれ」
はぁい、と間延びした声が2つ廊下へと消えて行く。
溜め息を1つ吐いて、二郎が落とした買い物袋を確認する。
お一人様2パック限り本日の目玉商品が謳い文句のアイツが変わり果てた姿で顔を出す。
「二郎ォ!お前!玉子割れてるじゃねえか‼︎」
一郎の悲痛な叫びが山田家に響き渡った。