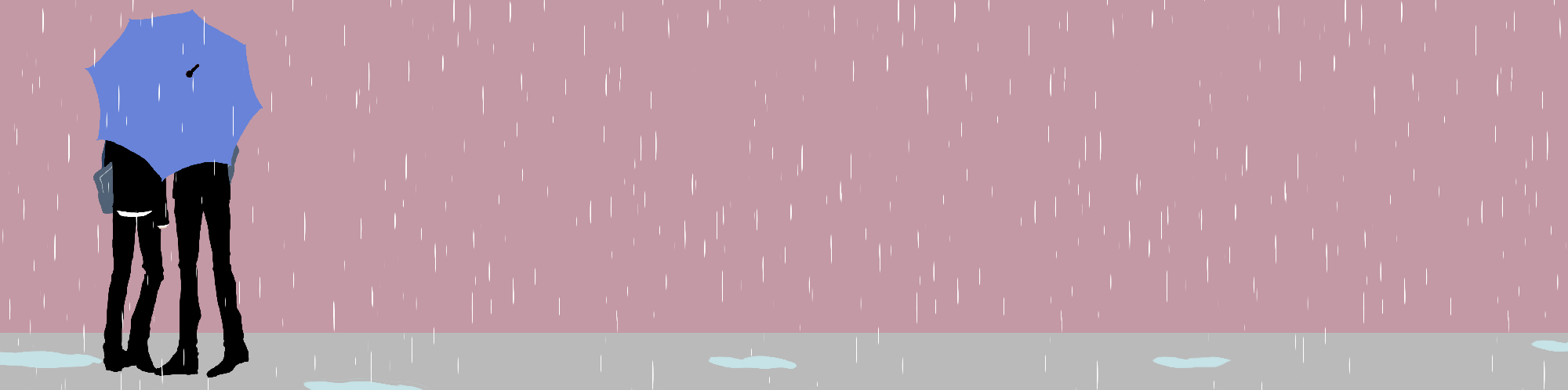『大きくなったら番になって』
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
——フロイド君が兄弟であるジェイド君と共に寮に帰ってから、早いもので数週間が経とうとしていた……
その間に彼からその日にあった事の連絡や、ジェイド君や幼馴染のアズール君とこんな事をやろうとしているけど、どう思うかなどの意見を求められたり、私の好きな物や好きな事などをメッセージアプリでやりとりする事は続いていた。あんな小さな子なのにそんな難しそうな事が出来るんだろうかと何度も思ったけれど、彼は有名な魔法士養成学校に通えるほど賢かったんだと思い直したら納得出来た。
「じゃあ、お疲れ様でした」
「ポピーちゃん、最近変な人があんたが帰る方向でうろついてるらしいから気を付けて帰るんだよ?」
「ありがとうございます」
また明日と頭を下げて店を出るとポケットからスマホを取り出し、新着のメッセージを確認すると、今日もマジカメの方に気持ちの悪いメッセージが届いていた。ここ数日同じ人からのメッセージがこうして届いており、フロイド君にも気を付けて帰ってねとは言われているのだけれど、メッセージのみで実際に出会ってない為、気を付けるのも限界があった。
「こんなに毎日送ってくるし、〝ずっと見てる〟なんて書いて来るのは気持ち悪いけど、どんな人なんだろう?」
「今日も可愛いね? ポピーちゃん」
「?! え……? 誰、ですか?」
「君がさっき〝どんな人なんだろう〟って言った人だよぉ?」
後ろからいきなり声を掛けられ驚いて振り返ると、そこには目が血走った小太りの男が立っていた。その人には見覚えがあって、ここ数日店に何度も来るお客さんの一人であった。でも、この人の対応はいつも別の店員がしており、私が対応したのは一度きりだったのに何故? と思っていると、彼の汗ばんだ手が私の手首をグッと掴んできた。
「ひっ! 何するんですか!」
「君が一人になるのをずっと待ってたのに、この道は何でか絶対人が通ってたんだよね? でも、今日は君と僕の二人きりだ。はぁ、はぁ、やっと君を僕のお嫁さんに出来る!」
「私がお嫁さん?!」
「そうだよぉ? 僕の家に行って明日二人きりで結婚式を挙げるんだ!!」
「いやっ、誰かっ!」
男の汗ばんだ手が掴んでいる手首を上下に振ってもびくともせず、ズルズルと彼の進む方へと引き摺られて行くばかりで、抵抗らしい抵抗が出来ずにいた。どうしよう。このままだと本当に素性も知れない男のモノにされてしまうと、耐えていた涙が頬を伝った瞬間、掴まれていた手首が解放され、がっしりとした体にギュッと抱き締められた。
「迎えに来たよ? クマノミちゃん♡」
「え……?」
「だ、誰だ! その子は僕のお嫁さんだぞ!」
「あ゛ぁ? この子はオレのお嫁さんなんだけど? 舐めた事言ってっと絞めんぞ?」
「ひっ……! ごめんなさぁぁあい!!」
バタバタと転がるように走って逃げていった男を呆然と見送り、へなへなとその場に座り込む。お礼を言わないとと思い、私を助けてくれた男の人を見上げて、驚きに目を見開いた。
「フ、ロイド……君?」
「うん♡ また会ったね? クマノミちゃん」
「え? ジェイド君じゃなくて、本当にフロイド君?」
「……ジェイドのが良かったの?」
「違っ、そうじゃなくて、大きくなったフロイド君にこんなに早く会えるなんて思ってなくて、ビックリしちゃって……」
「言ったじゃん、〝稚魚になる魔法薬〟飲んだって」
「あ……」
確かに彼と初めて会った時にそう言ってたのを聞いた気がする。という事は、彼の本来の姿はこっちという事になる。そっか、本当にジェイド君とよく似てる。腰が抜けて座り込んでいる私を軽々と抱き上げ、数週間前まで一緒に住んでいた家へとその長い脚を動かして歩き出した。
「クマノミちゃん、こんなにちっさくて軽かったんだね?」
「フロイド君はそんなにおっきくてカッコ良かったんだね? 稚魚の時から顔は整ってるなって思ってたけど」
「……クマノミちゃんさ? それって無自覚?」
「え? 何が?」
「はぁ~……ホントズルいよね……」
フロイド君の少しムッとした表情を首を傾げて見上げると、彼は拗ねたようにこっち見んな! と言い放ち、彼が被っていたオシャレな帽子を顔に乗せられた。年相応なその態度にクスクス笑っていると、知らない間に家に辿り着いたようで、ドアの前に下ろされた。鍵を開けてと促され、鞄から鍵を出して開錠すると、彼は私の頭に手を置くと、ポンポンと触ってクルッと向きを変えた。
「じゃ、オレは帰るね?」
「え? 帰っちゃうの?」
「……クマノミちゃん。自分が何言ってるかちゃんと分かってる?」
「え?」
彼の言わんとしている事が分からなくてキョトンとして見上げていると、はぁ……まぁ、クマノミちゃんだもんね? と一人で納得したように嘆息された。何かバカにされたような気がしてムッとしていると、彼は特に気にした様子もなく、私の耳元にツヤツヤの唇を寄せて言葉を紡いだ。
「オレを引き留めるって事は、オレに食べられても良いって事だよ?」
「食べ……? ?! なっ?! お、大人を揶揄うんじゃありません!!」
「揶揄ってなかったら良いの?」
「そんな事言ってな……んっ?!」
彼の大きな手に頬を包まれ、抵抗する間もなく重なった唇は少しひんやりとしていて、今は人間の姿だが、本来は人魚だという事を実感するには十分だった。チュッ、チュッと啄むようなキスを繰り返す彼の、薄紫のシャツの胸元を掴むと、スッとオリーブの瞳が私を映し出した。啄むようなキスなのに、すごく気持ちが良くて、もっとと誘うように薄く唇を開くと、彼は待ってましたとばかりに長い舌を差し込んできた。そのまま私の舌を迷う事無く絡め取り、吸い上げた。そのまま歯列や上顎を舐め、再び舌を絡めた所で私の足が限界を迎え、カクンと膝から崩れ落ちた。
「んっ、はぁっ……フロイド君、もぅ……」
「キスだけで腰砕けちゃったの? んふふ♡ かわいーね? クマノミちゃん」
「はぁっ、はぁっ……」
「今日はこれで帰るけど、今度同じ事したら……覚悟しといてね?」
じゃあ、おやすみ♡ すぐ鍵掛けてね? と、座り込んでいる私の額と唇にキスを落として、フロイド君は夜の闇へとユラユラと揺れるように歩きながら溶け込んでいった。ぼんやりと彼の後姿を見送っていたけれど、チラッとこちらを見たような気がし、ハッとしてすぐに扉を閉めて家の鍵を締めた。そして、そのままズルズルと座り込み、彼が触れた唇に指先で触れると、熱の篭った息が漏れた。
「あんなキス、出来るくらい色んな女の子と付き合って来たのかな……」
唇に触れながら一人呟いた言葉は、誰かに肯定も否定もされる事なく、夜の少しひんやりとした空気へと溶けた。
.