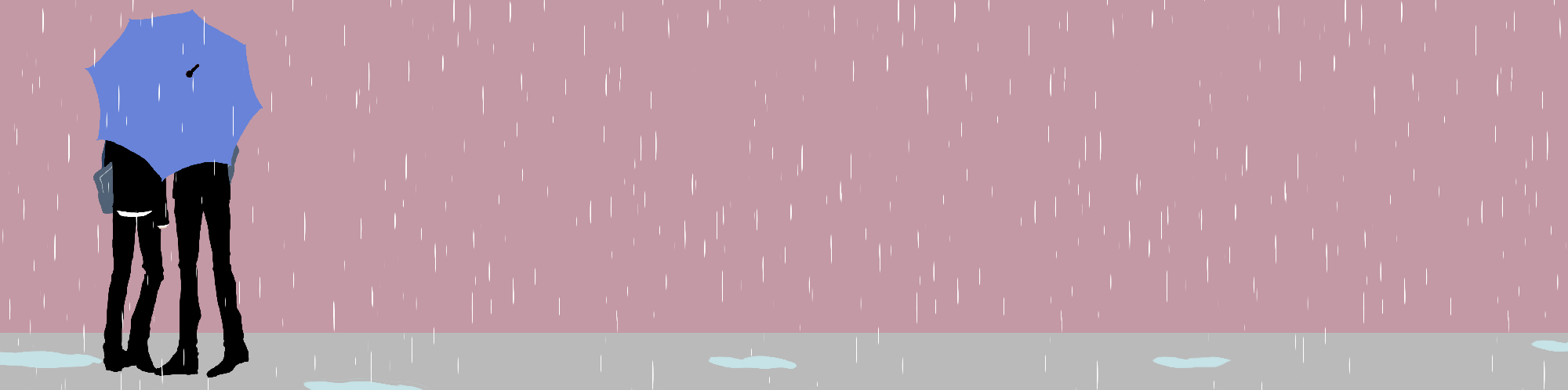『大きくなったら番になって』
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「お先に失礼しまーす!」
「あ、ポピー! 忘れもんだぜ?」
「本当だ! ありがとうギル」
「おう!」
出入り口の扉に掛かっているベルをカランカランと軽快に鳴らし、同僚から受け取った紙袋を腕に抱えて家路へと急いでいると、道端にウミネコの群れが何かを突いているのが見えた。時間帯が遅く、人通りが少ない事もありその中心にいるのが何かなんて気に留める人間はいないようだった。私もそのまま通り過ぎようとしたが、その中心から微かに小さな子供の声が聞こえた気がして、慌ててウミネコ達の群れへと駆け寄った。そこで目にしたものに驚き目を奪われた。
「に……んぎょ?」
「はぁ……はぁ……」
「このままじゃ死んじゃう!」
ぐったりとしている人魚さんを抱きかかえ、バタバタと自宅へと駆け込むと、浴槽に水を張りそこにぐったりと体を横たえたままの彼を沈めた。塩を入れると傷に沁みるんじゃないだろうかと思い、そのまま入れたけれど大丈夫だろうか? これで少しでも元気になってくれたらいいんだけどと思いながら見つめていると、水の中だからか意識が浮上したのだろう彼の閉じられていた瞳がゆっくりと開かれた。
「あ、起きた?」
「ココは?」
「ココは私の家のお風呂場」
「ふぅん? 一人暮らし?」
「うん。だから気にせずゆっくりしていいよ? あ、私はポピー。君のお名前聞いていい?」
「フロイド」
彼の傷の手当をしながら名前や何処から来たのか、どうしてウミネコの群れに囲まれていたのかなどを聞いてみたら、彼はその道では有名な魔法士養成学校に通っている生徒で、外に出てはいけないという言いつけを破って出てしまい、海を漂っている時に急に現れた大きな鳥に捕獲されたらしい。そして、運悪く路地裏に放り出されてしまい、ウミネコの群れに囲まれて今のような状態になってしまったとの事だった。
「そっか……。大変だったね? お腹は? 空いてる?」
「うん、お腹空いた」
「すぐ作るからちょっと待っててね?」
彼のターコイズブルーのサラサラとした綺麗な髪を撫でて風呂場を出ると、二人分の食事を作る為にキッチンへと立った。今日は何を作ろうかな? と冷蔵庫を開けて中身を確認する。そういえば彼は好き嫌いとかアレルギーがあったりするんだろうか? とふと思い、再び風呂場に向かうと怯えられた。
「く、クマノミちゃん、、お、オレを食べようとしてる?」
「え? 何の話?」
「だって、それ……」
「それ?」
彼の鋭い爪が指す方を見ると、どうやら私が包丁を持ったまま彼の元に来てしまったから、捌かれると思ってしまったらしい。 怖がらせるつもりがなかった事、食べようとは思ってなかった事、ただ食の好みを聞きに来ただけだった事を話して、やっと警戒を解いて貰えた。
「キノコが嫌い。オレの兄弟が毎日のように育てたキノコ食わせて来るんだよねぇ……」
「キノコはイヤか。好きな物は?」
「タコ焼き!」
「なるほど。丁度新鮮なタコ貰ったから今日はタコ料理にしようか」
「タコ焼きも入る?」
「もちろん! 少し時間かかっちゃうけど待っててね?」
じゃあ作って来るね? と彼に背を向けるとキッチンへと立ち、手早く数種類の料理を作ると、彼のいる浴室へと運び皿を差し出した。彼が一番食べたがっていたタコ焼きを作って運ぶと、やっぱりそれが一番最初に無くなった。それを目の当たりにして本当に好きなんだろうなと思わず笑みが零れた。
「おなかいっぱ~い♡」
「満足した?」
「うん!」
「なら、今日はもう歯磨きして寝ようね?」
あーんと口を開けた彼の鋭い歯を歯ブラシで丁寧に磨いてやると、おやすみと電気を消そうとしたのだが、彼にお風呂入らなくていいの? と問われてしまった。入りたいけれど、彼に見られながら入るのは嫁入り前の身としては恥ずかしくて、勇気がなかった。
「じゃあ、クマノミちゃんが入ってる間、シャワーカーテンするし見ないから入ったら?」
「……絶対?」
「絶対」
「分かった……じゃあ用意して来るからシャワーカーテン閉めて寝てて」
絶対見ないでね? と念を押して部屋へと戻ると、入浴準備をして浴室へと足を踏み入れた。いくら稚魚と言えども相手は男の子なのだから、羞恥心というものがあるのは普通だと思う。フェイスタオルで前を隠しながら入り、シャワーのコックを捻る。手で湯加減を調節し、丁度いい温度になったのを確認して洗顔に手を伸ばした。丁寧にメイクを落とすと髪を洗い、そのまま体を洗った。一通り洗い終わって体に纏った泡を流し、ふぅと息を吐くと、バスタオルを体に巻き付けて浴室を後にした。その際チラッと彼がいる浴槽を見たが、約束通り見ないようにしてくれたようで目が合うなんて事はなかった。
「おやすみ、フロイド君」
彼からの返事はなかったけれど、それが眠っている証だと思い、パチッと浴室の電気を消してキッチンで水分補給をすると、今日はリビングのソファーで就寝した。部屋だと夜中に彼に何かあって、呼ばれても聞こえないからという心配もあったからだけど。特に何もないまま穏やかに朝を迎えた。
.
1/8ページ