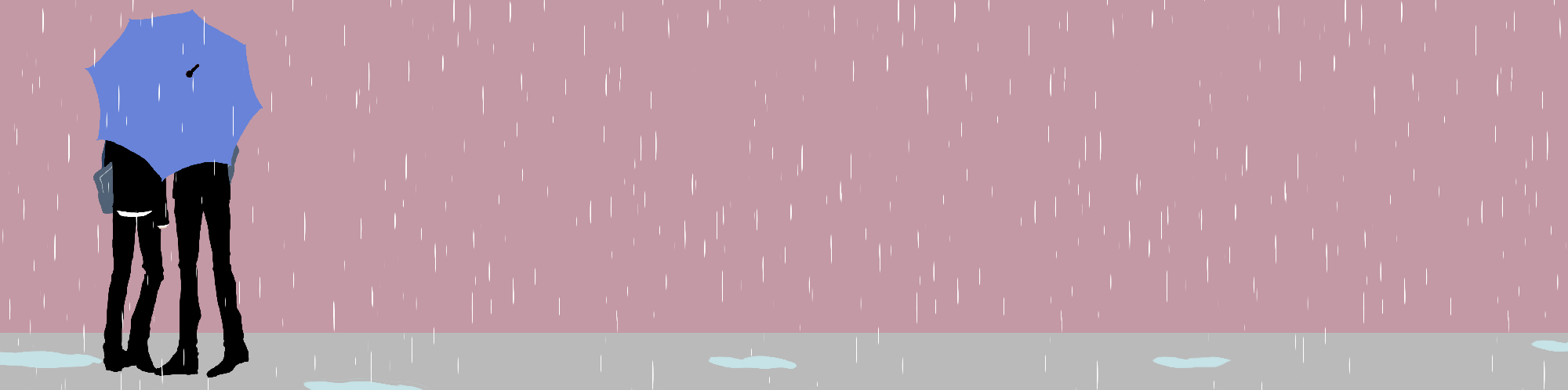『傷跡』
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
その日の飛行術は合同授業で、バルガス先生の指導のもと行われていたのだが、いつもの通り上手く飛べない者が数名。その筆頭はオクタヴィネル寮寮長のアズールと、副寮長であるジェイドだった。ジェイドの片割れのフロイドは、調子がいい時は誰よりも高い遥か上空まで飛んでいるのに、えらい違いだと思いながら順番が来るのを待っていると、彼女の名前が呼ばれた。
「次、アザレア・バーガンディー]
「はい」
綺麗な濃いめのピンクの髪を一つに結んでいる彼女はアザレア・バーガンディー。この学園にいる女子二人の内の一人である。もう一人は一年生にいる監督生だ。そんな彼女だが、成績優秀、容姿端麗、という事もあり、飛行術も難なく飛んで見せた。バルガス先生はそんな彼女を褒めると、次! と、次の生徒の名前を読み上げた。
「どうして同じ人魚なのにあなたはそんな簡単に飛んでしまうんですか?」
「うーん……この間教えた感覚で飛んでもらうのが一番早いと思うんだけど……」
「それが出来たらこんな無様な姿をあなたに見せていないんですよ……」
「ふふふ。私はそういう出来ない事を頑張ってるジェイドの姿、好きよ?」
目の前で繰り広げられる砂を吐きそうな甘さの会話にげんなりしていると、俺の番が来た。ここで少しでもアザレアちゃんにいいところを見せたい! そう思って頑張って上空まで飛び、彼女は⁈ と見下ろすと、全くこちらを見ていなかった。
「ジェイド、頑張って!」
「はぁ……」
「リーチ、いつでも飛んでいいぞ?」
「……いきます」
彼女が見守る中で飛んだジェイドは、案の定いつも通りの位置までしか上がらず、補習を言い渡されていた。そんな彼に、私も付き合うからと声を掛けている彼女を見て、優しいなと思うと同時に何で飛べない魚にそこまで入れ込むんだという気持ちが湧いた。
「あ、でも今日はラウンジがあるんじゃなかった?」
「アズールも補習なのでその点は大丈夫だと思います」
「そっか! なら大丈夫だね?」
彼女によく頑張りましたとその綺麗な手で撫でられているのを見ると、少し……いや、かなり羨ましかった。ジェイド達と彼女は同郷の出らしい。そういう繋がりもあって特に仲が良いようだが、彼女が誰かと付き合っているという話は聞いていないので、今ならまだ恋人の枠に収まれるかもしれない。そう思い、今度彼女が一人の時に声を掛けてみようと決めると同時に、授業終了の鐘が鳴った。
——あの日から数日が経ったある日……
「そこまで! 解答用紙を後ろから前に回せ」
その日のクルーウェル先生の授業の最後に小テストがあった。運よく彼女の後ろに座れた俺が前にいる彼女に解答用紙を回そうとしたら、彼女の隣にいたジェイドに回しますね? と取られた。俺が何か言う前にもう手元から用紙は無くなっていたし、今更抗議したところでジェイドの奴に何か? と、にっこりと綺麗に笑って聞かれるのがオチだと思い、俺は溜息を吐くだけで済ませた。
「アザレア、後ろの彼からの解答用紙です」
「あ、ジェイドありがとう。テスト出来た?」
「えぇ。アザレアは出来ましたか?」
「自信はないけど大丈夫だと思う」
「昨日ちゃんと“ベンキョウ”したんですから大丈夫では?」
「あ、あれは“勉強”って言わないの‼」
白く滑らかな頬を真っ赤に染めてジェイドを睨み付ける彼女を、クスクスと笑って見下ろし、彼女のフェイスラインに沿うように垂らしている綺麗な髪に手を伸ばし、一束掬い上げるとそのままチュッとそこに口付けた。クソ、顔が良いやつは何しても様になりやがる。
「あの勉強法ではお気に召しませんでした?」
「当たり前でしょ⁈ 次したら嫌いになるから」
「おやおや、昨日はあんなに……むぐっ」
「それ以上言ったら本気で怒るよ?」
ムッとした表情を浮かべた彼女に、これ以上は本当にダメだと察したらしいジェイドが、分かりましたと告げ、損ねてしまった彼女の機嫌を取るべくあれやこれやと提案を出すも、No! と首を振られ続けていた。その様子にざまぁみろと思っていたが、ジェイドに耳元で何かを言われたらしい彼女は、彼を驚いた表情で見つめた後、さっきまでの不機嫌さを感じさせないような満面の笑みで頷いていた。ジェイドは何を言ったんだろうか。直すのが難しそうだった彼女の機嫌をあそこまで回復させるなんて、よっぽどの事を提示したんだろうか? ジェイドが何を言ったのか皆目見当も付かなくて首を傾げていると、ジェイドと目が合った気がした。
「度々うるさくしてしまい申し訳ありません」
「え?」
「え? うるさかった? ごめんね? すぐどっか行くから」
「あ、いや、別に……」
俺の言葉を聞く前に彼女はジェイドの腕を掴んで立たせ、今日のお昼ご飯はみんなで食べよう? と誘っていた。そのみんなというのはきっとジェイドを含めたオクタヴィネルの三人だろうと思っていたら、メンバーはそれだけじゃなかった。他の奴とも食べるなら俺も彼女と一緒に食べたい。
「今日は監督生ちゃんとそのお友達も一緒だよ? みんなの分とは別に、ジェイドの分もいっぱい作ったから遠慮なく食べてね?」
「ふふふ。それは楽しみです」
ジェイドの隣に立ち、彼と話しながら歩く彼女の腰をジェイドが支えるようにして教室から出て行った姿を見て、もしかして彼女はジェイドの? という考えが頭を過ったが、彼女が誰かと付き合っているという話を自分の耳で聞いていない俺は、違うと頭を振ってその考えを否定した。
——その日の放課後、以前バルガス先生に補習を言い渡されていたアズールとジェイドとその他数名の生徒とそこに運動着姿の彼女の姿もいた。彼女はバルガス先生側に立っていたので、恐らく飛行術の見本としてだろう。本当に補習に付き合ってあげている姿を見て、監督生に負けず劣らずのお人好し具合だなと思っていると、バルガス先生の指示のもと箒に横座りした彼女の小さな体がふわりと浮いた。
「よーし! それじゃあ、バーガンディーの飛び方を見本にして順番に飛んでみろ!」
「ジェイド、頑張って」
「……はい」
渋々というように箒に跨り、集中して少しずつ浮上していき、木の一番低い枝の辺りまで浮上すると、バルガス先生の合格の言葉を貰っていた。ジェイドの合格の言葉を聞き、良かったね! と彼に抱き付きながら喜ぶ彼女の髪を撫で、こちらに視線を向けたジェイドと再び目が合った。何だろうかと彼の口元を見ていると、その薄く綺麗な唇がゆっくりと開き、こちらに向かって何かを話しているような気がしてジッと目を凝らす。
「えっと……『アザレアは僕のです。……僕のです⁈』」
ジェイドの唇の動きを見つつ一言ずつ声に出していくと、まさかの言葉になった。アザレアちゃんがアイツの? でも、彼女がそれを否定も肯定もしていないので、彼女が戻ってきたら思い切って告白する事にした。
のだが、その彼女が一向に戻ってこない。補習もとっくに終わっているので違う道で寮へと戻ってしまったのかもしれないと、彼女達が所属するオクタヴィネルへと向かっていると、その途中の廊下でひそひそと話す声が耳に届いた。誰の声だろうかと耳を澄ませると、それは俺が探していた彼女の声とその彼女の近くに常にいるジェイドのものだった。一体何をしているんだろうとチラッと覗いた事を俺は心底後悔した。
「あっ、ジェイド! こんな所でシなくてもっ、ンッ!」
「そう言いながらも気持ち良さそうですよ?」
「あっ、あっ、バカッ、んんっ……」
彼女のTシャツを着た小さな背中を廊下の壁に預けさせ、つなぎを脱がせた事で現れた、白く滑らかな両足を腕に掛けた所謂駅弁スタイルで彼女を攻めているジェイドの姿がそこにあった。
「あっ、ジェイドッ、私もうっ……」
「えぇ、僕も限界なのでいいですよ?」
「んっ、あっあっ、ダメッ、ソコやっ、んんんー‼」
「ッ、くっ……!」
「(……クソッ!)」
二人の荒い息遣いと、衣服を整えているのだろう布擦れの音に耐え切れなくなった俺は、告白する前に破れた淡い恋と共に静かにその場を後にした。
「クスッ、少し可哀想な事をしましたかね?」
「何の話?」
「何でもありませんよ? 歩けますか?」
「足がガクガクするから無理。抱っこ」
「仰せのままに」
ジェイドに向かって細い腕を伸ばし、抱っこしろと強請った彼女を嬉しそうにその長い腕に抱き上げ、ジェイドは自寮であるオクタヴィネルへと彼女を腕に収めたまま歩き出した。
衝撃の失恋から数日後、不運にもまたジェイドと合同授業になってしまった。気が重いまま着替えていたら、スラッとした白い背中が視界に入り、ジッとそれを見ていると、その背中に目立つ赤い複数の線と首から肩へと続く位置に赤い痕。まさか……?
「ジェイドぉ、それってアカネハナゴイちゃんの?」
「あぁ、そうなんです。昨日少し激しくし過ぎてしまったようで……」
「痛くねぇの?」
「そうですね? 痛みはあまりありませんし、これのお陰で昨夜の可愛く色っぽい彼女の姿がすぐに思い出せるので♡」
「はぁ……バカな話をしていないで行きますよ?」
「「はぁい♡/はい」」
先頭を歩くアズールに付いて行くように出て行ったのを見送っていると、俺の想いを知っていたクラスメイトに肩をポンと叩かれ、ジェイドが番じゃ勝ち目ないよな? と、憐れまれた。え? 今なんて?
「え? 番……? いつから⁈」
「え? アザレアちゃんはここに入る前からアイツの番だぜ?」
「てことは……最初から俺には望みがなかったって事?」
「頑張ってるお前見てたら言えなくてな? 悪い……」
「はぁ……」
彼に慰められながら俺達も更衣室を後にしたのだった。
fin.
「次、アザレア・バーガンディー]
「はい」
綺麗な濃いめのピンクの髪を一つに結んでいる彼女はアザレア・バーガンディー。この学園にいる女子二人の内の一人である。もう一人は一年生にいる監督生だ。そんな彼女だが、成績優秀、容姿端麗、という事もあり、飛行術も難なく飛んで見せた。バルガス先生はそんな彼女を褒めると、次! と、次の生徒の名前を読み上げた。
「どうして同じ人魚なのにあなたはそんな簡単に飛んでしまうんですか?」
「うーん……この間教えた感覚で飛んでもらうのが一番早いと思うんだけど……」
「それが出来たらこんな無様な姿をあなたに見せていないんですよ……」
「ふふふ。私はそういう出来ない事を頑張ってるジェイドの姿、好きよ?」
目の前で繰り広げられる砂を吐きそうな甘さの会話にげんなりしていると、俺の番が来た。ここで少しでもアザレアちゃんにいいところを見せたい! そう思って頑張って上空まで飛び、彼女は⁈ と見下ろすと、全くこちらを見ていなかった。
「ジェイド、頑張って!」
「はぁ……」
「リーチ、いつでも飛んでいいぞ?」
「……いきます」
彼女が見守る中で飛んだジェイドは、案の定いつも通りの位置までしか上がらず、補習を言い渡されていた。そんな彼に、私も付き合うからと声を掛けている彼女を見て、優しいなと思うと同時に何で飛べない魚にそこまで入れ込むんだという気持ちが湧いた。
「あ、でも今日はラウンジがあるんじゃなかった?」
「アズールも補習なのでその点は大丈夫だと思います」
「そっか! なら大丈夫だね?」
彼女によく頑張りましたとその綺麗な手で撫でられているのを見ると、少し……いや、かなり羨ましかった。ジェイド達と彼女は同郷の出らしい。そういう繋がりもあって特に仲が良いようだが、彼女が誰かと付き合っているという話は聞いていないので、今ならまだ恋人の枠に収まれるかもしれない。そう思い、今度彼女が一人の時に声を掛けてみようと決めると同時に、授業終了の鐘が鳴った。
——あの日から数日が経ったある日……
「そこまで! 解答用紙を後ろから前に回せ」
その日のクルーウェル先生の授業の最後に小テストがあった。運よく彼女の後ろに座れた俺が前にいる彼女に解答用紙を回そうとしたら、彼女の隣にいたジェイドに回しますね? と取られた。俺が何か言う前にもう手元から用紙は無くなっていたし、今更抗議したところでジェイドの奴に何か? と、にっこりと綺麗に笑って聞かれるのがオチだと思い、俺は溜息を吐くだけで済ませた。
「アザレア、後ろの彼からの解答用紙です」
「あ、ジェイドありがとう。テスト出来た?」
「えぇ。アザレアは出来ましたか?」
「自信はないけど大丈夫だと思う」
「昨日ちゃんと“ベンキョウ”したんですから大丈夫では?」
「あ、あれは“勉強”って言わないの‼」
白く滑らかな頬を真っ赤に染めてジェイドを睨み付ける彼女を、クスクスと笑って見下ろし、彼女のフェイスラインに沿うように垂らしている綺麗な髪に手を伸ばし、一束掬い上げるとそのままチュッとそこに口付けた。クソ、顔が良いやつは何しても様になりやがる。
「あの勉強法ではお気に召しませんでした?」
「当たり前でしょ⁈ 次したら嫌いになるから」
「おやおや、昨日はあんなに……むぐっ」
「それ以上言ったら本気で怒るよ?」
ムッとした表情を浮かべた彼女に、これ以上は本当にダメだと察したらしいジェイドが、分かりましたと告げ、損ねてしまった彼女の機嫌を取るべくあれやこれやと提案を出すも、No! と首を振られ続けていた。その様子にざまぁみろと思っていたが、ジェイドに耳元で何かを言われたらしい彼女は、彼を驚いた表情で見つめた後、さっきまでの不機嫌さを感じさせないような満面の笑みで頷いていた。ジェイドは何を言ったんだろうか。直すのが難しそうだった彼女の機嫌をあそこまで回復させるなんて、よっぽどの事を提示したんだろうか? ジェイドが何を言ったのか皆目見当も付かなくて首を傾げていると、ジェイドと目が合った気がした。
「度々うるさくしてしまい申し訳ありません」
「え?」
「え? うるさかった? ごめんね? すぐどっか行くから」
「あ、いや、別に……」
俺の言葉を聞く前に彼女はジェイドの腕を掴んで立たせ、今日のお昼ご飯はみんなで食べよう? と誘っていた。そのみんなというのはきっとジェイドを含めたオクタヴィネルの三人だろうと思っていたら、メンバーはそれだけじゃなかった。他の奴とも食べるなら俺も彼女と一緒に食べたい。
「今日は監督生ちゃんとそのお友達も一緒だよ? みんなの分とは別に、ジェイドの分もいっぱい作ったから遠慮なく食べてね?」
「ふふふ。それは楽しみです」
ジェイドの隣に立ち、彼と話しながら歩く彼女の腰をジェイドが支えるようにして教室から出て行った姿を見て、もしかして彼女はジェイドの? という考えが頭を過ったが、彼女が誰かと付き合っているという話を自分の耳で聞いていない俺は、違うと頭を振ってその考えを否定した。
——その日の放課後、以前バルガス先生に補習を言い渡されていたアズールとジェイドとその他数名の生徒とそこに運動着姿の彼女の姿もいた。彼女はバルガス先生側に立っていたので、恐らく飛行術の見本としてだろう。本当に補習に付き合ってあげている姿を見て、監督生に負けず劣らずのお人好し具合だなと思っていると、バルガス先生の指示のもと箒に横座りした彼女の小さな体がふわりと浮いた。
「よーし! それじゃあ、バーガンディーの飛び方を見本にして順番に飛んでみろ!」
「ジェイド、頑張って」
「……はい」
渋々というように箒に跨り、集中して少しずつ浮上していき、木の一番低い枝の辺りまで浮上すると、バルガス先生の合格の言葉を貰っていた。ジェイドの合格の言葉を聞き、良かったね! と彼に抱き付きながら喜ぶ彼女の髪を撫で、こちらに視線を向けたジェイドと再び目が合った。何だろうかと彼の口元を見ていると、その薄く綺麗な唇がゆっくりと開き、こちらに向かって何かを話しているような気がしてジッと目を凝らす。
「えっと……『アザレアは僕のです。……僕のです⁈』」
ジェイドの唇の動きを見つつ一言ずつ声に出していくと、まさかの言葉になった。アザレアちゃんがアイツの? でも、彼女がそれを否定も肯定もしていないので、彼女が戻ってきたら思い切って告白する事にした。
のだが、その彼女が一向に戻ってこない。補習もとっくに終わっているので違う道で寮へと戻ってしまったのかもしれないと、彼女達が所属するオクタヴィネルへと向かっていると、その途中の廊下でひそひそと話す声が耳に届いた。誰の声だろうかと耳を澄ませると、それは俺が探していた彼女の声とその彼女の近くに常にいるジェイドのものだった。一体何をしているんだろうとチラッと覗いた事を俺は心底後悔した。
「あっ、ジェイド! こんな所でシなくてもっ、ンッ!」
「そう言いながらも気持ち良さそうですよ?」
「あっ、あっ、バカッ、んんっ……」
彼女のTシャツを着た小さな背中を廊下の壁に預けさせ、つなぎを脱がせた事で現れた、白く滑らかな両足を腕に掛けた所謂駅弁スタイルで彼女を攻めているジェイドの姿がそこにあった。
「あっ、ジェイドッ、私もうっ……」
「えぇ、僕も限界なのでいいですよ?」
「んっ、あっあっ、ダメッ、ソコやっ、んんんー‼」
「ッ、くっ……!」
「(……クソッ!)」
二人の荒い息遣いと、衣服を整えているのだろう布擦れの音に耐え切れなくなった俺は、告白する前に破れた淡い恋と共に静かにその場を後にした。
「クスッ、少し可哀想な事をしましたかね?」
「何の話?」
「何でもありませんよ? 歩けますか?」
「足がガクガクするから無理。抱っこ」
「仰せのままに」
ジェイドに向かって細い腕を伸ばし、抱っこしろと強請った彼女を嬉しそうにその長い腕に抱き上げ、ジェイドは自寮であるオクタヴィネルへと彼女を腕に収めたまま歩き出した。
衝撃の失恋から数日後、不運にもまたジェイドと合同授業になってしまった。気が重いまま着替えていたら、スラッとした白い背中が視界に入り、ジッとそれを見ていると、その背中に目立つ赤い複数の線と首から肩へと続く位置に赤い痕。まさか……?
「ジェイドぉ、それってアカネハナゴイちゃんの?」
「あぁ、そうなんです。昨日少し激しくし過ぎてしまったようで……」
「痛くねぇの?」
「そうですね? 痛みはあまりありませんし、これのお陰で昨夜の可愛く色っぽい彼女の姿がすぐに思い出せるので♡」
「はぁ……バカな話をしていないで行きますよ?」
「「はぁい♡/はい」」
先頭を歩くアズールに付いて行くように出て行ったのを見送っていると、俺の想いを知っていたクラスメイトに肩をポンと叩かれ、ジェイドが番じゃ勝ち目ないよな? と、憐れまれた。え? 今なんて?
「え? 番……? いつから⁈」
「え? アザレアちゃんはここに入る前からアイツの番だぜ?」
「てことは……最初から俺には望みがなかったって事?」
「頑張ってるお前見てたら言えなくてな? 悪い……」
「はぁ……」
彼に慰められながら俺達も更衣室を後にしたのだった。
fin.
1/1ページ