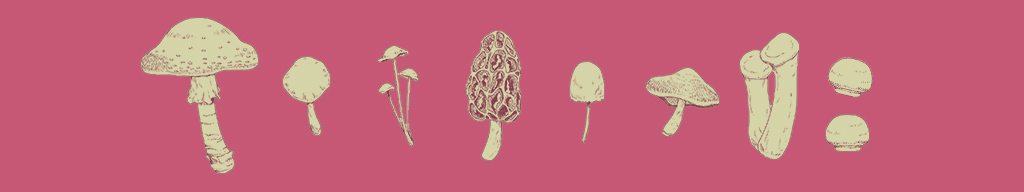さびしい
夕日が朦朧と揺らぎながら、咽返る湿度は僕を包み込んでいる。
空っぽの躰はとうに干上がって、誰か水をくれないか。
遠くの警報音に、膿んだ傷をかき混ぜながら。
歩く、歩く。
---
下駄箱には、僕一人。
しばらくの間、他の生徒も、先生も誰も居なかったけれど。遠くから話し声が近づいてきたので、僕は素早く靴を履き替え、校舎を後にした。
裏門に向かう途中、中庭から校舎を見上げれば、教室では生徒達が工作をしていた。
とある男子生徒がこちらに気が付き、怪訝そうに様子を伺っていたが、僕はフイと目を逸らし、そのまま振り返ることは無かった。
校舎を出てすぐ、学校に隣接している幼稚園の脇を通り過ぎる。
僕の通う小学校には、この幼稚園出身の生徒も多いのだが、僕の通学圏から外れたここは、縁もゆかりも無い場所だった。
当然、中の様子にも興味は無かったが、甲高いはしゃぎ声が聞こえてきたので、まだ子供が残っているのだろうな、とだけ思った。
簡素な住宅が並ぶ風景を、薄らぼんやりと眺めながら、僕は歩みを進めた。
相当な年季が入った住宅の庭には、幾つかの盆栽が置かれていた。
丁寧に切り揃えられた枝には、持ち主の生真面目さが映し出されていた。
この辺りにしては、比較的小奇麗な住宅の縁側では、よく肥えた三毛猫が溶けていた。
無理もない、この暑さだ。
同情の眼差しを向けていると、ふいにそれが交わり、僕は思わず足を留めた。
お前は、誰を映しているんだ?
やがて、部屋の奥から洗濯物を持った女が現れた。
もう僕のことなんか気にも留めず、猫は嬉しそうに女の元へ駆け寄っていった。
余計なお世話だったな。
僕は目を逸らし、再び歩き出した
しばらくの間、女の怪訝そうな視線が、背中にチクチクと刺さっていた。
住宅、住宅……。
「子ども110番の家」と書かれたプレートが印象的な、とある住宅が目に留まった。
馴染み深いこのプレートは、僕のアパートの玄関にも貼られているものだ。
子供を守るボランティア活動の一環であり、日中も誰かしらが在宅しているという印でもある。
子供好きの高齢者が住む家か、はたまた子持ちの専業主婦が住む家か。
もし住人が後者であれば、きっと、母は子の帰宅を待ち望んでいるのだろう。
子供が事件や事故に巻き込まれず、自分の元へと帰ってくることを望みながら、一人過ごしてるのだろう。
いやもしかしたら、この家の子供は、とっくに帰宅しているのかもしれない。
代わり映えのしない「おかえり」と「ただいま」。
勉強を頑張った、友達と仲良く遊んだ、先生に褒められた、でも午後の授業はちょっとだけ寝てしまった。
母は、喜んで聞いてくれるだろう。 *ここ削る?
ドアの向こう側、日々の営みを想像した。
黒板を淡く引っ搔いたかのような不快感に、僕はもう住宅を眺めるのはやめた。
この道は田園に続いており、脇には用水路が流れている。
人々の営みを乗せた水は稲を育み、やがて、どんな形で結実するのだろうか。
気が付けば、ぬるい風が吹いていた。
気温に反した冷めたい汗が、頬を伝う。
カン、カン、カン……。
風に乗ってきたのだろうか。
何処かで、遠い遮断機の音が響いた。
気がした。
---
「つかれたー」
間の抜けた声で我に帰り、隣に目を向けると、化け物が渋い表情を浮かべていた。
眉間に皺を寄せているが、口は逆三角の半開きでどうにも威厳に欠ける。
マジックペンでも書けそうな雑さだな、と思った。
「かわいたー」
化け物は意味もなく、くねくねと全身を揺らし、僕と並び歩く。
「水なら無いよ」
「うるおいは?」
「無いから期待するな」
その対応が無慈悲だと思ったのか、単に水分補給が出来ない事に落胆したのか。
化け物は露骨に肩を落とし(と表現をしたものの、おそらくこいつに肩は無い)、こちらを非難してのけた。
「ひどいー」
蝉はやかましく鳴き続けている。
---
*このパートは特に悩み中
僕は化け物と歩き続けた。
そんなに時間は経過していない。
住宅の数が減ると同時に、視界には一気に田園が広がった。
この開けた世界と、僕の意識の境目は、ひどく曖昧だった。
何処にだって駆け出せるのに、決して何処に行く事も叶わない。
勿論、そんな事は全く無く。
雑草や小石は多いけど、田んぼの間にはちゃんと歩ける道がある
そこを真っ直ぐに歩く
化け物が周辺をきょろきょろ見ている
「田んぼを区切ってる、細い方の道は歩くなよ。お前落ちそうだから」
「どぼーん」
「するな」
↓入れるか悩み中
カン、カン、カン……。
「なんか、ずっと踏切が鳴ってないか?」
「えー。せみ、だよ」
息を吸うように嘘を吐くな、というツッコミは心の中に留め、
警報が鳴っているなら渡れない
---
「かわいたー」
化け物がTシャツの裾を引っ張り、歩みを静止させる。
グッと力を溜めるようにしゃがんだ後、立ち上がりながら躰をくねくねさせる。
子供番組の体操か何かだろうか
「うる、おい」
「お前、またそれか……」
こんな下らない事で、ただでさえよれているTシャツの皺を増やさないで欲しい
化け物は意味もなく、くねくねと全身を揺らしている
チラチラと僕のほうを見てくる化け物
どうやら、僕に対して水を求めているらしい
田圃の水を飲むと言い出さないだけまだマシだけど、もし言い出したらどうしよう……という不安を抱きながら、化け物に話しかける
「お前は僕に期待しているのだろうけど、残念ながら水は持ってない。
水筒を学校に忘れてしまったから。
でも、仮に僕が水を持っていたとしても、それに期待してはならないよ。」
必要だと思うなら、他人の施しに期待をせず、用意をしておくべき。
こんな炎天下に水を持ってこないのは、お前の怠慢。
水筒を忘れた僕が、道中で干上がったとしても、それも僕の怠慢。
化け物はいまいち理解していないようで、「んー」と首を傾げている。
「あめ、ふればいいのにー」
「その考えは駄目だよ。空模様は変わってはくれない。
何かを求めないこと。自分が落胆するだけだから」
「わー。おっとなー」
「いや……」
その言葉に僕は一瞬口を開きかけたが、すぐに飲み込んだ。
これ以上の言葉は自己満足だから。
けれど化け物が興味深そうに、真っ直ぐに瞳を覗き込んでくる。
結局続きを言うことにした。
「僕の考えが大人だっていうなら、それは違う
なぜなら、大人も子供も、本質は変わらないからだ」
「他者と触れ合い接する時、どんな人間も相手に自分を映し出している
他人は『自分の鏡』を相手に求めているんだ」
*「他人の鏡」の例になるような事柄
『鏡の心は何処へ行く?』
『誰も僕を見てくれはしない。誰も、誰も……。』
何故だかわからないけれど、妙に感情的な言葉が出かけたので、慌てて自制した
きっと、この言葉は何処にも届かず、僕の中にだけ響いていた
「雨ね。かつては、僕も望んでいたよ。けどもうやめた
結局は、自分が変わるしかないから」
化け物を見据えて一言
「だからお前も、勿論僕だってそうするんだ」
「さびしーい」
間の抜けた喋り方で、考える人のような仕草をする化け物
けれど珍しく、感慨深そうに頷いてみせた。
---
青い稲が生い茂る田んぼ道を僕と化け物で歩き続ける
もしかしたら、上は綺麗でも、根腐れしているのではないか
色々な思いの混ざったそれは、もはや汚水でしかなく
ずぶずぶに浸って、そして……
「ふふん、ふふんふん」
化け物の鼻歌で我に帰った
僕達の行動自体は何も変わらないのに、何故か上機嫌に見えた
口はアヒルのような曲線を描いている。
「水はもういいのか?」
「いる。でも、うるおった」
全身をくねくねと揺らし歩く
謎の動きは水の流れを表現しているのかも、と気が付いた
僕はわざと化け物より遅く歩き、化け物の斜め後ろを陣取る
コソコソとランドセルのポケットの奥底を漁る
幸い、化け物は気が付いていないようだった
500円玉が出てきた
学校への金銭の持ち込みは禁止されているけど、非常時のためにこっそり持ち歩いていたもの
ちゃんと入っていて良かった
これで缶ジュースか何かでも買ってやろうと思った
僕は現実主義なだけで、無慈悲な人間ではないのだ
変に期待を持たせても良くないから、自販機が見つかるまで黙っていることにした
僕達は歩みを止めない
やがて田んぼ道は終わりを告げ、歩きやすく舗装された道に出た
*地獄への道は善意で舗装されている
奇妙なまでに、道は何処までも真っ直ぐに続いていた
---
真っ直ぐな道
暑さでアスファルトが揺らめく
道の終わりが見えない
僕達はどれだけの間歩き続けていたのだろう。
炎天下の中歩き続けていたので、黒いランドセルの表面は熱を持っている
こういう時、違う色を買って欲しかったのになと強く思うが、こんな感情は意味のないものだと一蹴
ため息交じりに呟く
「……つかれた」
「つかれた!」
呟いた途端、化け物がぬるりと勢いよく動き、僕の顔を覗き込んできた。
その目はキラキラに輝いていた。
僕は思わずたじろぎ、立ち止まる。
「やっぱり、なかま」
何を言っているんだ、こいつは
僕にはこんな奇妙な存在との共通点は無い
「ねー、なんであるくの」
「なんでって、家に帰るためだろ」
「いえ?いきたいー。いく」
「いや来るな。って、いきなり走るなよ!?」
化け物は勢いよく一本道を駆け出す
僕からゆるやかに遠ざかっていく
しかし化け物の動きは非常にのろく、全力疾走だと思われるそれは
僕の早歩きとあまり変わらない
少し離れた地点で、べちゃりとすっ転ぶ
地面にうつ伏せになっている
「あーあ……」
僕はゆるゆると、化け物が転んだ地点まで歩く
歩きながら、化け物に聞こえるように声を張りながら話しかける
「そもそも、僕の家は反対側!」
「えー……」
ぐるりとこちらを振り向き、意味がわからないという風に顔をしかめ、道と僕の顔を交互に見ている
「家に帰るため。そのために、お腹が空くまで歩き続けてたんだ
そうしたら、きっと、自然に帰りたくなると思ったから」
*帰らない・通学圏じゃない道を歩き続ける理由は、適合性考えて要調整
「さっき少し話しただろ
現実が変わらないのなら、僕が変わるだけだって」
適応出来ないのなら、それは僕が悪いだけだ
「我ながら賢い行動だと思うよ」
そうやって、これまでも、これからも僕は生きていく
「うそだー」
体が一瞬跳ね、僕の時間は止まる
なんてことのない言葉
「嘘って、何が」
「それうそだよー。わかってるよー」
「さびしい」
けれど、ひどく神経を逆なでされた
大きく目を見開いた目は、すぐに化け物にガンを飛ばすような表情に
「何がさびしいんだよ」
腹の底から絞り出すような声が出た
今までとは違う、端的で冷静な化け物の一言
化け物の見透かしているような言い方に腹が立った
「 」
誰かの言葉がフラッシュバックし、途端におぞましくなった
他人に己の根幹を理解して貰う必要は無い
けれど、理解してくれないのであれば、わかった気でいるのをやめろ
反吐が出そうだ
僕はこの手の人間(こいつは人間ではないけど)が、大嫌いなんだ
感情的になりそうなので、なんとか頭を落ちつけようとする。
ここで怒ったら図星を突かれた人みたいだから。
今の状況を冷静に反芻する
僕は裏門から学校を抜け出した
一人きりで
一人きり……?
「いや、お前誰だよ…!?」
化け物と一緒に歩く事に、何の疑問も持っていなかった。
そうだ、僕はずっと一人きりだった
化け物という非現実的な存在の意味もわからない。
「ぼくは、ぼくだよ」
「なに言って……」
「わかるよ」
「……お前は、なんなんだよ!?」
僕の感情などお構いなしに、化け物はまくし立てる
「どうしてー。どうしてこんなにさびしいのー」
泣いている化け物の描写
見知った声色に表情
化け物を見て気が付く僕
どうしてこんな大事なものを忘れていたのだろう
めそめそと泣きじゃくる目の前の君は
遥か遠くに置き去りにしていた、僕自身だった
「五月蠅い、五月蠅い、五月蠅い!!
泣きたいのは僕のほうだ。僕だってこんなのは嫌だ、嫌なんだよ……」
激昂した僕の言葉の最後は、掻き消えるような小ささだった
---
*学校を勝手に抜け出すまでに生じたやり取り
とても惨めだった。僕は、惨めだ。
下駄箱には、僕一人。
---
気が付けば青空は終わっていた
人気は一切無く、空は真っ赤に染まっている
僕は振り返らずスタスタと歩き続ける。
化け物はてちてちと幼稚な歩みで付いてくる。
僕が足を速めると、化け物もぎこちなく足を速める。
こいつはそのうち怒り出すんじゃないか。
それとも愛想を尽かしてついて来なくなるのではないか。
そんな想像で頭が一杯になり、異常に鼓動が早くなる。
けれど、自分の行動のせいで他人が困っているという状況は、とても気分が良かった。
……あぁでも、せっかく自販機があったのに、素通りしてしまった
僕が早く歩きすぎたせいか、滑稽な音がして化け物が転んだ。
僕の歩みが遅くなる。
歩き疲れたから、足が悲鳴を上げているだけだ。
早く、起き上がれよ。
これじゃ、お前に追いかけて欲しいみたいじゃないか
「 」
化け物がポツリと呟いた
君の笑顔は、いつだって泣き出す寸前の子供のそれだった
涙が零れる寸前で、精一杯の優しさでこちらを撫でてくれる
真綿のような優しい手で触れなければ、壊れてしまうもの
僕は振り返らないが、足音が再開するまで止まって待っていた。
足音が徐々に近づいてくる。
隣に化け物が並ぶ。
この距離がひどく懐かしいと感じた。
僕はペースを落として歩いた。
君がもう転んでしまわないように、無くさないように、強く手を握りしめて
僕は気恥ずかしさからぶすーっとして隣には目もくれない
けれど、確かに君は泣いていた
「……本当は、みんな大嫌いなんだ
溶けて無くなっちゃえばいいんだ」
*ここで言った内容が主人公の末路なので、ラストと併せて調整
精一杯の強がり
本当は誰かに消えて欲しい訳じゃなかった
ただ、ずっと何処かに行きたかった
黙って歩き続ける
ふとどちらかが口を開いた
「この道に果てに、君は何を求めているの?」
「……希望」
---
遠い踏切の音が、すぐ近くに聞こえた。
手を取り合いながら、音の発生源へと駆け出していく
「行こう」
音が僕の意識の手を引く
ずっと、真っ白い闇はガーゼを被せていた
警報が鳴り響いていることにも気がつかなかった
カン、カン、カン。
遮断機は降りていた
立ち止まっていると、電車が通り過ぎた
遮断機はまだ開かない
電車が何度も通り過ぎる
永遠に開かない様な気がした
今までの出来事を思い返す
学校・家の事
化け物との会話
僕が誰かの鏡に囚われていただけ?
最後の電車が通り過ぎる
遮断機が開いた
「一緒に行けるよ。君となら」
お互いに微笑み合い、力強く頷いた。
せぇの。
---
ずっと、探し求めていた
僕の『鏡』が欲しかった
羨ましくなったのだ
道に迷えるその誰もが、僕に己を視るから
『鏡の心は何処へ行く?』
『誰も僕を見てくれはしない。誰も、誰も……』
其処に在った何かが溶けたのか、粘度の高い液体が水たまりになっている
よれたTシャツはズブズブに浸って、色が変わっている
残骸を鏡が映すことは無く、ただ虚ろに今日も彷徨うのみ。
蝉はやかましく鳴き続けている。
「さびしーい」
空っぽの躰はとうに干上がって、誰か水をくれないか。
遠くの警報音に、膿んだ傷をかき混ぜながら。
歩く、歩く。
---
下駄箱には、僕一人。
しばらくの間、他の生徒も、先生も誰も居なかったけれど。遠くから話し声が近づいてきたので、僕は素早く靴を履き替え、校舎を後にした。
裏門に向かう途中、中庭から校舎を見上げれば、教室では生徒達が工作をしていた。
とある男子生徒がこちらに気が付き、怪訝そうに様子を伺っていたが、僕はフイと目を逸らし、そのまま振り返ることは無かった。
校舎を出てすぐ、学校に隣接している幼稚園の脇を通り過ぎる。
僕の通う小学校には、この幼稚園出身の生徒も多いのだが、僕の通学圏から外れたここは、縁もゆかりも無い場所だった。
当然、中の様子にも興味は無かったが、甲高いはしゃぎ声が聞こえてきたので、まだ子供が残っているのだろうな、とだけ思った。
簡素な住宅が並ぶ風景を、薄らぼんやりと眺めながら、僕は歩みを進めた。
相当な年季が入った住宅の庭には、幾つかの盆栽が置かれていた。
丁寧に切り揃えられた枝には、持ち主の生真面目さが映し出されていた。
この辺りにしては、比較的小奇麗な住宅の縁側では、よく肥えた三毛猫が溶けていた。
無理もない、この暑さだ。
同情の眼差しを向けていると、ふいにそれが交わり、僕は思わず足を留めた。
お前は、誰を映しているんだ?
やがて、部屋の奥から洗濯物を持った女が現れた。
もう僕のことなんか気にも留めず、猫は嬉しそうに女の元へ駆け寄っていった。
余計なお世話だったな。
僕は目を逸らし、再び歩き出した
しばらくの間、女の怪訝そうな視線が、背中にチクチクと刺さっていた。
住宅、住宅……。
「子ども110番の家」と書かれたプレートが印象的な、とある住宅が目に留まった。
馴染み深いこのプレートは、僕のアパートの玄関にも貼られているものだ。
子供を守るボランティア活動の一環であり、日中も誰かしらが在宅しているという印でもある。
子供好きの高齢者が住む家か、はたまた子持ちの専業主婦が住む家か。
もし住人が後者であれば、きっと、母は子の帰宅を待ち望んでいるのだろう。
子供が事件や事故に巻き込まれず、自分の元へと帰ってくることを望みながら、一人過ごしてるのだろう。
いやもしかしたら、この家の子供は、とっくに帰宅しているのかもしれない。
代わり映えのしない「おかえり」と「ただいま」。
勉強を頑張った、友達と仲良く遊んだ、先生に褒められた、でも午後の授業はちょっとだけ寝てしまった。
母は、喜んで聞いてくれるだろう。 *ここ削る?
ドアの向こう側、日々の営みを想像した。
黒板を淡く引っ搔いたかのような不快感に、僕はもう住宅を眺めるのはやめた。
この道は田園に続いており、脇には用水路が流れている。
人々の営みを乗せた水は稲を育み、やがて、どんな形で結実するのだろうか。
気が付けば、ぬるい風が吹いていた。
気温に反した冷めたい汗が、頬を伝う。
カン、カン、カン……。
風に乗ってきたのだろうか。
何処かで、遠い遮断機の音が響いた。
気がした。
---
「つかれたー」
間の抜けた声で我に帰り、隣に目を向けると、化け物が渋い表情を浮かべていた。
眉間に皺を寄せているが、口は逆三角の半開きでどうにも威厳に欠ける。
マジックペンでも書けそうな雑さだな、と思った。
「かわいたー」
化け物は意味もなく、くねくねと全身を揺らし、僕と並び歩く。
「水なら無いよ」
「うるおいは?」
「無いから期待するな」
その対応が無慈悲だと思ったのか、単に水分補給が出来ない事に落胆したのか。
化け物は露骨に肩を落とし(と表現をしたものの、おそらくこいつに肩は無い)、こちらを非難してのけた。
「ひどいー」
蝉はやかましく鳴き続けている。
---
*このパートは特に悩み中
僕は化け物と歩き続けた。
そんなに時間は経過していない。
住宅の数が減ると同時に、視界には一気に田園が広がった。
この開けた世界と、僕の意識の境目は、ひどく曖昧だった。
何処にだって駆け出せるのに、決して何処に行く事も叶わない。
勿論、そんな事は全く無く。
雑草や小石は多いけど、田んぼの間にはちゃんと歩ける道がある
そこを真っ直ぐに歩く
化け物が周辺をきょろきょろ見ている
「田んぼを区切ってる、細い方の道は歩くなよ。お前落ちそうだから」
「どぼーん」
「するな」
↓入れるか悩み中
カン、カン、カン……。
「なんか、ずっと踏切が鳴ってないか?」
「えー。せみ、だよ」
息を吸うように嘘を吐くな、というツッコミは心の中に留め、
警報が鳴っているなら渡れない
---
「かわいたー」
化け物がTシャツの裾を引っ張り、歩みを静止させる。
グッと力を溜めるようにしゃがんだ後、立ち上がりながら躰をくねくねさせる。
子供番組の体操か何かだろうか
「うる、おい」
「お前、またそれか……」
こんな下らない事で、ただでさえよれているTシャツの皺を増やさないで欲しい
化け物は意味もなく、くねくねと全身を揺らしている
チラチラと僕のほうを見てくる化け物
どうやら、僕に対して水を求めているらしい
田圃の水を飲むと言い出さないだけまだマシだけど、もし言い出したらどうしよう……という不安を抱きながら、化け物に話しかける
「お前は僕に期待しているのだろうけど、残念ながら水は持ってない。
水筒を学校に忘れてしまったから。
でも、仮に僕が水を持っていたとしても、それに期待してはならないよ。」
必要だと思うなら、他人の施しに期待をせず、用意をしておくべき。
こんな炎天下に水を持ってこないのは、お前の怠慢。
水筒を忘れた僕が、道中で干上がったとしても、それも僕の怠慢。
化け物はいまいち理解していないようで、「んー」と首を傾げている。
「あめ、ふればいいのにー」
「その考えは駄目だよ。空模様は変わってはくれない。
何かを求めないこと。自分が落胆するだけだから」
「わー。おっとなー」
「いや……」
その言葉に僕は一瞬口を開きかけたが、すぐに飲み込んだ。
これ以上の言葉は自己満足だから。
けれど化け物が興味深そうに、真っ直ぐに瞳を覗き込んでくる。
結局続きを言うことにした。
「僕の考えが大人だっていうなら、それは違う
なぜなら、大人も子供も、本質は変わらないからだ」
「他者と触れ合い接する時、どんな人間も相手に自分を映し出している
他人は『自分の鏡』を相手に求めているんだ」
*「他人の鏡」の例になるような事柄
『鏡の心は何処へ行く?』
『誰も僕を見てくれはしない。誰も、誰も……。』
何故だかわからないけれど、妙に感情的な言葉が出かけたので、慌てて自制した
きっと、この言葉は何処にも届かず、僕の中にだけ響いていた
「雨ね。かつては、僕も望んでいたよ。けどもうやめた
結局は、自分が変わるしかないから」
化け物を見据えて一言
「だからお前も、勿論僕だってそうするんだ」
「さびしーい」
間の抜けた喋り方で、考える人のような仕草をする化け物
けれど珍しく、感慨深そうに頷いてみせた。
---
青い稲が生い茂る田んぼ道を僕と化け物で歩き続ける
もしかしたら、上は綺麗でも、根腐れしているのではないか
色々な思いの混ざったそれは、もはや汚水でしかなく
ずぶずぶに浸って、そして……
「ふふん、ふふんふん」
化け物の鼻歌で我に帰った
僕達の行動自体は何も変わらないのに、何故か上機嫌に見えた
口はアヒルのような曲線を描いている。
「水はもういいのか?」
「いる。でも、うるおった」
全身をくねくねと揺らし歩く
謎の動きは水の流れを表現しているのかも、と気が付いた
僕はわざと化け物より遅く歩き、化け物の斜め後ろを陣取る
コソコソとランドセルのポケットの奥底を漁る
幸い、化け物は気が付いていないようだった
500円玉が出てきた
学校への金銭の持ち込みは禁止されているけど、非常時のためにこっそり持ち歩いていたもの
ちゃんと入っていて良かった
これで缶ジュースか何かでも買ってやろうと思った
僕は現実主義なだけで、無慈悲な人間ではないのだ
変に期待を持たせても良くないから、自販機が見つかるまで黙っていることにした
僕達は歩みを止めない
やがて田んぼ道は終わりを告げ、歩きやすく舗装された道に出た
*地獄への道は善意で舗装されている
奇妙なまでに、道は何処までも真っ直ぐに続いていた
---
真っ直ぐな道
暑さでアスファルトが揺らめく
道の終わりが見えない
僕達はどれだけの間歩き続けていたのだろう。
炎天下の中歩き続けていたので、黒いランドセルの表面は熱を持っている
こういう時、違う色を買って欲しかったのになと強く思うが、こんな感情は意味のないものだと一蹴
ため息交じりに呟く
「……つかれた」
「つかれた!」
呟いた途端、化け物がぬるりと勢いよく動き、僕の顔を覗き込んできた。
その目はキラキラに輝いていた。
僕は思わずたじろぎ、立ち止まる。
「やっぱり、なかま」
何を言っているんだ、こいつは
僕にはこんな奇妙な存在との共通点は無い
「ねー、なんであるくの」
「なんでって、家に帰るためだろ」
「いえ?いきたいー。いく」
「いや来るな。って、いきなり走るなよ!?」
化け物は勢いよく一本道を駆け出す
僕からゆるやかに遠ざかっていく
しかし化け物の動きは非常にのろく、全力疾走だと思われるそれは
僕の早歩きとあまり変わらない
少し離れた地点で、べちゃりとすっ転ぶ
地面にうつ伏せになっている
「あーあ……」
僕はゆるゆると、化け物が転んだ地点まで歩く
歩きながら、化け物に聞こえるように声を張りながら話しかける
「そもそも、僕の家は反対側!」
「えー……」
ぐるりとこちらを振り向き、意味がわからないという風に顔をしかめ、道と僕の顔を交互に見ている
「家に帰るため。そのために、お腹が空くまで歩き続けてたんだ
そうしたら、きっと、自然に帰りたくなると思ったから」
*帰らない・通学圏じゃない道を歩き続ける理由は、適合性考えて要調整
「さっき少し話しただろ
現実が変わらないのなら、僕が変わるだけだって」
適応出来ないのなら、それは僕が悪いだけだ
「我ながら賢い行動だと思うよ」
そうやって、これまでも、これからも僕は生きていく
「うそだー」
体が一瞬跳ね、僕の時間は止まる
なんてことのない言葉
「嘘って、何が」
「それうそだよー。わかってるよー」
「さびしい」
けれど、ひどく神経を逆なでされた
大きく目を見開いた目は、すぐに化け物にガンを飛ばすような表情に
「何がさびしいんだよ」
腹の底から絞り出すような声が出た
今までとは違う、端的で冷静な化け物の一言
化け物の見透かしているような言い方に腹が立った
「 」
誰かの言葉がフラッシュバックし、途端におぞましくなった
他人に己の根幹を理解して貰う必要は無い
けれど、理解してくれないのであれば、わかった気でいるのをやめろ
反吐が出そうだ
僕はこの手の人間(こいつは人間ではないけど)が、大嫌いなんだ
感情的になりそうなので、なんとか頭を落ちつけようとする。
ここで怒ったら図星を突かれた人みたいだから。
今の状況を冷静に反芻する
僕は裏門から学校を抜け出した
一人きりで
一人きり……?
「いや、お前誰だよ…!?」
化け物と一緒に歩く事に、何の疑問も持っていなかった。
そうだ、僕はずっと一人きりだった
化け物という非現実的な存在の意味もわからない。
「ぼくは、ぼくだよ」
「なに言って……」
「わかるよ」
「……お前は、なんなんだよ!?」
僕の感情などお構いなしに、化け物はまくし立てる
「どうしてー。どうしてこんなにさびしいのー」
泣いている化け物の描写
見知った声色に表情
化け物を見て気が付く僕
どうしてこんな大事なものを忘れていたのだろう
めそめそと泣きじゃくる目の前の君は
遥か遠くに置き去りにしていた、僕自身だった
「五月蠅い、五月蠅い、五月蠅い!!
泣きたいのは僕のほうだ。僕だってこんなのは嫌だ、嫌なんだよ……」
激昂した僕の言葉の最後は、掻き消えるような小ささだった
---
*学校を勝手に抜け出すまでに生じたやり取り
とても惨めだった。僕は、惨めだ。
下駄箱には、僕一人。
---
気が付けば青空は終わっていた
人気は一切無く、空は真っ赤に染まっている
僕は振り返らずスタスタと歩き続ける。
化け物はてちてちと幼稚な歩みで付いてくる。
僕が足を速めると、化け物もぎこちなく足を速める。
こいつはそのうち怒り出すんじゃないか。
それとも愛想を尽かしてついて来なくなるのではないか。
そんな想像で頭が一杯になり、異常に鼓動が早くなる。
けれど、自分の行動のせいで他人が困っているという状況は、とても気分が良かった。
……あぁでも、せっかく自販機があったのに、素通りしてしまった
僕が早く歩きすぎたせいか、滑稽な音がして化け物が転んだ。
僕の歩みが遅くなる。
歩き疲れたから、足が悲鳴を上げているだけだ。
早く、起き上がれよ。
これじゃ、お前に追いかけて欲しいみたいじゃないか
「 」
化け物がポツリと呟いた
君の笑顔は、いつだって泣き出す寸前の子供のそれだった
涙が零れる寸前で、精一杯の優しさでこちらを撫でてくれる
真綿のような優しい手で触れなければ、壊れてしまうもの
僕は振り返らないが、足音が再開するまで止まって待っていた。
足音が徐々に近づいてくる。
隣に化け物が並ぶ。
この距離がひどく懐かしいと感じた。
僕はペースを落として歩いた。
君がもう転んでしまわないように、無くさないように、強く手を握りしめて
僕は気恥ずかしさからぶすーっとして隣には目もくれない
けれど、確かに君は泣いていた
「……本当は、みんな大嫌いなんだ
溶けて無くなっちゃえばいいんだ」
*ここで言った内容が主人公の末路なので、ラストと併せて調整
精一杯の強がり
本当は誰かに消えて欲しい訳じゃなかった
ただ、ずっと何処かに行きたかった
黙って歩き続ける
ふとどちらかが口を開いた
「この道に果てに、君は何を求めているの?」
「……希望」
---
遠い踏切の音が、すぐ近くに聞こえた。
手を取り合いながら、音の発生源へと駆け出していく
「行こう」
音が僕の意識の手を引く
ずっと、真っ白い闇はガーゼを被せていた
警報が鳴り響いていることにも気がつかなかった
カン、カン、カン。
遮断機は降りていた
立ち止まっていると、電車が通り過ぎた
遮断機はまだ開かない
電車が何度も通り過ぎる
永遠に開かない様な気がした
今までの出来事を思い返す
学校・家の事
化け物との会話
僕が誰かの鏡に囚われていただけ?
最後の電車が通り過ぎる
遮断機が開いた
「一緒に行けるよ。君となら」
お互いに微笑み合い、力強く頷いた。
せぇの。
---
ずっと、探し求めていた
僕の『鏡』が欲しかった
羨ましくなったのだ
道に迷えるその誰もが、僕に己を視るから
『鏡の心は何処へ行く?』
『誰も僕を見てくれはしない。誰も、誰も……』
其処に在った何かが溶けたのか、粘度の高い液体が水たまりになっている
よれたTシャツはズブズブに浸って、色が変わっている
残骸を鏡が映すことは無く、ただ虚ろに今日も彷徨うのみ。
蝉はやかましく鳴き続けている。
「さびしーい」
1/1ページ