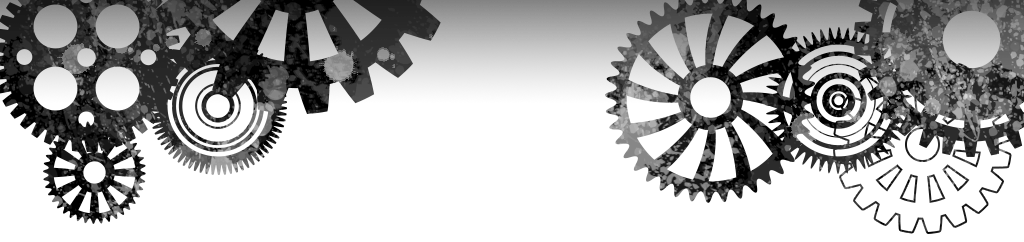幼少期
カイは遊び疲れていた。
大きすぎるベッドに沈むようにして眠るカイは、行儀よく布団に包まり死んだかのように静かだった。
すると、ふとドアが音を立てずに開いた。
カイの部屋に入ってきたのは、紛れもなくヴォルデモートであった。
ヴォルデモートは、もう深夜3時を回ってるにも関わらず相も変わらず黒いスーツに黒いローブを着用していた。
そしてヴォルデモートは、部屋をぐるりと一瞥した。
8歳ほどの子供が欲しいものなんて、分からなかった。だから、黒を基調とした部屋に最低限の彩りとして青と緑をシーツや絨毯に取り入れたのだが、こう見ると典型的な子ども部屋とは程遠いと感じる。
カイは、欲しいものをねだらない。
小さい子は何でも、新しいものに目がいくだろう。
カラフルなお菓子に、プラモデル。
あるいは山盛りのレゴブロック。
そういった類のものは一切欲しがらず、カイは一日中呪文の練習や、屋敷の書斎で本を読み漁るなどをした。
だから、ヴォルデモートはアブラクサスに子どもが遊ぶおもちゃを聞いて、カイの部屋に、ブロックや、ボール、キッズテントなどとりあえず形式的に置いてみたはいいものの、どれも部屋を訪れた時にはきっちりと整頓がされて置いてあり、使っているような様子は無かった。
だから遊び相手として、アブラクサスの長男ルシウスをカイの前にヴォルデモートはよこした。
純血思想の子供が遊び相手になる事は、カイの成長に都合のいい影響をもたらすと考えたからだ。
カイにもこれが1番効果があったようで、カイは何よりもルシウスといる時が子供らしいとヴォルデモートは感じた。
関われば関わるほどに
所詮、カイもただの子供だった。
そんな当たり前の事実に、ヴォルデモートはため息を着いた。彼は何を期待していたのだろうか。
そして、ゆっくりとカイが眠るベッド足元あたりに腰を掛けた。
なんの穢れもない、白くてサラサラの頬。
1本1本繊細な、長いまつ毛。
上向きの小さいがぽってりとした唇。
どれも、こどもだった。
布団にくるまった姿も儚く小さい。
普段、軽口を叩く生意気なカイも眠ってしまえば、余計に無力だった。
杖なんてなくても手を伸ばせば直ぐに絶やせてしまいそうだ。
ヴォルデモートは、無意識下に何の考えもなしに、爪が綺麗に伸びた手をカイの方にゆっくりと伸ばした。
そして、カイの頼りない首元に手を置く。
すると、ヴォルデモートの親指と人差し指を跳ね返すような拍動が感じられる。
その拍動が煩わしくなり、ヴォルデモートは僅かに力を加えてみる。彼は、自覚が無い。自分が今何をしているのかが。みるみると、指に伝わる感覚が薄れていくが分かる。なのにヴォルデモートはカイが何も抵抗しないのをいい事に、ひとつの表情も変えずそれを辞めることは無かった。
するとカイは、ついに身を捩らせた。
そして薄らと、重い瞼を開けた
「……ヴォル……?」
カイがそう小さく、狭くなった気道から懸命に絞り出して答える。
すると、ヴォルデモートは首にかけていた手を、何事も無かったかのようにそっと離した。
そして赤みのある頬がすっかり青白くなったカイは、先程まで自分の首を締めていたヴォルデモートの手を求めるかのようにギュッと掴んだ。
そして、ヴォルデモートのあまりに冷たい深紅の目をじっと見つめた。
「カイ……寂しくないから。
我儘も言わないから……。」
そう、カイは消え入りそうなほど小さな声で呟いた。
ヴォルデモートは、僅かにだが目を見開いた。
「だから……、置いていかないで。」
そう言ってカイは再び目を閉じた。
しかし、ヴォルデモートの手は握り続けたままだ。
再び、すやすやと寝息が聞こえても、もうヴォルデモートはカイの首元に手をかけようとはしなかった。
ヴォルデモートが、思い起こしたのはカイと出会った公園だった。寒い冬の日、カイは確かにそこにいた。
何も求めない純真な瞳でヴォルデモートを見た。
冬が明けて、気温が陽気になった頃、ふと同じ公園をヴォルデモートは訪ねた。
すると、カイは前よりもさらに小さくなっているようだった。あちこちが傷だらけで、なのにカイは1つも悲しそうな表情をせずにブランコに座っていた。
そして、ヴォルデモートが立ち去ろうとすると、
カイは再びヴォルデモートの方を見たのだ。
デジャブのような出来事に、思わず目が離せなくなってしまった。
それから、決まってヴォルデモートはマグル狩りの為にこの街付近を訪れた後、カイのいる公園に訪れるようになった。
初めは遠くからカイを見つめていたが、徐々にその近くのベンチに腰掛けるようになった。
なぜ、自分でもこんな事をしているのか分からなかった。だけどこうしていることが、どうも、落ち着きに変わり人間の血肉を忘れることが出来た。
互いにもう顔見知りのはずなのに、言葉を交わすことは無かった。
ただ、お互いの存在を認識し合いながら、時間を共有するかのように、すっかり日が暮れてしまうまでそこにいた。
そして何度、訪れたか分からない公園にまたヴォルデモートが足を運んだ時の事だった。
カイの目線の先には、指をさして笑う子供たちがいた。カイと同じ歳ぐらいだが、それよりも大きくて、快活な雰囲気を身にまとっていた。
その子供たちの表情は、無垢ながらも汚かった。
その汚い手で、カイを押し倒したのだ。
ああ、汚い。
もういっそ丸ごと壊してしまおうか。
ヴォルデモートは、自分の手が勝手に杖を握るのに気がついていなかった。
しかしその前に、カイは立ち上がった。
大きく吠えた。
さらにまたそのせいで少年たちから制裁を受ける羽目になったのだが、カイの仲間と思わしき子供たちが彼女の周りに集まって来た。
カイは、笑顔だった。
ヴォルデモートがカイに重ね合わせた劣等感を、彼女は違う形で跳ね返したのだ。
……勘違いしていた。
……私と違うんだな。
数年後、カイとの再会は意図だったのだろうか、それとも偶然だったのだろうか。
大きすぎるベッドに沈むようにして眠るカイは、行儀よく布団に包まり死んだかのように静かだった。
すると、ふとドアが音を立てずに開いた。
カイの部屋に入ってきたのは、紛れもなくヴォルデモートであった。
ヴォルデモートは、もう深夜3時を回ってるにも関わらず相も変わらず黒いスーツに黒いローブを着用していた。
そしてヴォルデモートは、部屋をぐるりと一瞥した。
8歳ほどの子供が欲しいものなんて、分からなかった。だから、黒を基調とした部屋に最低限の彩りとして青と緑をシーツや絨毯に取り入れたのだが、こう見ると典型的な子ども部屋とは程遠いと感じる。
カイは、欲しいものをねだらない。
小さい子は何でも、新しいものに目がいくだろう。
カラフルなお菓子に、プラモデル。
あるいは山盛りのレゴブロック。
そういった類のものは一切欲しがらず、カイは一日中呪文の練習や、屋敷の書斎で本を読み漁るなどをした。
だから、ヴォルデモートはアブラクサスに子どもが遊ぶおもちゃを聞いて、カイの部屋に、ブロックや、ボール、キッズテントなどとりあえず形式的に置いてみたはいいものの、どれも部屋を訪れた時にはきっちりと整頓がされて置いてあり、使っているような様子は無かった。
だから遊び相手として、アブラクサスの長男ルシウスをカイの前にヴォルデモートはよこした。
純血思想の子供が遊び相手になる事は、カイの成長に都合のいい影響をもたらすと考えたからだ。
カイにもこれが1番効果があったようで、カイは何よりもルシウスといる時が子供らしいとヴォルデモートは感じた。
関われば関わるほどに
所詮、カイもただの子供だった。
そんな当たり前の事実に、ヴォルデモートはため息を着いた。彼は何を期待していたのだろうか。
そして、ゆっくりとカイが眠るベッド足元あたりに腰を掛けた。
なんの穢れもない、白くてサラサラの頬。
1本1本繊細な、長いまつ毛。
上向きの小さいがぽってりとした唇。
どれも、こどもだった。
布団にくるまった姿も儚く小さい。
普段、軽口を叩く生意気なカイも眠ってしまえば、余計に無力だった。
杖なんてなくても手を伸ばせば直ぐに絶やせてしまいそうだ。
ヴォルデモートは、無意識下に何の考えもなしに、爪が綺麗に伸びた手をカイの方にゆっくりと伸ばした。
そして、カイの頼りない首元に手を置く。
すると、ヴォルデモートの親指と人差し指を跳ね返すような拍動が感じられる。
その拍動が煩わしくなり、ヴォルデモートは僅かに力を加えてみる。彼は、自覚が無い。自分が今何をしているのかが。みるみると、指に伝わる感覚が薄れていくが分かる。なのにヴォルデモートはカイが何も抵抗しないのをいい事に、ひとつの表情も変えずそれを辞めることは無かった。
するとカイは、ついに身を捩らせた。
そして薄らと、重い瞼を開けた
「……ヴォル……?」
カイがそう小さく、狭くなった気道から懸命に絞り出して答える。
すると、ヴォルデモートは首にかけていた手を、何事も無かったかのようにそっと離した。
そして赤みのある頬がすっかり青白くなったカイは、先程まで自分の首を締めていたヴォルデモートの手を求めるかのようにギュッと掴んだ。
そして、ヴォルデモートのあまりに冷たい深紅の目をじっと見つめた。
「カイ……寂しくないから。
我儘も言わないから……。」
そう、カイは消え入りそうなほど小さな声で呟いた。
ヴォルデモートは、僅かにだが目を見開いた。
「だから……、置いていかないで。」
そう言ってカイは再び目を閉じた。
しかし、ヴォルデモートの手は握り続けたままだ。
再び、すやすやと寝息が聞こえても、もうヴォルデモートはカイの首元に手をかけようとはしなかった。
ヴォルデモートが、思い起こしたのはカイと出会った公園だった。寒い冬の日、カイは確かにそこにいた。
何も求めない純真な瞳でヴォルデモートを見た。
冬が明けて、気温が陽気になった頃、ふと同じ公園をヴォルデモートは訪ねた。
すると、カイは前よりもさらに小さくなっているようだった。あちこちが傷だらけで、なのにカイは1つも悲しそうな表情をせずにブランコに座っていた。
そして、ヴォルデモートが立ち去ろうとすると、
カイは再びヴォルデモートの方を見たのだ。
デジャブのような出来事に、思わず目が離せなくなってしまった。
それから、決まってヴォルデモートはマグル狩りの為にこの街付近を訪れた後、カイのいる公園に訪れるようになった。
初めは遠くからカイを見つめていたが、徐々にその近くのベンチに腰掛けるようになった。
なぜ、自分でもこんな事をしているのか分からなかった。だけどこうしていることが、どうも、落ち着きに変わり人間の血肉を忘れることが出来た。
互いにもう顔見知りのはずなのに、言葉を交わすことは無かった。
ただ、お互いの存在を認識し合いながら、時間を共有するかのように、すっかり日が暮れてしまうまでそこにいた。
そして何度、訪れたか分からない公園にまたヴォルデモートが足を運んだ時の事だった。
カイの目線の先には、指をさして笑う子供たちがいた。カイと同じ歳ぐらいだが、それよりも大きくて、快活な雰囲気を身にまとっていた。
その子供たちの表情は、無垢ながらも汚かった。
その汚い手で、カイを押し倒したのだ。
ああ、汚い。
もういっそ丸ごと壊してしまおうか。
ヴォルデモートは、自分の手が勝手に杖を握るのに気がついていなかった。
しかしその前に、カイは立ち上がった。
大きく吠えた。
さらにまたそのせいで少年たちから制裁を受ける羽目になったのだが、カイの仲間と思わしき子供たちが彼女の周りに集まって来た。
カイは、笑顔だった。
ヴォルデモートがカイに重ね合わせた劣等感を、彼女は違う形で跳ね返したのだ。
……勘違いしていた。
……私と違うんだな。
数年後、カイとの再会は意図だったのだろうか、それとも偶然だったのだろうか。