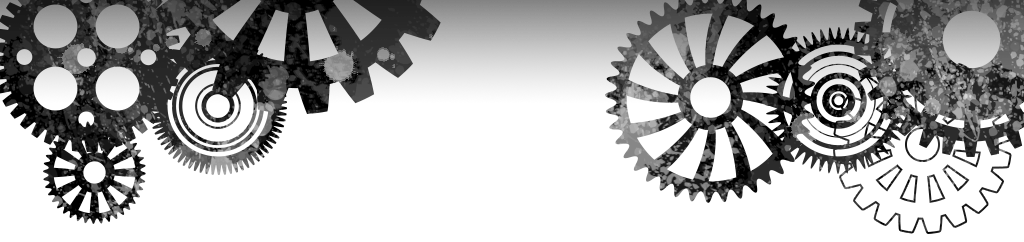幼少期
ヴォルデモートは、カイにマグル生活のあらゆる1片を漏らさないように言った。
でないと、カイの立場はこの組織では地の底に大転落を遂げてしまうからだ。ヴォルデモートが、部下に崇めろという特別な子供なのだからそんな事はないのは明白だが、ここで自分への疑心を無駄に産むのも面倒だったからだ。現にアブラクサスがそうだ。
しかし、問題が発生する。
カイは思った以上のお喋りだった。ヴォルデモートの言っていることは分かっても、テンションが上がるとノリで発してしまいそうになるのだ。
でも、寸止めの所でなんとかカイは自制を働く。それはもうヴォルデモートの恐怖からの防衛本能とでも言えるだろう。
カイの話は、ヴォルデモートの地雷。
こうして完全にカイはベールがかかった存在としてもはや触れられない場所にいた。
ひそかに"死喰い人の砦"として意識するものまでいる。
それは、完全にヴォルデモートの範疇だった。
「貴様、魔法はどのくらい使える。」
ヴォルデモートは書斎にカイを呼び寄せて問うた。
「昼間から、こんなに部屋を暗くして。
目が悪くなっちゃうよ?」
黒いデスクに僅かに灯るライトと黒枠の窓から辛うじて注ぎ込む光だけが頼りのヴォルデモートの書斎は確かに昼間とは思えないほどに暗かった。
「いいから答えろ。」
「手で、物は浮かせられるよ。あと自分より軽いものは吹き飛ばせられる。あと、誰かの肩をいちいち叩かなくても振り向かせられる。」
「振り向かせられる?」
「そう、振り向けって念じたら振り向くんだ。」
服従の呪文を杖なしで……ヴォルデモートはまさかと思い自分にやって見るように促した。
するとヴォルデモートは、確かに体の中に他力の支配が及んでいることがわかった。
もちろん軽くはねのけたが。
「へぇ、拒むこともできるんだ。」
カイは素直に感心するふうに言ったので、今までの成功率は100%だったのだろう。
しかし、これが服従の呪文に近いものだとすればなんの悪事も簡単に及ぶことができる。
現に自分は何度もその行為に及んだ。
「人を操ったことは。」
「ないよ。考えたことも。」
カイは当然だと言わんばかりに、目を見開いた。
……利口な道徳心だ事。
ヴォルデモートはそう馬鹿にしたが、内心のところ余計な心配を働かずに済むので少し安心していた。
倫理観は後で養うのは難しい。
しかし後でいくらでも潰すことは出来る。
自主的にでも誰かの手によっても。
「一度でも、こう考えたことはないか?
好きなだけ自分の力を使えたらできたらいいのにって。」
ヴォルデモートは、棘もない語りかけるように楽しげな口調でそう尋ねた。
「それはあるよ。どんだけ家の中を暴れてもあとで直せるし!友達の前で水を出して、プールにして遊べる!あ、今友達いないんだった……」
「ガキ臭い。もっと違う発想はないのか?」
「そんなこと言ったって……。
あっ!もし……。いや悪い人がいたら惜しみなく倒せる。」
カイにはいじめっ子にいじめられた時の苦い記憶の連想、もしくは子供心を揺さぶるヒーローとしての憧れ両方を兼ねていた。
しかし、ヴォルデモートはカイのその言葉が正しく自分に欲しかったものに近い答えだとして、思わず口角を上げた。
「悪いんだろう……?倒せばいいじゃないか。」
「でもね、それは魔法が使えない人にしちゃダメなんだって。私の所を訪ねてきたおじいさんが言ってた。ルールだからってさ。」
「ルール?それ誰から聞いた?」
「前だから、ちょっと曖昧だけど……。髭がねすごく長かったんだ!あと目は青くてキラキラしてたよ。
同じ魔法使いなんだよって、わたしのところに来てくれたんだ。」
「あの……ジジイ。」
(同じ過ちは繰り返さないと?)
ヴォルデモートは幼少期、自分のところに訪ねてきた老人の姿を思い浮かべた。
そして、カイがウール孤児院にいた事を思い出しヴォルデモートはその老人の行動の意図が全て読めたような気がして気分が良くなった。
「じゃあそのおじいさんは、お前の危険に駆けつけたか?」
「……もう一度も会ってないよ。」
カイはついこの間ヴォルデモートにより起こった危険を思い出したのか少し悲しそうに返事をした。
「ルールで縛り付けた本人が、ルールのせいで迫った危険から守らないなんておかしな話ではないか?カイ。」
ヴォルデモートは、オーバーに手をカイの方に差し出した。さすがのカイも、これには少し納得したらしく言葉が出ないようだった。
「でも……ルールだから。
守らないと、罰がおりるよ。それに、傷つけちゃう。」
「ルールは、誰のためにある?」
「みんなの……ため?幸せに暮らせるため。」
「ではルールにお前の安全が保証されていないとわかった今、なぜみんなのためのルールと言える?」
「それは、わかんないよ。」
「なぜ、貴様の存在を危ぶむルールを守る必要がある?お前ではない、みんなのためのルール?
カイ・アーデン、ただお前という存在を、魔法が使える それだけの理由で怪物扱いをした忌々しいみんなという存在。 そう、非魔法族・弱者共のためのルールだ。」
ヴォルデモートは、カイにもわかるような言葉でゆっくりと説明をした。
巧みに言葉を操り、それが本当だと信じ込ませるセンスはやはりお手の物らしい。
証拠にあの正義感の強いカイは黙り込んでしまったのだから。
「まあ、無理して破れとはいわない。
現状破ればお前は、牢屋行きだからな。
ああ、おかしな仕組みの世の中だろう?」
「牢屋は嫌だよ。」
「行かない方法は簡単さ。……奴ら馬鹿な連中に気づかないようにする。」
「そんな上手くやれない!
それに嘘はつけない!」
カイはまたいつもの調子になったのか、お得意の倫理観を振りかざす。
「では、カイ。嘘をつかなくていい方法がある。そうだ、そもそもルールを無くしてしまう方法がひとつな。」
ヴォルデモートが人差し指を優雅に立てたあと、西日がようやく彼の輪郭を輝くように照らしだした。
カイは、その光景が綺麗だと思った。
「私が、ルールを作る人間になる。
我々より弱い人間を下に従えて奴らを導いてあげるんだ。そして堂々とこの世に魔法をかざす。
穢れた血と崇高な血を分別して、お前のように力に 苦しむものが出ないようにする。
私たちはもう、何も困らない。自由だ。」
静かに揺れる黒いカーテンがカイの顔に模様をかける。呆気に取られた碧のカイの瞳には、不敵に笑う美しい男の姿がただ鮮明に映し出されていた。
でないと、カイの立場はこの組織では地の底に大転落を遂げてしまうからだ。ヴォルデモートが、部下に崇めろという特別な子供なのだからそんな事はないのは明白だが、ここで自分への疑心を無駄に産むのも面倒だったからだ。現にアブラクサスがそうだ。
しかし、問題が発生する。
カイは思った以上のお喋りだった。ヴォルデモートの言っていることは分かっても、テンションが上がるとノリで発してしまいそうになるのだ。
でも、寸止めの所でなんとかカイは自制を働く。それはもうヴォルデモートの恐怖からの防衛本能とでも言えるだろう。
カイの話は、ヴォルデモートの地雷。
こうして完全にカイはベールがかかった存在としてもはや触れられない場所にいた。
ひそかに"死喰い人の砦"として意識するものまでいる。
それは、完全にヴォルデモートの範疇だった。
「貴様、魔法はどのくらい使える。」
ヴォルデモートは書斎にカイを呼び寄せて問うた。
「昼間から、こんなに部屋を暗くして。
目が悪くなっちゃうよ?」
黒いデスクに僅かに灯るライトと黒枠の窓から辛うじて注ぎ込む光だけが頼りのヴォルデモートの書斎は確かに昼間とは思えないほどに暗かった。
「いいから答えろ。」
「手で、物は浮かせられるよ。あと自分より軽いものは吹き飛ばせられる。あと、誰かの肩をいちいち叩かなくても振り向かせられる。」
「振り向かせられる?」
「そう、振り向けって念じたら振り向くんだ。」
服従の呪文を杖なしで……ヴォルデモートはまさかと思い自分にやって見るように促した。
するとヴォルデモートは、確かに体の中に他力の支配が及んでいることがわかった。
もちろん軽くはねのけたが。
「へぇ、拒むこともできるんだ。」
カイは素直に感心するふうに言ったので、今までの成功率は100%だったのだろう。
しかし、これが服従の呪文に近いものだとすればなんの悪事も簡単に及ぶことができる。
現に自分は何度もその行為に及んだ。
「人を操ったことは。」
「ないよ。考えたことも。」
カイは当然だと言わんばかりに、目を見開いた。
……利口な道徳心だ事。
ヴォルデモートはそう馬鹿にしたが、内心のところ余計な心配を働かずに済むので少し安心していた。
倫理観は後で養うのは難しい。
しかし後でいくらでも潰すことは出来る。
自主的にでも誰かの手によっても。
「一度でも、こう考えたことはないか?
好きなだけ自分の力を使えたらできたらいいのにって。」
ヴォルデモートは、棘もない語りかけるように楽しげな口調でそう尋ねた。
「それはあるよ。どんだけ家の中を暴れてもあとで直せるし!友達の前で水を出して、プールにして遊べる!あ、今友達いないんだった……」
「ガキ臭い。もっと違う発想はないのか?」
「そんなこと言ったって……。
あっ!もし……。いや悪い人がいたら惜しみなく倒せる。」
カイにはいじめっ子にいじめられた時の苦い記憶の連想、もしくは子供心を揺さぶるヒーローとしての憧れ両方を兼ねていた。
しかし、ヴォルデモートはカイのその言葉が正しく自分に欲しかったものに近い答えだとして、思わず口角を上げた。
「悪いんだろう……?倒せばいいじゃないか。」
「でもね、それは魔法が使えない人にしちゃダメなんだって。私の所を訪ねてきたおじいさんが言ってた。ルールだからってさ。」
「ルール?それ誰から聞いた?」
「前だから、ちょっと曖昧だけど……。髭がねすごく長かったんだ!あと目は青くてキラキラしてたよ。
同じ魔法使いなんだよって、わたしのところに来てくれたんだ。」
「あの……ジジイ。」
(同じ過ちは繰り返さないと?)
ヴォルデモートは幼少期、自分のところに訪ねてきた老人の姿を思い浮かべた。
そして、カイがウール孤児院にいた事を思い出しヴォルデモートはその老人の行動の意図が全て読めたような気がして気分が良くなった。
「じゃあそのおじいさんは、お前の危険に駆けつけたか?」
「……もう一度も会ってないよ。」
カイはついこの間ヴォルデモートにより起こった危険を思い出したのか少し悲しそうに返事をした。
「ルールで縛り付けた本人が、ルールのせいで迫った危険から守らないなんておかしな話ではないか?カイ。」
ヴォルデモートは、オーバーに手をカイの方に差し出した。さすがのカイも、これには少し納得したらしく言葉が出ないようだった。
「でも……ルールだから。
守らないと、罰がおりるよ。それに、傷つけちゃう。」
「ルールは、誰のためにある?」
「みんなの……ため?幸せに暮らせるため。」
「ではルールにお前の安全が保証されていないとわかった今、なぜみんなのためのルールと言える?」
「それは、わかんないよ。」
「なぜ、貴様の存在を危ぶむルールを守る必要がある?お前ではない、みんなのためのルール?
カイ・アーデン、ただお前という存在を、魔法が使える それだけの理由で怪物扱いをした忌々しいみんなという存在。 そう、非魔法族・弱者共のためのルールだ。」
ヴォルデモートは、カイにもわかるような言葉でゆっくりと説明をした。
巧みに言葉を操り、それが本当だと信じ込ませるセンスはやはりお手の物らしい。
証拠にあの正義感の強いカイは黙り込んでしまったのだから。
「まあ、無理して破れとはいわない。
現状破ればお前は、牢屋行きだからな。
ああ、おかしな仕組みの世の中だろう?」
「牢屋は嫌だよ。」
「行かない方法は簡単さ。……奴ら馬鹿な連中に気づかないようにする。」
「そんな上手くやれない!
それに嘘はつけない!」
カイはまたいつもの調子になったのか、お得意の倫理観を振りかざす。
「では、カイ。嘘をつかなくていい方法がある。そうだ、そもそもルールを無くしてしまう方法がひとつな。」
ヴォルデモートが人差し指を優雅に立てたあと、西日がようやく彼の輪郭を輝くように照らしだした。
カイは、その光景が綺麗だと思った。
「私が、ルールを作る人間になる。
我々より弱い人間を下に従えて奴らを導いてあげるんだ。そして堂々とこの世に魔法をかざす。
穢れた血と崇高な血を分別して、お前のように力に 苦しむものが出ないようにする。
私たちはもう、何も困らない。自由だ。」
静かに揺れる黒いカーテンがカイの顔に模様をかける。呆気に取られた碧のカイの瞳には、不敵に笑う美しい男の姿がただ鮮明に映し出されていた。