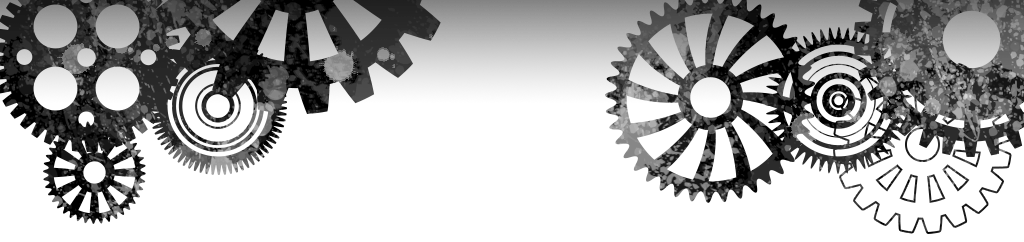幼少期
今まで7年間過ごしてきた友達も、仲間も、カイの力を知ってしまえば全て無くなってしまったのだ。
その事を、泣きながら今の家主に話せば、
「そんなのに振り回されるなんて可哀想だな、お前は。全て初めから虚構だ。」
と、カイに哀れな目を向けて言ってきた。
家主のどこか引っかかる物言いと、目の奥が冷たいことに気がつきカイの心はさらに沈みそうになる。
だけど家主は、大きな手のひらでカイの頭を優しく撫でてくれた。
ただ単に、家主が冷たい人なのか、それとも優しさに不器用なのかはカイにはまだ分からない。
だけど、その家主の行動が傷ついたカイの心に蓋をしてくれた。
ヴォルデモートが、どうして一人ぼっちになったカイを引き取ったのかは分からない。
しかし紛れもなくカイの中の事実としては、
ヴォルデモートはカイに居場所をくれた人。
この世界ではそうなのだ。
カイは子供であるため大人の難しい話は分からない。
だから今は、ヴォルデモートがカイの道標になる。
それが悲しくも、現実だ。
カイに新しい居場所を与えてくれる誰かが現れない限り、きっとずっとこのままなのだろう。
だからそれまで生きていくために、カイは彼に見放され殺されるようなことがあってはならない。
「どうして……彼女を引き取った?」
1度、ヴォルデモートの側近がこう訪ねてきたことがあった。男は、アブラクサス・マルフォイ。
ヴォルデモートの、学生時代からの旧知の仲にあたる。
彼は、1番ヴォルデモートにフランクに接せることができる唯一の人物と言っても過言ではないだろう。
そんな、アブラクサスだからこそ、ヴォルデモートが突然手元に置いた謎の小さな子供の存在が気になって仕方がないようだ。
魔法界ならず周辺の行方不明情報、孤児の情報を辿ろうが何の手かがりもない。謎のベールに包まれる血筋も不明な少女の存在を野放しにできないアブラクサスはヴォルデモート同様、疑り深い人物であった。
「彼女はいったい……誰なんだ?」
アブラクサスは無意識の内にまるでマグルを語る時のように、顔を歪めてヴォルデモートに問うた。
しかしヴォルデモートは、アブラクサスの目を刺すような冷たい視線を向けた。
アブラクサスは、ヴォルデモートのその反応で自分は聞いてはいけないことを聞いてしまったのだと先程の言動を酷く後悔した。
「まるで俺が穢らわしい血でも拾ってきたのかと言いようだな?」
「いや……そんなつもりは……無礼をお許し下さいませ我が君。」
アブラクサスは、頭を下げ1歩後ろに下がる。額からは静かに汗が込み上げていた。
「あの子はいずれ手となり足となる。たとえ子供でも身を尽くして敬え。周りの噂好きの死喰い人にもそう伝えろ。」
「……ああ、分かった。」
「それと……自身に陶酔しては足元を掬われる。これもだな。」
ヴォルデモートは、口元に薄ら笑を浮かべた。
彼の背中が見えなくなった後、アブラクサスは自分の膝が情けなくも震えているに気がついたのだった。
その日から、組織の過激な権力争いの中、カイはスルリと確かな地位を確立できた。
しかしそれはこれから辿るべき道を暗示されるのと同じ事であったのだ。
その事を、泣きながら今の家主に話せば、
「そんなのに振り回されるなんて可哀想だな、お前は。全て初めから虚構だ。」
と、カイに哀れな目を向けて言ってきた。
家主のどこか引っかかる物言いと、目の奥が冷たいことに気がつきカイの心はさらに沈みそうになる。
だけど家主は、大きな手のひらでカイの頭を優しく撫でてくれた。
ただ単に、家主が冷たい人なのか、それとも優しさに不器用なのかはカイにはまだ分からない。
だけど、その家主の行動が傷ついたカイの心に蓋をしてくれた。
ヴォルデモートが、どうして一人ぼっちになったカイを引き取ったのかは分からない。
しかし紛れもなくカイの中の事実としては、
ヴォルデモートはカイに居場所をくれた人。
この世界ではそうなのだ。
カイは子供であるため大人の難しい話は分からない。
だから今は、ヴォルデモートがカイの道標になる。
それが悲しくも、現実だ。
カイに新しい居場所を与えてくれる誰かが現れない限り、きっとずっとこのままなのだろう。
だからそれまで生きていくために、カイは彼に見放され殺されるようなことがあってはならない。
「どうして……彼女を引き取った?」
1度、ヴォルデモートの側近がこう訪ねてきたことがあった。男は、アブラクサス・マルフォイ。
ヴォルデモートの、学生時代からの旧知の仲にあたる。
彼は、1番ヴォルデモートにフランクに接せることができる唯一の人物と言っても過言ではないだろう。
そんな、アブラクサスだからこそ、ヴォルデモートが突然手元に置いた謎の小さな子供の存在が気になって仕方がないようだ。
魔法界ならず周辺の行方不明情報、孤児の情報を辿ろうが何の手かがりもない。謎のベールに包まれる血筋も不明な少女の存在を野放しにできないアブラクサスはヴォルデモート同様、疑り深い人物であった。
「彼女はいったい……誰なんだ?」
アブラクサスは無意識の内にまるでマグルを語る時のように、顔を歪めてヴォルデモートに問うた。
しかしヴォルデモートは、アブラクサスの目を刺すような冷たい視線を向けた。
アブラクサスは、ヴォルデモートのその反応で自分は聞いてはいけないことを聞いてしまったのだと先程の言動を酷く後悔した。
「まるで俺が穢らわしい血でも拾ってきたのかと言いようだな?」
「いや……そんなつもりは……無礼をお許し下さいませ我が君。」
アブラクサスは、頭を下げ1歩後ろに下がる。額からは静かに汗が込み上げていた。
「あの子はいずれ手となり足となる。たとえ子供でも身を尽くして敬え。周りの噂好きの死喰い人にもそう伝えろ。」
「……ああ、分かった。」
「それと……自身に陶酔しては足元を掬われる。これもだな。」
ヴォルデモートは、口元に薄ら笑を浮かべた。
彼の背中が見えなくなった後、アブラクサスは自分の膝が情けなくも震えているに気がついたのだった。
その日から、組織の過激な権力争いの中、カイはスルリと確かな地位を確立できた。
しかしそれはこれから辿るべき道を暗示されるのと同じ事であったのだ。