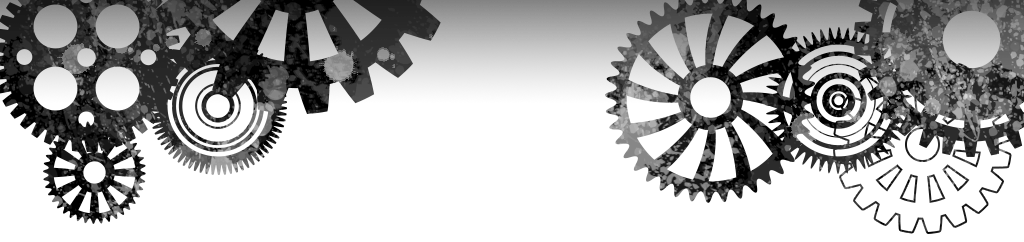幼少期
忍びこんだお化け屋敷こと、あの魔法使いの洋館はヴォルデモートの配下にある死喰い人専用のアジトらしい。
ヴォルデモートに促されて彼の左手を取ると、カイはなにか小さいところに無理やり体をねじ込まれていくような感覚に陥った。どうやらこれが姿表しというらしい。実に気分が悪い感覚にカイは頭を抱えた。
そして、ヴォルデモートの屋敷にたどり着き今に至る。
屋敷と言っても、最初はなんにも無い森に見えた。
ヴォルデモートの構える屋敷はさっき洋館よりもっと綺麗。
1人で暮らしているにもかかわらず、大所帯の孤児院よりも広々としており、そしてガランと寂しい。
ホコリひとつない、ピカピカの大きなダイニングテーブルも、ふかふかのソファが並べられた客間も、人が住んでいる全く感じられないモデルルームのようだった。
そう言えばカイ達は先程から一言も会話をしていない。
彼はなにも喋らないのだ。
ヴォルデモートという悪者と歩いているカイの身はもう持ちそうにない。というか、そもそもこの男はつるっパゲで蛇のように恐ろしい成りをしていた気がするのだが、なんというかカイの前にいるヴォルデモートは一般的に言えば…いや凄く美しい。
だからこそ、その違いが余計に今という現実をリアルにさせる。
なにか話さなければいけない。
カイは言葉を探そうとするが、なんにも見つからない。
「広いですね」とかそんな野暮すぎること言えないし、
「なんで私を連れてきたんですか」とか核心を着けば殺されそう。
「ヴォルデモートって長いですよね、お呼びすれば?」とかは論外だし、「そもそも、本当に一緒に暮らすんですか?」なんて聞けば無かったことにされそうだ。
カイの比較的フレンドリーな性格も、所詮井の中の蛙だった。悪者を前にするとなんにも出てこない。
「……遅い。」
カイは、その声にハッと顔を上げる。ヴォルデモートと私の距離はなんと10mほど開いていた。どうやら考え事をしている内にそうなってしまったようだ。カイは急いで彼の方に近づいた。
だけど、ヴォルデモートはカイとの距離を見つめた。
2m程ある。カイにはこの2mが限界の距離なのだが、ヴォルデモートはその距離を詰めた。思わずびっくりするカイ。
「俺が怖い?」
まさか、いや、悟られない方がおかしいか。
カイは自分の膝が少し震えているのをみて納得した。ヴォルデモートという壮大すぎる悪者に直接、「怖い?」と聞かれるほど怖いことはない。怖いもの本体に怖い?と聞かれるのはわりと相当なダメージを受ける。
でも、怖がっていては何も始まらない。
カイの目の前にいるのは、ヴォルデモートだ。
だけど、カイの世界のヴォルデモートなのだ。
前を向かなければならない。
「怖く……ない。」
ヴォルデモートは、カイがそう言いながらも下唇を噛んでいるのを見て笑った。
「お前がそうやって、強がってくれる方が悪くない。ビクビクされるのには飽きたからな。」
「お前じゃない。カイ……です。」
「分かっているよ。だが俺の好きにする。
そうだ、この際行っておく。分かっているね、この家でのルールは俺だ。」
ヴォルデモートは、カイの方に身を屈めた。
カイは少し横暴なヴォルデモートの物言いに、無意識の内に眉をひそめた。
「俺が、この部屋に入るなと言えば入るな。寝ろと言ったら寝ろ。勉強しろと言ったら勉強しろ。あと黙れと言ったら黙る。」
ヴォルデモートは、少し宙を仰ぎながら流暢に言葉を並べる。
そして、急に声の色を変え、低くした。
「つまり……やれと言ったらやれ。」
ヴォルデモートの深紅の瞳にカイの背中はゾクッとした。
「その代わりだ。
俺は君には欲しいものを与えると言っただろう?
手始めに何が欲しいか言ってみろ。」
ヴォルデモートは、優しくそれでもどこか威圧的にカイに問いかけた。その中でカイの頭に浮かんだのは、ひとつしか無かった。
これを言えば、きっとヴォルデモートは嫌な顔をするだろう、私の事を疎ましく思うだろう。
予感でそう感じたけど、嘘をつきたいとはなぜかこの時思わなかったのだ。だから、カイはヴォルデモートの目を真っ直ぐに見つめて言う。
「居場所……が欲しい。
私は家族が欲しい。」
ヴォルデモートは少し呆気を取られたように、一瞬目を見開いた後鼻で笑った。
「家族……ねえ。
なんて人並みで反吐が出る幸せだ。」
「それでもいい。この世界の皆が家族を持っていないとしても、私は家族が欲しいんだ。」
「……なに?そんなにお前は孤独?」
「孤独じゃないよ、私の心の中は1人じゃない。」
あまりに、カイがそう無垢に言うものだからヴォルデモートは呆気にとられてしまった。悪者に向かって何を言っているのだろう。カイは一瞬そんなこと考えたが別に良かった。前に真っ直ぐに愛された記憶があるから、家族が欲しい。
ただそれだけの事なのだ。
「本当に意味が分からない。
ならば、いらないだろう?」
「でもわたしには家族っていいねって言える人がいないから。」
「……忌々しいな。
もっとマシなことを言えるガキかと勘違いしていたのに。」
ヴォルデモートは絞り出すように気だるげなため息をついたが、カイは特段気にする様子も無く周りの景色を興味深そうに見渡した。そして、「聞かれたことに答えただけなのに」と小さく呟いた。
少なからず闇の魔法使いということを自覚しているヴォルデモートは、あまりにも察しの悪い目の前の子供に心底腹が立っている……よりも期待が外れた事により自分自身に嫌悪感を感じていた。
「あなたに、家族はいないの?」
「………………は?」
ヴォルデモートは、自分の喉から酷く低い音が鳴るのを感じた。同時に、目元がカッと燃えるような感覚を覚える。
しかし、目の前の少女は尚も言葉を飲み込もうとはしなかった。
「だって家族って言う度、あなたはさっきからとても悲しそうな目をしているから。」
カイがそう言った途端、廊下にあった花瓶が割れた。
そして、その破片はカイの頬を掠めた。
カイは、恐る恐るヴォルデモートの方を見ると、ヴォルデモートの瞳は血が染ったような赤だった。
ヴォルデモートの、白い肌が余計にそのコントラストを増長させた。
「悲しそう?笑わせるな。
お前のような子供に何がわかる?」
「大体お前は孤児だ。所詮手に余る存在だろう?さっきだって、お前は裏切られたんだ。なのに、いつまで家族なんて夢を見てる?」
ヴォルデモートは、必死で怒りを抑えようと静かに話すがそれが余計に恐ろしかった。
そして、ヴォルデモートは右手にある扉をバタンと大きな音を立てて開いた。
「お前の部屋だ。
夕飯までここにいろ。」
カイは、ガチガチに固まった体をなんとか部屋の方に向けた。
すると、ヴォルデモートがカイの方に歩いてきた。
そして、カイの白い頬から垂れる赤い血を見て少し身震いをした。見慣れている色に関わらず感じたことの無い感情が、ヴォルデモートを押し寄せた。
それに、余計に腹を立てた。
「いいか?2度はない。
そして、俺に家族だなんて淡い期待を持っても無駄だ。
諦めろ。」
ヴォルデモートは、そう言ってカイの前から姿を消した。
カイは、自分の部屋を見る。
そこには、見たこと無いぐらいに大きな天秤ベッドが部屋の中央に置かれてあった。
ヴォルデモートに促されて彼の左手を取ると、カイはなにか小さいところに無理やり体をねじ込まれていくような感覚に陥った。どうやらこれが姿表しというらしい。実に気分が悪い感覚にカイは頭を抱えた。
そして、ヴォルデモートの屋敷にたどり着き今に至る。
屋敷と言っても、最初はなんにも無い森に見えた。
ヴォルデモートの構える屋敷はさっき洋館よりもっと綺麗。
1人で暮らしているにもかかわらず、大所帯の孤児院よりも広々としており、そしてガランと寂しい。
ホコリひとつない、ピカピカの大きなダイニングテーブルも、ふかふかのソファが並べられた客間も、人が住んでいる全く感じられないモデルルームのようだった。
そう言えばカイ達は先程から一言も会話をしていない。
彼はなにも喋らないのだ。
ヴォルデモートという悪者と歩いているカイの身はもう持ちそうにない。というか、そもそもこの男はつるっパゲで蛇のように恐ろしい成りをしていた気がするのだが、なんというかカイの前にいるヴォルデモートは一般的に言えば…いや凄く美しい。
だからこそ、その違いが余計に今という現実をリアルにさせる。
なにか話さなければいけない。
カイは言葉を探そうとするが、なんにも見つからない。
「広いですね」とかそんな野暮すぎること言えないし、
「なんで私を連れてきたんですか」とか核心を着けば殺されそう。
「ヴォルデモートって長いですよね、お呼びすれば?」とかは論外だし、「そもそも、本当に一緒に暮らすんですか?」なんて聞けば無かったことにされそうだ。
カイの比較的フレンドリーな性格も、所詮井の中の蛙だった。悪者を前にするとなんにも出てこない。
「……遅い。」
カイは、その声にハッと顔を上げる。ヴォルデモートと私の距離はなんと10mほど開いていた。どうやら考え事をしている内にそうなってしまったようだ。カイは急いで彼の方に近づいた。
だけど、ヴォルデモートはカイとの距離を見つめた。
2m程ある。カイにはこの2mが限界の距離なのだが、ヴォルデモートはその距離を詰めた。思わずびっくりするカイ。
「俺が怖い?」
まさか、いや、悟られない方がおかしいか。
カイは自分の膝が少し震えているのをみて納得した。ヴォルデモートという壮大すぎる悪者に直接、「怖い?」と聞かれるほど怖いことはない。怖いもの本体に怖い?と聞かれるのはわりと相当なダメージを受ける。
でも、怖がっていては何も始まらない。
カイの目の前にいるのは、ヴォルデモートだ。
だけど、カイの世界のヴォルデモートなのだ。
前を向かなければならない。
「怖く……ない。」
ヴォルデモートは、カイがそう言いながらも下唇を噛んでいるのを見て笑った。
「お前がそうやって、強がってくれる方が悪くない。ビクビクされるのには飽きたからな。」
「お前じゃない。カイ……です。」
「分かっているよ。だが俺の好きにする。
そうだ、この際行っておく。分かっているね、この家でのルールは俺だ。」
ヴォルデモートは、カイの方に身を屈めた。
カイは少し横暴なヴォルデモートの物言いに、無意識の内に眉をひそめた。
「俺が、この部屋に入るなと言えば入るな。寝ろと言ったら寝ろ。勉強しろと言ったら勉強しろ。あと黙れと言ったら黙る。」
ヴォルデモートは、少し宙を仰ぎながら流暢に言葉を並べる。
そして、急に声の色を変え、低くした。
「つまり……やれと言ったらやれ。」
ヴォルデモートの深紅の瞳にカイの背中はゾクッとした。
「その代わりだ。
俺は君には欲しいものを与えると言っただろう?
手始めに何が欲しいか言ってみろ。」
ヴォルデモートは、優しくそれでもどこか威圧的にカイに問いかけた。その中でカイの頭に浮かんだのは、ひとつしか無かった。
これを言えば、きっとヴォルデモートは嫌な顔をするだろう、私の事を疎ましく思うだろう。
予感でそう感じたけど、嘘をつきたいとはなぜかこの時思わなかったのだ。だから、カイはヴォルデモートの目を真っ直ぐに見つめて言う。
「居場所……が欲しい。
私は家族が欲しい。」
ヴォルデモートは少し呆気を取られたように、一瞬目を見開いた後鼻で笑った。
「家族……ねえ。
なんて人並みで反吐が出る幸せだ。」
「それでもいい。この世界の皆が家族を持っていないとしても、私は家族が欲しいんだ。」
「……なに?そんなにお前は孤独?」
「孤独じゃないよ、私の心の中は1人じゃない。」
あまりに、カイがそう無垢に言うものだからヴォルデモートは呆気にとられてしまった。悪者に向かって何を言っているのだろう。カイは一瞬そんなこと考えたが別に良かった。前に真っ直ぐに愛された記憶があるから、家族が欲しい。
ただそれだけの事なのだ。
「本当に意味が分からない。
ならば、いらないだろう?」
「でもわたしには家族っていいねって言える人がいないから。」
「……忌々しいな。
もっとマシなことを言えるガキかと勘違いしていたのに。」
ヴォルデモートは絞り出すように気だるげなため息をついたが、カイは特段気にする様子も無く周りの景色を興味深そうに見渡した。そして、「聞かれたことに答えただけなのに」と小さく呟いた。
少なからず闇の魔法使いということを自覚しているヴォルデモートは、あまりにも察しの悪い目の前の子供に心底腹が立っている……よりも期待が外れた事により自分自身に嫌悪感を感じていた。
「あなたに、家族はいないの?」
「………………は?」
ヴォルデモートは、自分の喉から酷く低い音が鳴るのを感じた。同時に、目元がカッと燃えるような感覚を覚える。
しかし、目の前の少女は尚も言葉を飲み込もうとはしなかった。
「だって家族って言う度、あなたはさっきからとても悲しそうな目をしているから。」
カイがそう言った途端、廊下にあった花瓶が割れた。
そして、その破片はカイの頬を掠めた。
カイは、恐る恐るヴォルデモートの方を見ると、ヴォルデモートの瞳は血が染ったような赤だった。
ヴォルデモートの、白い肌が余計にそのコントラストを増長させた。
「悲しそう?笑わせるな。
お前のような子供に何がわかる?」
「大体お前は孤児だ。所詮手に余る存在だろう?さっきだって、お前は裏切られたんだ。なのに、いつまで家族なんて夢を見てる?」
ヴォルデモートは、必死で怒りを抑えようと静かに話すがそれが余計に恐ろしかった。
そして、ヴォルデモートは右手にある扉をバタンと大きな音を立てて開いた。
「お前の部屋だ。
夕飯までここにいろ。」
カイは、ガチガチに固まった体をなんとか部屋の方に向けた。
すると、ヴォルデモートがカイの方に歩いてきた。
そして、カイの白い頬から垂れる赤い血を見て少し身震いをした。見慣れている色に関わらず感じたことの無い感情が、ヴォルデモートを押し寄せた。
それに、余計に腹を立てた。
「いいか?2度はない。
そして、俺に家族だなんて淡い期待を持っても無駄だ。
諦めろ。」
ヴォルデモートは、そう言ってカイの前から姿を消した。
カイは、自分の部屋を見る。
そこには、見たこと無いぐらいに大きな天秤ベッドが部屋の中央に置かれてあった。