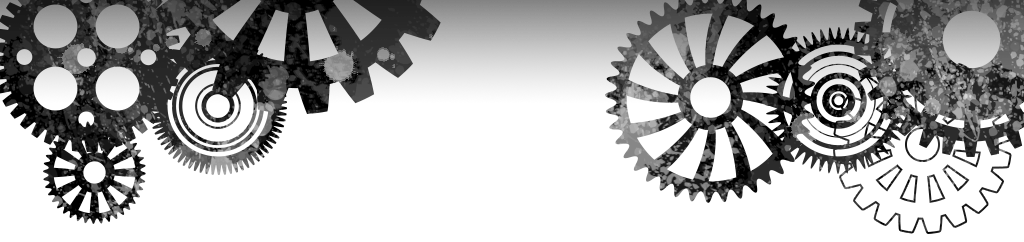幼少期
運命とは残酷だ。
やっぱり神さまなんて居ない。
私を、この世に送り出した女神は偽物だ。
どれだけ、善人であろうが、前世のパパとママの掟を守ろうがこの世界では関係無いことなのだ。
カイは心からそう思うことになる。
カイは、この屋敷に囚われた。
初めは本当に些細な事だった。それが、カイの人生をこんなにも大きく左右してしまうなんて思いもしなかった。
予測出来ていたならば、カイは誰になんと言われようが一目散にこの場から逃げ出したであろう。
孤児院の友達に連れられて不本意に近づいたこの屋敷。
友達たちにはどうしても廃墟のようにしか見えなかったようだ。
確かに、無法地帯のそこに生える草木はカイたちの身長を悠々に飛び越している。ツタの葉は、割れた窓ガラスから豪快に侵入している。建物はもとは頑丈な作りなのか、どこか風格がありかないい所の良家がすんでいたのかもしれない。
しかし、煤だらけ。
すると、その"お化け屋敷"を先日孤児院から自転車でうんと遠くまで行った少年達が見つけてきたのだ。
「すっげえお化け屋敷があるぜ!」と、お調子者で天真爛漫な少年・タイラーがそうみんなに働きかければ、好奇心旺盛な子供たちは黙ってはおけない。小心者の男の子も、怖いものが嫌いな女の子も、皆が行くとなれば話は別らしい。ノリノリの雰囲気の中カイが、「マザーに怒られるよ」と咎めても、「どうした、いつも済ました顔してるくせに!怖いんだな?」と茶化されるだけだった。しまいには、1番の仲良しのライラから「ついてきてよ!貴方がいないと、タイラーの暴走を止めれる人はいないもの!」としつこくお願いされ、行かざるを得なかった、という話だ。
こうなると仕方が無い。
先頭でみんなを従えるタイラーを筆頭に、カイは一番後ろからついて行くこととなった。
しかし、その場所に住み着いていたのはゴーストでもなんでもない。それよりももっと恐ろしい、闇の魔法使い達だったのだ。
""お化け屋敷""はマグルのための見掛け倒しにしか過ぎなかった。物騒な雰囲気を醸し出す扉を開け、皆に並んでついて行くと、肌でどこかただならぬ雰囲気を感じた。
この古く恐ろしい洋館は、歩く度にミシミシと音を立てる。蜘蛛の巣があちこち張り巡らせてあって、当然気味が悪く、皆思い思いに小さく悲鳴をあげる。
「おい、何怖がってんだよお前ら。」と、タイラーの声も少しばかりだがいつもより上ずっていた。
しかし、皆と、カイが感じる恐怖は別のものだ。
お化けやそんなものでは無い。この屋敷に入った途端、自分の持つ魔力が何かに反応しているよう気がするのだ。
それも、背筋が凍るような恐ろしい感じがする。カイ自身、誰かの魔法に触れるのははじめてのことで、これが魔法なのかは分からない。
すると突然、ライラがカイの方を振り向いて、「なんだか、倒れそうなの……」と真っ青な顔をして話しかけてきた。その目は虚ろで、怖くて真っ青な顔をしているのでは無いのだとカイは一瞬で分かった。それをきりに明らかに皆の様子がおかしい。それぞれの脚はもたつきはじめ、しまいには、苦しいのか微かに呻き声をあげる子までいた。
このままでは皆なにかに飲み込まれてしまう。
早くここから出なくちゃならない。
「出るよ!」カイは皆に聞こえるように声を張り上げて、真っ青な顔をしたライラを引っ張り、出口を目指そうとした。
しかしその瞬間、バタン!!と何かが倒れる音がした。カイは、反射的に大きく振り返ると、何と倒れていたのはさっきまで1番先頭にいたタイラーだった。
カイは彼の方へ一目散に駆け寄るが、突然何か白いモヤのようなものに目の前が遮られてしまった。ただならぬこの状況に誰かの泣き叫ぶ声がが聞こえるが今はそれどころではない。
とにかく、タイラーの無事を確かめるべく白いモヤをかき分けるとようやく彼の顔が見えた。
「タイラー!しっかり!」
しかし、彼の目は固く閉じられ、唇は青かった。
息はしているようだったが、タイラーは完全に失神していて起きる気配が全くない。
起こったことを頭の中で整理しようとするけど、全くカイの脳みそは機能していない。だけど、ただ一心ここから早く逃げ出さなくてはという堅い決意がカイの心を支配していた。
タイラーの方を揺さぶり続けるとようやく彼の目は開かれた。カイは、彼をいたわる暇なんてなくタイラーの腕をグイッとカイの肩に乗せた。
「みんな、逃げるよ!」
ようやく白いモヤが消えた。
座り込む仲間達を必死で立つように促し、出口を目指す。
カイよりも体重の重い上、意識がまだハッキリとしないタイラーを支えながら走るのはとても難しく辛かった。
これは魔法の罠だ。
みんなをここから無事に出してあげないといけない。
だって、私はパパとママの子だ。そして、魔法使いなんだ。
"無駄だよ。たかがマグルが、逃げ出そうなんてね。"
突然、ノイズ音のように低い声が聞こえてきた。
"ここは、子供が来る場所では無いんだよ。
まんまと、捕らわれにくるなんてね。"
「誰だよ!」
思わず立ち止まって、気持ちの悪い声に反応する。
「おい!カイ!何止まってるんだよ!早く行くぞ!」
「ねえ、マイク。聞こえないの?」
「何がだよ!!お化けの声だとかいうなら後にしてくれよな!」
マイクは、怒りと興奮を抑えられない様子でそう言った。
自分以外に聞こえないなんて、これが魔法使いの仕業だと言うことは確証的だと思った。しかし、この魔法使い、マグルを相当恨んでいるのだろうか。
だけど今は、探偵ごっこをしている暇はない。
カイは、またタイラーを支えて走り出す。
"無駄なのになあ。走ったって出口は無い。"
気味悪い声がそういった途端、足元がぐらついた。
そして、古びた洋館の様子が変わっていく。なんと、先程まで廊下に敷かれていたボロボロの暗赤色の絨毯は、シルクのようにキメ細やかで真新しい黒いカーペットに変わっていく。
煤だらけの壁紙にあった外れ掛けの古びた肖像画は、なんの装飾も汚れもない唐草模様の黒い壁紙に変わっていく。
なるほど。
ホグワーツと同じ仕掛けだ。
マグルには、廃墟の洋館にしか見えないようにしてあるんだ。
「おかしいわよ、カイ!走っても走ってもお化け屋敷から抜け出せないの!」
そして、マグルのライラ達にはずっと見た目はお化け屋敷のままで、魔法がかけられたせいで今は出口の場所が変わり、永遠に同じ場所をループしているようになっているのかもしれない。
全部、予想だけれどそう考えるのが1番早いだろう。
だけどカイは、魔法使いだ。
例え魔法がかけられ出口が変わっても、それが分かる。
カイは、タイラーをマイクに預けて、みんなが自分に着いてくるように指示をした。
「大丈夫!景色は変わらないかもしれないけど、私についてきたらきっと抜け出せるから!着いてきて!」
そう言って、みんなには見えない廊下の突き当たりを曲がったりしながら出口を模索した。
「なんも、変わんないよ!本当に大丈夫なの?」
「大丈夫よ!ライラ!私を信じたらいい、お願いだから。」
カイの必死の口調が伝わったのか、みんな素直にカイに従って着いてきてくれているようだった。
するとようやく、扉が見えた。
その扉は、来た時よりも随分と背が高く木目も無くただひたすらに黒かった。
「見えたよ!」
ようやく出られるんだ。
カイの表情は思わず、綻んだ。
だけど、すぐに崩れ落ちた。
"逃げられないって言ったはずだ。"
そこに現れたのは、無機質なドクロのお面を被り、黒いローブを身にまとった男だった。
「……誰ですか。あなた」
声が震えないようにカイがそう言うと、男は高笑いをした。
そして、気色悪い声から人間味のある男の声に変わった。
「君、私のことが見えるんだね。
多分後ろのお仲間達には見えないと思うよ。」
カイが後ろを振り向くと、みんな埃を払うようにして手を振っている。
「また、白いモヤだ……、なんなのこれ?」
そうライラが言うのが聞こえた。
カイには白いモヤが全く見えない。
魔法使いには見えないように、仕掛けてあるのだろう。
「マグルには到底目指せないはずだが、君たちは随分と真っ直ぐに出口に向かうと思ったんだ。それもそのはず、君には屋敷全体に掛けられたこの錯乱呪文が効かないんだからね。」
そう男は言うと、カイの元に徐々に近づいてくる。
「来るな!」
カイはみんなを庇うように、手を広げた。
「へえ、魔法使いのヒーローか。立派だねぇマグル達を守るなんて。。」
男はそう言うと、カイの後ろにいるライラに目をやった。
ライラは、そんなこと気にもとめず、「あなたさっきから何と話しているの?!」と、心底気味が悪そうにカイの方に尋ねてきた。
「子供の魂……か。利用価値はさぞあるだろうね。」
そうしてライラの方に杖を向けた。
「ライラに手を出すな!」
ライラの前に目いっぱい立ふさがる。
「では、代わりに君の魂を差し出す?」
男は今度はカイの方に杖を向ける。
絶対に怯んでやるものか。
「……それで皆、助けてくれるというのなら。
惜しくないし、怖くもない。」
「たかが、赤の他人に命を差し出すなんてね。
彼女達ちそれほどまでの価値があるというのかな?」
そう言うと、男はこれでもかと言うほど大きく笑った。
そして、閃光をマイクの方に飛ばした。
すると突然、マイクは大声を出して苦しみ始めたのだ。
「うわあああああア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"」
「何すんだやめろ!私にやればいい全部!!」
「この状態を見てもまだ、庇うんだね?本当に感心するよ。
如何なる時にも切れない絆ってやつか。そんなもの存在しないのに。」
「ガタガタうるさい!友達だから!助けたいから助けるんだ!」
そう言い、男の方に向かっていくと男は今度はカイに杖を向けてた。
「フリペンド」
カイは吹き飛んだ。
そして勢いよくもがき苦しむマイクの方に向かって投げ出された。
マイクにかかった呪文はそこで途絶えたのか力尽きたようにへたんと床に座り込んでしまった。
「あまり信じすぎない方がいい。人は簡単に裏切る。特にマグル……とかいう存在はね。」
「……アンタは一体なんなの?」
「私?……そうだな……。
魔法使いの君になら歳期にくらい教えてあげてもいいか。」
男は、仮面を外した。そして、身にまとっていたフードを外した。すると、仮面の下から光った瞳は赤だった。深紅のその色は相手の目を射抜く。絹のようにサラサラの黒い髪は、几帳面に目元にかかる程度に流されてある。
男と呼ぶには妖しくそれでも逞しく、カイの出会ったものの中でいちばん美しい人だった。
カイが思わず息を飲み見とれるその数秒後新たに男とは反対方向に黒いローブの輩が一人現れた。
「穢らわしい、人間のガキ共が……。
卿の屋敷に入って許されるとでも思うなよ! 」
輩の声は冷静さをまるで失っている。
「いい、下がれ。
俺様が全て方を付ける。」
男は、輩に向かって恐ろしく冷たい声でそう命令したが、輩の耳には届いていないようだ。
「こんなガキ共のために、卿が手を穢していい訳が無い……!
是非、吾輩にお任せ下さい!」
そう言葉にする輩を、男は何も言わずただ冷たい目で見つめていた。ライラ達には、もちろんこの輩も霧により見えておらず何が何だか分からないようだ。
そして得体の知れぬ不穏な空気を感じとっている。
それをいいことに、輩はニヤリと口角を上げて1番近くにいた女の子に杖を振り上げた。
「やめろ!」
カイが止める声と、奴が呪文を放った声は重なった。
「デパルソ」
女の子の体は宙を舞い、大きく壁に打ち付けられた。
ただ事では無い事態に、ライラもマイク達も悲鳴を上げて、完全にパニック状態だ。
「もうやめて!誰なの!?」
ライラがそう叫ぶと、輩は今度はライラの方に目線をやり笑い声を上げた。
「馬鹿な、ガキ。自分の身に起こっていることすら分からず死んでいくなんてな!!」
そして、ライラの体を呪文でキツく縛り上げた。
「やめてってば!ねえ!!」
カイがそう叫んで泣き叫ぼうが、ライラの呻き声を上げ苦しんでいる。輩はそれを見てさぞ愉快そうにし、杖を振り上げたままだ。
そして男は、そんな様子をずっと静かに眺めていた。
こんなのおかしい。なんで何も知らない、力を持たないライラ達が苦しめられなければならないのか。
わたしの、友達なのに。
ライラは私がこの世界に来て初めて出来た友達なのに。
そう思うと、カイの中から今まで感じたことがないほどの怒りが込み上げてきた。その怒りはカイの体内を凄まじい勢いで駆け巡り、手に込められる力とは別の力が湧き上がってくるのだ。
だけど、これをもう止めようとは思わない。
いや、止められない。
「アバダ……」
輩がそう呟くとその瞬間、すざましい爆発音を上がる。
そこら中の物が吹き飛び、当たりは燃え上がった。
だけど、私の周りには何一つ変化がない。ただ輩の周りに降り注ぐ炎だけが延々と萌え続けているのだ。
輩はその燃え上がる炎をただ、唖然として見つめている。
そして次にカイの方をみて輩はこれでもかと言うほど目を見開いた。
その輩の目に込められたものは、かつてカイ達の目にあった恐怖だった。
カイは不審に思い自分の体を見渡す。
すると、カイの手のひらには炎が燃え盛っていた。
だけど、不思議なことにちっとも熱くない。それどころか、湧き上がるエネルギーをどこまでも爆発させられそうな程に高揚感に満ちていた。
男が、炎に包まれたカイを、驚いたように見つめる。
しかし、すぐに表情を戻し形のいい唇の口角を上げて見せた。
「……面白い。」
炎は全てカイの魔力の暴走によるもの。
カイ自身もそれを何となく察していた。だけど、初めて感情による魔力を爆発させたせいで、おさめ方が分からないのだ。そのおかげで炎は燃え盛るばかりだ。
このカイの様子を見たのは、もちろん男と輩だけではない。
ライラ、マイク、タイラー含め、孤児院の子達全員なのだ。
全てのものを吹き飛ばし、カイの手に燃え盛る炎を見て、彼らは唖然としていた。そして、カイから1歩2歩後退りをする。
カイの1番近くにいたライラも物凄い勢いでカイから離れ、今まで縛りつけられていた苦しみと、この目の前の光景への恐怖がごちゃ混ぜになってしまっていた。
「全部、お前が……?」
タイラーは、小さくそう呟いた。
「違う!!!」
カイは、タイラーに手を伸ばそうとするが自分の燃え盛る手を見て慌てて引っ込めた。
はやく、おさまって!お願いだから!カイはそう、心の中で願うも炎は収まることも知らず次第に天井のシャンデリアは音を立ててカタカタと震え出す。
「じゃあ、お前以外に誰がいるんだよ!!!」
マイクは声をはりあげてそう言う。
「違うの!聞いてってば!」
「周りにお前以外おかしいものは無い!俺らを怖がらせて楽しいかよ!怖がらせるだけじゃない!!タイラーを失神させたり、俺や、ライラをもがき苦しめたり!!!!」
「だから、私じゃないんだってば!!」
「そんな化け物みたいな炎出しているお前以外誰がいるんだよ!!!」
タイラーは、そう声を張り上げる。
カイはついに何も言い返せなくなった。
タイラーだけでない。他のみんなが自分を見る目は、明らかに軽蔑。怪物を見るような目だった。
そんな中、ふとカイはライラと目が合った。
「ち、ちがうの、ねえライラ。」
カイは絞り出すようにそう言い、ライラの元に歩み寄る。
「お願いだから来ないで!!!」
しかし金切り声でそうピシャリと言い放たれてしまったのだ。
まるで、カイは体を引き裂かれる呪文を受けたのかと言うほどに心臓が痛かった。
ショックのあまり表情筋がひとつも動かないのだ。
その反動なのか、カイの手だけでなく今度は足元からも炎が湧き出てくる。
ライラたちはまた悲鳴をあげた。
「逃げるぞ!!」
そう叫んだのはタイラーだった。
タイラーが目指した先は、先程まであった背の高い光沢に満ちた黒いドアでは無く、この屋敷に入った時に見た古びた厚い木の扉だった。
どうやら、この屋敷にかけられた呪文が解けた……あるいは何かに阻まれたおかげでもとの"お化け屋敷"のビジュアルに戻ったようだ。
タイラー達は、カイも、その様子をただ静かに眺めていた端正な男にも目もくれず、一目散に駆け出して言ったのだ。
親友だと言ってくれたライラですらも、1度もカイの方を振り向くことは無かった。
男は、屋敷から逃げ出すライラ達を見ても引き止めることも何もせずに興味無さげにその後ろ姿を見送った。
そして男は視線をカイの方に移した。
男の目の色にはなんの感情も感じられない。ただ、ひたすらに深紅の瞳が、炎に包まれたカイを映し出すだけだった。
そのまま彼女達はどんどん遠ざかっていく。
でも、カイはもうあの背中を追いかけることは出来ない。
彼らの戻る場所は、どこか知っている。
だけど、そこに自分は行くことは出来ない。
あれほどまでに失いたくなかった居場所は、自分を包むこの炎のように一瞬で失われてしまった。
カイはその場にヘタりと、力なく座り込んでしまった。
この炎は、どうして自分ごと焼き消してしまわないのか。
カイは自分の手を見てそう思った。
男は、そんなカイの元へコツコツと革靴を鳴らしながら近づいていく。そしてカイの周りを燃え盛る炎にむかって、杖をひと振りした。一瞬炎に手をかざした後、炎のサークルの中に足を踏み入れたのだ。
しかし男の身にはなんの変化もなく表情も変わらない。
男はカイの横にしゃがみ、カイの炎に包まれた手を握る。
すると、カイの手から炎は静かに消え、本来の白く細い手が顕になったのだ。その様子に、カイは若干目を見開く。
あれほどまでに制御出来なかった炎を、この男は一瞬で沈めて見せたのだ。
呆気に取られるカイを見て男は小さく笑った。
見るものによっては冷たく見るものによっては温かい。そんな笑みだった。
「君が今望むものは何?」
男は真っ直ぐに、カイの目を捉える。
「絆ではなく、もっと確かな物?
安心できる場所……とかね。」
そして男は、震えるカイの小さな手に自身の大きく骨ばった手を添えた。
「君、名前は?」
男は、低く落ち着いた声でそう尋ねる。
「カイ……。カイ・アーデン。」
カイはうつむき加減にそう答えた。
カイの瞳は、睫毛がかかって男にはよく見えない。
すると、男はカイの頬に手を添えて顔を上げさせた。
「カイ。君の力は素晴らしいよ。
だから、俺は君の望むものを与えられる。
確かな物ならなんだって。」
「あなたは……誰?」
そう問いかけるカイの神秘的な瞳に、僅かに光があることを男は見逃さなかった。
だから、男はまた小さく笑ったのだ。
口角を上げて。
「ヴォルデモートだよ。
そして……カイの居場所でもある。 」
そうして差し出された男の手を取ったのは絶望した少女だった。
否、愛に飢えたのはどちらだったのだろうか。
やっぱり神さまなんて居ない。
私を、この世に送り出した女神は偽物だ。
どれだけ、善人であろうが、前世のパパとママの掟を守ろうがこの世界では関係無いことなのだ。
カイは心からそう思うことになる。
カイは、この屋敷に囚われた。
初めは本当に些細な事だった。それが、カイの人生をこんなにも大きく左右してしまうなんて思いもしなかった。
予測出来ていたならば、カイは誰になんと言われようが一目散にこの場から逃げ出したであろう。
孤児院の友達に連れられて不本意に近づいたこの屋敷。
友達たちにはどうしても廃墟のようにしか見えなかったようだ。
確かに、無法地帯のそこに生える草木はカイたちの身長を悠々に飛び越している。ツタの葉は、割れた窓ガラスから豪快に侵入している。建物はもとは頑丈な作りなのか、どこか風格がありかないい所の良家がすんでいたのかもしれない。
しかし、煤だらけ。
すると、その"お化け屋敷"を先日孤児院から自転車でうんと遠くまで行った少年達が見つけてきたのだ。
「すっげえお化け屋敷があるぜ!」と、お調子者で天真爛漫な少年・タイラーがそうみんなに働きかければ、好奇心旺盛な子供たちは黙ってはおけない。小心者の男の子も、怖いものが嫌いな女の子も、皆が行くとなれば話は別らしい。ノリノリの雰囲気の中カイが、「マザーに怒られるよ」と咎めても、「どうした、いつも済ました顔してるくせに!怖いんだな?」と茶化されるだけだった。しまいには、1番の仲良しのライラから「ついてきてよ!貴方がいないと、タイラーの暴走を止めれる人はいないもの!」としつこくお願いされ、行かざるを得なかった、という話だ。
こうなると仕方が無い。
先頭でみんなを従えるタイラーを筆頭に、カイは一番後ろからついて行くこととなった。
しかし、その場所に住み着いていたのはゴーストでもなんでもない。それよりももっと恐ろしい、闇の魔法使い達だったのだ。
""お化け屋敷""はマグルのための見掛け倒しにしか過ぎなかった。物騒な雰囲気を醸し出す扉を開け、皆に並んでついて行くと、肌でどこかただならぬ雰囲気を感じた。
この古く恐ろしい洋館は、歩く度にミシミシと音を立てる。蜘蛛の巣があちこち張り巡らせてあって、当然気味が悪く、皆思い思いに小さく悲鳴をあげる。
「おい、何怖がってんだよお前ら。」と、タイラーの声も少しばかりだがいつもより上ずっていた。
しかし、皆と、カイが感じる恐怖は別のものだ。
お化けやそんなものでは無い。この屋敷に入った途端、自分の持つ魔力が何かに反応しているよう気がするのだ。
それも、背筋が凍るような恐ろしい感じがする。カイ自身、誰かの魔法に触れるのははじめてのことで、これが魔法なのかは分からない。
すると突然、ライラがカイの方を振り向いて、「なんだか、倒れそうなの……」と真っ青な顔をして話しかけてきた。その目は虚ろで、怖くて真っ青な顔をしているのでは無いのだとカイは一瞬で分かった。それをきりに明らかに皆の様子がおかしい。それぞれの脚はもたつきはじめ、しまいには、苦しいのか微かに呻き声をあげる子までいた。
このままでは皆なにかに飲み込まれてしまう。
早くここから出なくちゃならない。
「出るよ!」カイは皆に聞こえるように声を張り上げて、真っ青な顔をしたライラを引っ張り、出口を目指そうとした。
しかしその瞬間、バタン!!と何かが倒れる音がした。カイは、反射的に大きく振り返ると、何と倒れていたのはさっきまで1番先頭にいたタイラーだった。
カイは彼の方へ一目散に駆け寄るが、突然何か白いモヤのようなものに目の前が遮られてしまった。ただならぬこの状況に誰かの泣き叫ぶ声がが聞こえるが今はそれどころではない。
とにかく、タイラーの無事を確かめるべく白いモヤをかき分けるとようやく彼の顔が見えた。
「タイラー!しっかり!」
しかし、彼の目は固く閉じられ、唇は青かった。
息はしているようだったが、タイラーは完全に失神していて起きる気配が全くない。
起こったことを頭の中で整理しようとするけど、全くカイの脳みそは機能していない。だけど、ただ一心ここから早く逃げ出さなくてはという堅い決意がカイの心を支配していた。
タイラーの方を揺さぶり続けるとようやく彼の目は開かれた。カイは、彼をいたわる暇なんてなくタイラーの腕をグイッとカイの肩に乗せた。
「みんな、逃げるよ!」
ようやく白いモヤが消えた。
座り込む仲間達を必死で立つように促し、出口を目指す。
カイよりも体重の重い上、意識がまだハッキリとしないタイラーを支えながら走るのはとても難しく辛かった。
これは魔法の罠だ。
みんなをここから無事に出してあげないといけない。
だって、私はパパとママの子だ。そして、魔法使いなんだ。
"無駄だよ。たかがマグルが、逃げ出そうなんてね。"
突然、ノイズ音のように低い声が聞こえてきた。
"ここは、子供が来る場所では無いんだよ。
まんまと、捕らわれにくるなんてね。"
「誰だよ!」
思わず立ち止まって、気持ちの悪い声に反応する。
「おい!カイ!何止まってるんだよ!早く行くぞ!」
「ねえ、マイク。聞こえないの?」
「何がだよ!!お化けの声だとかいうなら後にしてくれよな!」
マイクは、怒りと興奮を抑えられない様子でそう言った。
自分以外に聞こえないなんて、これが魔法使いの仕業だと言うことは確証的だと思った。しかし、この魔法使い、マグルを相当恨んでいるのだろうか。
だけど今は、探偵ごっこをしている暇はない。
カイは、またタイラーを支えて走り出す。
"無駄なのになあ。走ったって出口は無い。"
気味悪い声がそういった途端、足元がぐらついた。
そして、古びた洋館の様子が変わっていく。なんと、先程まで廊下に敷かれていたボロボロの暗赤色の絨毯は、シルクのようにキメ細やかで真新しい黒いカーペットに変わっていく。
煤だらけの壁紙にあった外れ掛けの古びた肖像画は、なんの装飾も汚れもない唐草模様の黒い壁紙に変わっていく。
なるほど。
ホグワーツと同じ仕掛けだ。
マグルには、廃墟の洋館にしか見えないようにしてあるんだ。
「おかしいわよ、カイ!走っても走ってもお化け屋敷から抜け出せないの!」
そして、マグルのライラ達にはずっと見た目はお化け屋敷のままで、魔法がかけられたせいで今は出口の場所が変わり、永遠に同じ場所をループしているようになっているのかもしれない。
全部、予想だけれどそう考えるのが1番早いだろう。
だけどカイは、魔法使いだ。
例え魔法がかけられ出口が変わっても、それが分かる。
カイは、タイラーをマイクに預けて、みんなが自分に着いてくるように指示をした。
「大丈夫!景色は変わらないかもしれないけど、私についてきたらきっと抜け出せるから!着いてきて!」
そう言って、みんなには見えない廊下の突き当たりを曲がったりしながら出口を模索した。
「なんも、変わんないよ!本当に大丈夫なの?」
「大丈夫よ!ライラ!私を信じたらいい、お願いだから。」
カイの必死の口調が伝わったのか、みんな素直にカイに従って着いてきてくれているようだった。
するとようやく、扉が見えた。
その扉は、来た時よりも随分と背が高く木目も無くただひたすらに黒かった。
「見えたよ!」
ようやく出られるんだ。
カイの表情は思わず、綻んだ。
だけど、すぐに崩れ落ちた。
"逃げられないって言ったはずだ。"
そこに現れたのは、無機質なドクロのお面を被り、黒いローブを身にまとった男だった。
「……誰ですか。あなた」
声が震えないようにカイがそう言うと、男は高笑いをした。
そして、気色悪い声から人間味のある男の声に変わった。
「君、私のことが見えるんだね。
多分後ろのお仲間達には見えないと思うよ。」
カイが後ろを振り向くと、みんな埃を払うようにして手を振っている。
「また、白いモヤだ……、なんなのこれ?」
そうライラが言うのが聞こえた。
カイには白いモヤが全く見えない。
魔法使いには見えないように、仕掛けてあるのだろう。
「マグルには到底目指せないはずだが、君たちは随分と真っ直ぐに出口に向かうと思ったんだ。それもそのはず、君には屋敷全体に掛けられたこの錯乱呪文が効かないんだからね。」
そう男は言うと、カイの元に徐々に近づいてくる。
「来るな!」
カイはみんなを庇うように、手を広げた。
「へえ、魔法使いのヒーローか。立派だねぇマグル達を守るなんて。。」
男はそう言うと、カイの後ろにいるライラに目をやった。
ライラは、そんなこと気にもとめず、「あなたさっきから何と話しているの?!」と、心底気味が悪そうにカイの方に尋ねてきた。
「子供の魂……か。利用価値はさぞあるだろうね。」
そうしてライラの方に杖を向けた。
「ライラに手を出すな!」
ライラの前に目いっぱい立ふさがる。
「では、代わりに君の魂を差し出す?」
男は今度はカイの方に杖を向ける。
絶対に怯んでやるものか。
「……それで皆、助けてくれるというのなら。
惜しくないし、怖くもない。」
「たかが、赤の他人に命を差し出すなんてね。
彼女達ちそれほどまでの価値があるというのかな?」
そう言うと、男はこれでもかと言うほど大きく笑った。
そして、閃光をマイクの方に飛ばした。
すると突然、マイクは大声を出して苦しみ始めたのだ。
「うわあああああア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"ア"」
「何すんだやめろ!私にやればいい全部!!」
「この状態を見てもまだ、庇うんだね?本当に感心するよ。
如何なる時にも切れない絆ってやつか。そんなもの存在しないのに。」
「ガタガタうるさい!友達だから!助けたいから助けるんだ!」
そう言い、男の方に向かっていくと男は今度はカイに杖を向けてた。
「フリペンド」
カイは吹き飛んだ。
そして勢いよくもがき苦しむマイクの方に向かって投げ出された。
マイクにかかった呪文はそこで途絶えたのか力尽きたようにへたんと床に座り込んでしまった。
「あまり信じすぎない方がいい。人は簡単に裏切る。特にマグル……とかいう存在はね。」
「……アンタは一体なんなの?」
「私?……そうだな……。
魔法使いの君になら歳期にくらい教えてあげてもいいか。」
男は、仮面を外した。そして、身にまとっていたフードを外した。すると、仮面の下から光った瞳は赤だった。深紅のその色は相手の目を射抜く。絹のようにサラサラの黒い髪は、几帳面に目元にかかる程度に流されてある。
男と呼ぶには妖しくそれでも逞しく、カイの出会ったものの中でいちばん美しい人だった。
カイが思わず息を飲み見とれるその数秒後新たに男とは反対方向に黒いローブの輩が一人現れた。
「穢らわしい、人間のガキ共が……。
卿の屋敷に入って許されるとでも思うなよ! 」
輩の声は冷静さをまるで失っている。
「いい、下がれ。
俺様が全て方を付ける。」
男は、輩に向かって恐ろしく冷たい声でそう命令したが、輩の耳には届いていないようだ。
「こんなガキ共のために、卿が手を穢していい訳が無い……!
是非、吾輩にお任せ下さい!」
そう言葉にする輩を、男は何も言わずただ冷たい目で見つめていた。ライラ達には、もちろんこの輩も霧により見えておらず何が何だか分からないようだ。
そして得体の知れぬ不穏な空気を感じとっている。
それをいいことに、輩はニヤリと口角を上げて1番近くにいた女の子に杖を振り上げた。
「やめろ!」
カイが止める声と、奴が呪文を放った声は重なった。
「デパルソ」
女の子の体は宙を舞い、大きく壁に打ち付けられた。
ただ事では無い事態に、ライラもマイク達も悲鳴を上げて、完全にパニック状態だ。
「もうやめて!誰なの!?」
ライラがそう叫ぶと、輩は今度はライラの方に目線をやり笑い声を上げた。
「馬鹿な、ガキ。自分の身に起こっていることすら分からず死んでいくなんてな!!」
そして、ライラの体を呪文でキツく縛り上げた。
「やめてってば!ねえ!!」
カイがそう叫んで泣き叫ぼうが、ライラの呻き声を上げ苦しんでいる。輩はそれを見てさぞ愉快そうにし、杖を振り上げたままだ。
そして男は、そんな様子をずっと静かに眺めていた。
こんなのおかしい。なんで何も知らない、力を持たないライラ達が苦しめられなければならないのか。
わたしの、友達なのに。
ライラは私がこの世界に来て初めて出来た友達なのに。
そう思うと、カイの中から今まで感じたことがないほどの怒りが込み上げてきた。その怒りはカイの体内を凄まじい勢いで駆け巡り、手に込められる力とは別の力が湧き上がってくるのだ。
だけど、これをもう止めようとは思わない。
いや、止められない。
「アバダ……」
輩がそう呟くとその瞬間、すざましい爆発音を上がる。
そこら中の物が吹き飛び、当たりは燃え上がった。
だけど、私の周りには何一つ変化がない。ただ輩の周りに降り注ぐ炎だけが延々と萌え続けているのだ。
輩はその燃え上がる炎をただ、唖然として見つめている。
そして次にカイの方をみて輩はこれでもかと言うほど目を見開いた。
その輩の目に込められたものは、かつてカイ達の目にあった恐怖だった。
カイは不審に思い自分の体を見渡す。
すると、カイの手のひらには炎が燃え盛っていた。
だけど、不思議なことにちっとも熱くない。それどころか、湧き上がるエネルギーをどこまでも爆発させられそうな程に高揚感に満ちていた。
男が、炎に包まれたカイを、驚いたように見つめる。
しかし、すぐに表情を戻し形のいい唇の口角を上げて見せた。
「……面白い。」
炎は全てカイの魔力の暴走によるもの。
カイ自身もそれを何となく察していた。だけど、初めて感情による魔力を爆発させたせいで、おさめ方が分からないのだ。そのおかげで炎は燃え盛るばかりだ。
このカイの様子を見たのは、もちろん男と輩だけではない。
ライラ、マイク、タイラー含め、孤児院の子達全員なのだ。
全てのものを吹き飛ばし、カイの手に燃え盛る炎を見て、彼らは唖然としていた。そして、カイから1歩2歩後退りをする。
カイの1番近くにいたライラも物凄い勢いでカイから離れ、今まで縛りつけられていた苦しみと、この目の前の光景への恐怖がごちゃ混ぜになってしまっていた。
「全部、お前が……?」
タイラーは、小さくそう呟いた。
「違う!!!」
カイは、タイラーに手を伸ばそうとするが自分の燃え盛る手を見て慌てて引っ込めた。
はやく、おさまって!お願いだから!カイはそう、心の中で願うも炎は収まることも知らず次第に天井のシャンデリアは音を立ててカタカタと震え出す。
「じゃあ、お前以外に誰がいるんだよ!!!」
マイクは声をはりあげてそう言う。
「違うの!聞いてってば!」
「周りにお前以外おかしいものは無い!俺らを怖がらせて楽しいかよ!怖がらせるだけじゃない!!タイラーを失神させたり、俺や、ライラをもがき苦しめたり!!!!」
「だから、私じゃないんだってば!!」
「そんな化け物みたいな炎出しているお前以外誰がいるんだよ!!!」
タイラーは、そう声を張り上げる。
カイはついに何も言い返せなくなった。
タイラーだけでない。他のみんなが自分を見る目は、明らかに軽蔑。怪物を見るような目だった。
そんな中、ふとカイはライラと目が合った。
「ち、ちがうの、ねえライラ。」
カイは絞り出すようにそう言い、ライラの元に歩み寄る。
「お願いだから来ないで!!!」
しかし金切り声でそうピシャリと言い放たれてしまったのだ。
まるで、カイは体を引き裂かれる呪文を受けたのかと言うほどに心臓が痛かった。
ショックのあまり表情筋がひとつも動かないのだ。
その反動なのか、カイの手だけでなく今度は足元からも炎が湧き出てくる。
ライラたちはまた悲鳴をあげた。
「逃げるぞ!!」
そう叫んだのはタイラーだった。
タイラーが目指した先は、先程まであった背の高い光沢に満ちた黒いドアでは無く、この屋敷に入った時に見た古びた厚い木の扉だった。
どうやら、この屋敷にかけられた呪文が解けた……あるいは何かに阻まれたおかげでもとの"お化け屋敷"のビジュアルに戻ったようだ。
タイラー達は、カイも、その様子をただ静かに眺めていた端正な男にも目もくれず、一目散に駆け出して言ったのだ。
親友だと言ってくれたライラですらも、1度もカイの方を振り向くことは無かった。
男は、屋敷から逃げ出すライラ達を見ても引き止めることも何もせずに興味無さげにその後ろ姿を見送った。
そして男は視線をカイの方に移した。
男の目の色にはなんの感情も感じられない。ただ、ひたすらに深紅の瞳が、炎に包まれたカイを映し出すだけだった。
そのまま彼女達はどんどん遠ざかっていく。
でも、カイはもうあの背中を追いかけることは出来ない。
彼らの戻る場所は、どこか知っている。
だけど、そこに自分は行くことは出来ない。
あれほどまでに失いたくなかった居場所は、自分を包むこの炎のように一瞬で失われてしまった。
カイはその場にヘタりと、力なく座り込んでしまった。
この炎は、どうして自分ごと焼き消してしまわないのか。
カイは自分の手を見てそう思った。
男は、そんなカイの元へコツコツと革靴を鳴らしながら近づいていく。そしてカイの周りを燃え盛る炎にむかって、杖をひと振りした。一瞬炎に手をかざした後、炎のサークルの中に足を踏み入れたのだ。
しかし男の身にはなんの変化もなく表情も変わらない。
男はカイの横にしゃがみ、カイの炎に包まれた手を握る。
すると、カイの手から炎は静かに消え、本来の白く細い手が顕になったのだ。その様子に、カイは若干目を見開く。
あれほどまでに制御出来なかった炎を、この男は一瞬で沈めて見せたのだ。
呆気に取られるカイを見て男は小さく笑った。
見るものによっては冷たく見るものによっては温かい。そんな笑みだった。
「君が今望むものは何?」
男は真っ直ぐに、カイの目を捉える。
「絆ではなく、もっと確かな物?
安心できる場所……とかね。」
そして男は、震えるカイの小さな手に自身の大きく骨ばった手を添えた。
「君、名前は?」
男は、低く落ち着いた声でそう尋ねる。
「カイ……。カイ・アーデン。」
カイはうつむき加減にそう答えた。
カイの瞳は、睫毛がかかって男にはよく見えない。
すると、男はカイの頬に手を添えて顔を上げさせた。
「カイ。君の力は素晴らしいよ。
だから、俺は君の望むものを与えられる。
確かな物ならなんだって。」
「あなたは……誰?」
そう問いかけるカイの神秘的な瞳に、僅かに光があることを男は見逃さなかった。
だから、男はまた小さく笑ったのだ。
口角を上げて。
「ヴォルデモートだよ。
そして……カイの居場所でもある。 」
そうして差し出された男の手を取ったのは絶望した少女だった。
否、愛に飢えたのはどちらだったのだろうか。
1/8ページ