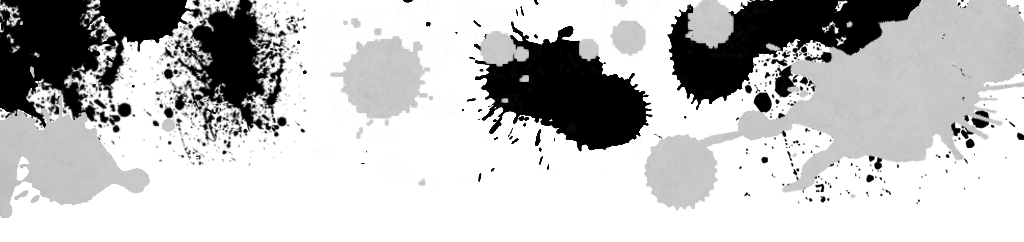Christmas
夢小説設定
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
[ねえ、まだ起きてる?]
[ん]
[あ、起きてた、ねえ、明日クリスマスだよ、どっか行こうよ]
[俺明日昼過ぎまで仕事なんだが]
[終わってからでいいよ]
[明日休日だぞ、人多いんじゃねえか]
[えー、だめ?]
[しかたねえな]
[やった!じゃあ、アイゼンの仕事場の近くまで行くね]
[あ?おう、わかった]
[じゃあ、明日ね]
[ん]
満足して携帯を置く
よし、明日は久しぶりのデートだ
最近仕事が忙しいだのなんだのってうるさくて、全然会ってくれてなかった
アイフリード社長とわたし、どっちが大事なんだっての、
まあ、彼が副社長だから、そんなに強くも言えないんだけど
朝になってテレビを付けると、クリスマスの話題ばかりだった
『彼氏彼女にプレゼントされたいものランキング、かぁ』
あの人はプレゼントとか、考えてなさそう
前のあたしの誕生日のときは、直接何がほしい?って訊かれたし
訊かれてないってことは、多分、何も考えてない
まあ、そういう適当な彼も好きなんだけど
わたしはメディアにのせられてプレゼント、用意しちゃったけど
お昼を適当に済ませて、アイゼンの仕事が終わるであろう時間から逆算して、そろそろ家を出ようとしたとき
ピンポーン
インターホンが鳴った
『あれ、なんか頼んでたっけな』
小走りで玄関まで行き、ドアを開けると
「め、メリークリスマス」
金髪の愛しい彼がいた
「ん、駄目だな、慣れない言葉は言うもんじゃねえな」
『えっ、あっ、アイゼンっ、なんで?』
「仕事が早く終わったんだ、アイフリードのやつが、女持ちはさっさと帰れってな、だから、迎えに来てやったぜ?」
不敵な笑みを浮かべる彼が格好よくて
「おい、お前顔赤いぞ?久しぶりの俺に惚れ直したか?」
『ふふっ…、うん』
「うん、じゃねえよ…俺まで恥ずかしくなるだろうが…」
『えへへ、ごめん』
「行けるなら、早く行こうぜ、」
『あっ、ちょっと待って』
わたしは部屋の奥に、鞄と、一つの紙袋を取りに行く
『これ、いきなりだけど、クリスマスプレゼント、ね』
「ん、開けていいか」
『うん』
アイゼンにあげたのは、橙色のマフラー
だってこの人、いつもコートを羽織ってるだけで、見てるほうが寒いんだもの
「……いいな、この色」
『あたりまえでしょ、アイゼンを知り尽くしたあたしが選んだんだから』
「………うるせえ」
アイゼンは、心なしか嬉しそうだ
アイゼンはさっとそのマフラーを首に巻くと
「ほらトシユキ、行くぞ」
『あ、うん、』
彼女の手を引いて外へ出た
私の家から、駅まで歩く
『なんかごめんね、わざわざ来させて』
「別に気にするな」
12月らしい寒さで、頬が冷たくなる
「どこいきたいとか、あるのか?」
『あ、えっとね、この間言ってたとこのイルミネーションが見たいなって』
「あぁ?絶対混んでるだろ…今日何日だと思ってる…」
『そうかな…』
「まあ、他にあてもないし、とりあえず行くか」
『やった~』
「やっぱり、混んでんな」
到着した街中のイルミネーション
メディアでも何度も取り上げられていた場所だ
『やっぱりカップルが多いねえ』
「他人のこと言えねえからな」
『それもそうだ』
人は多いものの、やはりイルミネーションは綺麗だ
ただ電飾が集まってるだけじゃない
ドスッ
誰かと肩が当たってよろける
『あっ、ごめんなさっ』
よろけた瞬間に違う人の流れに巻き込まれて
パシッ
流される身体を、アイゼンに手を掴まれて引き留められる
「馬鹿、勝手にどっか行くな」
『ご、ごめん、流されちゃって』
「お前ちいせえから、どっか行くとすぐ分かんなくなるからな、ほら、行くぞ」
自然に繋がれた手が暖かくて
ぎゅっ、と強く握り返す
彼女の手は、柔らかくて、下手したら壊れてしまいそうなくらい
『アイゼン、ほら、見えてきたよ』
「あれが、噂の」
『そうそう、巨大クリスマスツリー』
人が多くて、とても近くまではいけそうにない
『綺麗だなあ』
彼女はきらきらと目を輝かせて、
「………トシユキ」
『ん?どうしたの…んっ』
チュ、と小さく口づけをする
『へっ、あっ、アイゼンっ、な、なにいきなり』
彼女は驚きと焦りで、顔が真っ赤になる
「……今キスしなかったら、後悔しそうだった」
『馬鹿じゃないの…』
「……馬鹿でいい」
ご飯を食べる場所を探していたけど、街ということもあって、どこも混んでいて入れそうになかった
『やっぱり今日はどこも予約でいっぱいなのかなあ』
「だろうな」
『どうする?』
「んー…」
酒がのみたいなあ、と多分お互いに考えている
「俺の家の近くに、新しい居酒屋、出来てたが」
『えー、クリスマスに居酒屋…?』
「やっぱりだめだよな」
『いや、いいよ、このへんのお店空いてないし、そこにしよ?クリスマス気分はイルミネーションで味わえたし』
「ん、そうか、じゃあ、行こう」
電車で彼の家の最寄りまで
行き慣れた駅
「ここだ」
『おー』
ドアをあけると、気の良さそうな、すこしおしゃれな店主さんがいた
「いらっしゃい、お、来たね」
「うるせえ」
『?』
「気にすんな」
『ああ、うん』
アイゼンと店主の、謎のアイコンタクト
『来たことあるの?』
「ん?ああ、まあな、それより、なにのむ」
お酒がすすむ
ここは、お酒も料理も美味しい
『いいね、このお店』
「だろう?早くお前も連れてきたかったんだ」
『えー、じゃあ早く呼んでよ…』
「今日がよかったんだよ、なあ親父、頼む」
「はいはい~お待ちどおさま、クリスマスケーキだよ~」
居酒屋の店主がテーブルに持ってきたのは、小さなクリスマスケーキ
おしゃれな花火のようなロウソクがパチパチと燃えている
『えっ、え、え?』
状況が飲み込めない
「ここに来れる保証は無かったけどな、店主に頼んでおいたんだ」
アイゼンはにっと笑う
「サプライズなんて柄じゃないんだけどな」
「昨日夜中に突然電話が来てビックリしたよ~!小さいのしか用意できなくてごめんね~!」
店主はニコニコと嬉しそうにしている
『どうしよう…すごく嬉しい…』
「喜んでもらえてよかった、柄にもないことをした甲斐があったな」
『こんなの用意してたなら言ってよ…街でどこか店入っちゃってたらどうするつもりだったの…』
「後日受け取って一人で食べる」
『ほんと馬鹿だなあ…』
「お前が喜ぶなら、それでいい」
『嬉しいけど、早く食べないと、そろそろ終電の時間来ちゃ…』
「あ?今日は俺の家に泊まっていけばいいだろ」
『え、あ、うん…』
「お客さん強引だね~」
「おいそこ、うるさいぞ」
「あははっ、ごめんねえ、お嬢さんも、ゆっくりしていっていいからねえ」
『あ、はい、ありがとうございます…』
久々の強引な彼に、少しだけドキドキする
「あ、あとな、もう1つ渡すものがあるんだ」
『ん?なになに』
彼が取り出したのは小さな黒い箱
『え、ちょ、ま』
「あ、まて、早とちりするな、落ち着け」
『え、あ、うん、わ、わかった』
彼はその小さな黒い箱をそっと開ける
中には、黒とシルバーの輪が重なったような、指輪
「俺は、まだ責任を持てるほど収入も安定してないし、まだ、その、駄目だと思ってる、でも、俺の覚悟が出来るまで、隣で、待っていてほしい」
『おっ、おおう…』
「この指輪は、クリスマスプレゼントの意味と、その、予約だ、お前の」
『よ、予約…』
「そうだ、俺以外の男にうつつを抜かすことは許さん、ほら、俺とお揃いなんだぞ」
アイゼンは自身のポケットから同じデザインの指輪を取り出して見せた
「どうする?左手の薬指に付けてしまうか?」
『えっえええ~、えっと、ど、どうすれば、いいのかな…』
「お前がどうしたいか訊いてる」
『ええ、じゃ、じゃあ、アイゼンが付けてほしいとこに付けていいよ』
両手を広げて差し出す
「ん、良いんだな?」
するとアイゼンはわたしの左手を取って、迷いなく薬指に指輪をはめた
『ま、迷いないね…』
「これでトシユキに変な虫が付くことはないな」
左手の薬指にはめられた指輪は、サイズもぴったりで、デザインもすごく素敵で
『アイゼン…ありがとう…なんか…泣きそう…』
「喜んでもらえたならよかった」
『あーー、なんか恥ずかしい…もう呑むね、呑むからねあたし』
「おう、呑め呑め」
2時過ぎに、気の良い店主とも別れを告げて店を出た
恥ずかしさを紛らわせたくて、いつもよりも呑んでしまった
「おい、大丈夫か、ちゃんと真っ直ぐ歩け」
『んーーー…』
頭が痛い
「俺の家、すぐだから、もうちょっと耐えろ」
夜風に当たりながら歩いていたら、案外すぐに酔いは醒めてきて、アイゼンの家につく頃には大分増しになっていた
『おじゃましまーす、』
「なんだ、すっかり正気じゃねえか、酔ってるのにかまけて襲ってやろうと思ってたのにな」
『アイゼン、そういうのは口に出すもんじゃないよ』
「………トシユキ」
『あっ、ちょっ、と…』
腰を抱かれて強引にベッドに押し倒される
『結局こうなるんじゃん…』
「素直に俺の家まで来たんだ、いいんだろ?」
彼の腕がわたしの腰を離さない
『い、いい、けど、シャワーくらい浴びたいな、って…』
「だめだ、俺は今すぐがいい」
きつく抱き締めたまま、まっすぐに見つめてくる
こうなったら拒否できないのは知っている
『あ、明日は、仕事ないの?』
「ない、休みをとった」
『……わかった、楽しませてよ、あたしだけのサンタさん?』
「当たり前だ、とびきりのプレゼントをお見舞いしてやるよ」
朝目が覚めて、
無防備に寝ている彼と、わたしの薬指には、素敵な指輪がある
『……帰りたくないなあ』
指輪を眺めながら、そう呟いたら
「もう、一緒に住んじまうか?」
彼が薄目を開いて、私にそう言った
[ん]
[あ、起きてた、ねえ、明日クリスマスだよ、どっか行こうよ]
[俺明日昼過ぎまで仕事なんだが]
[終わってからでいいよ]
[明日休日だぞ、人多いんじゃねえか]
[えー、だめ?]
[しかたねえな]
[やった!じゃあ、アイゼンの仕事場の近くまで行くね]
[あ?おう、わかった]
[じゃあ、明日ね]
[ん]
満足して携帯を置く
よし、明日は久しぶりのデートだ
最近仕事が忙しいだのなんだのってうるさくて、全然会ってくれてなかった
アイフリード社長とわたし、どっちが大事なんだっての、
まあ、彼が副社長だから、そんなに強くも言えないんだけど
朝になってテレビを付けると、クリスマスの話題ばかりだった
『彼氏彼女にプレゼントされたいものランキング、かぁ』
あの人はプレゼントとか、考えてなさそう
前のあたしの誕生日のときは、直接何がほしい?って訊かれたし
訊かれてないってことは、多分、何も考えてない
まあ、そういう適当な彼も好きなんだけど
わたしはメディアにのせられてプレゼント、用意しちゃったけど
お昼を適当に済ませて、アイゼンの仕事が終わるであろう時間から逆算して、そろそろ家を出ようとしたとき
ピンポーン
インターホンが鳴った
『あれ、なんか頼んでたっけな』
小走りで玄関まで行き、ドアを開けると
「め、メリークリスマス」
金髪の愛しい彼がいた
「ん、駄目だな、慣れない言葉は言うもんじゃねえな」
『えっ、あっ、アイゼンっ、なんで?』
「仕事が早く終わったんだ、アイフリードのやつが、女持ちはさっさと帰れってな、だから、迎えに来てやったぜ?」
不敵な笑みを浮かべる彼が格好よくて
「おい、お前顔赤いぞ?久しぶりの俺に惚れ直したか?」
『ふふっ…、うん』
「うん、じゃねえよ…俺まで恥ずかしくなるだろうが…」
『えへへ、ごめん』
「行けるなら、早く行こうぜ、」
『あっ、ちょっと待って』
わたしは部屋の奥に、鞄と、一つの紙袋を取りに行く
『これ、いきなりだけど、クリスマスプレゼント、ね』
「ん、開けていいか」
『うん』
アイゼンにあげたのは、橙色のマフラー
だってこの人、いつもコートを羽織ってるだけで、見てるほうが寒いんだもの
「……いいな、この色」
『あたりまえでしょ、アイゼンを知り尽くしたあたしが選んだんだから』
「………うるせえ」
アイゼンは、心なしか嬉しそうだ
アイゼンはさっとそのマフラーを首に巻くと
「ほらトシユキ、行くぞ」
『あ、うん、』
彼女の手を引いて外へ出た
私の家から、駅まで歩く
『なんかごめんね、わざわざ来させて』
「別に気にするな」
12月らしい寒さで、頬が冷たくなる
「どこいきたいとか、あるのか?」
『あ、えっとね、この間言ってたとこのイルミネーションが見たいなって』
「あぁ?絶対混んでるだろ…今日何日だと思ってる…」
『そうかな…』
「まあ、他にあてもないし、とりあえず行くか」
『やった~』
「やっぱり、混んでんな」
到着した街中のイルミネーション
メディアでも何度も取り上げられていた場所だ
『やっぱりカップルが多いねえ』
「他人のこと言えねえからな」
『それもそうだ』
人は多いものの、やはりイルミネーションは綺麗だ
ただ電飾が集まってるだけじゃない
ドスッ
誰かと肩が当たってよろける
『あっ、ごめんなさっ』
よろけた瞬間に違う人の流れに巻き込まれて
パシッ
流される身体を、アイゼンに手を掴まれて引き留められる
「馬鹿、勝手にどっか行くな」
『ご、ごめん、流されちゃって』
「お前ちいせえから、どっか行くとすぐ分かんなくなるからな、ほら、行くぞ」
自然に繋がれた手が暖かくて
ぎゅっ、と強く握り返す
彼女の手は、柔らかくて、下手したら壊れてしまいそうなくらい
『アイゼン、ほら、見えてきたよ』
「あれが、噂の」
『そうそう、巨大クリスマスツリー』
人が多くて、とても近くまではいけそうにない
『綺麗だなあ』
彼女はきらきらと目を輝かせて、
「………トシユキ」
『ん?どうしたの…んっ』
チュ、と小さく口づけをする
『へっ、あっ、アイゼンっ、な、なにいきなり』
彼女は驚きと焦りで、顔が真っ赤になる
「……今キスしなかったら、後悔しそうだった」
『馬鹿じゃないの…』
「……馬鹿でいい」
ご飯を食べる場所を探していたけど、街ということもあって、どこも混んでいて入れそうになかった
『やっぱり今日はどこも予約でいっぱいなのかなあ』
「だろうな」
『どうする?』
「んー…」
酒がのみたいなあ、と多分お互いに考えている
「俺の家の近くに、新しい居酒屋、出来てたが」
『えー、クリスマスに居酒屋…?』
「やっぱりだめだよな」
『いや、いいよ、このへんのお店空いてないし、そこにしよ?クリスマス気分はイルミネーションで味わえたし』
「ん、そうか、じゃあ、行こう」
電車で彼の家の最寄りまで
行き慣れた駅
「ここだ」
『おー』
ドアをあけると、気の良さそうな、すこしおしゃれな店主さんがいた
「いらっしゃい、お、来たね」
「うるせえ」
『?』
「気にすんな」
『ああ、うん』
アイゼンと店主の、謎のアイコンタクト
『来たことあるの?』
「ん?ああ、まあな、それより、なにのむ」
お酒がすすむ
ここは、お酒も料理も美味しい
『いいね、このお店』
「だろう?早くお前も連れてきたかったんだ」
『えー、じゃあ早く呼んでよ…』
「今日がよかったんだよ、なあ親父、頼む」
「はいはい~お待ちどおさま、クリスマスケーキだよ~」
居酒屋の店主がテーブルに持ってきたのは、小さなクリスマスケーキ
おしゃれな花火のようなロウソクがパチパチと燃えている
『えっ、え、え?』
状況が飲み込めない
「ここに来れる保証は無かったけどな、店主に頼んでおいたんだ」
アイゼンはにっと笑う
「サプライズなんて柄じゃないんだけどな」
「昨日夜中に突然電話が来てビックリしたよ~!小さいのしか用意できなくてごめんね~!」
店主はニコニコと嬉しそうにしている
『どうしよう…すごく嬉しい…』
「喜んでもらえてよかった、柄にもないことをした甲斐があったな」
『こんなの用意してたなら言ってよ…街でどこか店入っちゃってたらどうするつもりだったの…』
「後日受け取って一人で食べる」
『ほんと馬鹿だなあ…』
「お前が喜ぶなら、それでいい」
『嬉しいけど、早く食べないと、そろそろ終電の時間来ちゃ…』
「あ?今日は俺の家に泊まっていけばいいだろ」
『え、あ、うん…』
「お客さん強引だね~」
「おいそこ、うるさいぞ」
「あははっ、ごめんねえ、お嬢さんも、ゆっくりしていっていいからねえ」
『あ、はい、ありがとうございます…』
久々の強引な彼に、少しだけドキドキする
「あ、あとな、もう1つ渡すものがあるんだ」
『ん?なになに』
彼が取り出したのは小さな黒い箱
『え、ちょ、ま』
「あ、まて、早とちりするな、落ち着け」
『え、あ、うん、わ、わかった』
彼はその小さな黒い箱をそっと開ける
中には、黒とシルバーの輪が重なったような、指輪
「俺は、まだ責任を持てるほど収入も安定してないし、まだ、その、駄目だと思ってる、でも、俺の覚悟が出来るまで、隣で、待っていてほしい」
『おっ、おおう…』
「この指輪は、クリスマスプレゼントの意味と、その、予約だ、お前の」
『よ、予約…』
「そうだ、俺以外の男にうつつを抜かすことは許さん、ほら、俺とお揃いなんだぞ」
アイゼンは自身のポケットから同じデザインの指輪を取り出して見せた
「どうする?左手の薬指に付けてしまうか?」
『えっえええ~、えっと、ど、どうすれば、いいのかな…』
「お前がどうしたいか訊いてる」
『ええ、じゃ、じゃあ、アイゼンが付けてほしいとこに付けていいよ』
両手を広げて差し出す
「ん、良いんだな?」
するとアイゼンはわたしの左手を取って、迷いなく薬指に指輪をはめた
『ま、迷いないね…』
「これでトシユキに変な虫が付くことはないな」
左手の薬指にはめられた指輪は、サイズもぴったりで、デザインもすごく素敵で
『アイゼン…ありがとう…なんか…泣きそう…』
「喜んでもらえたならよかった」
『あーー、なんか恥ずかしい…もう呑むね、呑むからねあたし』
「おう、呑め呑め」
2時過ぎに、気の良い店主とも別れを告げて店を出た
恥ずかしさを紛らわせたくて、いつもよりも呑んでしまった
「おい、大丈夫か、ちゃんと真っ直ぐ歩け」
『んーーー…』
頭が痛い
「俺の家、すぐだから、もうちょっと耐えろ」
夜風に当たりながら歩いていたら、案外すぐに酔いは醒めてきて、アイゼンの家につく頃には大分増しになっていた
『おじゃましまーす、』
「なんだ、すっかり正気じゃねえか、酔ってるのにかまけて襲ってやろうと思ってたのにな」
『アイゼン、そういうのは口に出すもんじゃないよ』
「………トシユキ」
『あっ、ちょっ、と…』
腰を抱かれて強引にベッドに押し倒される
『結局こうなるんじゃん…』
「素直に俺の家まで来たんだ、いいんだろ?」
彼の腕がわたしの腰を離さない
『い、いい、けど、シャワーくらい浴びたいな、って…』
「だめだ、俺は今すぐがいい」
きつく抱き締めたまま、まっすぐに見つめてくる
こうなったら拒否できないのは知っている
『あ、明日は、仕事ないの?』
「ない、休みをとった」
『……わかった、楽しませてよ、あたしだけのサンタさん?』
「当たり前だ、とびきりのプレゼントをお見舞いしてやるよ」
朝目が覚めて、
無防備に寝ている彼と、わたしの薬指には、素敵な指輪がある
『……帰りたくないなあ』
指輪を眺めながら、そう呟いたら
「もう、一緒に住んじまうか?」
彼が薄目を開いて、私にそう言った