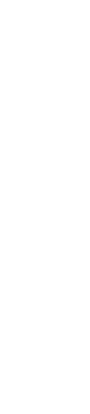『レッドマテリア』
履き慣れないハイヒールをまた履く。
でも2、3日前に履いたばかりだからその時よりは足はハイヒールに馴染んでいると思う。
それにホテルまでは優雅にタクシーで行くので厳しい道のりにはならなかった。
オマケに走る度に窓からチラチラと差し込む街灯や建物の光に照らされるヴィンセントの横顔を盗み見れるのて嬉しい事だらけだ。
「私の顔に何かついているか?」
「う、ううん!そっちの方に見えるお店は何かな~って思っただけ!」
こちらの視線に気付いたヴィンセントが尋ねてきたので慌てて顔を横に振って面白そうな店を探すフリをして自分が座っている方の窓の外に顔を向ける。
でも景色なんて目に映るだけで頭に中に入ってこない。
頭の中は先程のヴィンセントの横顔でいっぱいだ。
長い睫毛、通った鼻筋、一つに束ねられた黒い髪、それによって露出している首筋。
普段見られないものが多くてユフィはそれだけで満足していた。
もしかしたらこれは夢なのではないだろうかとこっそり自分の太腿を少し抓ったが痛かったので夢じゃなかった。
「手を」
ホテルに到着すると先に降りたヴィンセントが手を差し出してくれた。
紳士のような振る舞いに胸をときめかせながらヴィンセントの手を取ってタクシーを降りる。
到着したホテルは成る程、高級なだけあって内装はそれ相応の豪華さと煌びやかさを兼ね備えており、ロビーには美しいシャンデリアが天井から吊り下げられていてつい目を奪われてしまう。
「綺麗だな」
ずっと上を向いていると耳元でポツリと低音で呟かれ、ユフィはすぐに我に返る。
振り返ればヴィンセントはすぐ目の前にいて、優しい瞳でこちらを見下ろしていた。
ユフィは内心慌てながらも、はしたなくならないように平静を取り繕って言葉を返す。
「ほ、ホントだよね。あのシャンデリア凄いよね」
「シャンデリもだが・・・そのドレスを着たお前が綺麗だ」
「へ・・・?」
予想していなかったセリフにユフィは素っ頓狂な声を漏らして思わず自分の身に纏っているドレスを見下ろす。
ヴィンセントのマントと同じくらい紅い、ひざ丈のドレス。
これはヴィンセントが一緒にドレスを買いに行くと言った日にヴィンセントに似合うと言われて購入したもの。
ユフィも一目見た時からヴィンセントをイメージするドレスとして着てみたいと思ったが、流石に意図が分かり易過ぎててドン引きされるだろうと思って最初は買うのを諦めていた。
だから冗談めかして「みてみて、ヴィンセントのマントと同じ色のドレス」なんて言ってハンガーのかかったドレスを自分にあてがいながら見せて、「そうだな」と言われて、それでそのまま軽く流してもらう予定だった。
そしたらほんの少しの未練は残しつつもそのドレスを諦める事が出来た筈だったのだ。
なのにヴィンセントは笑うでもなく呆れるでもなくただ一言
『よく似合っている』
と、そう言った。
勿論最初は耳を疑った。
しかしヴィンセントの表情は至って真剣で、嘘を言っているようには見えなかった。
そこからは店員が介入してきて流されるままに試着をし、ヴィンセントの意外なひと押しもあって購入する運びとなったのだ。
ヴィンセントに似合うと言われ、ヴィンセントに後押ししてもらった紅いドレス。
今日家で着た時に凄くはしゃいで思わず自撮りしたのはここだけの話。
それを綺麗と言われたのだと漸く理解が追い付いてユフィの顔は一瞬にして茹蛸のように真っ赤に染まった。
「・・・!!」
「だが、そろそろ時間だ。行くぞ」
固まっているユフィの返事を待たずしてヴィンセントはユフィの手に己の手を絡め―――所謂恋人繋ぎという奴だ―――やや引っ張るようにしてエレベーターに向かって歩き始める。
それに対してユフィは黙って俯いて着いて行く事しか出来なかった。
その後の食事についての記憶は朧げだ。
夜景が綺麗でディナーも高級ホテルなだけあって見た目は美しかった。
味は・・・覚えていない。
それよりも目の前で食事をするヴィンセントの所作があまりにも優雅でずっと目を奪われていた。
思わず食べるのを忘れてしまい、何度ヴィンセントに心配された事か。
今は食事を終えてホテルの敷地内にある薔薇の大庭園の恐らく中心にある噴水の前にいる。
迷路のような庭園で何度か行き止まりに当たる事もあったがそこには可愛らしい動物のトピアリーが置いてあったので悪い気がするどころか他にはどんな動物のトピアリーが置いてあるのか気になる程だった。
探してみたかったけれど、噴水の前でヴィンセントが立ち止まったのでユフィも止まった。
・・・なんとなく、そういうフンイキだと思った。
「気分の方はどうだ?」
「え?別に全然良い感じだけど?」
「そうか。ならいい。食事中に何度もボーっとしていたから気分が悪いのかと心配した」
「ち、知的なレディのユフィちゃんは料理をじっくり味わってたんだよ!高級な食材がどんな風に料理されているのかじっくり―――」
続きの言葉はヴィンセントの人差し指を当てられて封じられてしまう。
「夜にこのような場所で大きな声を出すものではない」
そう咎めながらもヴィンセントの瞳は優しく、何かを言いたげだった。
暗に、今はそんな事を言っている場合ではないだろう、と語り掛けているようで。
ユフィは無理矢理言葉を飲み込むと小さく頷いた。
細長い人差し指が唇から離れてしまったのは残念だけれど、それでもそれ以上のものを得られそうな予感がしている。
何度かヴィンセントの瞳と地面に視線を彷徨わせるが、漸く視線をヴィンセントの首元に留めてもじもじしながらユフィは口を開く。
「・・・今のはマナー違反、だよね?」
「そうだな」
「じゃあ、こういう時はどういう事をするのがマナーなの?」
「談笑をする時は静かな声で周りの迷惑にならないようにする」
「好きな人といる時は?」
「何も言わず見つめ合う。そして・・・」
「そして?」
「周りに人がいなければ抱きしめ合う」
「なら、マナーに従わなきゃだね」
頬を朱に染め、地面を軽く蹴るようにしてユフィがヴィンセントの胸に飛び込むのとヴィンセントが迎え入れるように腕を広げたのはほぼ同時だった。
ユフィはヴィンセントの胸に頬を摺り寄せ、ヴィンセントはユフィの髪に鼻先を沈める。
ヴィンセントがユフィの後頭部や腰に腕を回してまるで宝物のように抱きしめるのに対してユフィはぎこちなくヴィンセントの背中に腕を回す。
同性の子にスキンシップのハグはよくするが異性に特別な想いで抱きしめるのは初めてだ。
「固いな。もう少し力を抜け」
耳元で笑う様に囁かれて体が震え上がる。
「ぬ、抜くったって・・・どうやるんだよ~・・・」
こんな低音ボイスを間近で注ぎ込まれて固くなるなという方が無理な話というもの。
益々緊張して力が入ってしまうユフィを諫めるようにヴィンセントが背中を優しく叩いてくる。
子供扱いされているようで少し不満だったが、緊張が解れたのは確かなのでお決まりの抗議は控えておく事にした。
「これでは・・・少々やりづらいな」
「・・・何が?アタシ、頑張って何でもするよ・・・?」
「・・・なら、体の力を抜いて目を瞑れ」
『きた!!!』と心の中で叫びつつ、言われた通りに何とか力を抜いて目を瞑る。
ドクドクと心臓の音が耳元で煩く鳴り響く。
「・・・」
ヴィンセントの体が少し離れ、それから顎を上向かせられる。
心臓の音がもっと煩くなった。
「・・・っ・・・」
吐息が唇にかかる。
心臓が破裂しそうなくらい鼓動が激しくなる。
あと1センチで重なりそうになったその時―――
「信じられない!私を差し置いて他の女に鼻の下伸ばすなんて!!」
不意にヒステリックな声を上げる女性の声が夜空に響いて二人は驚いて思わず声の方を同時に振り向く。
振り向いた先に人の影はなかったが、どうやら薔薇の垣根の向こうで男性と口論しているようだった。
しょーもない男女の口論ですっかり場が白けてしまい、キスの瞬間が流れてしまい呆けるユフィ。
真っ白になっている頭のどこかで、先程ヴィンセントが言ったようにこういった所で大声を出すのは確かにマナー違反だと実感するもう一人の自分がいたとか。
「続きは次回だな」
苦笑するような吐息を漏らしてヴィンセントは呆けたままのユフィの手を引っ張って庭園の出口を目指した。
その後はタクシーに乗って帰宅コースとなった。
時間的に夜遅いのと、あんな雰囲気の後にどこかに行って仕切り直すのが難しいと判断したのかもしれない。
実際の所ヴィンセントがどう思ったかは分からないが少なくともユフィはそう判断した。
自分の身に置き換えても仕切り直すには空気作りが大変だし、何より変に意識しすぎてもっと酷い事になりそうだと思った。
名残惜しいが今日は潔く諦めなければいけないのかもしれない。
それにヴィンセントがキスをしようとしてくれたのだからそれだけでも大きな収穫だ。
そう自分に言い聞かせる程にユフィの両の拳は固く握られて行く。
「到着しました。料金は3200ギルになります」
財布からお金を取り出して運転手に渡す。
降りて、ヴィンセントに別れの挨拶をしなければ―――
「降りるよ、ヴィンセント!」
お礼とお休みの挨拶を紡ぐ筈だった自分の口は降車を促す言葉を紡いでいた。
手はバイバイと横に振るのではなくゴツゴツとした大きな手を引っ張って外に連れ出そうとしている。
ヴィンセントは一瞬だけ驚いた表情をしたものの、すぐにいつものポーカーフェイスに戻ってユフィに引っ張られるがままにタクシーを降りてくれた。
タクシーの運転手は「ご利用ありがとうございました」というお決まりの営業セリフを言うと扉を閉めて走り去り、ヴィンセントとユフィの二人がそこに残される。
「・・・部屋、こっち・・・」
ユフィは頬を赤く染めて俯きながらヴィンセントの手を引っ張る。
それに対してヴィンセントは何も言わずユフィの誘導に従って部屋の中に入ってくれた。
大人しく従ってくれるのを良い事に部屋に入るなりそのまま一直線にベッドに向かい、ベッドに座るように促す。
少し緊張するけどリモコンで部屋の電気を点けた。
けれど頭の中が真っ白になってどうしても言いたい事を紡ぎ出す事が出来ない。
「・・・大丈夫か?」
俯いたまましばらく無言でいたユフィを心配してヴィンセントが声をかける。
ぎこちなくはあったが何度か頷いて意思表示をする。
しかしこのまま無言でいる訳にもいかないのでユフィは何度か深呼吸すると視線を下に向けながら固い声で言葉を発した。
「・・・・・・さっきの・・・続き・・・」
「さっき、とは?」
「・・・『続きは次回』ってやつ・・・」
「アレか・・・」
「ここなら誰にも邪魔されないし・・・」
「誰にも助けてもらえないぞ?」
「助けて?何で?」
「ユフィ、落ち着いて考えて欲しい。今は夜で、ここはお前の部屋で、私たちはベッドの上に座っている。今ここで先程の『続き』をしたら私は間違いなく全てを自分の都合の良いように解釈してお前を傷付けてしまう。私は・・・お前と共にいたいが、お前を傷付けたくない」
目を伏せて緩く顔を横に振りながらヴィンセントは静かに語る。
ずるい男だ、優しく諭しておきながらさりげなく自分の想いを伝えてくるなんて。
この想いに答えない程、ユフィ・キサラギは子供ではない。
ユフィはヴィンセントの右手を両手で掴むと、その掌を自分の頬に宛がい、微笑みながら言った。
「・・・それだけアタシの事を思ってくれてるなら十分だよ。アタシだってもう大人だよ?今自分がしてる事も自分がしようとしてる事もちゃんと分かってる」
「なら―――本気にしていいんだな?」
「勿論。だからアタシもさ・・・本気にしていい?」
「本気にしてくれ」
真剣で熱い眼差しに射抜かれ、ユフィの心は蕩けてしまう。
そして『そういうフンイキ』を感じ取って静かに目を閉じた。
唇に熱い吐息を感じた直後に重ねてきて塞いでくる柔らかい感触。
僅か数秒で離れてしまったがすぐに二回目、三回目と重ねってきてその度に口付けは深いものとなっていた。
そうして気付けば熱くねっとりとしたヴィンセントの舌が口内に侵入していて、ユフィはすっかりそれに絡め取られていた。
「んっ・・・」
舌を絡め合う大人のキスに夢中になっていてもそれには気付いた。
ドレスのファスナーの摘まみをヴィンセントの指先が弄ぶ感覚。
薄く瞼を開けば同じようなタイミングで開かれた紅い瞳と視線がかちあう。
迷いなんてなかったからまた瞼を閉じてヴィンセントのシャツの胸元をキュッと握る。
火に焼かれるような熱い夜が始まった。
つづく
でも2、3日前に履いたばかりだからその時よりは足はハイヒールに馴染んでいると思う。
それにホテルまでは優雅にタクシーで行くので厳しい道のりにはならなかった。
オマケに走る度に窓からチラチラと差し込む街灯や建物の光に照らされるヴィンセントの横顔を盗み見れるのて嬉しい事だらけだ。
「私の顔に何かついているか?」
「う、ううん!そっちの方に見えるお店は何かな~って思っただけ!」
こちらの視線に気付いたヴィンセントが尋ねてきたので慌てて顔を横に振って面白そうな店を探すフリをして自分が座っている方の窓の外に顔を向ける。
でも景色なんて目に映るだけで頭に中に入ってこない。
頭の中は先程のヴィンセントの横顔でいっぱいだ。
長い睫毛、通った鼻筋、一つに束ねられた黒い髪、それによって露出している首筋。
普段見られないものが多くてユフィはそれだけで満足していた。
もしかしたらこれは夢なのではないだろうかとこっそり自分の太腿を少し抓ったが痛かったので夢じゃなかった。
「手を」
ホテルに到着すると先に降りたヴィンセントが手を差し出してくれた。
紳士のような振る舞いに胸をときめかせながらヴィンセントの手を取ってタクシーを降りる。
到着したホテルは成る程、高級なだけあって内装はそれ相応の豪華さと煌びやかさを兼ね備えており、ロビーには美しいシャンデリアが天井から吊り下げられていてつい目を奪われてしまう。
「綺麗だな」
ずっと上を向いていると耳元でポツリと低音で呟かれ、ユフィはすぐに我に返る。
振り返ればヴィンセントはすぐ目の前にいて、優しい瞳でこちらを見下ろしていた。
ユフィは内心慌てながらも、はしたなくならないように平静を取り繕って言葉を返す。
「ほ、ホントだよね。あのシャンデリア凄いよね」
「シャンデリもだが・・・そのドレスを着たお前が綺麗だ」
「へ・・・?」
予想していなかったセリフにユフィは素っ頓狂な声を漏らして思わず自分の身に纏っているドレスを見下ろす。
ヴィンセントのマントと同じくらい紅い、ひざ丈のドレス。
これはヴィンセントが一緒にドレスを買いに行くと言った日にヴィンセントに似合うと言われて購入したもの。
ユフィも一目見た時からヴィンセントをイメージするドレスとして着てみたいと思ったが、流石に意図が分かり易過ぎててドン引きされるだろうと思って最初は買うのを諦めていた。
だから冗談めかして「みてみて、ヴィンセントのマントと同じ色のドレス」なんて言ってハンガーのかかったドレスを自分にあてがいながら見せて、「そうだな」と言われて、それでそのまま軽く流してもらう予定だった。
そしたらほんの少しの未練は残しつつもそのドレスを諦める事が出来た筈だったのだ。
なのにヴィンセントは笑うでもなく呆れるでもなくただ一言
『よく似合っている』
と、そう言った。
勿論最初は耳を疑った。
しかしヴィンセントの表情は至って真剣で、嘘を言っているようには見えなかった。
そこからは店員が介入してきて流されるままに試着をし、ヴィンセントの意外なひと押しもあって購入する運びとなったのだ。
ヴィンセントに似合うと言われ、ヴィンセントに後押ししてもらった紅いドレス。
今日家で着た時に凄くはしゃいで思わず自撮りしたのはここだけの話。
それを綺麗と言われたのだと漸く理解が追い付いてユフィの顔は一瞬にして茹蛸のように真っ赤に染まった。
「・・・!!」
「だが、そろそろ時間だ。行くぞ」
固まっているユフィの返事を待たずしてヴィンセントはユフィの手に己の手を絡め―――所謂恋人繋ぎという奴だ―――やや引っ張るようにしてエレベーターに向かって歩き始める。
それに対してユフィは黙って俯いて着いて行く事しか出来なかった。
その後の食事についての記憶は朧げだ。
夜景が綺麗でディナーも高級ホテルなだけあって見た目は美しかった。
味は・・・覚えていない。
それよりも目の前で食事をするヴィンセントの所作があまりにも優雅でずっと目を奪われていた。
思わず食べるのを忘れてしまい、何度ヴィンセントに心配された事か。
今は食事を終えてホテルの敷地内にある薔薇の大庭園の恐らく中心にある噴水の前にいる。
迷路のような庭園で何度か行き止まりに当たる事もあったがそこには可愛らしい動物のトピアリーが置いてあったので悪い気がするどころか他にはどんな動物のトピアリーが置いてあるのか気になる程だった。
探してみたかったけれど、噴水の前でヴィンセントが立ち止まったのでユフィも止まった。
・・・なんとなく、そういうフンイキだと思った。
「気分の方はどうだ?」
「え?別に全然良い感じだけど?」
「そうか。ならいい。食事中に何度もボーっとしていたから気分が悪いのかと心配した」
「ち、知的なレディのユフィちゃんは料理をじっくり味わってたんだよ!高級な食材がどんな風に料理されているのかじっくり―――」
続きの言葉はヴィンセントの人差し指を当てられて封じられてしまう。
「夜にこのような場所で大きな声を出すものではない」
そう咎めながらもヴィンセントの瞳は優しく、何かを言いたげだった。
暗に、今はそんな事を言っている場合ではないだろう、と語り掛けているようで。
ユフィは無理矢理言葉を飲み込むと小さく頷いた。
細長い人差し指が唇から離れてしまったのは残念だけれど、それでもそれ以上のものを得られそうな予感がしている。
何度かヴィンセントの瞳と地面に視線を彷徨わせるが、漸く視線をヴィンセントの首元に留めてもじもじしながらユフィは口を開く。
「・・・今のはマナー違反、だよね?」
「そうだな」
「じゃあ、こういう時はどういう事をするのがマナーなの?」
「談笑をする時は静かな声で周りの迷惑にならないようにする」
「好きな人といる時は?」
「何も言わず見つめ合う。そして・・・」
「そして?」
「周りに人がいなければ抱きしめ合う」
「なら、マナーに従わなきゃだね」
頬を朱に染め、地面を軽く蹴るようにしてユフィがヴィンセントの胸に飛び込むのとヴィンセントが迎え入れるように腕を広げたのはほぼ同時だった。
ユフィはヴィンセントの胸に頬を摺り寄せ、ヴィンセントはユフィの髪に鼻先を沈める。
ヴィンセントがユフィの後頭部や腰に腕を回してまるで宝物のように抱きしめるのに対してユフィはぎこちなくヴィンセントの背中に腕を回す。
同性の子にスキンシップのハグはよくするが異性に特別な想いで抱きしめるのは初めてだ。
「固いな。もう少し力を抜け」
耳元で笑う様に囁かれて体が震え上がる。
「ぬ、抜くったって・・・どうやるんだよ~・・・」
こんな低音ボイスを間近で注ぎ込まれて固くなるなという方が無理な話というもの。
益々緊張して力が入ってしまうユフィを諫めるようにヴィンセントが背中を優しく叩いてくる。
子供扱いされているようで少し不満だったが、緊張が解れたのは確かなのでお決まりの抗議は控えておく事にした。
「これでは・・・少々やりづらいな」
「・・・何が?アタシ、頑張って何でもするよ・・・?」
「・・・なら、体の力を抜いて目を瞑れ」
『きた!!!』と心の中で叫びつつ、言われた通りに何とか力を抜いて目を瞑る。
ドクドクと心臓の音が耳元で煩く鳴り響く。
「・・・」
ヴィンセントの体が少し離れ、それから顎を上向かせられる。
心臓の音がもっと煩くなった。
「・・・っ・・・」
吐息が唇にかかる。
心臓が破裂しそうなくらい鼓動が激しくなる。
あと1センチで重なりそうになったその時―――
「信じられない!私を差し置いて他の女に鼻の下伸ばすなんて!!」
不意にヒステリックな声を上げる女性の声が夜空に響いて二人は驚いて思わず声の方を同時に振り向く。
振り向いた先に人の影はなかったが、どうやら薔薇の垣根の向こうで男性と口論しているようだった。
しょーもない男女の口論ですっかり場が白けてしまい、キスの瞬間が流れてしまい呆けるユフィ。
真っ白になっている頭のどこかで、先程ヴィンセントが言ったようにこういった所で大声を出すのは確かにマナー違反だと実感するもう一人の自分がいたとか。
「続きは次回だな」
苦笑するような吐息を漏らしてヴィンセントは呆けたままのユフィの手を引っ張って庭園の出口を目指した。
その後はタクシーに乗って帰宅コースとなった。
時間的に夜遅いのと、あんな雰囲気の後にどこかに行って仕切り直すのが難しいと判断したのかもしれない。
実際の所ヴィンセントがどう思ったかは分からないが少なくともユフィはそう判断した。
自分の身に置き換えても仕切り直すには空気作りが大変だし、何より変に意識しすぎてもっと酷い事になりそうだと思った。
名残惜しいが今日は潔く諦めなければいけないのかもしれない。
それにヴィンセントがキスをしようとしてくれたのだからそれだけでも大きな収穫だ。
そう自分に言い聞かせる程にユフィの両の拳は固く握られて行く。
「到着しました。料金は3200ギルになります」
財布からお金を取り出して運転手に渡す。
降りて、ヴィンセントに別れの挨拶をしなければ―――
「降りるよ、ヴィンセント!」
お礼とお休みの挨拶を紡ぐ筈だった自分の口は降車を促す言葉を紡いでいた。
手はバイバイと横に振るのではなくゴツゴツとした大きな手を引っ張って外に連れ出そうとしている。
ヴィンセントは一瞬だけ驚いた表情をしたものの、すぐにいつものポーカーフェイスに戻ってユフィに引っ張られるがままにタクシーを降りてくれた。
タクシーの運転手は「ご利用ありがとうございました」というお決まりの営業セリフを言うと扉を閉めて走り去り、ヴィンセントとユフィの二人がそこに残される。
「・・・部屋、こっち・・・」
ユフィは頬を赤く染めて俯きながらヴィンセントの手を引っ張る。
それに対してヴィンセントは何も言わずユフィの誘導に従って部屋の中に入ってくれた。
大人しく従ってくれるのを良い事に部屋に入るなりそのまま一直線にベッドに向かい、ベッドに座るように促す。
少し緊張するけどリモコンで部屋の電気を点けた。
けれど頭の中が真っ白になってどうしても言いたい事を紡ぎ出す事が出来ない。
「・・・大丈夫か?」
俯いたまましばらく無言でいたユフィを心配してヴィンセントが声をかける。
ぎこちなくはあったが何度か頷いて意思表示をする。
しかしこのまま無言でいる訳にもいかないのでユフィは何度か深呼吸すると視線を下に向けながら固い声で言葉を発した。
「・・・・・・さっきの・・・続き・・・」
「さっき、とは?」
「・・・『続きは次回』ってやつ・・・」
「アレか・・・」
「ここなら誰にも邪魔されないし・・・」
「誰にも助けてもらえないぞ?」
「助けて?何で?」
「ユフィ、落ち着いて考えて欲しい。今は夜で、ここはお前の部屋で、私たちはベッドの上に座っている。今ここで先程の『続き』をしたら私は間違いなく全てを自分の都合の良いように解釈してお前を傷付けてしまう。私は・・・お前と共にいたいが、お前を傷付けたくない」
目を伏せて緩く顔を横に振りながらヴィンセントは静かに語る。
ずるい男だ、優しく諭しておきながらさりげなく自分の想いを伝えてくるなんて。
この想いに答えない程、ユフィ・キサラギは子供ではない。
ユフィはヴィンセントの右手を両手で掴むと、その掌を自分の頬に宛がい、微笑みながら言った。
「・・・それだけアタシの事を思ってくれてるなら十分だよ。アタシだってもう大人だよ?今自分がしてる事も自分がしようとしてる事もちゃんと分かってる」
「なら―――本気にしていいんだな?」
「勿論。だからアタシもさ・・・本気にしていい?」
「本気にしてくれ」
真剣で熱い眼差しに射抜かれ、ユフィの心は蕩けてしまう。
そして『そういうフンイキ』を感じ取って静かに目を閉じた。
唇に熱い吐息を感じた直後に重ねてきて塞いでくる柔らかい感触。
僅か数秒で離れてしまったがすぐに二回目、三回目と重ねってきてその度に口付けは深いものとなっていた。
そうして気付けば熱くねっとりとしたヴィンセントの舌が口内に侵入していて、ユフィはすっかりそれに絡め取られていた。
「んっ・・・」
舌を絡め合う大人のキスに夢中になっていてもそれには気付いた。
ドレスのファスナーの摘まみをヴィンセントの指先が弄ぶ感覚。
薄く瞼を開けば同じようなタイミングで開かれた紅い瞳と視線がかちあう。
迷いなんてなかったからまた瞼を閉じてヴィンセントのシャツの胸元をキュッと握る。
火に焼かれるような熱い夜が始まった。
つづく