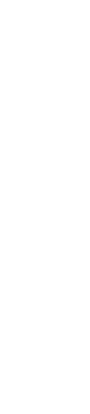『レッドマテリア』
そして翌日。
ユフィはガルディスが用意したドレスを身に纏って待ち合わせのラブレス駅前に向かっていた。
ガルディスがWROの備品室から見繕ってきたドレスはスカート丈の短い青いドレスで悔しい事にユフィ好みの可愛いくてちょっとセクシーなドレスだった。
歩きづらくてあまり好きではないヒールも今日はドレスを着ているお陰でコツコツという石を叩く音が耳に心地良い。
(これで相手がヴィンセントだったら言う事ないのになぁ)
「そんなあからさまにガッカリした顔しないでくれよ」
駅前に着くとグレーのスーツを着たガルディスが苦笑いしてそう言った。
しかしユフィは表情を改めるどころか更にガッカリ感を剥き出しにして先程思った事を今度は口にした。
「あーあ、これがヴィンセントだったらいいのになー」
「ちくしょう、今度は声に出して言いやがって。絶対に俺で良かったって言わせてみるからな」
「じゃあ言わせてみてよ?」
「上等だ。まずはバーで軽く一杯と行こうか」
ガルディスはあのニヒルな笑みを浮かべると顎で行く道を示すとそちらを向いて歩き始め、ユフィもそれに従って隣を歩いた。
紳士的な事にガルディスはユフィに合わせて歩幅を狭くして歩いており、ユフィに疲れる事なく会話する余裕を与える。
「そこってノンアルコールカクテルある?」
「まぁあるにはあるが酒飲めないのか?」
「最近二十歳になって漸く解禁したんだよ。そんでお酒に慣れてないから慣れるまでは仲間のみんなが一緒にいる時じゃないとダメってティファと約束してるんだ」
「ティファってセブンスヘブンのティファちゃん?」
「うん」
「あ~ティファちゃんとの約束なら仕方ないか~。それにアルハラされたとか訴えられたら嫌だしな」
「やっぱティファの事知ってんの?」
「そりゃぁ勿論。エッジで有名な美人さんだからな。前に口説き落とそうとしたら怖いお兄さんに首を切り落とされそうになったけど」
「それクラウドだね。ていうかクラウドがいるのにティファを口説こうなんて命知らずもいいとこだね~」
「あんな美人さん、口説かずにはいられないだろ?」
「でもフラれてアタシに狙いを定めたと」
「いや、それとは関係なくユフィちゃんの事は元々口説くつもりだったよ。ちょっとティファちゃんに寄り道しただけで」
「アタシ浮気男は嫌いなんだけどー?」
「安心しなって。俺の恋人になってくれたらずーっとユフィちゃんだけを見るからさ」
「嘘くさー」
「なら試しに俺の恋人になってみないか?証明してみせるよ」
「その手には乗りませーん」
「ハハ、やっぱダメか。こりゃ一旦仕切り直しだな」
ネオンの光が照らす夜道を歩いている途中に目的地に到着し、ガルディスが店の扉を押し開く。
「どうぞ」と言って紳士的に扉を開けたままにしてガルディスはユフィを招き入れ、ユフィもそれに従って店の中に入ろうとしたその時―――
「ん?」
何か視線を感じてユフィはすぐさま振り返る。
が、振り向いた先には誰もおらず、ネオンの光が朧げに地面を照らしているだけだった。
「どうした?」
「んー、さっき誰かに見られてたような気がしてさ」
「今日のユフィちゃんは綺麗で目立つから誰かが注目してたのかもなぁ」
「そういうのとは違った気がするんだけど・・・まぁいいや。それよりカクテル~!」
「ノンアルコールのな」
大人っぽく着飾った外見とは裏腹に子供っぽいユフィのセリフに苦笑交じりに笑いながら付けたすとガルディスは店の扉を閉めた。
バーなだけあって店の中は暗く、青と紫を基調にした仄かな明かりが店内に静けさと落ち着きをもたらす。
あまり入った事のないバーの大人な雰囲気にユフィは内心興奮しながらも、しかし大人のレディとして振る舞わなければという理性によるストッパーの元、頑張って感情を抑えた。
そしてカウンターチェアに座ったガルディスに倣ってユフィもカウンターチェアに座る。
ガルディスはメニュー表を取るとそれをユフィに渡して尋ねる。
「俺の奢りだ。好きなのを飲んでいいぞ」
「んーと・・・じゃあこれ!」
「シンデレラだな。マスター、俺いつもの。この子にはシンデレラで」
「かしこまりました」
スキンヘッドで髭のダンディなマスターは頷くと早速シェイカーや材料を用意してカクテルを作り始めた。
手際が良く鮮やかでユフィは思わず見惚れてしまう。
ティファのカクテル作りも似たように綺麗でカッコよくてユフィは見るのが好きなのだが、それとはまた違った雰囲気のカクテル作りをマスターは披露している。
というよりも、ティファもマスターも店の雰囲気に合ったカクテルの作り方をしているだけなのかもしれない。
だから雰囲気も違っていて当然なのだろう。
そんな風に考えていると瞬く間にカクテルは出来上がり、ガルディスとユフィの前に静かに提供された。
「それじゃ、乾杯」
「乾杯」
いつもだったらバレットやシドと一緒になって豪快に音頭を取っているが今いるのは小洒落た静かなバー。
ユフィも店の雰囲気を壊さないように、また馴染もうとして静かに言葉を紡いだ。
チン、とガラスのぶつかり合う音を奏でて二人は最初の一口を飲む。
フルーツの甘い香りが鼻に抜け、舌の上を踊る感覚にユフィは笑みを溢さずにはいられなかった。
「美味しい・・・!」
「俺もユフィちゃんと一緒に飲めて美味しいよ」
「お?早速口説きモード?」
「俺は最初から口説きモードだよ。ユフィちゃんの好感度をMAXにまで上げてみせるよ」
「残念でしたー。ユフィちゃんの好感度はそう簡単には上がりませ~ん」
「でもこうやって軽快な会話が出来るんだから俺達は色々相性が良いと思うんだけどな」
「こりゃっ」
言いながらどさくさに紛れて自分の腰に回されそうになった手に気付いてユフィはぺちっと叩いてその手を払う。
「全く、油断も隙もないんだから」
「残念、バレたか」
「今ので好感度暴落したから」
「そんなに?」
「いきなりえっちぃ事するやつは嫌いだよーだ」
「悪かったよ。美味しいアイスクリーム奢ってあげるから機嫌を治してくれ」
ガルディスがチラリと目配せをするとマスターは頷き、ものの数分でオシャレなグラスに盛り付けられたアイスを提供してくれた。
提供する際に「可愛らしいお嬢さんの来客を記念して」と言葉を添えて小さな板チョコもトッピングしてもらった。
嬉しいオマケにユフィはすぐに笑顔になってアイスを食べ始める。
「サンキューマスター。マスターへの好感度がうなぎ上りだよ」
「おいおい、奢った俺の好感度はうなぎ上りにならないのかよ?」
「ま、ほんのちょっとは上げてあげてもいいけど?」
「手強いなぁ。少しくらいは多めに見てくれてもいいんじゃないか?任務に支障が出ちまう」
「今の内に厳しくしとかないと任務で調子に乗って色んな事してきそうだもん」
「流石に任務では真面目だよ、俺は」
「ホントに〜?」
「本当だよ。この間だって犯罪組織『スカルゴブリン』を壊滅させたしさ」
「へー、あれアンタがやったんだ?」
「少し骨が折れたけどね」
「うむうむ、ご苦労。アンタのその働きで街の人たちがまた笑顔になったぞ」
「上司にも同じ事言われたよ。ユフィちゃんからはもっと別の労いが欲しいな」
「んじゃあ、おつかれ」
「足りないなぁ」
「ガルディスおつかれ。頑張ったんだからゆっくり休みなよ」
「お、いいね〜。ガルディスじゃなくてガルって呼んでくれたら満点だった」
「ならもっと早く言ってくれればそう呼んだのに」
「悪い、タイミングがなかったもんでさ」
「そういえばガルって何でWROに入ろうと思ったの?言っちゃ悪いけどあんまそういう慈善活動っぽいのに興味ない感じするからさ」
「んー?」
ガルディスはカクテルを一口煽ると笑う様に短く息を吐く。
そしてその瞳は正面のキープボトルを見つめるが意味を持って見つめているようではなかった。
まるで遠い日を懐かしむような、そんな瞳にユフィには見えた。
「ユフィちゃんの言う通り・・・俺はさ、元はそういうのに興味なかったんだよ。酒飲んでギャンブルで遊んでって感じで要はちゃらんぽらんな男だった訳よ。その日が楽しけりゃそれで良いみたいな生き方をしてたんだ」
「うん」
「でもある日大変な事が起きてなぁ・・・」
「大変な事?」
「ああ、凄く大変な事だ。それに直面した俺はみっともなくもパニックになって慌てて逃げようとしたんだが転んで崩れて来た瓦礫に足を挟まれて動けなくなっちまったんだ」
「マジで?それでどうなったの?」
「俺の人生もここで終わりだと諦めかけた時に颯爽とヒーローが現れて助けてくれたんだ」
「へ~。どんなヒーロー?」
「俺よりも少し年下だけど強くて活力のある子だよ」
「子、って事は女の子?」
「そうだ。俺なんかよりもしっかりしててテキパキと周りの大人たちに指示を出して俺の事を助けてくれたんだ。その時のその子の凛々しい横顔は今でも忘れられない」
ガルディスの脳裏に4年前の騒動―――メテオ災害がフラッシュバックする。
上空にメテオの影が浮かんで周りの人間が絶望している中、自分は相変わらず酒を飲んで遊んでいた。
どうせ神羅が何とかしてくれる、2,3日寝てりゃすぐに消える、そんな風に思っていた。
けれど事態はどんどん悪化していき、メテオは消えるどころか目前まで迫ってきた。
オマケにウェポンとやらが攻めて来て神羅ビルは文字通り崩壊。
何とかしてくれると思っていた神羅もいよいよ当てにならなくなり、逃げだそうとした所で躓き、不運にも崩れて来た建物の瓦礫に足を挟まれた。
元々スラムの建物なんてのは寄せ集めの資材や廃墟を再利用して作られた家屋が殆どで、ちゃんと造られた建物なんて少ししかない。
だから大きな衝撃が起きれば簡単に崩れる建物が多く、自分はその中でもそういった建物が多く立ち並ぶ地域にいた。
自分の人生もここまでかと諦め、これまでのくだらない人生を振り返っていた時に張りのある大きな声が響いた。
『誰かこっち手伝って!動けなくなってる人がいる!!』
声の主は見るからに自分よりも年下の女の子なのにすぐに自分の元に駆け寄って大きな瓦礫をどかそうと必死に持ち上げようとしてくれていた。
大の大人である自分でさえメテオに恐れ慄いて慌てて逃げようとしていたのに、その女の子は逃げるどころか自分のような逃げ遅れた人間を探して避難誘導に当たっていたのだ。
『ユフィさん、ここは我々が対応します!』
『あちらで神羅の実験用モンスターが暴れているとの報告がありました!』
『分かった!後宜しく!』
(ユフィ・・・)
ガルディスは自分を見つけて助けようとしてくれた少女の凛々しい横顔と名前を心に深く刻み付けた。
それから救出されて安全な場所に避難し、メテオとライフストリームの衝突をやり過ごしてからは生き方を少し変えた。
酒とギャンブルはやめなかったがそれで一日を終える事はしなかった。
むしろそれを一日の終わりに持ってきて、それまでの日中の時間は鍛錬に時間を当てた。
力を付けて、武術を身に付けて、困っている人がいたら助けて。
そうした日々を過ごしている内に元神羅社員の男によるWROという世界の復興を目指す組織が設立された。
元神羅社員って点がどうにも引っ掛かって入る気になれなかったが、自分を救ってくれたあのユフィがその男と死線を潜り抜けた間柄であり、そこに在籍していると噂で聞いて入社する事を即決した。
あのユフィが信頼している男なら間違いない。
ユフィの信じたものを自分も信じる。
そしていつか横に並び立って彼女を助けたい。
あの時助けてもらったお礼をしたい。
その想いを胸に、そしてユフィという人間を目標にして今日まで生きて来た。
(漸くその願いが叶った訳だ)
チラリと隣のユフィを盗み見て浮かびそうになった笑みを隠すようにガルディスはまたカクテルを一口含む。
ユフィとは本社の廊下で四年ぶりに再会したがこちらに気付いた様子はなく、そのまま素通りされた。
しかしそれも無理もない。
救出された時、辺りは暗かったしユフィも必死だったからこちらの顔を確認している余裕はなかっただろうしそんな場合でもなかった。
だからガルディスとしては覚えてくれていなくて良かったし、むしろあんな無様な姿を覚えていてほしくなかったのである意味都合が良かった。
それからは何とかしてユフィに近付けないかとあれこれ努力し、漸く今回の潜入ミッションのペアに漕ぎ着けたのである。
ついでにお礼を兼ねた模擬デートを取り付けられたのも大きな幸運だった。
(まさか赤マントさんに夢中だったとは思わなかったけどな)
WROの女性社員の胸をときめかす美青年・ヴィンセント・ヴァレンタイン。
ユフィはその男とも死線を潜り抜けた間柄らしく、ミッションに同行したり訓練を共にしている所をよく見かける。
最初は仲間だから距離が近いのだろうと思っていたのだがユフィを見ている内に段々そうではない事を知って強力なライバルが現れたものだと思わず溜息を吐いた。
しかもユフィ自身は一途な少女でその気持ちをこちらに向けるのも一苦労しそうである。
そんなガルディスの複雑な内心など露知らずユフィが質問を投げかけてくる。
「その子に助けられた後はどうしたの?」
「一旦避難してメテオをやり過ごして、それから体を鍛えて戦い方も学ぶようになった。いつかその子に会った時にだらしないって言われて笑われないようにな」
「ふーん。会えるといいね」
「ああ、そうだな」
「それからちゃんとお礼も言うんだぞ」
「ハハ!そうだな」
きっとお礼を言えるのはまだまだ先になるだろうが、と心の中で付け足してガルディスはカクテルの残りを全て煽った。
グラスをテーブルに置いてチラリとユフィの方を見れば既にアイスは綺麗に食べられており、シンデレラもカクテルグラスの中から消えていた。
「良い感じに盛り上がって来たし次の店に行こうか。ユフィちゃん、ダーツは出来る?」
「超得意だよ」
「なら早速行こうか。負けたらコーヒー奢りね」
「じゃあアタシが勝ったらムーンバックスの期間限定トロピカルフラペチーノね」
「おいおい、俺のコーヒーより明らか高いだろ。ユフィちゃんはオレンジジュースな」
「え~?」
他愛の無い会話をしながらガルディスは会計を済ませ、ユフィと共に店を出て次の店に足を運んだ。
それからはダーツで対戦をしたりビリヤードを教えたり、ユフィのリクエストで喫茶店で休憩をした。
履き慣れないハイヒールの所為で足を痛めたらしい。
そんな状態のユフィを連れ回すのは酷だという事で喫茶店でケーキやコーヒーを楽しんだ所で本日の模擬デートはお開きとなった。
今は二人で月明かりの道をユフィの自宅を目指して歩いている。
勿論ガルディスに下心はなく、純粋なジェントルマンシップでユフィを送っているだけだった。
「や~いっぱい遊んだね~」
「そうだな」
「これで任務には臨めそう?」
「ダメって言ったら?」
「リーブのおっちゃんに別の人に交代してもらうように掛け合っておくよ」
「冗談だって。今日ので十分だ。とりあえずユフィちゃんは過剰なボディタッチはNGだな?」
「大体の女の人はNGだよ」
「でも肩を抱くくらいは我慢してもらえないか?」
「えー?やだ」
「頼むよ。今度の任務では恋人を演じるんだからさ」
「それを口実にベタベタ触ってくんなって言ってんの」
「いやいや、下心全開で言ってる訳じゃないさ。考えてもみろ、そういうアンダーグラウンドな店に入るカップルが仲良く手を繋いで入る光景をさ」
「・・・ちょっと浮いてる?」
「ちょっとどころかかなり浮いてるぞ。門前払い喰らうのがオチだ。ああいう所に入る時はそういう火遊びに慣れてそうなカップルを演じないと怪しまれる以前の問題だ」
「じゃあ肩抱くだけだよ?それ以上やったら後でぶん殴るから!」
シュシュシュ、とシャドーボクシングのように手を三回突き出してくるユフィに、そんな事はしないと笑って約束する。
本人に殴られるのも嫌だし、彼女と親しい人物たちにもこぞって殴られるのも嫌だ。
交友関係の広いユフィは色んな人と仲が良いし愛されている。
ユフィが嫌がる事や泣かせるような事をすればタダでは済まされないだろう。
それに強引に迫ってどうにかなるタイプでもないし、任務が終わっても何かしら理由を付けて接点を保つ方がまだ良策だ。
ガルディスはユフィの住んでるアパートの前まで来るとそこで別れの挨拶を交わした。
「じゃあなユフィちゃん。今日は一緒に酒が飲めて楽しかったよ」
「ノンアルコールだけどね」
「次はアルコール入りで飲んでくれるかい?」
「飲み会でならいいけど?」
「手強いなぁ。仕方ない、飲み会で向かい側の席を今から予約させてもらおうか」
「早いもん勝ちだよ。アタシは保証してやんないから」
「分かってるよ。じゃ、お休み」
「うん、お休みー。今日はありがとね」
「ああ」
部屋の中に消えて行くユフィを見届けてから自分も帰路を辿る。
今日は良い夢が見れそうだと思ったその時―――
「ん?」
鋭い視線が背中に刺さった。
驚いて振り返ったがそこには暗闇しかなく、人の姿は全くなかった。
「・・・気のせいか?」
首を傾げつつも前を向いてまた歩き始める。
そういえばデートの最中に何回か見られているような気配を感じたが、楽しい時間を過ごしたかった自分は気の所為だと思ってをそれを流した。
何か怪しいものが襲ってくるような気配もないし、それにそういう気配がする時は決まって自分とユフィの距離が近い時だった。
こうなると種類的にユフィに好意を寄せる者の嫉妬の眼差しの類だろう。
ユフィはウータイの統治者の娘だと聞いていて、その隣に並び立つのは楽じゃないだろうと思っていたがそれ以上の障害が立ちはだかっている事を今改めて思い知った。
「つくづく手強い子だ」
苦笑いするように溜息を吐くとガルディスは飲み直しに目についたバーに入って行くのだった。
つづく
ユフィはガルディスが用意したドレスを身に纏って待ち合わせのラブレス駅前に向かっていた。
ガルディスがWROの備品室から見繕ってきたドレスはスカート丈の短い青いドレスで悔しい事にユフィ好みの可愛いくてちょっとセクシーなドレスだった。
歩きづらくてあまり好きではないヒールも今日はドレスを着ているお陰でコツコツという石を叩く音が耳に心地良い。
(これで相手がヴィンセントだったら言う事ないのになぁ)
「そんなあからさまにガッカリした顔しないでくれよ」
駅前に着くとグレーのスーツを着たガルディスが苦笑いしてそう言った。
しかしユフィは表情を改めるどころか更にガッカリ感を剥き出しにして先程思った事を今度は口にした。
「あーあ、これがヴィンセントだったらいいのになー」
「ちくしょう、今度は声に出して言いやがって。絶対に俺で良かったって言わせてみるからな」
「じゃあ言わせてみてよ?」
「上等だ。まずはバーで軽く一杯と行こうか」
ガルディスはあのニヒルな笑みを浮かべると顎で行く道を示すとそちらを向いて歩き始め、ユフィもそれに従って隣を歩いた。
紳士的な事にガルディスはユフィに合わせて歩幅を狭くして歩いており、ユフィに疲れる事なく会話する余裕を与える。
「そこってノンアルコールカクテルある?」
「まぁあるにはあるが酒飲めないのか?」
「最近二十歳になって漸く解禁したんだよ。そんでお酒に慣れてないから慣れるまでは仲間のみんなが一緒にいる時じゃないとダメってティファと約束してるんだ」
「ティファってセブンスヘブンのティファちゃん?」
「うん」
「あ~ティファちゃんとの約束なら仕方ないか~。それにアルハラされたとか訴えられたら嫌だしな」
「やっぱティファの事知ってんの?」
「そりゃぁ勿論。エッジで有名な美人さんだからな。前に口説き落とそうとしたら怖いお兄さんに首を切り落とされそうになったけど」
「それクラウドだね。ていうかクラウドがいるのにティファを口説こうなんて命知らずもいいとこだね~」
「あんな美人さん、口説かずにはいられないだろ?」
「でもフラれてアタシに狙いを定めたと」
「いや、それとは関係なくユフィちゃんの事は元々口説くつもりだったよ。ちょっとティファちゃんに寄り道しただけで」
「アタシ浮気男は嫌いなんだけどー?」
「安心しなって。俺の恋人になってくれたらずーっとユフィちゃんだけを見るからさ」
「嘘くさー」
「なら試しに俺の恋人になってみないか?証明してみせるよ」
「その手には乗りませーん」
「ハハ、やっぱダメか。こりゃ一旦仕切り直しだな」
ネオンの光が照らす夜道を歩いている途中に目的地に到着し、ガルディスが店の扉を押し開く。
「どうぞ」と言って紳士的に扉を開けたままにしてガルディスはユフィを招き入れ、ユフィもそれに従って店の中に入ろうとしたその時―――
「ん?」
何か視線を感じてユフィはすぐさま振り返る。
が、振り向いた先には誰もおらず、ネオンの光が朧げに地面を照らしているだけだった。
「どうした?」
「んー、さっき誰かに見られてたような気がしてさ」
「今日のユフィちゃんは綺麗で目立つから誰かが注目してたのかもなぁ」
「そういうのとは違った気がするんだけど・・・まぁいいや。それよりカクテル~!」
「ノンアルコールのな」
大人っぽく着飾った外見とは裏腹に子供っぽいユフィのセリフに苦笑交じりに笑いながら付けたすとガルディスは店の扉を閉めた。
バーなだけあって店の中は暗く、青と紫を基調にした仄かな明かりが店内に静けさと落ち着きをもたらす。
あまり入った事のないバーの大人な雰囲気にユフィは内心興奮しながらも、しかし大人のレディとして振る舞わなければという理性によるストッパーの元、頑張って感情を抑えた。
そしてカウンターチェアに座ったガルディスに倣ってユフィもカウンターチェアに座る。
ガルディスはメニュー表を取るとそれをユフィに渡して尋ねる。
「俺の奢りだ。好きなのを飲んでいいぞ」
「んーと・・・じゃあこれ!」
「シンデレラだな。マスター、俺いつもの。この子にはシンデレラで」
「かしこまりました」
スキンヘッドで髭のダンディなマスターは頷くと早速シェイカーや材料を用意してカクテルを作り始めた。
手際が良く鮮やかでユフィは思わず見惚れてしまう。
ティファのカクテル作りも似たように綺麗でカッコよくてユフィは見るのが好きなのだが、それとはまた違った雰囲気のカクテル作りをマスターは披露している。
というよりも、ティファもマスターも店の雰囲気に合ったカクテルの作り方をしているだけなのかもしれない。
だから雰囲気も違っていて当然なのだろう。
そんな風に考えていると瞬く間にカクテルは出来上がり、ガルディスとユフィの前に静かに提供された。
「それじゃ、乾杯」
「乾杯」
いつもだったらバレットやシドと一緒になって豪快に音頭を取っているが今いるのは小洒落た静かなバー。
ユフィも店の雰囲気を壊さないように、また馴染もうとして静かに言葉を紡いだ。
チン、とガラスのぶつかり合う音を奏でて二人は最初の一口を飲む。
フルーツの甘い香りが鼻に抜け、舌の上を踊る感覚にユフィは笑みを溢さずにはいられなかった。
「美味しい・・・!」
「俺もユフィちゃんと一緒に飲めて美味しいよ」
「お?早速口説きモード?」
「俺は最初から口説きモードだよ。ユフィちゃんの好感度をMAXにまで上げてみせるよ」
「残念でしたー。ユフィちゃんの好感度はそう簡単には上がりませ~ん」
「でもこうやって軽快な会話が出来るんだから俺達は色々相性が良いと思うんだけどな」
「こりゃっ」
言いながらどさくさに紛れて自分の腰に回されそうになった手に気付いてユフィはぺちっと叩いてその手を払う。
「全く、油断も隙もないんだから」
「残念、バレたか」
「今ので好感度暴落したから」
「そんなに?」
「いきなりえっちぃ事するやつは嫌いだよーだ」
「悪かったよ。美味しいアイスクリーム奢ってあげるから機嫌を治してくれ」
ガルディスがチラリと目配せをするとマスターは頷き、ものの数分でオシャレなグラスに盛り付けられたアイスを提供してくれた。
提供する際に「可愛らしいお嬢さんの来客を記念して」と言葉を添えて小さな板チョコもトッピングしてもらった。
嬉しいオマケにユフィはすぐに笑顔になってアイスを食べ始める。
「サンキューマスター。マスターへの好感度がうなぎ上りだよ」
「おいおい、奢った俺の好感度はうなぎ上りにならないのかよ?」
「ま、ほんのちょっとは上げてあげてもいいけど?」
「手強いなぁ。少しくらいは多めに見てくれてもいいんじゃないか?任務に支障が出ちまう」
「今の内に厳しくしとかないと任務で調子に乗って色んな事してきそうだもん」
「流石に任務では真面目だよ、俺は」
「ホントに〜?」
「本当だよ。この間だって犯罪組織『スカルゴブリン』を壊滅させたしさ」
「へー、あれアンタがやったんだ?」
「少し骨が折れたけどね」
「うむうむ、ご苦労。アンタのその働きで街の人たちがまた笑顔になったぞ」
「上司にも同じ事言われたよ。ユフィちゃんからはもっと別の労いが欲しいな」
「んじゃあ、おつかれ」
「足りないなぁ」
「ガルディスおつかれ。頑張ったんだからゆっくり休みなよ」
「お、いいね〜。ガルディスじゃなくてガルって呼んでくれたら満点だった」
「ならもっと早く言ってくれればそう呼んだのに」
「悪い、タイミングがなかったもんでさ」
「そういえばガルって何でWROに入ろうと思ったの?言っちゃ悪いけどあんまそういう慈善活動っぽいのに興味ない感じするからさ」
「んー?」
ガルディスはカクテルを一口煽ると笑う様に短く息を吐く。
そしてその瞳は正面のキープボトルを見つめるが意味を持って見つめているようではなかった。
まるで遠い日を懐かしむような、そんな瞳にユフィには見えた。
「ユフィちゃんの言う通り・・・俺はさ、元はそういうのに興味なかったんだよ。酒飲んでギャンブルで遊んでって感じで要はちゃらんぽらんな男だった訳よ。その日が楽しけりゃそれで良いみたいな生き方をしてたんだ」
「うん」
「でもある日大変な事が起きてなぁ・・・」
「大変な事?」
「ああ、凄く大変な事だ。それに直面した俺はみっともなくもパニックになって慌てて逃げようとしたんだが転んで崩れて来た瓦礫に足を挟まれて動けなくなっちまったんだ」
「マジで?それでどうなったの?」
「俺の人生もここで終わりだと諦めかけた時に颯爽とヒーローが現れて助けてくれたんだ」
「へ~。どんなヒーロー?」
「俺よりも少し年下だけど強くて活力のある子だよ」
「子、って事は女の子?」
「そうだ。俺なんかよりもしっかりしててテキパキと周りの大人たちに指示を出して俺の事を助けてくれたんだ。その時のその子の凛々しい横顔は今でも忘れられない」
ガルディスの脳裏に4年前の騒動―――メテオ災害がフラッシュバックする。
上空にメテオの影が浮かんで周りの人間が絶望している中、自分は相変わらず酒を飲んで遊んでいた。
どうせ神羅が何とかしてくれる、2,3日寝てりゃすぐに消える、そんな風に思っていた。
けれど事態はどんどん悪化していき、メテオは消えるどころか目前まで迫ってきた。
オマケにウェポンとやらが攻めて来て神羅ビルは文字通り崩壊。
何とかしてくれると思っていた神羅もいよいよ当てにならなくなり、逃げだそうとした所で躓き、不運にも崩れて来た建物の瓦礫に足を挟まれた。
元々スラムの建物なんてのは寄せ集めの資材や廃墟を再利用して作られた家屋が殆どで、ちゃんと造られた建物なんて少ししかない。
だから大きな衝撃が起きれば簡単に崩れる建物が多く、自分はその中でもそういった建物が多く立ち並ぶ地域にいた。
自分の人生もここまでかと諦め、これまでのくだらない人生を振り返っていた時に張りのある大きな声が響いた。
『誰かこっち手伝って!動けなくなってる人がいる!!』
声の主は見るからに自分よりも年下の女の子なのにすぐに自分の元に駆け寄って大きな瓦礫をどかそうと必死に持ち上げようとしてくれていた。
大の大人である自分でさえメテオに恐れ慄いて慌てて逃げようとしていたのに、その女の子は逃げるどころか自分のような逃げ遅れた人間を探して避難誘導に当たっていたのだ。
『ユフィさん、ここは我々が対応します!』
『あちらで神羅の実験用モンスターが暴れているとの報告がありました!』
『分かった!後宜しく!』
(ユフィ・・・)
ガルディスは自分を見つけて助けようとしてくれた少女の凛々しい横顔と名前を心に深く刻み付けた。
それから救出されて安全な場所に避難し、メテオとライフストリームの衝突をやり過ごしてからは生き方を少し変えた。
酒とギャンブルはやめなかったがそれで一日を終える事はしなかった。
むしろそれを一日の終わりに持ってきて、それまでの日中の時間は鍛錬に時間を当てた。
力を付けて、武術を身に付けて、困っている人がいたら助けて。
そうした日々を過ごしている内に元神羅社員の男によるWROという世界の復興を目指す組織が設立された。
元神羅社員って点がどうにも引っ掛かって入る気になれなかったが、自分を救ってくれたあのユフィがその男と死線を潜り抜けた間柄であり、そこに在籍していると噂で聞いて入社する事を即決した。
あのユフィが信頼している男なら間違いない。
ユフィの信じたものを自分も信じる。
そしていつか横に並び立って彼女を助けたい。
あの時助けてもらったお礼をしたい。
その想いを胸に、そしてユフィという人間を目標にして今日まで生きて来た。
(漸くその願いが叶った訳だ)
チラリと隣のユフィを盗み見て浮かびそうになった笑みを隠すようにガルディスはまたカクテルを一口含む。
ユフィとは本社の廊下で四年ぶりに再会したがこちらに気付いた様子はなく、そのまま素通りされた。
しかしそれも無理もない。
救出された時、辺りは暗かったしユフィも必死だったからこちらの顔を確認している余裕はなかっただろうしそんな場合でもなかった。
だからガルディスとしては覚えてくれていなくて良かったし、むしろあんな無様な姿を覚えていてほしくなかったのである意味都合が良かった。
それからは何とかしてユフィに近付けないかとあれこれ努力し、漸く今回の潜入ミッションのペアに漕ぎ着けたのである。
ついでにお礼を兼ねた模擬デートを取り付けられたのも大きな幸運だった。
(まさか赤マントさんに夢中だったとは思わなかったけどな)
WROの女性社員の胸をときめかす美青年・ヴィンセント・ヴァレンタイン。
ユフィはその男とも死線を潜り抜けた間柄らしく、ミッションに同行したり訓練を共にしている所をよく見かける。
最初は仲間だから距離が近いのだろうと思っていたのだがユフィを見ている内に段々そうではない事を知って強力なライバルが現れたものだと思わず溜息を吐いた。
しかもユフィ自身は一途な少女でその気持ちをこちらに向けるのも一苦労しそうである。
そんなガルディスの複雑な内心など露知らずユフィが質問を投げかけてくる。
「その子に助けられた後はどうしたの?」
「一旦避難してメテオをやり過ごして、それから体を鍛えて戦い方も学ぶようになった。いつかその子に会った時にだらしないって言われて笑われないようにな」
「ふーん。会えるといいね」
「ああ、そうだな」
「それからちゃんとお礼も言うんだぞ」
「ハハ!そうだな」
きっとお礼を言えるのはまだまだ先になるだろうが、と心の中で付け足してガルディスはカクテルの残りを全て煽った。
グラスをテーブルに置いてチラリとユフィの方を見れば既にアイスは綺麗に食べられており、シンデレラもカクテルグラスの中から消えていた。
「良い感じに盛り上がって来たし次の店に行こうか。ユフィちゃん、ダーツは出来る?」
「超得意だよ」
「なら早速行こうか。負けたらコーヒー奢りね」
「じゃあアタシが勝ったらムーンバックスの期間限定トロピカルフラペチーノね」
「おいおい、俺のコーヒーより明らか高いだろ。ユフィちゃんはオレンジジュースな」
「え~?」
他愛の無い会話をしながらガルディスは会計を済ませ、ユフィと共に店を出て次の店に足を運んだ。
それからはダーツで対戦をしたりビリヤードを教えたり、ユフィのリクエストで喫茶店で休憩をした。
履き慣れないハイヒールの所為で足を痛めたらしい。
そんな状態のユフィを連れ回すのは酷だという事で喫茶店でケーキやコーヒーを楽しんだ所で本日の模擬デートはお開きとなった。
今は二人で月明かりの道をユフィの自宅を目指して歩いている。
勿論ガルディスに下心はなく、純粋なジェントルマンシップでユフィを送っているだけだった。
「や~いっぱい遊んだね~」
「そうだな」
「これで任務には臨めそう?」
「ダメって言ったら?」
「リーブのおっちゃんに別の人に交代してもらうように掛け合っておくよ」
「冗談だって。今日ので十分だ。とりあえずユフィちゃんは過剰なボディタッチはNGだな?」
「大体の女の人はNGだよ」
「でも肩を抱くくらいは我慢してもらえないか?」
「えー?やだ」
「頼むよ。今度の任務では恋人を演じるんだからさ」
「それを口実にベタベタ触ってくんなって言ってんの」
「いやいや、下心全開で言ってる訳じゃないさ。考えてもみろ、そういうアンダーグラウンドな店に入るカップルが仲良く手を繋いで入る光景をさ」
「・・・ちょっと浮いてる?」
「ちょっとどころかかなり浮いてるぞ。門前払い喰らうのがオチだ。ああいう所に入る時はそういう火遊びに慣れてそうなカップルを演じないと怪しまれる以前の問題だ」
「じゃあ肩抱くだけだよ?それ以上やったら後でぶん殴るから!」
シュシュシュ、とシャドーボクシングのように手を三回突き出してくるユフィに、そんな事はしないと笑って約束する。
本人に殴られるのも嫌だし、彼女と親しい人物たちにもこぞって殴られるのも嫌だ。
交友関係の広いユフィは色んな人と仲が良いし愛されている。
ユフィが嫌がる事や泣かせるような事をすればタダでは済まされないだろう。
それに強引に迫ってどうにかなるタイプでもないし、任務が終わっても何かしら理由を付けて接点を保つ方がまだ良策だ。
ガルディスはユフィの住んでるアパートの前まで来るとそこで別れの挨拶を交わした。
「じゃあなユフィちゃん。今日は一緒に酒が飲めて楽しかったよ」
「ノンアルコールだけどね」
「次はアルコール入りで飲んでくれるかい?」
「飲み会でならいいけど?」
「手強いなぁ。仕方ない、飲み会で向かい側の席を今から予約させてもらおうか」
「早いもん勝ちだよ。アタシは保証してやんないから」
「分かってるよ。じゃ、お休み」
「うん、お休みー。今日はありがとね」
「ああ」
部屋の中に消えて行くユフィを見届けてから自分も帰路を辿る。
今日は良い夢が見れそうだと思ったその時―――
「ん?」
鋭い視線が背中に刺さった。
驚いて振り返ったがそこには暗闇しかなく、人の姿は全くなかった。
「・・・気のせいか?」
首を傾げつつも前を向いてまた歩き始める。
そういえばデートの最中に何回か見られているような気配を感じたが、楽しい時間を過ごしたかった自分は気の所為だと思ってをそれを流した。
何か怪しいものが襲ってくるような気配もないし、それにそういう気配がする時は決まって自分とユフィの距離が近い時だった。
こうなると種類的にユフィに好意を寄せる者の嫉妬の眼差しの類だろう。
ユフィはウータイの統治者の娘だと聞いていて、その隣に並び立つのは楽じゃないだろうと思っていたがそれ以上の障害が立ちはだかっている事を今改めて思い知った。
「つくづく手強い子だ」
苦笑いするように溜息を吐くとガルディスは飲み直しに目についたバーに入って行くのだった。
つづく