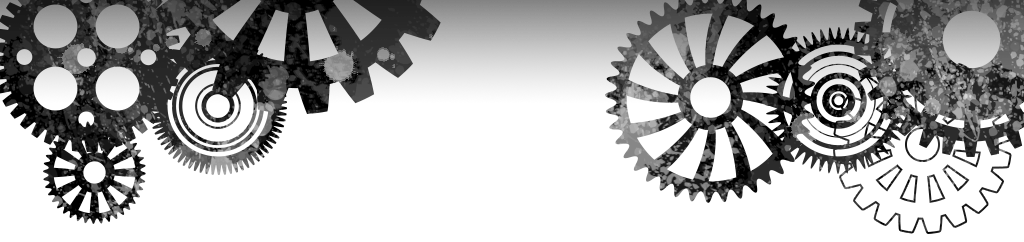君の血
暗い道を歩く。
星ひとつない暗闇は、まるで私の心のようだと感じながら重い足取りで。
いつからだろう。
女を抱いたあとに嫌悪感をいだくようになったのは。
(……っ)
かぶりをふって、脳裏に浮かんだ甘い嬌声をけそうとした。けれど泪に潤んだ琥珀色の瞳としなやかな肢体があまりに鮮明で、できなかった。自分がたった今抱いてきたのは名前も知らない女で"彼"ではないというのに。
吸血鬼という生き物は欲望に忠実だ。睡魔がくれば眠りにつき、喉が渇けば血を求め、その次は肉欲。人がもつ3大欲求に抗えない。
……あの日は、久しぶりに血を飲んだせいなのか、その反動が強くでてしまった。
,(ロイ……?あんたどうしたんだ、苦しいのか……?)
心配してくれた彼を私はーーーー。
一度だけこの手に触れた熱を、鮮明に覚えている。まるで昨日今日さっきの出来事のように。
家に帰るとリビングにエドワードの姿はなかった。自室だろうか。
最近彼は自室に籠ることが多くなった。夜も遅くまで調べ物をしているようだ。
……おおよその見当はついているが……。
邪魔はしない。調べても無駄だなんていえない。私は彼にかつての自分の姿を重ねているのかもしれない。身内が全て絶え、友を失いひとり孤独に狂い、絶望を終わらせる方法をただ探していたころの私を。
"高貴なる朱"。
長い時間をかけて私がたどりついたのは、そうよばれる血をもつ一族だった。その成熟した血は、たった一雫で吸血鬼を滅びに導くことができるという。
ただその血の稀少性からか他にも理由があったのか、一族は人間からさえも隠れ暮らしていると文献にあり私が幸運にもその里を見つけた時、里は何者かに襲撃されたあとであり、弟に折り重なるように倒れていた母親の亡骸のそばで真っ赤に染まったエドワード。
たくさんの死者のなか、生存者は彼と傷を負ったその弟だけだった。
死者の血では効果がないらしく、私はあの日彼に告げたのだった。
助かりたければその血が成熟するときに私を殺してくれ。そうすれば弟の安全と生活、それに君が私を殺すまでの君の生活も保証する。
そしてけして自分に情をうつしてはならない、心をゆるすな、と。
nextエドワード視点→