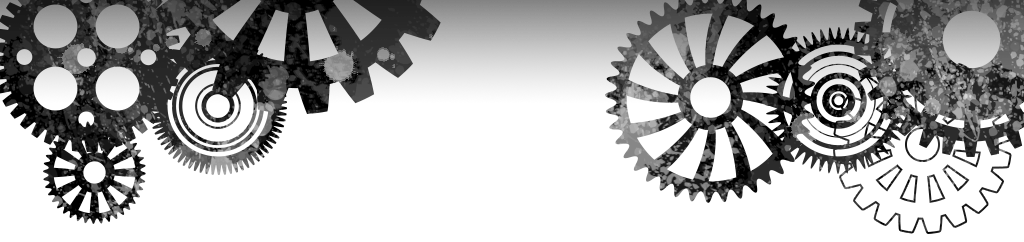君の血
心をゆるしてはならない。
いずれおとずれる別れが苦しく自分を苛んでしまうことは出会ったあの日にわかっていたはず。
なのにオレは……。
ロイがため息をはくのは言いたい言葉をのみこむときだ。嘘がつけない大人だとオレは思う。食器を片付ける手の動きをみていた。白い、大きな手を。あの手の感触を、オレは鮮明に覚えている。たった一度だけ触れられた優しい熱を。
「…?どうかしたかね?」
「べつに。」
グラスの水を一気に飲んで席を立つ。
……時間が足りない。調べても調べてもオレの欲しい答えにたどりつけない。もしかしたら答えなんてないのかもしれない。
(それでも)
なにかに縋らないと心がおかしくなりそうだった。呪いはすぐうしろまでせまってきている。ひたひたと足音をたてて。
「出かけてくるよ」
「……そう」
後片付けを終えたロイはコートを羽織ると帽子を手にとりオレに背をむけた。……いかないでほしい、なんで……のどもとをでかけた言葉をのみこむ。言ってしまったらいけない気がしたからだ。
(なんでオレじゃだめなの?)
いいかけた言葉はどろりと重たく胸をしめつける。
心をゆるしてはならないと決めていた……決められていた。だけどオレにとってのこの10年はとても鮮やかで優しい時間だった。……たとえそれがオレを利用するためのものだったとしても。
10年前、この身にながれる血のために家族を全て失ってしまったオレにはロイだけが全てだった。だけどロイにはそうじゃない。彼の瞳にとけ込んだ闇は深く昏い。彼は終わらせたいのだ。永く生きた生を。
パタン、と扉が閉まる。
ああ、また……。
吸血鬼というものは欲望に忠実な生き物らしい。渇きは血で満たし、飢えが満たされると次は……。
「……。」
たった一度だけ、触れた熱を思い出す。
→nextロイ視点