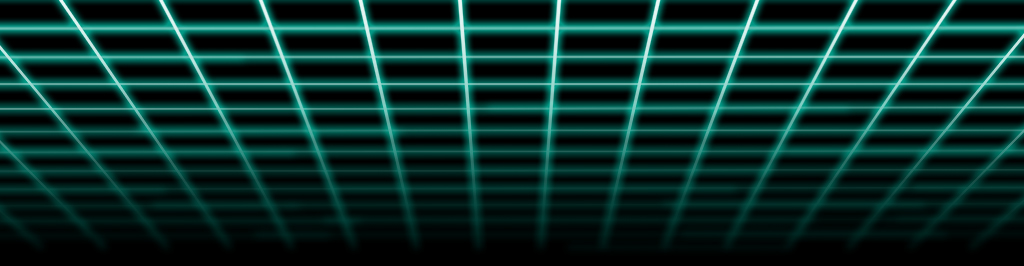Story.04≪Chapter.1-4≫
カルロスが掛けてくれた補助魔法の効果により、相手が仕掛ける前に至近距離に着いては剣を振るい、防御に転じさせる事に成功。
あまりの速さに、闘技場のチャンピオンもさすがに攻撃が出来ず苦悶の表情を浮かべている。
「くっ…!これだから相手側の風の補助魔法はキツいな…」
更にレヴィン自身が掛けた≪ヒート・ブレッシング≫により剣の威力も上乗せされ、下手に攻撃態勢を取ると逆にダメージを受けてしまうのも明白。
これは相手の傾向を読み違えたか、このままでは詠唱どころか別の行動に移す事すら難しい。
対するレヴィンは速度が速くなった事でひたすら攻め、隙が見えた所がチャンスだと思い剣に炎属性と光属性の魔力を集中させながら振るう。
「陽光刃(ヨウコウジン)!!」
太陽の如く輝いた刃はエンドルが持つ≪コールドエッジ≫を弾き飛ばし、周囲に包まれた寒気も少しずつ和らいでいく。
そして素早くレヴィンを通り抜けたのはカイザー、相手が武器を取り戻さぬ内に≪ティアマット・エンペラー≫を用いて一気に畳み掛けに入る。
「お得意の剣が弾き飛ばされたんじゃ、手も足も出ないだろ」
剣による攻撃や防御手段がなくなれば、接近戦を得意とする者にとって無防備も同然。
しかも詠唱の隙を与えなければ、魔法による反撃もままならないかと思いきや、エンドルは未だに余裕の表情を保っていた。
「僕の剣は魔術形成型武器。自分から何処まで離れていようが、この様に念じれば……っ!?」
目の前に突如現れた≪コールドエッジ≫を握ろうとした瞬間、背後から両肩に1発ずつ銃弾が撃ち込まれた。
彼の背後には笑みを浮かべながら二丁拳銃を構えたカルロスの姿があり、武器が取られる前に貫通性の高い弾丸を撃ち込む銃撃―≪ピアシング・ショット≫を放ったのだ。
これによる痛みで握れないだろうと思った時…、
「……ん?」
カイザーの目に映るのは、エンドルの両肩に傷こそ付いているが血が流れておらず、その臭いすら感じられなかった。
すると相手の身体が徐々に服装ごと白くなっていき、それがなんと雪で出来た人形である事が発覚した。
やられたと苦虫を噛み潰した様な顔をするカイザーだが、本物を探す余裕を与えないかの様に今度は白い霧が辺りを包み込み、レヴィンとカルロスの姿も見えなくなった。
「ちっ、厄介な状況作りやがって…」
この現象が発生してから水属性の魔力を感じ取り、自分達が雪の人形に気を取られている内にエンドルが発した魔法である事はすぐに分かった。
そしてカルロスがレヴィンに速度上昇の補助魔法を掛けるのを妨害しない理由は、こういうパターンを作る為に準備していたからだろうと予測出来る。
「カイザー!カルロス!大丈夫かーっ!?」
「俺は平気だけど、お前ら何処にいんだよーっ!」
すると何処からかレヴィンの声が響き渡り、また別の方向からカルロスの返答の声が聞こえた。
こちらも返事をしたいのは山々だが二人の正確な位置が把握出来ず、またエンドルの姿も見えぬまま。
この状況で下手に声を掛ければ相手に現在地を教えている様なモノであり、霧を利用して奇襲を仕掛けて来る可能性も十分にある。
まずは視界を晴らさなければと風属性の魔力を集中すると…、
「君はそこにいたんだ」
後ろからエンドルの声を耳にし、振り向いた時には既に白い結晶の刃が迫っていた。
「…!?しまった!」
魔力を集中するのもまた、相手に自分の位置を示している様なモノだと気付くのが遅かった。
水属性の魔力が宿る霧の中、『キィィン!!』と武器を弾く音が電脳空間(バーチャルスペース)内に響き渡った。
☆☆☆
レヴィン達3人対エンドルの試合をモニタールームで見ていたミシェル達2年生の生徒は、画面が白い霧に包まれて彼らと審判役のアンヘルの姿が見えない事にざわついていた。
あまりの速さに、闘技場のチャンピオンもさすがに攻撃が出来ず苦悶の表情を浮かべている。
「くっ…!これだから相手側の風の補助魔法はキツいな…」
更にレヴィン自身が掛けた≪ヒート・ブレッシング≫により剣の威力も上乗せされ、下手に攻撃態勢を取ると逆にダメージを受けてしまうのも明白。
これは相手の傾向を読み違えたか、このままでは詠唱どころか別の行動に移す事すら難しい。
対するレヴィンは速度が速くなった事でひたすら攻め、隙が見えた所がチャンスだと思い剣に炎属性と光属性の魔力を集中させながら振るう。
「陽光刃(ヨウコウジン)!!」
太陽の如く輝いた刃はエンドルが持つ≪コールドエッジ≫を弾き飛ばし、周囲に包まれた寒気も少しずつ和らいでいく。
そして素早くレヴィンを通り抜けたのはカイザー、相手が武器を取り戻さぬ内に≪ティアマット・エンペラー≫を用いて一気に畳み掛けに入る。
「お得意の剣が弾き飛ばされたんじゃ、手も足も出ないだろ」
剣による攻撃や防御手段がなくなれば、接近戦を得意とする者にとって無防備も同然。
しかも詠唱の隙を与えなければ、魔法による反撃もままならないかと思いきや、エンドルは未だに余裕の表情を保っていた。
「僕の剣は魔術形成型武器。自分から何処まで離れていようが、この様に念じれば……っ!?」
目の前に突如現れた≪コールドエッジ≫を握ろうとした瞬間、背後から両肩に1発ずつ銃弾が撃ち込まれた。
彼の背後には笑みを浮かべながら二丁拳銃を構えたカルロスの姿があり、武器が取られる前に貫通性の高い弾丸を撃ち込む銃撃―≪ピアシング・ショット≫を放ったのだ。
これによる痛みで握れないだろうと思った時…、
「……ん?」
カイザーの目に映るのは、エンドルの両肩に傷こそ付いているが血が流れておらず、その臭いすら感じられなかった。
すると相手の身体が徐々に服装ごと白くなっていき、それがなんと雪で出来た人形である事が発覚した。
やられたと苦虫を噛み潰した様な顔をするカイザーだが、本物を探す余裕を与えないかの様に今度は白い霧が辺りを包み込み、レヴィンとカルロスの姿も見えなくなった。
「ちっ、厄介な状況作りやがって…」
この現象が発生してから水属性の魔力を感じ取り、自分達が雪の人形に気を取られている内にエンドルが発した魔法である事はすぐに分かった。
そしてカルロスがレヴィンに速度上昇の補助魔法を掛けるのを妨害しない理由は、こういうパターンを作る為に準備していたからだろうと予測出来る。
「カイザー!カルロス!大丈夫かーっ!?」
「俺は平気だけど、お前ら何処にいんだよーっ!」
すると何処からかレヴィンの声が響き渡り、また別の方向からカルロスの返答の声が聞こえた。
こちらも返事をしたいのは山々だが二人の正確な位置が把握出来ず、またエンドルの姿も見えぬまま。
この状況で下手に声を掛ければ相手に現在地を教えている様なモノであり、霧を利用して奇襲を仕掛けて来る可能性も十分にある。
まずは視界を晴らさなければと風属性の魔力を集中すると…、
「君はそこにいたんだ」
後ろからエンドルの声を耳にし、振り向いた時には既に白い結晶の刃が迫っていた。
「…!?しまった!」
魔力を集中するのもまた、相手に自分の位置を示している様なモノだと気付くのが遅かった。
水属性の魔力が宿る霧の中、『キィィン!!』と武器を弾く音が電脳空間(バーチャルスペース)内に響き渡った。
☆☆☆
レヴィン達3人対エンドルの試合をモニタールームで見ていたミシェル達2年生の生徒は、画面が白い霧に包まれて彼らと審判役のアンヘルの姿が見えない事にざわついていた。