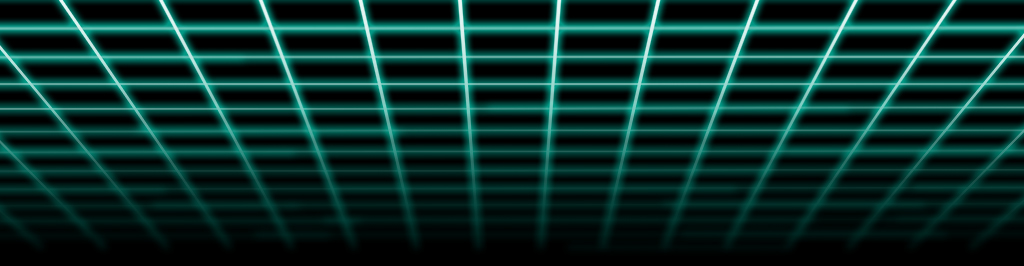Story.04≪Chapter.1-4≫
「けど今のでバテるとは思ってねぇぜ?じゃないと面目丸潰れになっちまう。そうだろ?」
むしろ闘技場のチャンピオンとの戦いに心の底から楽しんでいる様で、視線はエンドルに送っていた。
既に立ち上がっている彼の姿に、レヴィンは気を引き締めて≪シャインエッジ≫を握り直す。
「ああ。僕も王者としての意地っていうのがあってね。アンヘル先生から、君達2年生の中に僕が驚く程の実力者がいるって聞かされたんだ。でもそれは、君じゃない」
カルロスに向けられたエンドルの言葉に、レヴィンは一度カルロスに目を向けるが、彼は至って涼しい顔をしている。
「言ってくれるじゃねぇか。確かに俺は成績優秀者って言われる程じゃねぇし、色んな意味で先生に怒られてばっかりだよ」
多少私情は挟みつつ自らの実力を理解しており、それを踏まえてこう言い放った。
「けどこの手合わせを、俺が尊敬してる奴が見てるんでね。弱いながらも恥をかく戦いなんざしたくねぇ。だから、本気でかかって来いよ。あんたがびっくりする程の実力者の前でよ!」
その瞬間エンドルは目を大きく見開き、一瞬ではあるがプレッシャーを感じた。
この手合わせは電脳空間(バーチャルスペース)で行われているが、他の2年生の生徒達はそれを映すモニタールームで観戦している。
今目の前にいる3人と審判役のアンヘルはもちろん、向こう側にいる人達も当然武道大会の王者である自分を注目しているだろう。
事前の戦いを見て気になっていたレヴィンとカイザー、その後ろにいるカルロスを相手に、期待外れと言われるワケにはいかない。
「……その心意気に敬意を表して、僕も闘技場のチャンピオンとしての実力を見せてあげよう」
この一言を発した瞬間、電脳空間(バーチャルスペース)内の空気が冷たく感じた。
「一気に寒くなってきたな…」
「これがエンドルさんの氷の魔力…。カイザー、カルロス、気を付けろ!」
おそらくエンドルが今までよりも強い氷属性の技や魔法を放つだろうと思い、レヴィンはその属性に弱い風属性を持つカイザーとカルロスに注意を呼び掛けた。
二人もそれを理解して頷き、カイザーは相手の出方を窺い、カルロスは鋭く貫通性の高い弾丸を取り出しては≪アサルトコンバット・ウィンド≫に装填する。
するとふと思い出したかの様な顔をしながら、レヴィンとカイザーに視線を送る。
「レヴィン、カイザー、補助いるか?」
「あ、じゃあ頼むよ。この状況、俺ならどうにか切り開けそうだから、掛けてくれると助かる」
「俺はいらねぇ」
ここからはスピード勝負に持ち込んだ方が良さそうだと判断し、レヴィンに風の力を宿らせる事で動きが速くなる補助魔法―≪クイック・スピード≫を掛けた。
拒否したカイザーは≪ティアマット・エンペラー≫のメタリックグリーンの刃を先端にしている様だが、あれは風属性の技を放つ為に利用する筈。
それには何か彼なりの策があるだろうと信じ、レヴィンは真剣な目付きでエンドルを見る。
「そちらの準備は出来たかい?」
「補助の邪魔をしないとは、随分と余裕たっぷりじゃねぇか。こっちは氷に弱い風属性持ちが二人もいるからってか?」
「それだけの理由で確実に勝てるとは思っていないよ。どんな戦いでも何が起こるのかは分からない。それがたとえ、今回の手合わせでもね」
自分や仲間の強化による補助魔法は、敵に使われたら不利に傾く事が多い。
カイザーはそれを知っての挑発をしたが、エンドルは経験があるかの様に動じる気配を見せない。
武道大会で優勝に至るまで、数々の道のりを乗り越えて来たと感じさせる風格だろう。
相手の精神(メンタル)を崩す手段は通用しないと見て、改めて戦闘態勢を取る。
「……確かに、何が起こるのか分かんねぇよな」
「だから僕は手を抜くような真似はしない。君達も全力でかかって来なければ、死ぬと思った方が良いよ」
「わざわざ忠告どうも」
「じゃあ、行きますよ!」
そうして冷たい空気が溢れる電脳空間(バーチャルスペース)の中、レヴィンは駆け走る。
むしろ闘技場のチャンピオンとの戦いに心の底から楽しんでいる様で、視線はエンドルに送っていた。
既に立ち上がっている彼の姿に、レヴィンは気を引き締めて≪シャインエッジ≫を握り直す。
「ああ。僕も王者としての意地っていうのがあってね。アンヘル先生から、君達2年生の中に僕が驚く程の実力者がいるって聞かされたんだ。でもそれは、君じゃない」
カルロスに向けられたエンドルの言葉に、レヴィンは一度カルロスに目を向けるが、彼は至って涼しい顔をしている。
「言ってくれるじゃねぇか。確かに俺は成績優秀者って言われる程じゃねぇし、色んな意味で先生に怒られてばっかりだよ」
多少私情は挟みつつ自らの実力を理解しており、それを踏まえてこう言い放った。
「けどこの手合わせを、俺が尊敬してる奴が見てるんでね。弱いながらも恥をかく戦いなんざしたくねぇ。だから、本気でかかって来いよ。あんたがびっくりする程の実力者の前でよ!」
その瞬間エンドルは目を大きく見開き、一瞬ではあるがプレッシャーを感じた。
この手合わせは電脳空間(バーチャルスペース)で行われているが、他の2年生の生徒達はそれを映すモニタールームで観戦している。
今目の前にいる3人と審判役のアンヘルはもちろん、向こう側にいる人達も当然武道大会の王者である自分を注目しているだろう。
事前の戦いを見て気になっていたレヴィンとカイザー、その後ろにいるカルロスを相手に、期待外れと言われるワケにはいかない。
「……その心意気に敬意を表して、僕も闘技場のチャンピオンとしての実力を見せてあげよう」
この一言を発した瞬間、電脳空間(バーチャルスペース)内の空気が冷たく感じた。
「一気に寒くなってきたな…」
「これがエンドルさんの氷の魔力…。カイザー、カルロス、気を付けろ!」
おそらくエンドルが今までよりも強い氷属性の技や魔法を放つだろうと思い、レヴィンはその属性に弱い風属性を持つカイザーとカルロスに注意を呼び掛けた。
二人もそれを理解して頷き、カイザーは相手の出方を窺い、カルロスは鋭く貫通性の高い弾丸を取り出しては≪アサルトコンバット・ウィンド≫に装填する。
するとふと思い出したかの様な顔をしながら、レヴィンとカイザーに視線を送る。
「レヴィン、カイザー、補助いるか?」
「あ、じゃあ頼むよ。この状況、俺ならどうにか切り開けそうだから、掛けてくれると助かる」
「俺はいらねぇ」
ここからはスピード勝負に持ち込んだ方が良さそうだと判断し、レヴィンに風の力を宿らせる事で動きが速くなる補助魔法―≪クイック・スピード≫を掛けた。
拒否したカイザーは≪ティアマット・エンペラー≫のメタリックグリーンの刃を先端にしている様だが、あれは風属性の技を放つ為に利用する筈。
それには何か彼なりの策があるだろうと信じ、レヴィンは真剣な目付きでエンドルを見る。
「そちらの準備は出来たかい?」
「補助の邪魔をしないとは、随分と余裕たっぷりじゃねぇか。こっちは氷に弱い風属性持ちが二人もいるからってか?」
「それだけの理由で確実に勝てるとは思っていないよ。どんな戦いでも何が起こるのかは分からない。それがたとえ、今回の手合わせでもね」
自分や仲間の強化による補助魔法は、敵に使われたら不利に傾く事が多い。
カイザーはそれを知っての挑発をしたが、エンドルは経験があるかの様に動じる気配を見せない。
武道大会で優勝に至るまで、数々の道のりを乗り越えて来たと感じさせる風格だろう。
相手の精神(メンタル)を崩す手段は通用しないと見て、改めて戦闘態勢を取る。
「……確かに、何が起こるのか分かんねぇよな」
「だから僕は手を抜くような真似はしない。君達も全力でかかって来なければ、死ぬと思った方が良いよ」
「わざわざ忠告どうも」
「じゃあ、行きますよ!」
そうして冷たい空気が溢れる電脳空間(バーチャルスペース)の中、レヴィンは駆け走る。