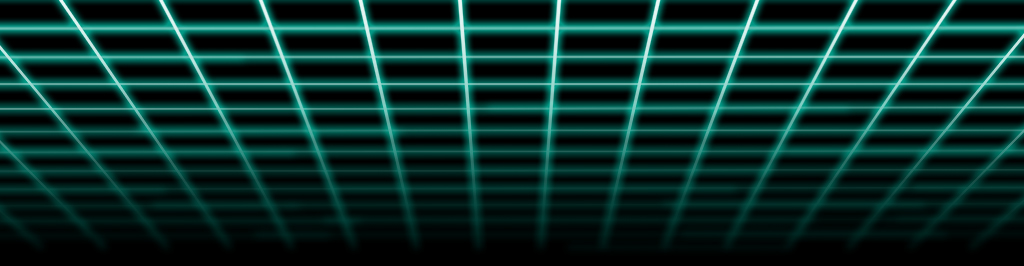Story.02≪Chapter.1-2≫
カルロスは自慢げにワイヤレスイヤホン型の通信機器でユリアン達に連絡を取ろうとするが、ノイズの音が響いた様で舌打ちをしていた。
ミシェルは何故この屋上に巨大な機械が配置されていたのか、そして腹部にあった赤紫の結晶は何なのかを調べるべく、黒い機械を可能な範囲での解体を始める。
…解体と云っても地道にドライバーを駆使するのではなく、彼女が持つ刀で覆い被さった金属を斬り込みながら取り出すの方法であるが。
「派手なやり方だな、オイ」
「2階があんな状態じゃ、チンタラしてらんねぇからな。気になったモンだけ取り出して、後は機械に詳しいヤツにじっくり解析して貰う方向で行くさ」
そんなやり方をカルロスが二丁拳銃をホルダーに仕舞いながら見つめる中、ミシェルは多く繋がれたケーブルの中から赤紫の結晶が見えた。
黒い機械はもう動かないが、それだけは今でもほのかに光っており、動力とは別に何らかの役割を持っていると見て切り離そうとすると、赤い光の様な結界に阻まれて刃が通らない。
「何だよコレ…」
「どうした?ミシェル」
「こいつの腹部にあった結晶を取り出そうとしたんだけどよ、結界が邪魔して上手く取れねぇんだ。ちょっと時間取らせてくれ」
ケーブルの方は阻害するモノがない為、結界に当たらぬよう繋がった所だけ切断し、興味本位で覗きに来たバーンの手伝いもあって弾かれない範囲で取り出せそうな所まで解体出来た。
そして結晶に繋がれている中で最も長いケーブルを二人で協力して引っ張り上げると、赤い結界に覆われながらも外に取り出す事に成功した。
「なんか超属性の魔力を感じるな。属性石か?」
属性石とは魔法や魔力を伴った攻撃などを繰り出す為に欠かせない存在であり、纏う属性の魔力は色ごとに異なる。
赤紫からして超能力や重力などに関わる超属性の石だと思われるが、色が違う結界に覆われるというのは聞いた事がない。
「それに似た、何かの品だろう。しかし結界がある以上、ここからどう調べれば良いのやら…」
形からして超属性の魔力を用いた品物であると見たエクセリオンだが、今の状態では調査が出来ずに困り果てている。
「だったら、次は私の番かな」
すると後ろから4人にとって聞き覚えのある男性の声がし、振り向くと前髪をオールバックにし、腰まで伸ばした黒髪を一つくくりにした金色の瞳を持つ男性がいた。
鼠色の袴に黒い着物の上に白い羽織り、白い足袋と黄土色の草履は和の雰囲気を感じさせ、優しそうな表情は周囲を安心させる。
「あ、師匠」
男性を師匠と呼ぶミシェルは普通に応対し、エクセリオンは少し緊張感を持ちながら先程の一言について問い掛ける。
「セロン殿、“私の出番”というのは…?」
「封殺術の出番ってか?」
「ご名答」
それに答えたのはミシェルであり、男性―セロンもその確認に頷きながら結界を纏う赤紫の結晶に歩み寄る。
何でお前が答えるんだ、そう思わせる様に彼女を不服そうに見るエクセリオンなのだが、これは師弟関係にあるからこそのやり取りである。
セロンは“第六代剣帝”という異名を持ち、それに相応しく卓越した剣術で他者を寄せ付けず、過去に“剣魔”と呼ばれる悪しき存在を封印させた経歴を持つ。
それに加え学院内では剣道の顧問として、ただ一人の教え子であるミシェルを指導した事で有名な人物でもあるのだ。
更に『封殺術』と呼ばれる、あらゆる生命に宿る能力や現象に溢れる魔力、そして生命の活動を封じる力を操る特殊な魔法を、剣術と混ぜて行使する事もある。
今回はそれを利用して、赤紫の結晶に纏った結界を消そうとしている様だ。
「そんなんで結界消えんのか?」
しかし彼自身、封殺術は余程の事がない限り使わない傾向にあり、実際に行使する姿を見た事がないカルロスに不安な視線を送られている。
「……この程度なら心配はない。すぐに終わるさ」
だが結晶を見ただけで結界の仕組みが分かったのか、セロンは穏やかな表情の裏に何処か自信に満ち溢れている様に見えた。
ミシェルは何故この屋上に巨大な機械が配置されていたのか、そして腹部にあった赤紫の結晶は何なのかを調べるべく、黒い機械を可能な範囲での解体を始める。
…解体と云っても地道にドライバーを駆使するのではなく、彼女が持つ刀で覆い被さった金属を斬り込みながら取り出すの方法であるが。
「派手なやり方だな、オイ」
「2階があんな状態じゃ、チンタラしてらんねぇからな。気になったモンだけ取り出して、後は機械に詳しいヤツにじっくり解析して貰う方向で行くさ」
そんなやり方をカルロスが二丁拳銃をホルダーに仕舞いながら見つめる中、ミシェルは多く繋がれたケーブルの中から赤紫の結晶が見えた。
黒い機械はもう動かないが、それだけは今でもほのかに光っており、動力とは別に何らかの役割を持っていると見て切り離そうとすると、赤い光の様な結界に阻まれて刃が通らない。
「何だよコレ…」
「どうした?ミシェル」
「こいつの腹部にあった結晶を取り出そうとしたんだけどよ、結界が邪魔して上手く取れねぇんだ。ちょっと時間取らせてくれ」
ケーブルの方は阻害するモノがない為、結界に当たらぬよう繋がった所だけ切断し、興味本位で覗きに来たバーンの手伝いもあって弾かれない範囲で取り出せそうな所まで解体出来た。
そして結晶に繋がれている中で最も長いケーブルを二人で協力して引っ張り上げると、赤い結界に覆われながらも外に取り出す事に成功した。
「なんか超属性の魔力を感じるな。属性石か?」
属性石とは魔法や魔力を伴った攻撃などを繰り出す為に欠かせない存在であり、纏う属性の魔力は色ごとに異なる。
赤紫からして超能力や重力などに関わる超属性の石だと思われるが、色が違う結界に覆われるというのは聞いた事がない。
「それに似た、何かの品だろう。しかし結界がある以上、ここからどう調べれば良いのやら…」
形からして超属性の魔力を用いた品物であると見たエクセリオンだが、今の状態では調査が出来ずに困り果てている。
「だったら、次は私の番かな」
すると後ろから4人にとって聞き覚えのある男性の声がし、振り向くと前髪をオールバックにし、腰まで伸ばした黒髪を一つくくりにした金色の瞳を持つ男性がいた。
鼠色の袴に黒い着物の上に白い羽織り、白い足袋と黄土色の草履は和の雰囲気を感じさせ、優しそうな表情は周囲を安心させる。
「あ、師匠」
男性を師匠と呼ぶミシェルは普通に応対し、エクセリオンは少し緊張感を持ちながら先程の一言について問い掛ける。
「セロン殿、“私の出番”というのは…?」
「封殺術の出番ってか?」
「ご名答」
それに答えたのはミシェルであり、男性―セロンもその確認に頷きながら結界を纏う赤紫の結晶に歩み寄る。
何でお前が答えるんだ、そう思わせる様に彼女を不服そうに見るエクセリオンなのだが、これは師弟関係にあるからこそのやり取りである。
セロンは“第六代剣帝”という異名を持ち、それに相応しく卓越した剣術で他者を寄せ付けず、過去に“剣魔”と呼ばれる悪しき存在を封印させた経歴を持つ。
それに加え学院内では剣道の顧問として、ただ一人の教え子であるミシェルを指導した事で有名な人物でもあるのだ。
更に『封殺術』と呼ばれる、あらゆる生命に宿る能力や現象に溢れる魔力、そして生命の活動を封じる力を操る特殊な魔法を、剣術と混ぜて行使する事もある。
今回はそれを利用して、赤紫の結晶に纏った結界を消そうとしている様だ。
「そんなんで結界消えんのか?」
しかし彼自身、封殺術は余程の事がない限り使わない傾向にあり、実際に行使する姿を見た事がないカルロスに不安な視線を送られている。
「……この程度なら心配はない。すぐに終わるさ」
だが結晶を見ただけで結界の仕組みが分かったのか、セロンは穏やかな表情の裏に何処か自信に満ち溢れている様に見えた。