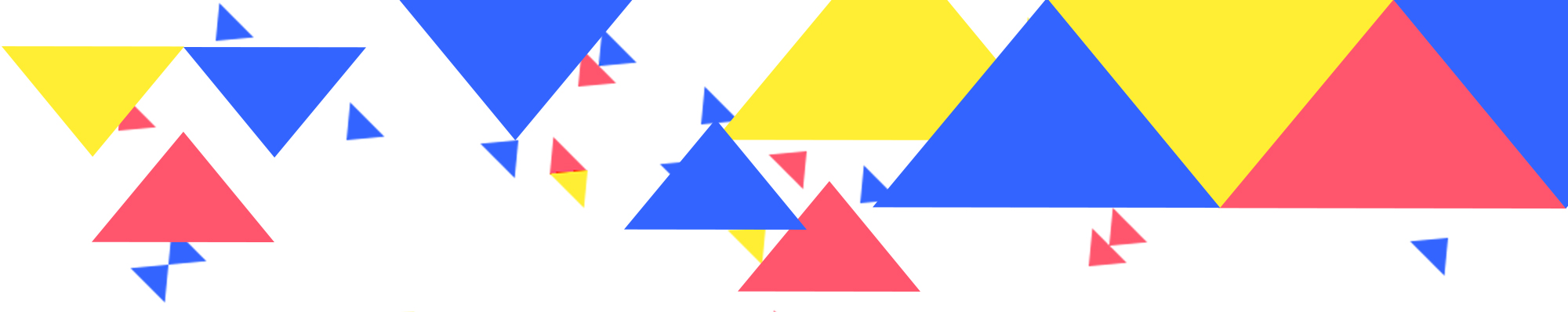ビューティフル・デイ
賑やかなランチタイムを過ごしたあと、セラに手を引かれて入ったのはランジェリーショップだった。
あまりにも自分とは縁のない世界で入るのをとてつもなく拒んだが、セラの何も言わせないという意思の強い目を向けられ怯んでしまった。その隙にぐっとつよく引かれて未知の世界に入ってしまったのだ。
「わぁー可愛い!お姉ちゃんみてみて!このレースのやつ。すごい可愛い」
「セラには似合うだろうが私は無理だ」
「無理じゃないの。お姉ちゃんなんでも似合うんだから…あ、そうだこの際だからちゃんと店員さんに測ってもらおうよ」
「な!?いい、いい!!嫌だ。他人に触られるのは好かない…」
「でもまたお姉ちゃん合わないやつ着るでしょう?」
「それはまぁ、そうだが…」
やはり、軍人歴が長いからか他人に触られたり、とくに後ろを取られるのがどうにも悪寒がする為セラに懇願して店員に同行してもらうのはなんとかやめにすることに成功した。
その代わり、セラが自分の下着を選ぶことに口を出さない、という条件が課されたのだが。
「うーん、お姉ちゃんはどれがいいかなぁ」
「あまりレースとかはやめてくれ。なるべく無地で装飾のないものがいい」
「だったらここに来る意味ないでしょう。普段は普段として、特別な時に着るのも必要だよお姉ちゃん」
「特別な時ってなんだ…」
「たとえば、こうやって2人で買い物する時…とか?」
「…まぁ、確かに特別だな」
「でしょ?こういう時は普段とは切り替えた方がいいんだよ!」
「そういうものなのか」
ふぅん、となんだか一理ある気がして納得する。
公私混同は良くない、それと同じことなのだろうと結論づけた。
「とりあえず、普段のと可愛いの、2種類は絶対買おうね」
「もうお前に任せる」
「ほんと?撤回しないでね!」
そういうとセラはいたずらっ子のような笑みを浮かべて店内を私の手を握りながら十分に巡回し、あーでもないこーでもない、と十面相を繰り広げた。
そんなセラの様子を眺めて、そういえばこうやっていろんなセラの表情を見るのは随分と久しいな、と感じた。
自分が軍に入ったきり、生活周期のズレや長期任務で家を開けたりなどが多くなったために必然的にセラと過ごす時間も少なくなっている。本当はこうしてセラとの時間を多く持った方がいいのだろうけど、それを生活が許さなかった。だからこそ、こうやって一日中セラと過ごす時間はとても――素晴らしいことなんだ、と改めて認識する。
そんなことを考えていると、どうやら納得したものを見つけたようでセラは知らぬ間に会計の所にいた。
慌てて駆けつけてセラが払う前になんとか無理やり自分の電子パスカードを差し出して、セラのリストにそれらを転送する。
セラは「お姉ちゃんにプレゼントしたかったのに!」と拗ねていたが、その資金は今度の誕生日にでも回してくれといって丸く収めた。
////////
買い物に満足し、帰路についた辺りで既に夕方になっていた。半日もモールで過ごしていたらしい。なかなか充実した時間だったな、とライトニングは思った。
「ところでセラ、結局…その、どんなのを買ったんだ?」
エアバイクにのって、ライトニングに抱きつくセラに肩越しに尋ねる。
「あれ?リスト転送する時に見なかった?」
「ああ、みてなかったんだ。だから…気になって」
「んーとね、普通に普段使うお姉ちゃんご所望の黒の動きやすい下着を3着、それとワインレッドのレースが可愛いやつでしょ、それと白のこれもレースが可愛いやつ」
「な、あ、…普通のはありがたいが、そういう、特殊なやつは2着もいらないだろう…!?」
「ちょ、お姉ちゃんちゃんと運転して!よろよろだよ!」
「…!すまない」
あまりにもセラの発言に動揺を隠しきれず、ついにはセラに運転を注意されてしまう始末。
それにしても、口を出さないとは言ったがそんないつ着るかもわからない恥ずかしい下着を2着も…!
「お姉ちゃん、着ないものをって思ったでしょ?」
「は!!いや、思ってないが!?」
「お姉ちゃんの考え、手に取るようにわかるよ。…あのね、言っときますけどあれでも普通に今どきの女の子は付けてるからね?」
「そ、そうなのか…!?」
「お姉ちゃん女の同僚の人いないの?見せてもらいなよ…」
「それはダメだろう」
「ダメなの?わからないなぁ…」
そういってセラは呆れながらクスクスと笑う。私もなぜだか釣られて口元が緩んだ。
「楽しかったなぁ。お姉ちゃん、付き合ってくれてありがとう」
「いいんだ。元々私がセラとこういう時間を取れないのが悪い」
「そんなことないよ。私、お姉ちゃんにいつも感謝してる。言葉じゃ全然足りないけどね…ありがとう、お姉ちゃん」
「……、なら、エデンにいってもしっかりしてくれ」
「もちろん!お姉ちゃんに負けないように頑張る!」
そういってセラは、自身に回す力を強めた。
背中に顔をうずめ私の体温を感じているようだった。
ふと、こうしてセラに背中を預けることも、別の誰かにいずれは委ねらばならないということに行き着いた。
自分もいつまでもセラを庇護する姉として一緒にいれる訳では無い。姉として出来ることもあるが、姉だからこそ出来ないことも沢山ある。もし、セラを預けれる人が現れたのなら、自分が埋めることが出来なかったセラの穴を満たしてやってほしいと願った。
私がセラと過ごしたりなかった分、セラのことをうんと甘やかして寂しい思いをさせないで欲しい、それが出来ないなら認めてやるものか。
エアバイクに乗る2人をファルシ=フェニックスの暖かなオレンジ色が包んでいた。
ライトニングとセラを裂き、世界に追われるまであと少し。
////////END
あまりにも自分とは縁のない世界で入るのをとてつもなく拒んだが、セラの何も言わせないという意思の強い目を向けられ怯んでしまった。その隙にぐっとつよく引かれて未知の世界に入ってしまったのだ。
「わぁー可愛い!お姉ちゃんみてみて!このレースのやつ。すごい可愛い」
「セラには似合うだろうが私は無理だ」
「無理じゃないの。お姉ちゃんなんでも似合うんだから…あ、そうだこの際だからちゃんと店員さんに測ってもらおうよ」
「な!?いい、いい!!嫌だ。他人に触られるのは好かない…」
「でもまたお姉ちゃん合わないやつ着るでしょう?」
「それはまぁ、そうだが…」
やはり、軍人歴が長いからか他人に触られたり、とくに後ろを取られるのがどうにも悪寒がする為セラに懇願して店員に同行してもらうのはなんとかやめにすることに成功した。
その代わり、セラが自分の下着を選ぶことに口を出さない、という条件が課されたのだが。
「うーん、お姉ちゃんはどれがいいかなぁ」
「あまりレースとかはやめてくれ。なるべく無地で装飾のないものがいい」
「だったらここに来る意味ないでしょう。普段は普段として、特別な時に着るのも必要だよお姉ちゃん」
「特別な時ってなんだ…」
「たとえば、こうやって2人で買い物する時…とか?」
「…まぁ、確かに特別だな」
「でしょ?こういう時は普段とは切り替えた方がいいんだよ!」
「そういうものなのか」
ふぅん、となんだか一理ある気がして納得する。
公私混同は良くない、それと同じことなのだろうと結論づけた。
「とりあえず、普段のと可愛いの、2種類は絶対買おうね」
「もうお前に任せる」
「ほんと?撤回しないでね!」
そういうとセラはいたずらっ子のような笑みを浮かべて店内を私の手を握りながら十分に巡回し、あーでもないこーでもない、と十面相を繰り広げた。
そんなセラの様子を眺めて、そういえばこうやっていろんなセラの表情を見るのは随分と久しいな、と感じた。
自分が軍に入ったきり、生活周期のズレや長期任務で家を開けたりなどが多くなったために必然的にセラと過ごす時間も少なくなっている。本当はこうしてセラとの時間を多く持った方がいいのだろうけど、それを生活が許さなかった。だからこそ、こうやって一日中セラと過ごす時間はとても――素晴らしいことなんだ、と改めて認識する。
そんなことを考えていると、どうやら納得したものを見つけたようでセラは知らぬ間に会計の所にいた。
慌てて駆けつけてセラが払う前になんとか無理やり自分の電子パスカードを差し出して、セラのリストにそれらを転送する。
セラは「お姉ちゃんにプレゼントしたかったのに!」と拗ねていたが、その資金は今度の誕生日にでも回してくれといって丸く収めた。
////////
買い物に満足し、帰路についた辺りで既に夕方になっていた。半日もモールで過ごしていたらしい。なかなか充実した時間だったな、とライトニングは思った。
「ところでセラ、結局…その、どんなのを買ったんだ?」
エアバイクにのって、ライトニングに抱きつくセラに肩越しに尋ねる。
「あれ?リスト転送する時に見なかった?」
「ああ、みてなかったんだ。だから…気になって」
「んーとね、普通に普段使うお姉ちゃんご所望の黒の動きやすい下着を3着、それとワインレッドのレースが可愛いやつでしょ、それと白のこれもレースが可愛いやつ」
「な、あ、…普通のはありがたいが、そういう、特殊なやつは2着もいらないだろう…!?」
「ちょ、お姉ちゃんちゃんと運転して!よろよろだよ!」
「…!すまない」
あまりにもセラの発言に動揺を隠しきれず、ついにはセラに運転を注意されてしまう始末。
それにしても、口を出さないとは言ったがそんないつ着るかもわからない恥ずかしい下着を2着も…!
「お姉ちゃん、着ないものをって思ったでしょ?」
「は!!いや、思ってないが!?」
「お姉ちゃんの考え、手に取るようにわかるよ。…あのね、言っときますけどあれでも普通に今どきの女の子は付けてるからね?」
「そ、そうなのか…!?」
「お姉ちゃん女の同僚の人いないの?見せてもらいなよ…」
「それはダメだろう」
「ダメなの?わからないなぁ…」
そういってセラは呆れながらクスクスと笑う。私もなぜだか釣られて口元が緩んだ。
「楽しかったなぁ。お姉ちゃん、付き合ってくれてありがとう」
「いいんだ。元々私がセラとこういう時間を取れないのが悪い」
「そんなことないよ。私、お姉ちゃんにいつも感謝してる。言葉じゃ全然足りないけどね…ありがとう、お姉ちゃん」
「……、なら、エデンにいってもしっかりしてくれ」
「もちろん!お姉ちゃんに負けないように頑張る!」
そういってセラは、自身に回す力を強めた。
背中に顔をうずめ私の体温を感じているようだった。
ふと、こうしてセラに背中を預けることも、別の誰かにいずれは委ねらばならないということに行き着いた。
自分もいつまでもセラを庇護する姉として一緒にいれる訳では無い。姉として出来ることもあるが、姉だからこそ出来ないことも沢山ある。もし、セラを預けれる人が現れたのなら、自分が埋めることが出来なかったセラの穴を満たしてやってほしいと願った。
私がセラと過ごしたりなかった分、セラのことをうんと甘やかして寂しい思いをさせないで欲しい、それが出来ないなら認めてやるものか。
エアバイクに乗る2人をファルシ=フェニックスの暖かなオレンジ色が包んでいた。
ライトニングとセラを裂き、世界に追われるまであと少し。
////////END
3/3ページ