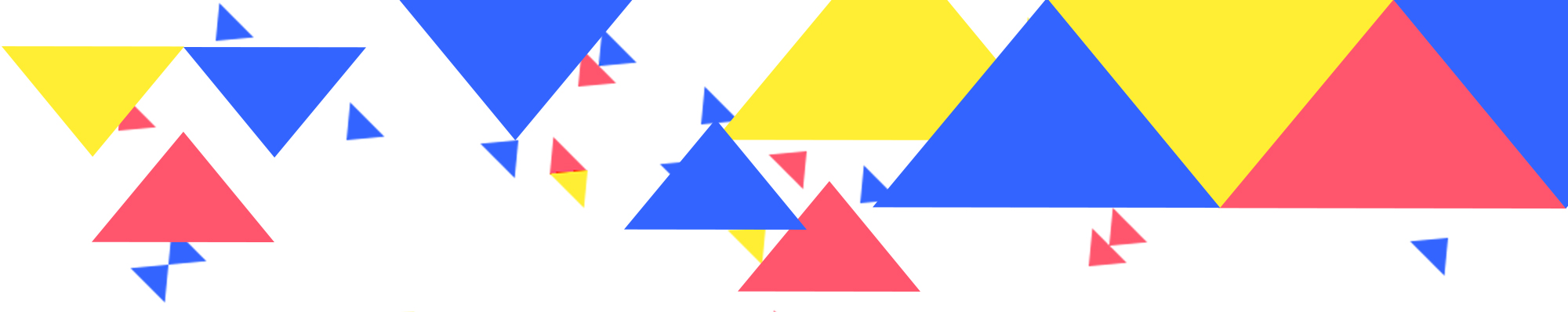ビューティフル・デイ
朝の心地良い喧騒が遠くから聞こえた時、ライトニングはゆっくりと長いまつ毛に縁取られた目を開けた。
窓から漏れ、部屋に差し込む日光が早朝であることを告げている。
のろのろと掛け布団を押しながら上体を起こし、数分、覚醒しない意識の中微睡んでいると扉の向こうから朝食を知らせる聞きなれた声が響いた。
その声に引き付けられるように意識がハッキリと鮮明になっていく。
あぁ、そうだ。今日はセラと一緒に出かけるんだった――と、思い出したライトニングはベッドから抜け出した。
ビューティフル・デイ////////2018.8.
「おはようお姉ちゃん。はい、コーヒー」
「ありがとうセラ」
「ねぇお姉ちゃん、またそんなカッコで寝てるの?」
もう、と1つため息を漏らしながらセラが指さすところにあるのはだらしなく着た緩めのコンビネゾンのルームウェアだ。
トップスがスバゲッティ・ストラップになっていて背中がざっくり空いている。そのために横から見ると際どい胸のラインを覗かせた。
自分の性格的に過労な軍任務を終え、帰宅してからセラのように顔のコンディションを整えたり、可愛いルームウェアに着替えたり、などなど――そういった所詮自分のお世話ということにめんどくささを覚えてしまうので、本当に最低限の身支度しかしない。
現にルームウェアを着る時も風呂から上がってそのまま着ているので下着は下のしか付けていなかった。セラが言いたいのはそういう所だろう。
「私がいない時に急な来客があったらどうするの?」
「大体そういう時は私の休日だろう?昼まで寝てるし、というか今までそういったことに遭遇してないから大丈夫だ」
言い終えたあとにコーヒーを口に入れる。
おいしい。いつも飲んでるものなのに何故か殊更に美味しいと感じるのはきっとセラがいるからなのだろうな、とぼんやり考えた。
それを他所に小さい子供のようにプリプリと怒りながらセラは続ける。
「もぅお姉ちゃんたら…。私が彼氏だったら彼女がこんなカッコしてるのやきもきしちゃうよ!」
「生憎彼氏に該当する人間はいない。」
「そういうことじゃなくて…まぁ、うん、はい。…でもブラジャー付けてないのはダメだよお姉ちゃん。形崩れちゃうし…。大きいんだから尚更だよ」
「…ダメか?」
「ダメだよ!…あ、そういえば前に一緒に下着買ったじゃない!お姉ちゃんアレはどうしたの?」
「なんだか気づいたら小さくなっていた。だから今だって着てないんだ」
「えっ?!またサイズ変わったの?じゃあ今日お姉ちゃんの分の買い物もしよう!せっかくエデンに行くんだし」
そう、今日はセラがエデンに一人暮らしをするための引越し準備として買い物にいくのだった。
エデンにあるラムウ・モールはコクーン内のショッピングモールで最大を誇る。一通りのものはそこで揃うため今日は1日そこでショッピングをする予定を立てていた。
セラがキッチンから運んできたサンドイッチを私の前に置き、向かい側に自分のを持って座る。皿の上には1枚分を4等分にしたサイズのサンドイッチが4つ置いてあった。中にはベーコン、トマト、レタスなどの王道な具材が沢山詰まっている。
1口含んで美味しさを噛み締めると、同じようにサンドイッチを食べるセラがあ、と思い出したように声を出した。
「そうだお姉ちゃん。せっかくエデンにいくんだから、適当な服着るのやめよう?」
「適当って……」
「お姉ちゃん美人で綺麗なんだからたまにはオシャレして着飾らないとダメだよ。あ、私の服貸してあげる!」
「いいのか?」
「私がしたいからいいの。ふふ、なんだか小さい時みたいだね。知らない街に出掛ける時、2人であーでもない、こーでもないってお互いの服選びあったの。覚えてる?」
「…そうだったか?」
2個目のサンドイッチに手をつけたところで幼少期の思い出を出されたことで胸がざわりとした。この感覚は、あまり思い出したくないのだと直感する。それを悟られないように、でもその話は”ナシ”だ、という意味を込めて伏し目がちにセラに言葉を返した。
それを汲み取ったのかセラは口を噤むと少し泣きそうな顔で微笑んだ。
そんな顔を朝からさせたくないのに、という思いと裏腹に記憶をほじくり返さなくてほっとする自分になんとも言えない気持ちになる。せっかく久しぶりに2人で朝食を共にできるのだから、このままではまずいと思い下手くそながらも自ら話題を振った。
「セラ、その…なんだ。今度、簡単な料理を教えてくれないか?」
「料理?いいけど…どうして?」
「この間ガプラ樹林で強化合宿があったのは知ってるだろう?そこで自炊したら曹長と部下に笑われたんだ。ファロン軍曹は素材を足すだけの料理しかできないのか、と」
「あー…、お姉ちゃん、具材入れてどうにかするっていうやり方しかできないもんね…」
「仕方ないだろう?料理はセラに任せっきりだったし…第一緊急時は凝った料理なんか作ってる暇ないくせにそう言ってきた」
「まぁね。でも今は平和なわけだし憧れのファロン曹長の料理が中の下レベルでした、ってちょっと悲しいね」
「なんだ憧れの、って…聞いたことないぞ」
「それは本人のところまで広がるわけないじゃない!でもお姉ちゃん、結構人気なんだよ?私の学校でもたまに話題になるんだ。ボーダムにいる警備軍の薔薇色の女神はだれだーって」
「薔薇色の女神…」
セラは楽しそうにクスクスと笑い、私は返ってイメージの合わなさに軽く呆れため息を吐いた。
でもね、と全てのサンドイッチを平らげ紅茶を啜ったあとにそのカップを大事そうに両手で抱えながらセラは言葉を零した。
「そうやってお姉ちゃんがいろんな人に認められるのを聞くのって、すごく嬉しいんだ。凄いでしょ、私のお姉ちゃん!っていつも誇らしくなれるの」
えへへ、と目をボーダムの海の境界線のように伏せて微笑むそんなセラを、私は一生かけてでも守っていきたい――ふとそう思った。
どんな形であれ、自分がこの子の迷惑な存在にならず、むしろ支えとして存在できているのだと知って肩が軽くなった気がした。
「そろそろ時間だわ。お姉ちゃんも最後の1切れ食べて、ついでに私の分もお皿洗っておいてくれる?その間に服選んでくるから!」
「わかった。あまりフリフリなのは…」
「だーめ!どんなの選んできても文句言わないでちゃんと着てね。今日は私に付き合ってくれるんでしょ?」
「そうともいったな」
楽しみだな、とひとりごちてパタパタとスリッパを鳴らし部屋に戻るセラを、コーヒーを啜りながら見送る。
急にセラとの生活も期限を迎えていると認識し始めると無性に切なさがこみ上げてきた。情けない、たかだか妹の独り立ちなんかにこんなセンチメンタルになってどうする、と己を奮い立たせ、残りのサンドイッチを無心で食べた。
窓から漏れ、部屋に差し込む日光が早朝であることを告げている。
のろのろと掛け布団を押しながら上体を起こし、数分、覚醒しない意識の中微睡んでいると扉の向こうから朝食を知らせる聞きなれた声が響いた。
その声に引き付けられるように意識がハッキリと鮮明になっていく。
あぁ、そうだ。今日はセラと一緒に出かけるんだった――と、思い出したライトニングはベッドから抜け出した。
ビューティフル・デイ////////2018.8.
「おはようお姉ちゃん。はい、コーヒー」
「ありがとうセラ」
「ねぇお姉ちゃん、またそんなカッコで寝てるの?」
もう、と1つため息を漏らしながらセラが指さすところにあるのはだらしなく着た緩めのコンビネゾンのルームウェアだ。
トップスがスバゲッティ・ストラップになっていて背中がざっくり空いている。そのために横から見ると際どい胸のラインを覗かせた。
自分の性格的に過労な軍任務を終え、帰宅してからセラのように顔のコンディションを整えたり、可愛いルームウェアに着替えたり、などなど――そういった所詮自分のお世話ということにめんどくささを覚えてしまうので、本当に最低限の身支度しかしない。
現にルームウェアを着る時も風呂から上がってそのまま着ているので下着は下のしか付けていなかった。セラが言いたいのはそういう所だろう。
「私がいない時に急な来客があったらどうするの?」
「大体そういう時は私の休日だろう?昼まで寝てるし、というか今までそういったことに遭遇してないから大丈夫だ」
言い終えたあとにコーヒーを口に入れる。
おいしい。いつも飲んでるものなのに何故か殊更に美味しいと感じるのはきっとセラがいるからなのだろうな、とぼんやり考えた。
それを他所に小さい子供のようにプリプリと怒りながらセラは続ける。
「もぅお姉ちゃんたら…。私が彼氏だったら彼女がこんなカッコしてるのやきもきしちゃうよ!」
「生憎彼氏に該当する人間はいない。」
「そういうことじゃなくて…まぁ、うん、はい。…でもブラジャー付けてないのはダメだよお姉ちゃん。形崩れちゃうし…。大きいんだから尚更だよ」
「…ダメか?」
「ダメだよ!…あ、そういえば前に一緒に下着買ったじゃない!お姉ちゃんアレはどうしたの?」
「なんだか気づいたら小さくなっていた。だから今だって着てないんだ」
「えっ?!またサイズ変わったの?じゃあ今日お姉ちゃんの分の買い物もしよう!せっかくエデンに行くんだし」
そう、今日はセラがエデンに一人暮らしをするための引越し準備として買い物にいくのだった。
エデンにあるラムウ・モールはコクーン内のショッピングモールで最大を誇る。一通りのものはそこで揃うため今日は1日そこでショッピングをする予定を立てていた。
セラがキッチンから運んできたサンドイッチを私の前に置き、向かい側に自分のを持って座る。皿の上には1枚分を4等分にしたサイズのサンドイッチが4つ置いてあった。中にはベーコン、トマト、レタスなどの王道な具材が沢山詰まっている。
1口含んで美味しさを噛み締めると、同じようにサンドイッチを食べるセラがあ、と思い出したように声を出した。
「そうだお姉ちゃん。せっかくエデンにいくんだから、適当な服着るのやめよう?」
「適当って……」
「お姉ちゃん美人で綺麗なんだからたまにはオシャレして着飾らないとダメだよ。あ、私の服貸してあげる!」
「いいのか?」
「私がしたいからいいの。ふふ、なんだか小さい時みたいだね。知らない街に出掛ける時、2人であーでもない、こーでもないってお互いの服選びあったの。覚えてる?」
「…そうだったか?」
2個目のサンドイッチに手をつけたところで幼少期の思い出を出されたことで胸がざわりとした。この感覚は、あまり思い出したくないのだと直感する。それを悟られないように、でもその話は”ナシ”だ、という意味を込めて伏し目がちにセラに言葉を返した。
それを汲み取ったのかセラは口を噤むと少し泣きそうな顔で微笑んだ。
そんな顔を朝からさせたくないのに、という思いと裏腹に記憶をほじくり返さなくてほっとする自分になんとも言えない気持ちになる。せっかく久しぶりに2人で朝食を共にできるのだから、このままではまずいと思い下手くそながらも自ら話題を振った。
「セラ、その…なんだ。今度、簡単な料理を教えてくれないか?」
「料理?いいけど…どうして?」
「この間ガプラ樹林で強化合宿があったのは知ってるだろう?そこで自炊したら曹長と部下に笑われたんだ。ファロン軍曹は素材を足すだけの料理しかできないのか、と」
「あー…、お姉ちゃん、具材入れてどうにかするっていうやり方しかできないもんね…」
「仕方ないだろう?料理はセラに任せっきりだったし…第一緊急時は凝った料理なんか作ってる暇ないくせにそう言ってきた」
「まぁね。でも今は平和なわけだし憧れのファロン曹長の料理が中の下レベルでした、ってちょっと悲しいね」
「なんだ憧れの、って…聞いたことないぞ」
「それは本人のところまで広がるわけないじゃない!でもお姉ちゃん、結構人気なんだよ?私の学校でもたまに話題になるんだ。ボーダムにいる警備軍の薔薇色の女神はだれだーって」
「薔薇色の女神…」
セラは楽しそうにクスクスと笑い、私は返ってイメージの合わなさに軽く呆れため息を吐いた。
でもね、と全てのサンドイッチを平らげ紅茶を啜ったあとにそのカップを大事そうに両手で抱えながらセラは言葉を零した。
「そうやってお姉ちゃんがいろんな人に認められるのを聞くのって、すごく嬉しいんだ。凄いでしょ、私のお姉ちゃん!っていつも誇らしくなれるの」
えへへ、と目をボーダムの海の境界線のように伏せて微笑むそんなセラを、私は一生かけてでも守っていきたい――ふとそう思った。
どんな形であれ、自分がこの子の迷惑な存在にならず、むしろ支えとして存在できているのだと知って肩が軽くなった気がした。
「そろそろ時間だわ。お姉ちゃんも最後の1切れ食べて、ついでに私の分もお皿洗っておいてくれる?その間に服選んでくるから!」
「わかった。あまりフリフリなのは…」
「だーめ!どんなの選んできても文句言わないでちゃんと着てね。今日は私に付き合ってくれるんでしょ?」
「そうともいったな」
楽しみだな、とひとりごちてパタパタとスリッパを鳴らし部屋に戻るセラを、コーヒーを啜りながら見送る。
急にセラとの生活も期限を迎えていると認識し始めると無性に切なさがこみ上げてきた。情けない、たかだか妹の独り立ちなんかにこんなセンチメンタルになってどうする、と己を奮い立たせ、残りのサンドイッチを無心で食べた。
1/3ページ