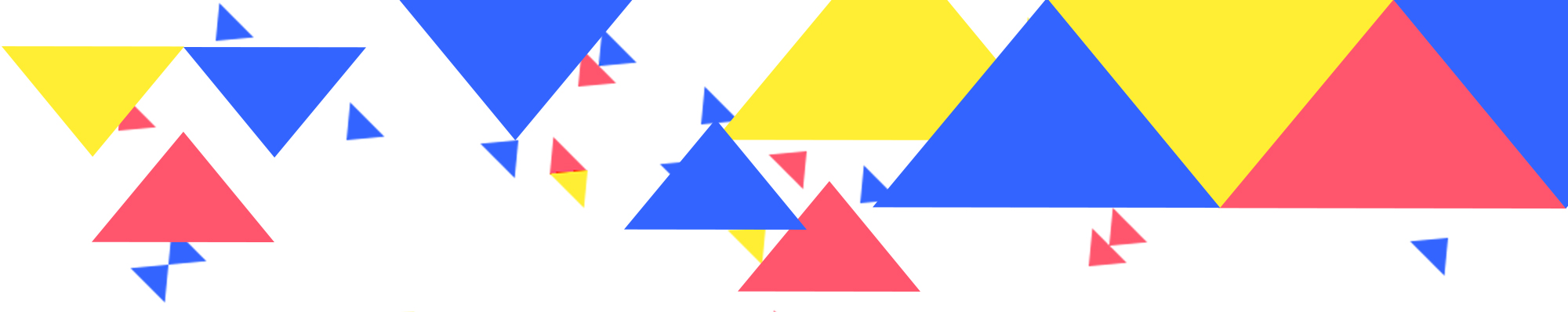ビューティフル・デイ
エデンへは軍で借りているエアバイクで向かった。
目的地のラムウ・モールに着くとエアバイクをターミナルに置き、早速モールの中へとはいっていく。
軍の警備任務などで度々こういったモールに来ることはあるのだが、今回は任務ではなく普通の一般客としてきたために、ショッピングモールの賑やかさやきらびやかさが新鮮なように思えた。
ただ、やっぱり自分は浮いているような気がしてならない。現にほら――何故か人の目線が自分たちの方に向いてる気がしてならないのだ。魔物に殺意を向けられるのとはまた別の、冷や汗が垂れるような感覚だった。
なんだか少し、恐ろしく感じて思わずセラにぶつかるように近づく。
セラはそれを恥ずかしいとみたのか――、笑顔でライトニングにこういった。
「お姉ちゃん、恥ずかしがることなんてないのに。だってこんなに似合ってるんだもん!私より私の服を着こなしててなんかずるいなぁ」
えい、とセラが私の腕に絡みつく。
いつもならそこには軍服の黒いアームカバーがあるはずなのだが、それらは見当たらずに透き通るような白い肌が露出していた。
セラがライトニングに貸してくれた服は、予想通り、ライトニング自身が絶対選ばないであろうフェミニンな服だった。
トップスはホワイトのオフショルダーで、二段フリルのブラウス。ボトムはピンク系統の花柄プリントのタイトスカートで真ん中に3つずつ、金色に輝くボタンが2列の縦並びで配置されている。
年上の雰囲気を漂わせつつでも女の子の部分もある、ある意味”エクレール”らしい装いだった。
「そ…んなことないだろう。その証拠になんだか人の視線が刺さる、気がする」
「それはお姉ちゃんが可愛いからだよ!ほら、あの人なんかお姉ちゃんのことずっとみてぽけーってしてるよ?」
そういって一瞬セラが指さした方を見てみれば、大学生くらいの男がこちらをじっと見つめている様子が見えた。
その男はライトニングが見ているのに気がつくや否やギョッとして視線を右往左往させたあと、元から真っ赤だった顔を爆発させて一目散にどこかへといってしまった。
「おいセラ、どこかへ行ってしまったぞ…目も当てられないぐらいに似合ってない、ということなのでは…?」
「お姉ちゃんほんと鈍感だね?節穴だね…」
セラは遠い目をしてひとつため息をついたが、目的の店が見つかったのか、一変して目を輝かせてお姉ちゃん!と弾む声で呼んだ。
「あのお店にいきたい!いこう!」
「ああ」
セラの浮き足立つ足の速さに合わせて、ライトニングは慣れないヒールで駆けていった。
////////
「うん、引越しの準備は一通りこんなところかな」
セラはそういいながら自身の電子パスカードからホログラムで映し出されたリストをスクロールして確認すると、ホログラムをタップして閉じた。
最初の店からぐるぐると転々し続け、今終わった時にはランチタイム後半に差し掛かっていた。
なかなかの時間歩き回っていたと思う。
ふと区切りがつくとさっきまで軽かった足が急に重く感じた。なにかに夢中になっている時には己の痛みなど気が付かないが、気が抜けると途端に忘れてた分のものが押し寄せてくる。下手すると訓練よりも疲れるな、とライトニングは考えた。
「お姉ちゃん、ご飯にしようか。あそこのファストフードとかでもいいかな?ちょうどランチタイムの間だからレストランとか満席みたいなの」
「構わない」
「ありがとう!」
慣れないヒールなのを見かねてか、セラはライトニングの歩幅に合わせてくれた。
そんな優しい心配りがなんだかむず痒くて、無意識に笑みを浮かべる。
そんな姉の姿をたまたま垣間見たセラは、とっても嬉しい気持ちになった。クールでリアリストで冷徹に見られがちな姉の、本当の一面に触れられるときがセラにとって心の底から安堵できるものだったし、心の隅で少し赦されたような気になった。
どこにでもあるファストフードで適当なものを選び、設置された席に座る。
セラはセットで頼んだドリンクをストローで吸いながら、目の前でハンバーガーを食べる姉をそっと覗き見る。
どこか禁欲的で、現世からどこか浮いたような美しさをもつ姉がこうして学生みたいにハンバーガーを食べている姿は、夢の続きをみているようでなんだか少し、嬉しさに交じって切なさを感じた。
本来ならもっとありえたはずの未来。こうして学校帰りに姉と待ち合わせてモールでショッピングをする。ハンバーガーにかじりついて、他愛のない話をして、好きな人の話をして――家に帰ってあなた達、最近素行が悪いわよ、と軽く笑いながら姉妹の頭にぽこ、と拳を落とす母がいて――
なんて夢の続き。叶うはずのない世界だ。
「セラ、食べないのか?こういうのは暖かいうちに食べないと時間とともに不味くなるぞ」
不意にライトニングの言葉で現実に引き戻された。慌ててライトニングの顔を見ると、とくに何も気にしていなさそうだった。
「ありがとお姉ちゃん。なんだかこういうのって、前にドラマで見たシーンにあったような…って思い出そうとしてたら本気になっちゃったみたい」
「なるほどな。それで、…思い出せなかったか。残念だったな」
ふいにライトニングはセラの頭に手を伸ばし、小さい子をあやす様にぽんぽん、と頭を軽くさわった。
思わず驚愕したまま固まると、ライトニングが歯切れが悪そうに口を開く。
「なんだか、小さい子みたいに拗ねてるように見えたからつい…やってしまった。そんな歳じゃなかったな」
「ううん。そんなことない。私いつだってお姉ちゃんに甘えていたいもん」
言ったあとに、あぁこうして姉を縛っていくのだ、と心の奥底で気づいたが見ないふりをした。
「お姉ちゃん、それ食べ終わったら今度はお姉ちゃんのお買い物、しよ?」
「別にいいんだがな」
「ダメだよ!私、どっちかっていうとそっちの方が楽しみできたんだから」
「それは本末転倒だろう」
「いいのー!」
ふわ、と花が開くように笑うお姉ちゃんはとても綺麗で、私も釣られて微笑む。
こんな時間を過ごせるのはとても素晴らしいことなんだなと思った。
目的地のラムウ・モールに着くとエアバイクをターミナルに置き、早速モールの中へとはいっていく。
軍の警備任務などで度々こういったモールに来ることはあるのだが、今回は任務ではなく普通の一般客としてきたために、ショッピングモールの賑やかさやきらびやかさが新鮮なように思えた。
ただ、やっぱり自分は浮いているような気がしてならない。現にほら――何故か人の目線が自分たちの方に向いてる気がしてならないのだ。魔物に殺意を向けられるのとはまた別の、冷や汗が垂れるような感覚だった。
なんだか少し、恐ろしく感じて思わずセラにぶつかるように近づく。
セラはそれを恥ずかしいとみたのか――、笑顔でライトニングにこういった。
「お姉ちゃん、恥ずかしがることなんてないのに。だってこんなに似合ってるんだもん!私より私の服を着こなしててなんかずるいなぁ」
えい、とセラが私の腕に絡みつく。
いつもならそこには軍服の黒いアームカバーがあるはずなのだが、それらは見当たらずに透き通るような白い肌が露出していた。
セラがライトニングに貸してくれた服は、予想通り、ライトニング自身が絶対選ばないであろうフェミニンな服だった。
トップスはホワイトのオフショルダーで、二段フリルのブラウス。ボトムはピンク系統の花柄プリントのタイトスカートで真ん中に3つずつ、金色に輝くボタンが2列の縦並びで配置されている。
年上の雰囲気を漂わせつつでも女の子の部分もある、ある意味”エクレール”らしい装いだった。
「そ…んなことないだろう。その証拠になんだか人の視線が刺さる、気がする」
「それはお姉ちゃんが可愛いからだよ!ほら、あの人なんかお姉ちゃんのことずっとみてぽけーってしてるよ?」
そういって一瞬セラが指さした方を見てみれば、大学生くらいの男がこちらをじっと見つめている様子が見えた。
その男はライトニングが見ているのに気がつくや否やギョッとして視線を右往左往させたあと、元から真っ赤だった顔を爆発させて一目散にどこかへといってしまった。
「おいセラ、どこかへ行ってしまったぞ…目も当てられないぐらいに似合ってない、ということなのでは…?」
「お姉ちゃんほんと鈍感だね?節穴だね…」
セラは遠い目をしてひとつため息をついたが、目的の店が見つかったのか、一変して目を輝かせてお姉ちゃん!と弾む声で呼んだ。
「あのお店にいきたい!いこう!」
「ああ」
セラの浮き足立つ足の速さに合わせて、ライトニングは慣れないヒールで駆けていった。
////////
「うん、引越しの準備は一通りこんなところかな」
セラはそういいながら自身の電子パスカードからホログラムで映し出されたリストをスクロールして確認すると、ホログラムをタップして閉じた。
最初の店からぐるぐると転々し続け、今終わった時にはランチタイム後半に差し掛かっていた。
なかなかの時間歩き回っていたと思う。
ふと区切りがつくとさっきまで軽かった足が急に重く感じた。なにかに夢中になっている時には己の痛みなど気が付かないが、気が抜けると途端に忘れてた分のものが押し寄せてくる。下手すると訓練よりも疲れるな、とライトニングは考えた。
「お姉ちゃん、ご飯にしようか。あそこのファストフードとかでもいいかな?ちょうどランチタイムの間だからレストランとか満席みたいなの」
「構わない」
「ありがとう!」
慣れないヒールなのを見かねてか、セラはライトニングの歩幅に合わせてくれた。
そんな優しい心配りがなんだかむず痒くて、無意識に笑みを浮かべる。
そんな姉の姿をたまたま垣間見たセラは、とっても嬉しい気持ちになった。クールでリアリストで冷徹に見られがちな姉の、本当の一面に触れられるときがセラにとって心の底から安堵できるものだったし、心の隅で少し赦されたような気になった。
どこにでもあるファストフードで適当なものを選び、設置された席に座る。
セラはセットで頼んだドリンクをストローで吸いながら、目の前でハンバーガーを食べる姉をそっと覗き見る。
どこか禁欲的で、現世からどこか浮いたような美しさをもつ姉がこうして学生みたいにハンバーガーを食べている姿は、夢の続きをみているようでなんだか少し、嬉しさに交じって切なさを感じた。
本来ならもっとありえたはずの未来。こうして学校帰りに姉と待ち合わせてモールでショッピングをする。ハンバーガーにかじりついて、他愛のない話をして、好きな人の話をして――家に帰ってあなた達、最近素行が悪いわよ、と軽く笑いながら姉妹の頭にぽこ、と拳を落とす母がいて――
なんて夢の続き。叶うはずのない世界だ。
「セラ、食べないのか?こういうのは暖かいうちに食べないと時間とともに不味くなるぞ」
不意にライトニングの言葉で現実に引き戻された。慌ててライトニングの顔を見ると、とくに何も気にしていなさそうだった。
「ありがとお姉ちゃん。なんだかこういうのって、前にドラマで見たシーンにあったような…って思い出そうとしてたら本気になっちゃったみたい」
「なるほどな。それで、…思い出せなかったか。残念だったな」
ふいにライトニングはセラの頭に手を伸ばし、小さい子をあやす様にぽんぽん、と頭を軽くさわった。
思わず驚愕したまま固まると、ライトニングが歯切れが悪そうに口を開く。
「なんだか、小さい子みたいに拗ねてるように見えたからつい…やってしまった。そんな歳じゃなかったな」
「ううん。そんなことない。私いつだってお姉ちゃんに甘えていたいもん」
言ったあとに、あぁこうして姉を縛っていくのだ、と心の奥底で気づいたが見ないふりをした。
「お姉ちゃん、それ食べ終わったら今度はお姉ちゃんのお買い物、しよ?」
「別にいいんだがな」
「ダメだよ!私、どっちかっていうとそっちの方が楽しみできたんだから」
「それは本末転倒だろう」
「いいのー!」
ふわ、と花が開くように笑うお姉ちゃんはとても綺麗で、私も釣られて微笑む。
こんな時間を過ごせるのはとても素晴らしいことなんだなと思った。