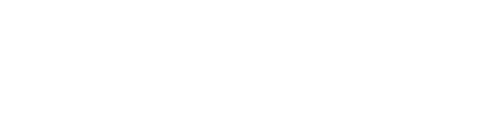氷の告白
「おはよう、煜瑾」
不安そうな顔をした煜瑾に向かって、文維はなるべく温柔に声を掛けた。
「文維…。おはよう、ございます」
無理に作った笑顔を浮かべて、煜瑾は恋人に応えた。
互いに思い合い、慕い合う2人であるのに、ぎこちなさが拭えない。
「煜瑾、心配を掛けましたね」
「いいえ。文維こそ、ゆっくり休めましたか?考え事もできましたか?」
心優しい煜瑾は、柔らかな表情の中にも疲れが残る恋人を気に掛けていた。そんな慈愛に満ちた煜瑾が心から愛しい文維だった。
「ありがとう、煜瑾。昨日のことは、今夜必ず全てお話すると約束します。だから、もう心配はしないでください」
文維の誠実な言葉と声色に、煜瑾はホッとしていつもと変わらない天使の笑顔を浮かべた。
「今夜、ですね」
「ええ。今夜まで、待ってもらえますか?」
「もちろんです。私は文維を信じています。何も疑うことはありません」
悠々とした空気の中、2人はいつもと同じように仲良く朝食を楽しみ、文維は自身のクリニックへ、新人インテリアコーディネーターの煜瑾はクライアントとの打ち合わせに、それぞれ出掛けた。
***
クリニックに到着した文維は、いやが上にも昨日の范青䒾とのセッションを思い出してしまう。
文維にとって、あれは恐怖の時間だった。
信じていたものに裏切られ、最愛の相手を傷つけるような、恐ろしい告白だった。
「おはようございます、文維先生。昨日おっしゃっていた、健診センターの予約、12時30分から取れていますわ。お昼休みに行かれるんですね」
定時より少し早くに出勤した、受付の張春梅女史からの報告に、文維は丁寧に会釈した。
「でも、特定のクライアントにそこまでされなくても…」
張女史は、昨日の新患が申し出たことに不満を抱いていた。新患とは言え、以前からの包文維医師の知り合いならば口出しすることではないと分かってはいるが、それでも彼女のために健診センターの予約を取り、付き添いまでするとは、親切過ぎるのではないかと張女史は思うのだ。
「いいんですよ」
「そうは言っても、唐家のお坊ちゃんはいい気持ちはしないのでは?」
まるで伝家の宝刀を振るうように、張女史は唐煜瑾の名を持ち出した。そのことを自覚している文維だが、真面目な顔をして張女史に言った。
「…煜瑾には、今夜、私から話すので、何も言わないでください」
「もちろん、私から唐家のお坊ちゃんに余計な事など言いませんわ。でも…」
愛していれば、隠し事などすべきではないし、隠し事をしたとしてもなぜだかバレてしまうものだ、と離婚経験者の張春梅は思う。
「大丈夫です。今夜…、煜瑾に話します」
「そうですか…」
文維を責めるつもりも、煜瑾を傷つけるつもりも無い張女史は、それ以上何も言わずに、自分の持ち場へと戻った。
不安そうな顔をした煜瑾に向かって、文維はなるべく温柔に声を掛けた。
「文維…。おはよう、ございます」
無理に作った笑顔を浮かべて、煜瑾は恋人に応えた。
互いに思い合い、慕い合う2人であるのに、ぎこちなさが拭えない。
「煜瑾、心配を掛けましたね」
「いいえ。文維こそ、ゆっくり休めましたか?考え事もできましたか?」
心優しい煜瑾は、柔らかな表情の中にも疲れが残る恋人を気に掛けていた。そんな慈愛に満ちた煜瑾が心から愛しい文維だった。
「ありがとう、煜瑾。昨日のことは、今夜必ず全てお話すると約束します。だから、もう心配はしないでください」
文維の誠実な言葉と声色に、煜瑾はホッとしていつもと変わらない天使の笑顔を浮かべた。
「今夜、ですね」
「ええ。今夜まで、待ってもらえますか?」
「もちろんです。私は文維を信じています。何も疑うことはありません」
悠々とした空気の中、2人はいつもと同じように仲良く朝食を楽しみ、文維は自身のクリニックへ、新人インテリアコーディネーターの煜瑾はクライアントとの打ち合わせに、それぞれ出掛けた。
***
クリニックに到着した文維は、いやが上にも昨日の范青䒾とのセッションを思い出してしまう。
文維にとって、あれは恐怖の時間だった。
信じていたものに裏切られ、最愛の相手を傷つけるような、恐ろしい告白だった。
「おはようございます、文維先生。昨日おっしゃっていた、健診センターの予約、12時30分から取れていますわ。お昼休みに行かれるんですね」
定時より少し早くに出勤した、受付の張春梅女史からの報告に、文維は丁寧に会釈した。
「でも、特定のクライアントにそこまでされなくても…」
張女史は、昨日の新患が申し出たことに不満を抱いていた。新患とは言え、以前からの包文維医師の知り合いならば口出しすることではないと分かってはいるが、それでも彼女のために健診センターの予約を取り、付き添いまでするとは、親切過ぎるのではないかと張女史は思うのだ。
「いいんですよ」
「そうは言っても、唐家のお坊ちゃんはいい気持ちはしないのでは?」
まるで伝家の宝刀を振るうように、張女史は唐煜瑾の名を持ち出した。そのことを自覚している文維だが、真面目な顔をして張女史に言った。
「…煜瑾には、今夜、私から話すので、何も言わないでください」
「もちろん、私から唐家のお坊ちゃんに余計な事など言いませんわ。でも…」
愛していれば、隠し事などすべきではないし、隠し事をしたとしてもなぜだかバレてしまうものだ、と離婚経験者の張春梅は思う。
「大丈夫です。今夜…、煜瑾に話します」
「そうですか…」
文維を責めるつもりも、煜瑾を傷つけるつもりも無い張女史は、それ以上何も言わずに、自分の持ち場へと戻った。