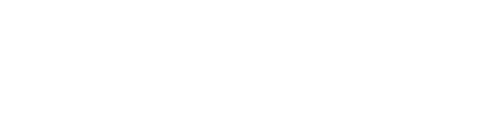氷の告白
「お久しぶり…」
相変らず、物静かな淑女といった様子で、范青䒾は文維の前に現れた。
「お久しぶりです、マダム・ガルニエ」
クライアントの心を開く、優秀なカウンセラーの笑みを浮かべて、包文維は范青䒾をその趣味の良い診察室で迎えた。
互いに穏やかな笑顔を交わしながら、文維は座り心地のよいカウチソファを勧め、范青䒾は優雅に腰を下ろした。
「お変わりなく?」
美しく、悩ましい顔と声で范青䒾は囁いた。文維には、かつて奔放だった頃の彼女に比べて、少し痩せて見える。
「あなたこそ、相変わらずお美しいですね。コーヒーでも?」
「ありがとう。コーヒーは結構よ。それより、大切な話があるから…」
范青䒾はそう言って、意味ありげに口元を歪めた。
「では、お話を伺いましょう」
カウンセラーとしての立場で、文維は范青䒾に向かい合った。
「…もう、違うの…」
「え?」
「…私、…もう…、『マダム・ガルニエ』じゃないの…」
文維は、旧友の范青䒾が、裕福な貿易商であるフランス人のピエール・ガルニエと離婚したのだと察した。そのことで精神的に不安定になり、このクリニックに来たのだろうか。
「…彼に、捨てられたわ…」
自嘲するように笑って、彼女は文維を見詰めた。
「その理由は、私にあるの」
すっと彼女の視線が冷ややかになった。多くの「恋人」たちに囲まれ、華やかで、晴れやかな時間を過ごしながら、時折こんな冷たい表情をすることがあった、と文維は思い出した。
張り付いたような笑みを浮かべ、疲れ切ったように范青䒾は言った。
「そのことで、あなたに言っておかなければならないことがあるわ」
文維は、彼女の言い方に少し引っ掛かった。
上流階級に身を置く彼女は聡明で、言葉遣いも正確だったはずだ。カウンセラーに「聞いて欲しい」「話したい」ということならともかく、「言っておかなければならない」とは、非常に含みのある言い方だ、と文維は思った。
「そうなんですね。続けましょう」
文維が彼女に促すと、范青䒾は急に老け込んだような陰鬱な、それでも冴え冴えとした美貌で口を開いた。
「実は、私…」
彼女の告白を受け止めるように、沈着冷静に耳を傾けていた文維だったが、その思いもよらない内容に、顔色を変え、言葉を失った。
相変らず、物静かな淑女といった様子で、范青䒾は文維の前に現れた。
「お久しぶりです、マダム・ガルニエ」
クライアントの心を開く、優秀なカウンセラーの笑みを浮かべて、包文維は范青䒾をその趣味の良い診察室で迎えた。
互いに穏やかな笑顔を交わしながら、文維は座り心地のよいカウチソファを勧め、范青䒾は優雅に腰を下ろした。
「お変わりなく?」
美しく、悩ましい顔と声で范青䒾は囁いた。文維には、かつて奔放だった頃の彼女に比べて、少し痩せて見える。
「あなたこそ、相変わらずお美しいですね。コーヒーでも?」
「ありがとう。コーヒーは結構よ。それより、大切な話があるから…」
范青䒾はそう言って、意味ありげに口元を歪めた。
「では、お話を伺いましょう」
カウンセラーとしての立場で、文維は范青䒾に向かい合った。
「…もう、違うの…」
「え?」
「…私、…もう…、『マダム・ガルニエ』じゃないの…」
文維は、旧友の范青䒾が、裕福な貿易商であるフランス人のピエール・ガルニエと離婚したのだと察した。そのことで精神的に不安定になり、このクリニックに来たのだろうか。
「…彼に、捨てられたわ…」
自嘲するように笑って、彼女は文維を見詰めた。
「その理由は、私にあるの」
すっと彼女の視線が冷ややかになった。多くの「恋人」たちに囲まれ、華やかで、晴れやかな時間を過ごしながら、時折こんな冷たい表情をすることがあった、と文維は思い出した。
張り付いたような笑みを浮かべ、疲れ切ったように范青䒾は言った。
「そのことで、あなたに言っておかなければならないことがあるわ」
文維は、彼女の言い方に少し引っ掛かった。
上流階級に身を置く彼女は聡明で、言葉遣いも正確だったはずだ。カウンセラーに「聞いて欲しい」「話したい」ということならともかく、「言っておかなければならない」とは、非常に含みのある言い方だ、と文維は思った。
「そうなんですね。続けましょう」
文維が彼女に促すと、范青䒾は急に老け込んだような陰鬱な、それでも冴え冴えとした美貌で口を開いた。
「実は、私…」
彼女の告白を受け止めるように、沈着冷静に耳を傾けていた文維だったが、その思いもよらない内容に、顔色を変え、言葉を失った。