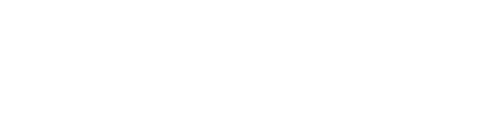氷の告白
睡眠障害を訴える、上海社交界では名の知れた大企業の総経理 のカウンセリングを終え、包文維 は立ち上がった。
「思い悩むな、というのは無理でしょうが、気分転換は大切ですよ。次回までに、何か気晴らしになるようなことを探してみてください。次回は、そのことについて、私たちは話し合いましょう」
寄り添うような包医生 の言葉に、今にも泣きそうな顔をして、還暦に近い男性は小さく頷いた。
「次回も、今日と同じく木曜日の夕方4時からでよろしいですか?」
「はい。同じ曜日、同じ時間でお願いします」
疲れ切った様子の男性クライアントは、そう言って包文維の診察室から出て行った。
会社が上手くいっていないこと、そのストレスで過食に走り、肥満し、運動不足もあって不眠であるのは、おそらくは本人も分かっている。だが、スポーツジムではなく、精神科医であり、かつ心理カウンセラーの資格を持つ包文維のクリニックを選んだのは、運動嫌いと言うよりも、話し相手が欲しいからだろう。
彼が「木曜日」「夕方4時」にこだわるのも、3年前に彼の妻が病院で息を引き取った時間だからだ。
彼にとって、おそらく唯一心を開いて話せる相手が亡き妻だったのだろうと文維は考えている。
(孤独な人なのだ…)
クライアントに対しては、常に客観的な視線を持って接する必要がある職業だが、文維はほんの少し、この男性に同情心を抱いた。
ぼんやりと考えに耽 っていた文維だったが、診察室のドアをノックする音に我に返った。
「文維先生?」
クライアントが出て行ったのを確認して、医療秘書で受付を担当している張春梅 女史が、遠慮がちにドアを開けて顔を出した。
「どうしました?」
知的で穏やかな、ビジネス用の笑みを浮かべて文維が応じると、張女史は憮然とした様子で口を開いた。
「またですよ。また、江芳 さんが予約をキャンセルしてきました」
広州出身の裕福な江芳嬢は、わずか16歳で、30歳も年上の北京の銀行家に嫁がされた。傲慢な夫に心身両面でのDV被害を受け、なんとか10年後に上海の親戚宅に逃げ込むことに成功した。その後、広州の両親に連絡を取ることができ、ようやく無事に離婚が成立したのだった。
だが、その頃にはすっかり心のバランスを崩してしまった彼女を、実家の両親は上海の「療養所」と言う名の隔離施設に閉じ込めてしまった。
そこからの退所までさらに5年。今は蘇州郊外にある豪邸にひっそりと暮らす彼女だが、上海の医療施設からの退所条件である「週に一度は、精神科医の診察を受ける」ということが守れなかった。
上海の富裕層である彼女の親戚が、評判の良い包文維を彼女の主治医と決めたのはいいが、彼女は蘇州から上海までの高鉄 での30分さえ苦痛なのだ。
文維は何度も蘇州で信頼のおけるクリニックを紹介しようとしたのだが、彼女の実家、親戚がそれを許さない。
彼らは大都会である上海での、包文維の精神科医としてのネームバリューに絶大な信頼を置いていた。今や「包文維」は、知る人ぞ知るコミュニティでは、その名を出すだけで「上海セレブ」だと認められたも同じだったからだ。
形だけでも診察をしたように見せかけるため、文維は、年老いた世話係と密やかに暮らす江芳女史に、メールを送る。彼女の状態を確認し、「異常無し」と医療施設に報告しなければならないからだ。
彼女がこのクリニックのクライアントになって2年半になるが、わずか3回ほどしか直接に面談をしていない。
小柄で、顔色が悪く、表情の無い、いかにも病人といったような小さく細い声で、ぽつりぽつりとしか話さない彼女だったが、その繊細な美貌は卓越していた。ただ、実年齢はまだ30代前半であるはずなのに、10歳以上は老けて見えるのが、彼女のこれまでの不幸な人生を物語っているようで、文維は痛々しく思った。
「構いません。後で私が連絡して、次の予約の手配をします」
そんなことをしても無駄だ、と張女史は思っているが、それを口には出さない。このクリニックは、それだけ特別なのだと、張女史も自覚しているからだ。
「では、どうされます?キャンセル待ちの新規の患者さんがおられますけど、連絡してみますか?」
「思い悩むな、というのは無理でしょうが、気分転換は大切ですよ。次回までに、何か気晴らしになるようなことを探してみてください。次回は、そのことについて、私たちは話し合いましょう」
寄り添うような包
「次回も、今日と同じく木曜日の夕方4時からでよろしいですか?」
「はい。同じ曜日、同じ時間でお願いします」
疲れ切った様子の男性クライアントは、そう言って包文維の診察室から出て行った。
会社が上手くいっていないこと、そのストレスで過食に走り、肥満し、運動不足もあって不眠であるのは、おそらくは本人も分かっている。だが、スポーツジムではなく、精神科医であり、かつ心理カウンセラーの資格を持つ包文維のクリニックを選んだのは、運動嫌いと言うよりも、話し相手が欲しいからだろう。
彼が「木曜日」「夕方4時」にこだわるのも、3年前に彼の妻が病院で息を引き取った時間だからだ。
彼にとって、おそらく唯一心を開いて話せる相手が亡き妻だったのだろうと文維は考えている。
(孤独な人なのだ…)
クライアントに対しては、常に客観的な視線を持って接する必要がある職業だが、文維はほんの少し、この男性に同情心を抱いた。
ぼんやりと考えに
「文維先生?」
クライアントが出て行ったのを確認して、医療秘書で受付を担当している
「どうしました?」
知的で穏やかな、ビジネス用の笑みを浮かべて文維が応じると、張女史は憮然とした様子で口を開いた。
「またですよ。また、
広州出身の裕福な江芳嬢は、わずか16歳で、30歳も年上の北京の銀行家に嫁がされた。傲慢な夫に心身両面でのDV被害を受け、なんとか10年後に上海の親戚宅に逃げ込むことに成功した。その後、広州の両親に連絡を取ることができ、ようやく無事に離婚が成立したのだった。
だが、その頃にはすっかり心のバランスを崩してしまった彼女を、実家の両親は上海の「療養所」と言う名の隔離施設に閉じ込めてしまった。
そこからの退所までさらに5年。今は蘇州郊外にある豪邸にひっそりと暮らす彼女だが、上海の医療施設からの退所条件である「週に一度は、精神科医の診察を受ける」ということが守れなかった。
上海の富裕層である彼女の親戚が、評判の良い包文維を彼女の主治医と決めたのはいいが、彼女は蘇州から上海までの
文維は何度も蘇州で信頼のおけるクリニックを紹介しようとしたのだが、彼女の実家、親戚がそれを許さない。
彼らは大都会である上海での、包文維の精神科医としてのネームバリューに絶大な信頼を置いていた。今や「包文維」は、知る人ぞ知るコミュニティでは、その名を出すだけで「上海セレブ」だと認められたも同じだったからだ。
形だけでも診察をしたように見せかけるため、文維は、年老いた世話係と密やかに暮らす江芳女史に、メールを送る。彼女の状態を確認し、「異常無し」と医療施設に報告しなければならないからだ。
彼女がこのクリニックのクライアントになって2年半になるが、わずか3回ほどしか直接に面談をしていない。
小柄で、顔色が悪く、表情の無い、いかにも病人といったような小さく細い声で、ぽつりぽつりとしか話さない彼女だったが、その繊細な美貌は卓越していた。ただ、実年齢はまだ30代前半であるはずなのに、10歳以上は老けて見えるのが、彼女のこれまでの不幸な人生を物語っているようで、文維は痛々しく思った。
「構いません。後で私が連絡して、次の予約の手配をします」
そんなことをしても無駄だ、と張女史は思っているが、それを口には出さない。このクリニックは、それだけ特別なのだと、張女史も自覚しているからだ。
「では、どうされます?キャンセル待ちの新規の患者さんがおられますけど、連絡してみますか?」
1/15ページ