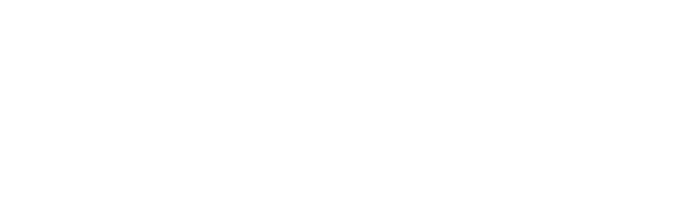甜蜜的聖誕節 ~スウィート・クリスマス~
午後からはクリニックを終えた文維が合流し、包夫妻のもてなしを存分に堪能した。
そして、それぞれにプレゼントの交換をした。
「まあ、嬉しい!」
文維と煜瑾からだとした、夫とお揃いのタブレットと色違いのカバーに、包夫人は大喜びだった。
そんな包夫人からは、それぞれ手編みの、小敏には赤のニット帽を、煜瑾にはオレンジのマフラーを、そして文維にはマフラーではなく輪になった白いネックウォーマーが贈られた。
「文維は昔からマフラーをすぐに失くしてしまうのよ」
そんな風に不満そうに言う恭安楽の目は、裏腹に慈愛に満ちた母親のものだった。
「私は彼女ほど器用じゃないし、煜瑾のお兄様のように裕福ではないからね」
包氏はそう言って、現金が入った紅包ホンパオ(ご祝儀袋)を3人の子供たちに渡した。
3人はお礼を述べて、包氏のためにクリスマス用の発泡ワインで献杯した。
それからは大いに食べ、大いに飲み、そして大いに笑った。こんなに楽しいクリスマスは初めてかもしれない、と煜瑾は思った。
去年のクリスマスイブから、1年でこれほど変わってしまった。文維が一緒にいれば、必ず自分は幸せになれるのだと、煜瑾は確信を持ったのだった。
「お義父とうさま、お義母かあさま、次はぜひ我が家で春節のお食事会をさせて下さい」
「楽しみにしているわ」「ありがとう」
夕方になり、文維と煜瑾は包家から帰ることになった。
大好きな義両親に挨拶をし、煜瑾はお土産に包夫人手作りのお菓子を受け取った。
「今夜は、楽しんで」
意味ありげな笑顔の親友に、一瞬キョトンとあどけない表情を浮かべた煜瑾だったが、その素直さゆえに、すぐに純真な笑みを浮かべた。
「ありがとう。今夜は小敏のおかげで、文維とステキな夜が迎えられます」
無邪気な煜瑾の答えに、小敏だけでなく、義両親や、文維までもが破顔した。
文維と煜瑾が連れ添って外に出ると、辺りはもう暗くなっていた。
「ねえ、文維…」
「なんですか、煜瑾?」
甘えるように言う煜瑾に、文維はいつもの温柔な態度で応える。
「あの…せっかく小敏が、スイートルームを予約してくれたので…。チェックインしてしまいませんか?」
早く、思い出のホテルのスイートルームで2人きりになりたいという、煜瑾の気持ちなど、文維はとっくに察していた。
それでもわざと、文維は素知らぬ振りをした。
「まだ5時前ですよ。買い物に行って、浦東のイルミネーションを見て、お食事をしてからでも間に合うでしょう?」
「そう…ですけど…。でも、でもね!私はもうお買い物なんて無いし、イルミネーションだって、ホテルのお部屋から街の灯りが見られるし、お食事だって!」
必死に訴える煜瑾が稚く、愛しく、文維は笑ってしまった。
「そうですね。お食事も7時に、今夜泊まるホテルの33階のレストランを予約していますしね」
「!」
小敏が去年のことを覚えている以上に、当事者である文維がこのホテルでの思い出を忘れるはずが無かった。
「それは…最初から?」
ほんの少し、煜瑾は不安そうに訊ねた。本当は、文維は、1年前の今夜、どれほど2人が幸せだったかを忘れているのではないかと心配していた。
「宿泊までは思いつかなかったのですけれど…。それでも、クリスマス・イブは、このホテルで煜瑾と過ごしたいと思って、レストランは半年前から予約していました」
それだけで、煜瑾は満足だった。
愛する人が同じ気持ちでいてくれるだけで、十分に幸せなのだ。
1年前は、好きだという気持ちさえうまく伝えられず、相手を誤解し、そのことで会えなくなった。
会えないというだけで、2人とも倒れてしまうほど、苦しくて、切なくて、悲しかった。
今は、そんな痛みも、喜びも、何もかも2人で一緒に分かち合える。
「やはり、先にスイートルームを見に行きましょうか」
文維が少年のようなチャーミングな笑顔で言うと、煜瑾は大きく頷いた。
そして、それぞれにプレゼントの交換をした。
「まあ、嬉しい!」
文維と煜瑾からだとした、夫とお揃いのタブレットと色違いのカバーに、包夫人は大喜びだった。
そんな包夫人からは、それぞれ手編みの、小敏には赤のニット帽を、煜瑾にはオレンジのマフラーを、そして文維にはマフラーではなく輪になった白いネックウォーマーが贈られた。
「文維は昔からマフラーをすぐに失くしてしまうのよ」
そんな風に不満そうに言う恭安楽の目は、裏腹に慈愛に満ちた母親のものだった。
「私は彼女ほど器用じゃないし、煜瑾のお兄様のように裕福ではないからね」
包氏はそう言って、現金が入った紅包ホンパオ(ご祝儀袋)を3人の子供たちに渡した。
3人はお礼を述べて、包氏のためにクリスマス用の発泡ワインで献杯した。
それからは大いに食べ、大いに飲み、そして大いに笑った。こんなに楽しいクリスマスは初めてかもしれない、と煜瑾は思った。
去年のクリスマスイブから、1年でこれほど変わってしまった。文維が一緒にいれば、必ず自分は幸せになれるのだと、煜瑾は確信を持ったのだった。
「お義父とうさま、お義母かあさま、次はぜひ我が家で春節のお食事会をさせて下さい」
「楽しみにしているわ」「ありがとう」
夕方になり、文維と煜瑾は包家から帰ることになった。
大好きな義両親に挨拶をし、煜瑾はお土産に包夫人手作りのお菓子を受け取った。
「今夜は、楽しんで」
意味ありげな笑顔の親友に、一瞬キョトンとあどけない表情を浮かべた煜瑾だったが、その素直さゆえに、すぐに純真な笑みを浮かべた。
「ありがとう。今夜は小敏のおかげで、文維とステキな夜が迎えられます」
無邪気な煜瑾の答えに、小敏だけでなく、義両親や、文維までもが破顔した。
文維と煜瑾が連れ添って外に出ると、辺りはもう暗くなっていた。
「ねえ、文維…」
「なんですか、煜瑾?」
甘えるように言う煜瑾に、文維はいつもの温柔な態度で応える。
「あの…せっかく小敏が、スイートルームを予約してくれたので…。チェックインしてしまいませんか?」
早く、思い出のホテルのスイートルームで2人きりになりたいという、煜瑾の気持ちなど、文維はとっくに察していた。
それでもわざと、文維は素知らぬ振りをした。
「まだ5時前ですよ。買い物に行って、浦東のイルミネーションを見て、お食事をしてからでも間に合うでしょう?」
「そう…ですけど…。でも、でもね!私はもうお買い物なんて無いし、イルミネーションだって、ホテルのお部屋から街の灯りが見られるし、お食事だって!」
必死に訴える煜瑾が稚く、愛しく、文維は笑ってしまった。
「そうですね。お食事も7時に、今夜泊まるホテルの33階のレストランを予約していますしね」
「!」
小敏が去年のことを覚えている以上に、当事者である文維がこのホテルでの思い出を忘れるはずが無かった。
「それは…最初から?」
ほんの少し、煜瑾は不安そうに訊ねた。本当は、文維は、1年前の今夜、どれほど2人が幸せだったかを忘れているのではないかと心配していた。
「宿泊までは思いつかなかったのですけれど…。それでも、クリスマス・イブは、このホテルで煜瑾と過ごしたいと思って、レストランは半年前から予約していました」
それだけで、煜瑾は満足だった。
愛する人が同じ気持ちでいてくれるだけで、十分に幸せなのだ。
1年前は、好きだという気持ちさえうまく伝えられず、相手を誤解し、そのことで会えなくなった。
会えないというだけで、2人とも倒れてしまうほど、苦しくて、切なくて、悲しかった。
今は、そんな痛みも、喜びも、何もかも2人で一緒に分かち合える。
「やはり、先にスイートルームを見に行きましょうか」
文維が少年のようなチャーミングな笑顔で言うと、煜瑾は大きく頷いた。