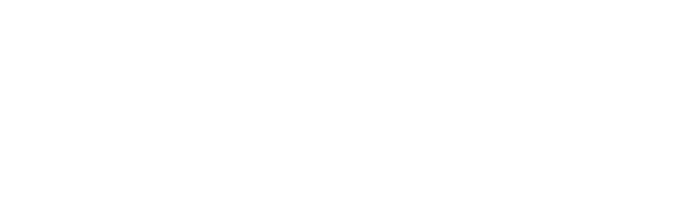聖夜
腕の中の温もりに、身体だけでなく、心の奥からも暖かさを感じる哲臣だった。これはまるで、雪と共に舞い降りた天使の存在……。
「叔父様。今夜は、サンタクロースが来るんですよね」
束の間の至福の時間を味わっていた哲臣に、唐突に裕章が問いかける。
「そうだね。君が来ると信じていれば、きっとね」
その真意を探るように、哲臣は少年の純真な瞳を凝視し続けた。
「じゃあ、きっと来ますね。絶対だ!」
裕章を見つめる哲臣の眼差しは、充分に暖められたこの部屋以上に、暖かく穏やかだった。
叔父の肩に体を預けていた裕章は、そのままゆっくりと倒れ込んだ。長い足を持て余したように座る哲臣の膝に、少年はその形の良い頭を乗せる。子供っぽい邪心の無い動作のはずだが、やけに艶めかしい。そう思った哲臣の神経が、思わず尖る。組んだ足から、少年の体温が伝わってくる。
日頃大人びている少年ではあっても、やはり心細さから人恋しさを感じているのだろう。だから、知らず知らずの内に、叔父の温もりに甘えたくもなっているに違いない。
「サンタクロースって、北極に住んでるって、本当かな」
何を思ってか、裕章はそう言った。
「どうかな。……でも、北極とはまた遠い所だね」
哲臣は、愛しむように心弱い甥の頭に手を置いた。
「サンタクロースは……、僕のことを知っているんだろうか」
「ああ、必ず知っているよ。君の欲しい物だって、知っているはずさ」
裕章の、欲しいもの。
裕章の、望むもの。
それを与えることは、今は誰にも出来ないだろう。けれど、それが人外の不思議な力であるなら……。決して単なるファンタジーとしてでは無く、切なる願いとして、裕章はサンタクロースを信じたかった。
哲臣の長い指先が、裕章の柔らかで素直な髪を絡め取る。
「君も、もうすっかり大人になってしまったと思っていたけれど……。君は、君のままだ。いつまでも、これからも……」
裕章は、ふっと顔を上げ、哲臣の端整な面差しを見つめた。
異国の血を感じさせるほど、目鼻だちのはっきりとした、華やかな美貌を持つ哲臣だった。それだけではない。学生時代に水泳部で鍛えたという、日本人には珍しい、イタリアンモードのスーツも見事に着こなす恵まれた肢体。絵画を中心とした芸術や文化を学ぶためにヨーロッパに留学していた時も、その圧倒的なルックスと、知性と、社交性をもってしてコンプレックスを跳ね除け、あらゆる日本人から羨望を受けていた。
裕章にとって、この素晴らしく優れた叔父は、自慢であり、自身の憧れでもあった。
「僕が、大人?」
誰よりも自分を認めて欲しいはずの叔父ではあったが、今はその言葉に不安な翳りが付きまとう。
「でも……、大人になってしまったら、サンタクロースは来なくなるでしょう?」
そう言って裕章は、窓の外の雪景色に目をやって、その表情を曇らせた。
「……もう、今夜は、来ないかもしれない」
「裕章……」
いたいけな少年の不安を、哲臣は笑い飛ばすことが出来なかった。
「裕章……。君は、どんなプレゼントが欲しいんだい?」
「……」
裕章のためらいが、言葉を見失う。それを口にすることは、なんだかいけないことのようで……。
「お父様とお母様……。特に今は、お母様がお元気になることかな」
哲臣が、裕章の心を慮って、その胸の内を敢えて言葉にしてみせた。
無言のままの裕章だったが、濡れたその頬が雄弁に彼の心を物語っている。
そんな裕章を見ているうちに、哲臣は疑問が浮かぶのを禁じ得ない。
裕章を出産し、夫・隆生(たかお)を失って以来、姉の志保子は心身共に弱っていった。その結果、息子の養育などはすっかり放棄していたし、弟である哲臣の目から見ても、裕章に対して母親らしいことをしているようには思えなかった。
それでもやはり、志保子は裕章にとってはたった1人の母親だったのだ。
そこまで思って、哲臣は苦々しく口元を歪めた。
志保子は、幼い頃から愛されることに慣れ過ぎて、自分以外の人間を愛するという情熱に欠けていた。たった1人の実子である裕章に対して淡々としていられるのも、そのせいだと思われる。そして、早世した夫に対しても、志保子はそれほどの深い愛情を示したことは無かった。
哲臣は、思う。
(それでも、みんな志保姉さんを愛している。姉さんでなくてはならないんだ。他の誰が代わりを務めることなんて出来ないんだ)
「お母様、すぐにお元気になられるんでしょう?」
すがるように裕章が、叔父を問い詰める。少年の純真な眼差しには、ただ一途にその思慕しか無かった。
「そんなに、お母様が恋しいのかい、裕章?」
哲臣の声は、心なしか冷やかだった。
「……叔父様の、仰りたいことは分かっているつもりです。お母様には、お体を大事にして頂かなくてはならないんだから、僕がわがまま言ったりしちゃ、いけないんですよね」
聞き分けの良すぎる裕章が、これほどまでに自制を強いられてきたとは、痛々しいことだった。
「でも! ……でも、毎年クリスマスにはお母様がいらしたのに……。このままじっとしていたら、僕の知らないうちに、お母様がどこかへ行ってしまわれるような気がして。お父様のように、お会い出来ないまま、僕にお母様がいるってことすら消えてしまいそうで……」
少年は、寂しいのだろう。両親の愛に、飢えているのだろう。幼い時に父を失い、今また母を失うことになるかもしれないという恐れが、彼の繊細な神経を切り裂いているに違いない。そんな裕章の心を、哲臣も痛いほど分かる。けれど一方で、言いようのないもどかしさを覚えるのだ。
自分は、どれほどこの少年を慈しんでも、少年にとっての「絶対」にはなれない。誰よりも愛を捧げているのに、その享受者にとって必要としているのは自分ではないのだ。自分は、決して姉・志保子に取って代わることなど出来ないのだ。
今も、そうだ。
あの時も、そうだった……。あの時も、狂わんほどの想いを捧げたにもかかわらず、選ばれたのは哲臣ではなく、姉の志保子だったのだ。
命さえも惜しくないと思うほど愛していた。他には、何1つ欲しいものはなかった。ただ、あの人だけ……。心から真に欲したのは、あの人1人だった。
「裕章。ピアノを弾いてくれないか」
哲臣は、あの人の面影を残した裕章の涙の零れる頬に手を寄せた。
「曲は、そう……、シューマンの『トロイメライ』がいい」
哲臣は、夢を見ていた。愛しい少年は自分の傍らにいて、決して裏切ることなく、ただ自分だけを必要として、それだけで幸せで……。だが、それは夢だ。
いつも、誰かを愛することは、夢を見ることなのかもしれない。届くことを知らない、1人よがりな夢。そのことを、10数年前、この少年の父・隆生に愛を告げ、拒絶された時に哲臣は痛切に実感したのだ。
「きっと、お父さまも聴きたがっていらっしゃるはずだ……」
裕章は、応えなかった。ただ、遠い目をしていた。
「叔父様の手……、冷たい」
裕章の無邪気な温もりに、哲臣は切ない痛みさえ感じた。
雪はまだ、降り続いていた。
【了】
「叔父様。今夜は、サンタクロースが来るんですよね」
束の間の至福の時間を味わっていた哲臣に、唐突に裕章が問いかける。
「そうだね。君が来ると信じていれば、きっとね」
その真意を探るように、哲臣は少年の純真な瞳を凝視し続けた。
「じゃあ、きっと来ますね。絶対だ!」
裕章を見つめる哲臣の眼差しは、充分に暖められたこの部屋以上に、暖かく穏やかだった。
叔父の肩に体を預けていた裕章は、そのままゆっくりと倒れ込んだ。長い足を持て余したように座る哲臣の膝に、少年はその形の良い頭を乗せる。子供っぽい邪心の無い動作のはずだが、やけに艶めかしい。そう思った哲臣の神経が、思わず尖る。組んだ足から、少年の体温が伝わってくる。
日頃大人びている少年ではあっても、やはり心細さから人恋しさを感じているのだろう。だから、知らず知らずの内に、叔父の温もりに甘えたくもなっているに違いない。
「サンタクロースって、北極に住んでるって、本当かな」
何を思ってか、裕章はそう言った。
「どうかな。……でも、北極とはまた遠い所だね」
哲臣は、愛しむように心弱い甥の頭に手を置いた。
「サンタクロースは……、僕のことを知っているんだろうか」
「ああ、必ず知っているよ。君の欲しい物だって、知っているはずさ」
裕章の、欲しいもの。
裕章の、望むもの。
それを与えることは、今は誰にも出来ないだろう。けれど、それが人外の不思議な力であるなら……。決して単なるファンタジーとしてでは無く、切なる願いとして、裕章はサンタクロースを信じたかった。
哲臣の長い指先が、裕章の柔らかで素直な髪を絡め取る。
「君も、もうすっかり大人になってしまったと思っていたけれど……。君は、君のままだ。いつまでも、これからも……」
裕章は、ふっと顔を上げ、哲臣の端整な面差しを見つめた。
異国の血を感じさせるほど、目鼻だちのはっきりとした、華やかな美貌を持つ哲臣だった。それだけではない。学生時代に水泳部で鍛えたという、日本人には珍しい、イタリアンモードのスーツも見事に着こなす恵まれた肢体。絵画を中心とした芸術や文化を学ぶためにヨーロッパに留学していた時も、その圧倒的なルックスと、知性と、社交性をもってしてコンプレックスを跳ね除け、あらゆる日本人から羨望を受けていた。
裕章にとって、この素晴らしく優れた叔父は、自慢であり、自身の憧れでもあった。
「僕が、大人?」
誰よりも自分を認めて欲しいはずの叔父ではあったが、今はその言葉に不安な翳りが付きまとう。
「でも……、大人になってしまったら、サンタクロースは来なくなるでしょう?」
そう言って裕章は、窓の外の雪景色に目をやって、その表情を曇らせた。
「……もう、今夜は、来ないかもしれない」
「裕章……」
いたいけな少年の不安を、哲臣は笑い飛ばすことが出来なかった。
「裕章……。君は、どんなプレゼントが欲しいんだい?」
「……」
裕章のためらいが、言葉を見失う。それを口にすることは、なんだかいけないことのようで……。
「お父様とお母様……。特に今は、お母様がお元気になることかな」
哲臣が、裕章の心を慮って、その胸の内を敢えて言葉にしてみせた。
無言のままの裕章だったが、濡れたその頬が雄弁に彼の心を物語っている。
そんな裕章を見ているうちに、哲臣は疑問が浮かぶのを禁じ得ない。
裕章を出産し、夫・隆生(たかお)を失って以来、姉の志保子は心身共に弱っていった。その結果、息子の養育などはすっかり放棄していたし、弟である哲臣の目から見ても、裕章に対して母親らしいことをしているようには思えなかった。
それでもやはり、志保子は裕章にとってはたった1人の母親だったのだ。
そこまで思って、哲臣は苦々しく口元を歪めた。
志保子は、幼い頃から愛されることに慣れ過ぎて、自分以外の人間を愛するという情熱に欠けていた。たった1人の実子である裕章に対して淡々としていられるのも、そのせいだと思われる。そして、早世した夫に対しても、志保子はそれほどの深い愛情を示したことは無かった。
哲臣は、思う。
(それでも、みんな志保姉さんを愛している。姉さんでなくてはならないんだ。他の誰が代わりを務めることなんて出来ないんだ)
「お母様、すぐにお元気になられるんでしょう?」
すがるように裕章が、叔父を問い詰める。少年の純真な眼差しには、ただ一途にその思慕しか無かった。
「そんなに、お母様が恋しいのかい、裕章?」
哲臣の声は、心なしか冷やかだった。
「……叔父様の、仰りたいことは分かっているつもりです。お母様には、お体を大事にして頂かなくてはならないんだから、僕がわがまま言ったりしちゃ、いけないんですよね」
聞き分けの良すぎる裕章が、これほどまでに自制を強いられてきたとは、痛々しいことだった。
「でも! ……でも、毎年クリスマスにはお母様がいらしたのに……。このままじっとしていたら、僕の知らないうちに、お母様がどこかへ行ってしまわれるような気がして。お父様のように、お会い出来ないまま、僕にお母様がいるってことすら消えてしまいそうで……」
少年は、寂しいのだろう。両親の愛に、飢えているのだろう。幼い時に父を失い、今また母を失うことになるかもしれないという恐れが、彼の繊細な神経を切り裂いているに違いない。そんな裕章の心を、哲臣も痛いほど分かる。けれど一方で、言いようのないもどかしさを覚えるのだ。
自分は、どれほどこの少年を慈しんでも、少年にとっての「絶対」にはなれない。誰よりも愛を捧げているのに、その享受者にとって必要としているのは自分ではないのだ。自分は、決して姉・志保子に取って代わることなど出来ないのだ。
今も、そうだ。
あの時も、そうだった……。あの時も、狂わんほどの想いを捧げたにもかかわらず、選ばれたのは哲臣ではなく、姉の志保子だったのだ。
命さえも惜しくないと思うほど愛していた。他には、何1つ欲しいものはなかった。ただ、あの人だけ……。心から真に欲したのは、あの人1人だった。
「裕章。ピアノを弾いてくれないか」
哲臣は、あの人の面影を残した裕章の涙の零れる頬に手を寄せた。
「曲は、そう……、シューマンの『トロイメライ』がいい」
哲臣は、夢を見ていた。愛しい少年は自分の傍らにいて、決して裏切ることなく、ただ自分だけを必要として、それだけで幸せで……。だが、それは夢だ。
いつも、誰かを愛することは、夢を見ることなのかもしれない。届くことを知らない、1人よがりな夢。そのことを、10数年前、この少年の父・隆生に愛を告げ、拒絶された時に哲臣は痛切に実感したのだ。
「きっと、お父さまも聴きたがっていらっしゃるはずだ……」
裕章は、応えなかった。ただ、遠い目をしていた。
「叔父様の手……、冷たい」
裕章の無邪気な温もりに、哲臣は切ない痛みさえ感じた。
雪はまだ、降り続いていた。
【了】
2/2ページ