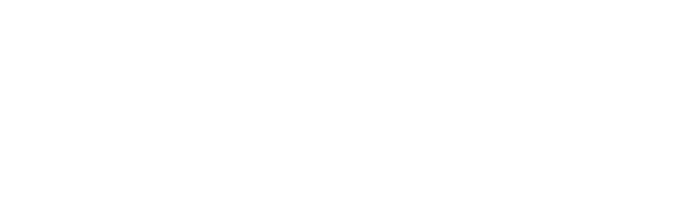聖夜
窓の外は、白い世界。
眩いような白片のきらめきの、向こうに見えるはずの港の風景も今日は消える。この無垢な白さが、意識までも封じ込めようとするかのようで……。聖夜と言えども、こんな静寂とした白い闇の中では、狂気すら伴うのかもしれない。
けれども、窓の中の世界は平和そのものだった。暖かなその部屋の内は、小さな安らぎに満ちている。
「叔父(おじ)様」
まるで白魔に支配されたような今宵、その悪意に押しつぶされることなく存在する小さな幸せの中に、聡明な瞳をした少年が1人……。
それは、印象的な瞳を持つ少年だった。子供の、無邪気なだけのそれではなく、かと言って、大人たちの多くが宿している類のものとも違う。強靱な意志の光に満ちながら、哀しいほど澄んだ孤高の瞳。これほど理知的でありながら、情緒的な繊細さを持つ不可思議な眼差し。ただ美しいだけでなく、少年は魅惑的だった。
その、利発そうに引き締められた口許に、純粋な笑みが浮かんだ。これほど素直で穏やかな笑顔を、この少年が見せるのは珍しいことだ。
「どうした、裕章(ひろあき)。私と2人だけのクリスマスでは、やはり寂しいのかい?」
中学に入学して初めてのクリスマスを、裕章少年は、母方の叔父と2人きりで迎えていた。いつもは大人びた表情を崩さない、優等生然とした裕章が、今夜に限ってはこれほどまでに無邪気に微笑んでいる。
「いいえ、叔父様。お祖母様には申し訳有りませんけれど、お祖母様の賑やかなばかりのパーティーより、僕は、叔父様とこうして静かに過ごしているほうが、ずっと好きです」
裕章は、国際貿易港を見下ろす丘の上の、旧家の1人息子として生まれた。父は代々の貿易商を手広く営んでいたが、裕章が3歳の時に突然他界した。まだ、29歳の若さだった。そして、元来体が丈夫ではなかったという母も、以来入退院を繰り返す事となってしまった。そのため、岩嶋(いわしま)家の跡継ぎとしての裕章の養育に主に当たったのは、父方の祖母・珠生であった。
「今頃、家では、昔からお付き合いのある方々が集まって……。お祖母(ばあ)様は、皆さんへのおもてなしで、座る暇もない位に忙しくなさってますね、きっと」
裕章は、切れ長の艶のある目を細めて、その情景を思い浮かべた。
名家の出自である岩嶋家では、毎年、各分野でそれなりのステータスを認められた人々を多く招いて、クリスマス・イヴの宵に華やかなパーティーを催すことを恒例としている。政財界はいうに及ばず、教育・研究分野から文化・芸術の方面に至るまで、長年岩嶋家が後援、出資してきた結果である。近年こそ一時の隆盛から見れば、質素な集まりになってはきたものの、それでもまだ名門としての岩嶋家の影響力は、なお十分生き残っている。
そのため、本来ならば次期岩嶋家当主として、若年と言えども裕章もそのパーティーに出席するはずだった。
「本当に良かったのか? 私なんかに着いて来て」
「でも、叔父様……」
裕章は、泣きそうな笑顔で、困ったように小首を傾げて見せた。
「お母様が、クリスマスにまで入院なさってたのは、これが初めてなんですよ」
無理をした笑みに、たった1人の叔父である三条(さんじょう)哲臣(あきおみ)の心が痛む。
彼の姉であり、裕章の母である志保子(しほこ)の病は、安静にさえしていれば自宅療養も不可能なことではなかった。ただ、早くに夫を亡くした婚家での静養は、本人も周囲の者も妙な気苦労に煩わされる。そこで志保子自身の希望もあって、彼女には都会の喧騒を離れたサナトリウムの特別室で、別荘暮らしのような優雅な生活が与えられていた。
もちろん無理さえしなければ、志保子は充分に裕章の側に居られるのだ。だが、それは毎年クリスマスから正月までとに決められていた。
岩嶋家の嫁として、当家の重要行事の一つであるクリスマスパーティーに出席するために、志保子は毎年この時期にだけ帰宅する。そして正月の3が日を終えると、また遠いサナトリウムへと発つのである。このわずか2週間足らずの間だけ、裕章は母親の側に居ることが許されるのだった。
しかし今年は、岩嶋家に嫁いで初めて、志保子は恒例のパーティーを欠席した。ついに病床で年末年始を迎えることになってしまったのである。
母の病状を思い、裕章のあの瞳は暗かった。
「裕章……」
哲臣は、自分の傍らへ少年を招いた。
三条家もまた、華族の流れを汲む名門の家柄である。両親は共に事故で失った。残されたたった2人の姉弟だったが、姉・志保子は無事岩嶋家に嫁ぎ、今は哲臣が当主としてたった1人で三条家を支えている。三条家は、名家ではあったが特に家業を持たなかった。戦後長くは、正に没落貴族の斜陽さながらと言えた。けれど、哲臣には才覚があった。姉が岩嶋家と縁を結んでからと言うもの、さらにその才は開花した。今では哲臣は、趣味が高じた画廊を始め、幾つかの事業を展開する程となっていた。誰にも邪魔されない夜を過ごすことが出来るこの心地よい空間も、哲臣が自分自身の力だけで手に入れた三条家の別荘である。
夜となってもなお、白い吹雪は空を覆い隠す。隔絶された別世界。まるで、この世には2人だけしか存在しないかのような錯覚。
哲臣が気に入ってわざわざ取り寄せたという、19世紀初頭のイギリスで作られた東洋趣味のある、大きな安楽椅子。そこに身を沈めるようにして座っていた裕章は、叔父に手招きされ、喜々として弾かれたように椅子から飛び出した。
早くに父を亡くした裕章にとって、父に代わる最愛の叔父だった。母の体調を憂い、沈みがちな裕章であるが、それでも、初めて迎えた叔父との2人だけのクリスマスに、自然と高揚する気分を抑えられない。
ゆったりとソファーに寛ぎ、年代物のブランデーの芳香を楽しんでいた哲臣の側に、はにかみながら裕章が寄り添った。
「僕、お祖母様が、ここへ来ることを許して下さるなんて、信じられなかったんです…本当は。今でも、ちょっと不思議。叔父様が、お祖母様に……」
小さく、裕章は呟いた。
母の病気のことを思い詰めている、僅か13歳の子供の裕章にとって、祖母の主催する壮麗なパーティーは、気晴らしどころか、かえって気の重い予定だった。その様子にいち早く気づいた哲臣が、裕章の祖母である岩嶋珠生(たまき)にその旨を申し出て、やっとこうして連れ出すことに成功したのである。
本来ならば、病弱な嫁でしかない志保子の実家である、三条家の弟の申し出など、気位の高い珠生が素直に受け入れるはずがなかった。だがさすがの珠生も、精彩のない愛孫を前にしては、折れる他なかったのだ。
「お祖母様も、君を心配して下さってるんだ。元気を出さなくてはね。お母様の耳にでも入ったら、きっとお母様も悲しまれるよ。お母様も1日も早く君の顔が見たいに違いない。君のように愛らしい息子を、1年も見ないでいられるわけないんだから」
哲臣は、優しく裕章の薄い肩を抱き寄せた。慰めるように、励ますように。
(姉さんも、これほど美しい者を遺して、逝けるはずがない)
眩いような白片のきらめきの、向こうに見えるはずの港の風景も今日は消える。この無垢な白さが、意識までも封じ込めようとするかのようで……。聖夜と言えども、こんな静寂とした白い闇の中では、狂気すら伴うのかもしれない。
けれども、窓の中の世界は平和そのものだった。暖かなその部屋の内は、小さな安らぎに満ちている。
「叔父(おじ)様」
まるで白魔に支配されたような今宵、その悪意に押しつぶされることなく存在する小さな幸せの中に、聡明な瞳をした少年が1人……。
それは、印象的な瞳を持つ少年だった。子供の、無邪気なだけのそれではなく、かと言って、大人たちの多くが宿している類のものとも違う。強靱な意志の光に満ちながら、哀しいほど澄んだ孤高の瞳。これほど理知的でありながら、情緒的な繊細さを持つ不可思議な眼差し。ただ美しいだけでなく、少年は魅惑的だった。
その、利発そうに引き締められた口許に、純粋な笑みが浮かんだ。これほど素直で穏やかな笑顔を、この少年が見せるのは珍しいことだ。
「どうした、裕章(ひろあき)。私と2人だけのクリスマスでは、やはり寂しいのかい?」
中学に入学して初めてのクリスマスを、裕章少年は、母方の叔父と2人きりで迎えていた。いつもは大人びた表情を崩さない、優等生然とした裕章が、今夜に限ってはこれほどまでに無邪気に微笑んでいる。
「いいえ、叔父様。お祖母様には申し訳有りませんけれど、お祖母様の賑やかなばかりのパーティーより、僕は、叔父様とこうして静かに過ごしているほうが、ずっと好きです」
裕章は、国際貿易港を見下ろす丘の上の、旧家の1人息子として生まれた。父は代々の貿易商を手広く営んでいたが、裕章が3歳の時に突然他界した。まだ、29歳の若さだった。そして、元来体が丈夫ではなかったという母も、以来入退院を繰り返す事となってしまった。そのため、岩嶋(いわしま)家の跡継ぎとしての裕章の養育に主に当たったのは、父方の祖母・珠生であった。
「今頃、家では、昔からお付き合いのある方々が集まって……。お祖母(ばあ)様は、皆さんへのおもてなしで、座る暇もない位に忙しくなさってますね、きっと」
裕章は、切れ長の艶のある目を細めて、その情景を思い浮かべた。
名家の出自である岩嶋家では、毎年、各分野でそれなりのステータスを認められた人々を多く招いて、クリスマス・イヴの宵に華やかなパーティーを催すことを恒例としている。政財界はいうに及ばず、教育・研究分野から文化・芸術の方面に至るまで、長年岩嶋家が後援、出資してきた結果である。近年こそ一時の隆盛から見れば、質素な集まりになってはきたものの、それでもまだ名門としての岩嶋家の影響力は、なお十分生き残っている。
そのため、本来ならば次期岩嶋家当主として、若年と言えども裕章もそのパーティーに出席するはずだった。
「本当に良かったのか? 私なんかに着いて来て」
「でも、叔父様……」
裕章は、泣きそうな笑顔で、困ったように小首を傾げて見せた。
「お母様が、クリスマスにまで入院なさってたのは、これが初めてなんですよ」
無理をした笑みに、たった1人の叔父である三条(さんじょう)哲臣(あきおみ)の心が痛む。
彼の姉であり、裕章の母である志保子(しほこ)の病は、安静にさえしていれば自宅療養も不可能なことではなかった。ただ、早くに夫を亡くした婚家での静養は、本人も周囲の者も妙な気苦労に煩わされる。そこで志保子自身の希望もあって、彼女には都会の喧騒を離れたサナトリウムの特別室で、別荘暮らしのような優雅な生活が与えられていた。
もちろん無理さえしなければ、志保子は充分に裕章の側に居られるのだ。だが、それは毎年クリスマスから正月までとに決められていた。
岩嶋家の嫁として、当家の重要行事の一つであるクリスマスパーティーに出席するために、志保子は毎年この時期にだけ帰宅する。そして正月の3が日を終えると、また遠いサナトリウムへと発つのである。このわずか2週間足らずの間だけ、裕章は母親の側に居ることが許されるのだった。
しかし今年は、岩嶋家に嫁いで初めて、志保子は恒例のパーティーを欠席した。ついに病床で年末年始を迎えることになってしまったのである。
母の病状を思い、裕章のあの瞳は暗かった。
「裕章……」
哲臣は、自分の傍らへ少年を招いた。
三条家もまた、華族の流れを汲む名門の家柄である。両親は共に事故で失った。残されたたった2人の姉弟だったが、姉・志保子は無事岩嶋家に嫁ぎ、今は哲臣が当主としてたった1人で三条家を支えている。三条家は、名家ではあったが特に家業を持たなかった。戦後長くは、正に没落貴族の斜陽さながらと言えた。けれど、哲臣には才覚があった。姉が岩嶋家と縁を結んでからと言うもの、さらにその才は開花した。今では哲臣は、趣味が高じた画廊を始め、幾つかの事業を展開する程となっていた。誰にも邪魔されない夜を過ごすことが出来るこの心地よい空間も、哲臣が自分自身の力だけで手に入れた三条家の別荘である。
夜となってもなお、白い吹雪は空を覆い隠す。隔絶された別世界。まるで、この世には2人だけしか存在しないかのような錯覚。
哲臣が気に入ってわざわざ取り寄せたという、19世紀初頭のイギリスで作られた東洋趣味のある、大きな安楽椅子。そこに身を沈めるようにして座っていた裕章は、叔父に手招きされ、喜々として弾かれたように椅子から飛び出した。
早くに父を亡くした裕章にとって、父に代わる最愛の叔父だった。母の体調を憂い、沈みがちな裕章であるが、それでも、初めて迎えた叔父との2人だけのクリスマスに、自然と高揚する気分を抑えられない。
ゆったりとソファーに寛ぎ、年代物のブランデーの芳香を楽しんでいた哲臣の側に、はにかみながら裕章が寄り添った。
「僕、お祖母様が、ここへ来ることを許して下さるなんて、信じられなかったんです…本当は。今でも、ちょっと不思議。叔父様が、お祖母様に……」
小さく、裕章は呟いた。
母の病気のことを思い詰めている、僅か13歳の子供の裕章にとって、祖母の主催する壮麗なパーティーは、気晴らしどころか、かえって気の重い予定だった。その様子にいち早く気づいた哲臣が、裕章の祖母である岩嶋珠生(たまき)にその旨を申し出て、やっとこうして連れ出すことに成功したのである。
本来ならば、病弱な嫁でしかない志保子の実家である、三条家の弟の申し出など、気位の高い珠生が素直に受け入れるはずがなかった。だがさすがの珠生も、精彩のない愛孫を前にしては、折れる他なかったのだ。
「お祖母様も、君を心配して下さってるんだ。元気を出さなくてはね。お母様の耳にでも入ったら、きっとお母様も悲しまれるよ。お母様も1日も早く君の顔が見たいに違いない。君のように愛らしい息子を、1年も見ないでいられるわけないんだから」
哲臣は、優しく裕章の薄い肩を抱き寄せた。慰めるように、励ますように。
(姉さんも、これほど美しい者を遺して、逝けるはずがない)
1/2ページ