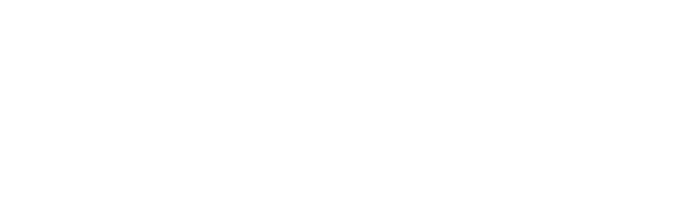生誕節是不安穏 ~クリスマスは落ち着かない~
その日、今年マッチングに成功した日中企業間の親睦を深めるためのクリスマス会に、開催側のスタッフとして駆り出された、桜花企画活動公司 の営業部第5班の主任・郎威軍 は、疲れ切って自宅に帰るなりベッドに倒れ込んだ。
(志津真 に…電話したい…)
せっかくのクリスマスイブだ。恋人に連絡を取りたいと思いながらも、パーティーでの飲酒と疲労のせいで、睡魔には勝てず、心を残したまま威軍は深く眠り込んだ。
同じ会社の営業部部長である、恋人の加瀬志津真 は、今夜は別のパーティーに参加していた。
上海の日本総領事館からも参加者がいる、上海に駐在する日系企業の交流団体主催の忘年会だ。元官僚で、領事館に出向していた経験を持つ加瀬は、このパーティーの参加者には顔見知りが多く、桜花企画活動公司の代表として参加する「仕事」が終えた後も、知り合いに誘われ、プライベートの2次会にも行くのが毎年恒例となっていた。
だから、クリスマスイブは毎年一緒には過ごせないのが加瀬志津真と郎威軍の当たり前となっていた。それでも大抵は、前日かクリスマス当日の25日の夜には一緒に過ごすのも、また恒例になっていたので、さほど苦にはしていない。いい歳をした大人の男2人にとって、クリスマスイブという日に、それほどの意味は無いのだ。
今さら、記念日が無ければ互いの絆を確かめられないほど、関係が浅い2人ではないのだから。
時刻は、深夜12時を過ぎて、クリスマスイブからクリスマス当日になった。
「…ん…?」
すっかり熟睡していたはずの郎威軍だったが、ベッドの中で違和感を覚えた。
完全に目覚める前の微睡 みの中で、威軍は何かが自分に触れたような気がした。
(夢?…、志津真?…)
横臥している自分を、背中から抱きしめられたような気がした。
(志津真…)
恋人に優しく包まれているような感覚に、威軍は幸せな夢を見ていると思った。
「!」
だが、次の瞬間、首筋に触れた濡れた感触に威軍はハッとして覚醒した。
「是什么(なんだ)?」
逃げようとして、背後から強く抱きしめられた。
「停(やめろ)!是誰(だれだ)!」
慌てる威軍を、背後の男は無遠慮に撫で回し、唇を押し付けてくる。
「?…志津真?志津真なんですか?」
怯える威軍が問いただすが、男は答えない。
「志津真なんでしょう?」
必死に威軍は身を捩 り、腕の中から逃れようとするが、男の力は動じない。
「イヤ、やめて下さい」
威軍の抵抗が真剣なのに気づいたのか、背後から抱きしめる男は笑いを堪 えながら、ようやく声を出した。
「心配はいらんって。サンタさんがプレゼント持って来たで」
その声に、やっと安心したのか威軍は抵抗をやめた。
「関西弁のサンタクロースですか」
ようやく落ち着いた威軍は、呆れたようにそう言った。
「そうやで。他には行かへん、お前だけのサンタさんや」
甘い声で囁き、抱きしめ、優しい愛撫で「サンタ」は郎威軍を宥 めた。
「もう…」
抵抗をやめてしまえば、「サンタ」からの拘束も緩み、威軍はくるりと体勢を換えると背後にいた男の顔を改めて確認した。
間違いなく、最愛の恋人がそこに居た。
「合鍵、渡してましたか?」
ようやく威軍は、どうして志津真がこんな時間に自分のベッドの中にいるのか、という不条理に気付いた。
「ん~、でも、合鍵作ってエエよ~って感じで貸してくれたことあったやん」
澄ました顔で言う志津真に、覚えの無い威軍は少し眉を顰めた。
そう言えば、2人で一晩過ごした後、早朝に急なトラブルで威軍がオフィスに呼び出されたことがあった。その時に、後から出勤する志津真に鍵を預けて、先に出たことはある。
「誰が合鍵を作っていいと言いましたか」
確かに、その後オフィスでこっそりと鍵を返却されたが、その時にはすでに合鍵を作っていたと言うのか。
さすがに加瀬部長。周到な男である。
「俺たちの仲で許可がいるなんて、考えてもみなかった~!」
大げさにそう言うと、子供のように唇を尖らせ、がっかりした表情をして、甘える子犬のような眼差しで、志津真は威軍に許しを請うた。
「私から、手渡したかったのに」
ちょっと機嫌を損ねた顔をして、小悪魔っぽく言う威軍に、志津真はドキリと魅了された。
これが、完全に計算でなく、無意識でやっているのが郎威軍という男の恐ろしさだ。
「ゴメンな」
なんだかよく分からないまま、志津真は威軍の美貌にひれ伏すように謝罪した。
「許してあげます」
そう言って、威軍は志津真に口づけた。最初は軽く触れあうだけだったキスが、繰り返すうちに、激しく、深くなっていく。
「さあ、…サンタのオジサンからのプレゼントやで」
柔らかい声で、志津真が威軍の心と体を擽 る。
そして、威軍のお気に入りのネイビーブルーのシルクのパジャマのボタンに指を掛けた。
「サンタが、私から奪ってどうするんです」
脱がされかけた手を掴んで、威軍が「サンタ」の暴挙を制止した。
「サンタのオジサンしか出来ひんプレゼントやで」
パジャマの上から威軍の身体の線をなぞるように触れ、志津真は恋人の官能を引き出そうとした。
そして腰から太腿に手を這わせると、志津真は露骨に好色な笑みを浮かべた。
「一番欲しいモン、あげるで」
相変わらず低く抑えた声が堪らなくセクシーで、威軍は性感を刺激される。
「私が、欲しい物を、知って、いるん、ですか?」
息も絶え絶えになりながら、威軍は逆に志津真の衣類をはぎ取ろうとしていた。
「サンタのオジサンとの、激しいセックス?」
意地悪く志津真が言うと、夢中になっていた威軍が、苛立ちを隠すことなく答えた。
「そんなもの、欲しがるわけがないでしょう」
勢いに任せ、威軍は志津真のシャツを脱がせ素肌を顕わにし、その逞しい胸に頬ずりをした。
「欲しいのは…コレだけ…です」
物欲しげな切ない声で、威軍が告白した。そんな一途さが愛しいが、それだけでは物足りないらしい志津真は、悪ふざけをやめようとはしない。
「知らないサンタのオジサンのナニが、欲しいって?」
「やめて下さい…」
志津真が、わざと猥褻な感じになるように、恋人の美しい体を弄る。その手を、いつもならウットリと身を任せるはずの威軍が振り払った。
「行きずりの、見知らぬオジサンに楽しませてもらうのは、どうや」
「やめて、下さいって、…言ってるじゃないですか」
そんな抵抗も、自分を煽るための演技だとさえ思い、さらに恋人が愛しいと思った志津真は、かなり強引に威軍の身体を開こうとした。
「エエやないか!」
とうとう志津真は、卑猥いな言い方をして、ねっとりと舌でいたぶるように威軍の艶やかな頬を舐め上げた。
「イヤです!」
その志津真の顔面に掌を押し付け、威軍は強い力で引き離した。そこまでされてもなお、志津真はまだ威軍が焦らして誘っているのだと信じて疑わなかった。
(随分と凝ったクリスマスプレゼントやないか)
薄ら笑いを浮かべ、志津真は単なるスケベ親父となり切って、威軍の抵抗を抑え込んだ。
「ほら、すぐに気持ちエエって言わせてやるから…」
志津真は威軍の両腕を掴み、ベッドに仰臥で押し付けると、膝で威軍の腹に乗り上げ、動きを封じた。
「イヤだ!ヤメろ!」
らしくない大きな声を出して威軍が拒絶する。その叫びにさえ興奮して、志津真は手を緩めない。
「欲しいんやろ」
すでにその気になっている部分を押し当てるように、志津真が腰を動かした。
「それ以上したら…!」
怒りが抑えきれないのか、威軍が低い声で恋人を見据えた。その眼は真剣で、明らかに志津真を非難していた。
「それ以上は、レイプですからね!」
「……は?」
きつい言葉に、さすがに威軍の激高を察して、志津真は我に返った。
威軍はかなり腹を立てている様子だが、その眼差しは冷え冷えとしていて、完全に志津真を拒絶していた。
驚いて動きを止めた志津真が、ようやく力づくで掴んでいた腕を放し、馬乗りになっていた体から離れた。
「私は、本気でに拒否しているんです。どうしてそれが分からないんですか!」
呆然となった志津真が自分の横に座り込んだ途端、威軍は勢いよく身を起こし、詰め寄るように叫んだ。
「あ、あの…ウェイウェイ?この程度の…」
言い訳するように志津真が口を開くが、すぐに威軍に言質を取られる。
「この程度?いつも私を尊重すると言いながら、本気で拒絶している時に、この程度って言いましたか?」
そこに居たのは、「羞花閉月」の譬えそのままの、絶世の美貌ゆえに一層冷徹に見える、完璧な「アンドロイド」だった。
「いや、…あの…、その…」
知り合って以来、これほど冷ややかな威軍を見たのは、志津真もこれが初めてだった。「怒り」も確かに感情の1つであるのに、それを顕わにしてなお、威軍は冷ややかだ。それほどに本気で怒っているということかもしれない。
「な、何、怒ってんの?」
付き合って以来、幾度となく志津真は威軍を怒らせている。志津真の子供っぽい態度が、生真面目な威軍の気持ちを逆なでするからだ。だが、目の前のこれは、そんな生易しい状況ではない。
「はい?今、なんと?」
志津真は、初めて恋人を本気で怒らせたのだった。
「い、いや…別に…」
もう志津真は一言たりとも返せない。
「貴方、今、私に何をしようとしたのか自覚しているのですか」
部下たちがゾッとするという、例の凍り付くような視線と声で、威軍が志津真に言った。
「何って…」
2人はベッドの上に向かい合って座っていた。完全に志津真が威軍に説教を喰らっている様相だ。
「貴方は、私が本気で拒否しているのに、無理やりに性交に至ろうとしたのですよ」
「…スンマセン…」
こんなに気を悪くするとは思いも寄らず、志津真は頭も上げられない。
「しかも、なぜ拒否してるのかも、分かってない」
大人しくなった志津真に、威軍の怒りも通り越したのか、表情が少し変わった。
「私が、どんな気持ちで…」
そう言うと、威軍の美貌は曇り、艶やかな唇を噛んだ。
「ウェイ…」
威軍の顔色に苦痛を読み取って、志津真はようやく自分の無邪気なジョークが、どれほどに恋人を傷つけたのかに気付いた。
「バカ…」
小さく呟いて、威軍は俯いてしまった。
(ウェイ!泣いてる?)
志津真は思わず、何かを言う前に、心細げな威軍をその胸に抱き寄せていた。
「ゴメン…、ゴメンな」
抱き締められた威軍もまた、両手を志津真の背中に回した。
「たとえ…」
聞き逃しそうな小さな声で、威軍が打ち明ける。
「たとえ、冗談でも、私は『加瀬志津真』以外の誰かとなんて…しません」
その言葉に志津真はハッと胸を突かれた。
恋人以外の「知らないサンタのオジサン」に抱かれることが、それほどにイヤだったのだ。本気で怒るほど。
理由が分かると、笑い飛ばせるほどつまらない理由だ、と志津真は思った。だが、それを口には出さない。
たったそれだけのこと。
そうは思うが、その潔癖さ、生真面目さが志津真が愛する郎威軍だと知っているから簡単に笑えない。
腕の中の恋人への愛しさが募り、志津真は落ち着いて囁いた。
「ゴメン。お前のこと、ちゃんと分かってなかった」
ただの言葉遊びだと、ふざけただけだと言うのは容易い。だが、郎威軍はそうじゃない。
こんな風なプライベートの時だけでなく、仕事でも同じだった。
郎威軍は、頑固で、融通が利かない。でもそれは、自分に正直で一途だとも言える。
仕事で言えば、もっと妥協すればラクになるだろう。それをしないのは、若さだと志津真は思う。
41歳になった志津真には、仕事のやり方が分かっている。手抜きと言えばそうなのだが、無駄なく、力まず、無難にまとめることが出来るのだ。
そんな志津真から見て、32歳の威軍はまだ若い。
若さは未熟と考えがちだが、それだけではない。果敢に挑戦する傍若無人さも、若さの特権だ。
威軍には、それがある。情熱や激情は見せないものの、信念を諦めない強さが若い威軍にはある。
それが、志津真は愛しかった。
そして、そんな一途で正直な気持ちで、自分は愛されているのだと改めて気づかされた。
「ありがとう…」
志津真もまた、真っ直ぐな威軍の気持ちに添うように、真摯に言った。
「俺も、大事なウェイが、俺以外の誰かに抱かれるのはイヤや」
「しづま…」
やっと自分の気持ちが届いたのだと威軍は安心した。
全てをリセットするように、2人はそっと口づけた。
「クリスマス、やり直そうか」
優しい気持ちで抱き合い、志津真が言うと、やっと機嫌を直した威軍が笑った。
「そんなの、どうでもいいんです」
そう言って志津真の腕の中にいた威軍が、そっと恋人を押し倒した。
ベッドで威軍が上になったまま抱き合って、2人はしっとりと見つめ合った。
「郎威軍を抱いていいのは、加瀬志津真だけですよ」
身を起こして、威軍は言った。そして、自分でパジャマのボタンを外
し、眩しいような美しい素肌を晒した。
「お前を抱くのは俺だけ。俺に抱かれるのはお前だけ。そうやろ?」
威軍は頷くと、ほんの少し頬を緩め、体を倒して、ちゃんと理解できたご褒美のキスを志津真に与えた。
「ちゃんと、お前のこと愛してるから…」
志津真はそう言って、もう一度恋人を腕の中に引き戻した。
「貴方になら、何をされてもいいんです」
志津真と威軍は幸せそうに微笑んで、その先の行為に没頭した。
今夜は、クリスマス。
凍てついた上海に、珍しく雪が降っていた。
(
せっかくのクリスマスイブだ。恋人に連絡を取りたいと思いながらも、パーティーでの飲酒と疲労のせいで、睡魔には勝てず、心を残したまま威軍は深く眠り込んだ。
同じ会社の営業部部長である、恋人の
上海の日本総領事館からも参加者がいる、上海に駐在する日系企業の交流団体主催の忘年会だ。元官僚で、領事館に出向していた経験を持つ加瀬は、このパーティーの参加者には顔見知りが多く、桜花企画活動公司の代表として参加する「仕事」が終えた後も、知り合いに誘われ、プライベートの2次会にも行くのが毎年恒例となっていた。
だから、クリスマスイブは毎年一緒には過ごせないのが加瀬志津真と郎威軍の当たり前となっていた。それでも大抵は、前日かクリスマス当日の25日の夜には一緒に過ごすのも、また恒例になっていたので、さほど苦にはしていない。いい歳をした大人の男2人にとって、クリスマスイブという日に、それほどの意味は無いのだ。
今さら、記念日が無ければ互いの絆を確かめられないほど、関係が浅い2人ではないのだから。
時刻は、深夜12時を過ぎて、クリスマスイブからクリスマス当日になった。
「…ん…?」
すっかり熟睡していたはずの郎威軍だったが、ベッドの中で違和感を覚えた。
完全に目覚める前の
(夢?…、志津真?…)
横臥している自分を、背中から抱きしめられたような気がした。
(志津真…)
恋人に優しく包まれているような感覚に、威軍は幸せな夢を見ていると思った。
「!」
だが、次の瞬間、首筋に触れた濡れた感触に威軍はハッとして覚醒した。
「是什么(なんだ)?」
逃げようとして、背後から強く抱きしめられた。
「停(やめろ)!是誰(だれだ)!」
慌てる威軍を、背後の男は無遠慮に撫で回し、唇を押し付けてくる。
「?…志津真?志津真なんですか?」
怯える威軍が問いただすが、男は答えない。
「志津真なんでしょう?」
必死に威軍は身を
「イヤ、やめて下さい」
威軍の抵抗が真剣なのに気づいたのか、背後から抱きしめる男は笑いを
「心配はいらんって。サンタさんがプレゼント持って来たで」
その声に、やっと安心したのか威軍は抵抗をやめた。
「関西弁のサンタクロースですか」
ようやく落ち着いた威軍は、呆れたようにそう言った。
「そうやで。他には行かへん、お前だけのサンタさんや」
甘い声で囁き、抱きしめ、優しい愛撫で「サンタ」は郎威軍を
「もう…」
抵抗をやめてしまえば、「サンタ」からの拘束も緩み、威軍はくるりと体勢を換えると背後にいた男の顔を改めて確認した。
間違いなく、最愛の恋人がそこに居た。
「合鍵、渡してましたか?」
ようやく威軍は、どうして志津真がこんな時間に自分のベッドの中にいるのか、という不条理に気付いた。
「ん~、でも、合鍵作ってエエよ~って感じで貸してくれたことあったやん」
澄ました顔で言う志津真に、覚えの無い威軍は少し眉を顰めた。
そう言えば、2人で一晩過ごした後、早朝に急なトラブルで威軍がオフィスに呼び出されたことがあった。その時に、後から出勤する志津真に鍵を預けて、先に出たことはある。
「誰が合鍵を作っていいと言いましたか」
確かに、その後オフィスでこっそりと鍵を返却されたが、その時にはすでに合鍵を作っていたと言うのか。
さすがに加瀬部長。周到な男である。
「俺たちの仲で許可がいるなんて、考えてもみなかった~!」
大げさにそう言うと、子供のように唇を尖らせ、がっかりした表情をして、甘える子犬のような眼差しで、志津真は威軍に許しを請うた。
「私から、手渡したかったのに」
ちょっと機嫌を損ねた顔をして、小悪魔っぽく言う威軍に、志津真はドキリと魅了された。
これが、完全に計算でなく、無意識でやっているのが郎威軍という男の恐ろしさだ。
「ゴメンな」
なんだかよく分からないまま、志津真は威軍の美貌にひれ伏すように謝罪した。
「許してあげます」
そう言って、威軍は志津真に口づけた。最初は軽く触れあうだけだったキスが、繰り返すうちに、激しく、深くなっていく。
「さあ、…サンタのオジサンからのプレゼントやで」
柔らかい声で、志津真が威軍の心と体を
そして、威軍のお気に入りのネイビーブルーのシルクのパジャマのボタンに指を掛けた。
「サンタが、私から奪ってどうするんです」
脱がされかけた手を掴んで、威軍が「サンタ」の暴挙を制止した。
「サンタのオジサンしか出来ひんプレゼントやで」
パジャマの上から威軍の身体の線をなぞるように触れ、志津真は恋人の官能を引き出そうとした。
そして腰から太腿に手を這わせると、志津真は露骨に好色な笑みを浮かべた。
「一番欲しいモン、あげるで」
相変わらず低く抑えた声が堪らなくセクシーで、威軍は性感を刺激される。
「私が、欲しい物を、知って、いるん、ですか?」
息も絶え絶えになりながら、威軍は逆に志津真の衣類をはぎ取ろうとしていた。
「サンタのオジサンとの、激しいセックス?」
意地悪く志津真が言うと、夢中になっていた威軍が、苛立ちを隠すことなく答えた。
「そんなもの、欲しがるわけがないでしょう」
勢いに任せ、威軍は志津真のシャツを脱がせ素肌を顕わにし、その逞しい胸に頬ずりをした。
「欲しいのは…コレだけ…です」
物欲しげな切ない声で、威軍が告白した。そんな一途さが愛しいが、それだけでは物足りないらしい志津真は、悪ふざけをやめようとはしない。
「知らないサンタのオジサンのナニが、欲しいって?」
「やめて下さい…」
志津真が、わざと猥褻な感じになるように、恋人の美しい体を弄る。その手を、いつもならウットリと身を任せるはずの威軍が振り払った。
「行きずりの、見知らぬオジサンに楽しませてもらうのは、どうや」
「やめて、下さいって、…言ってるじゃないですか」
そんな抵抗も、自分を煽るための演技だとさえ思い、さらに恋人が愛しいと思った志津真は、かなり強引に威軍の身体を開こうとした。
「エエやないか!」
とうとう志津真は、卑猥いな言い方をして、ねっとりと舌でいたぶるように威軍の艶やかな頬を舐め上げた。
「イヤです!」
その志津真の顔面に掌を押し付け、威軍は強い力で引き離した。そこまでされてもなお、志津真はまだ威軍が焦らして誘っているのだと信じて疑わなかった。
(随分と凝ったクリスマスプレゼントやないか)
薄ら笑いを浮かべ、志津真は単なるスケベ親父となり切って、威軍の抵抗を抑え込んだ。
「ほら、すぐに気持ちエエって言わせてやるから…」
志津真は威軍の両腕を掴み、ベッドに仰臥で押し付けると、膝で威軍の腹に乗り上げ、動きを封じた。
「イヤだ!ヤメろ!」
らしくない大きな声を出して威軍が拒絶する。その叫びにさえ興奮して、志津真は手を緩めない。
「欲しいんやろ」
すでにその気になっている部分を押し当てるように、志津真が腰を動かした。
「それ以上したら…!」
怒りが抑えきれないのか、威軍が低い声で恋人を見据えた。その眼は真剣で、明らかに志津真を非難していた。
「それ以上は、レイプですからね!」
「……は?」
きつい言葉に、さすがに威軍の激高を察して、志津真は我に返った。
威軍はかなり腹を立てている様子だが、その眼差しは冷え冷えとしていて、完全に志津真を拒絶していた。
驚いて動きを止めた志津真が、ようやく力づくで掴んでいた腕を放し、馬乗りになっていた体から離れた。
「私は、本気でに拒否しているんです。どうしてそれが分からないんですか!」
呆然となった志津真が自分の横に座り込んだ途端、威軍は勢いよく身を起こし、詰め寄るように叫んだ。
「あ、あの…ウェイウェイ?この程度の…」
言い訳するように志津真が口を開くが、すぐに威軍に言質を取られる。
「この程度?いつも私を尊重すると言いながら、本気で拒絶している時に、この程度って言いましたか?」
そこに居たのは、「羞花閉月」の譬えそのままの、絶世の美貌ゆえに一層冷徹に見える、完璧な「アンドロイド」だった。
「いや、…あの…、その…」
知り合って以来、これほど冷ややかな威軍を見たのは、志津真もこれが初めてだった。「怒り」も確かに感情の1つであるのに、それを顕わにしてなお、威軍は冷ややかだ。それほどに本気で怒っているということかもしれない。
「な、何、怒ってんの?」
付き合って以来、幾度となく志津真は威軍を怒らせている。志津真の子供っぽい態度が、生真面目な威軍の気持ちを逆なでするからだ。だが、目の前のこれは、そんな生易しい状況ではない。
「はい?今、なんと?」
志津真は、初めて恋人を本気で怒らせたのだった。
「い、いや…別に…」
もう志津真は一言たりとも返せない。
「貴方、今、私に何をしようとしたのか自覚しているのですか」
部下たちがゾッとするという、例の凍り付くような視線と声で、威軍が志津真に言った。
「何って…」
2人はベッドの上に向かい合って座っていた。完全に志津真が威軍に説教を喰らっている様相だ。
「貴方は、私が本気で拒否しているのに、無理やりに性交に至ろうとしたのですよ」
「…スンマセン…」
こんなに気を悪くするとは思いも寄らず、志津真は頭も上げられない。
「しかも、なぜ拒否してるのかも、分かってない」
大人しくなった志津真に、威軍の怒りも通り越したのか、表情が少し変わった。
「私が、どんな気持ちで…」
そう言うと、威軍の美貌は曇り、艶やかな唇を噛んだ。
「ウェイ…」
威軍の顔色に苦痛を読み取って、志津真はようやく自分の無邪気なジョークが、どれほどに恋人を傷つけたのかに気付いた。
「バカ…」
小さく呟いて、威軍は俯いてしまった。
(ウェイ!泣いてる?)
志津真は思わず、何かを言う前に、心細げな威軍をその胸に抱き寄せていた。
「ゴメン…、ゴメンな」
抱き締められた威軍もまた、両手を志津真の背中に回した。
「たとえ…」
聞き逃しそうな小さな声で、威軍が打ち明ける。
「たとえ、冗談でも、私は『加瀬志津真』以外の誰かとなんて…しません」
その言葉に志津真はハッと胸を突かれた。
恋人以外の「知らないサンタのオジサン」に抱かれることが、それほどにイヤだったのだ。本気で怒るほど。
理由が分かると、笑い飛ばせるほどつまらない理由だ、と志津真は思った。だが、それを口には出さない。
たったそれだけのこと。
そうは思うが、その潔癖さ、生真面目さが志津真が愛する郎威軍だと知っているから簡単に笑えない。
腕の中の恋人への愛しさが募り、志津真は落ち着いて囁いた。
「ゴメン。お前のこと、ちゃんと分かってなかった」
ただの言葉遊びだと、ふざけただけだと言うのは容易い。だが、郎威軍はそうじゃない。
こんな風なプライベートの時だけでなく、仕事でも同じだった。
郎威軍は、頑固で、融通が利かない。でもそれは、自分に正直で一途だとも言える。
仕事で言えば、もっと妥協すればラクになるだろう。それをしないのは、若さだと志津真は思う。
41歳になった志津真には、仕事のやり方が分かっている。手抜きと言えばそうなのだが、無駄なく、力まず、無難にまとめることが出来るのだ。
そんな志津真から見て、32歳の威軍はまだ若い。
若さは未熟と考えがちだが、それだけではない。果敢に挑戦する傍若無人さも、若さの特権だ。
威軍には、それがある。情熱や激情は見せないものの、信念を諦めない強さが若い威軍にはある。
それが、志津真は愛しかった。
そして、そんな一途で正直な気持ちで、自分は愛されているのだと改めて気づかされた。
「ありがとう…」
志津真もまた、真っ直ぐな威軍の気持ちに添うように、真摯に言った。
「俺も、大事なウェイが、俺以外の誰かに抱かれるのはイヤや」
「しづま…」
やっと自分の気持ちが届いたのだと威軍は安心した。
全てをリセットするように、2人はそっと口づけた。
「クリスマス、やり直そうか」
優しい気持ちで抱き合い、志津真が言うと、やっと機嫌を直した威軍が笑った。
「そんなの、どうでもいいんです」
そう言って志津真の腕の中にいた威軍が、そっと恋人を押し倒した。
ベッドで威軍が上になったまま抱き合って、2人はしっとりと見つめ合った。
「郎威軍を抱いていいのは、加瀬志津真だけですよ」
身を起こして、威軍は言った。そして、自分でパジャマのボタンを外
し、眩しいような美しい素肌を晒した。
「お前を抱くのは俺だけ。俺に抱かれるのはお前だけ。そうやろ?」
威軍は頷くと、ほんの少し頬を緩め、体を倒して、ちゃんと理解できたご褒美のキスを志津真に与えた。
「ちゃんと、お前のこと愛してるから…」
志津真はそう言って、もう一度恋人を腕の中に引き戻した。
「貴方になら、何をされてもいいんです」
志津真と威軍は幸せそうに微笑んで、その先の行為に没頭した。
今夜は、クリスマス。
凍てついた上海に、珍しく雪が降っていた。
1/1ページ