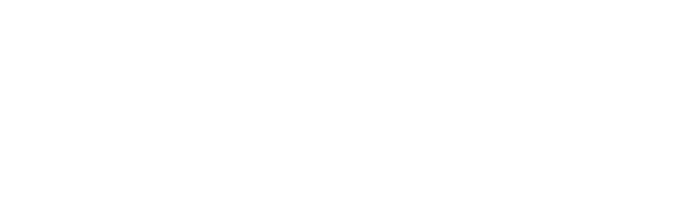第二章
玄関へと辿り着いた私はティフォンが扉を開けているのを見つめる。
何を言わなくてもいつもいつも私の行動の先を読めて行動ができる。執事としては主の手を煩わせないのが役割なのだが、それ以上にティフォンは私のことを理解してくれている。
ティフォンが開けてくれた扉から入り、大理石の床に立つ。その時ティフォンは私に手を差し伸べる。
昔からヒールでこの床を歩くのが苦手だった。それからティフォンはいつもカーペットが敷いてある廊下までエスコートをしてくれる。
そしてこう言うのだ。
「お嬢様、足元お気をつけください」
想像したこととまったく一緒のことを言うティフォンにクスッと笑って彼の手に自分の手を重ねる。
ティフォンも不思議そうな顔をしながらも微笑む。
そのまま自室へと戻った私は制服を脱いでティフォンに手伝ってもらいドレスを身に纏う。
ふぅ、とソファに腰を掛けると紅茶を淹れながらティフォンが口を開いた。
「お嬢様、使用人の件で国王陛下に謁見の許可を頂きに行きましょうか?」
『ええ、お願い』
「かしこまりました。側近のカリファー卿に聞いて参ります。お嬢様はごゆっくりお寛ぎください」
ティーカップを机に置いて姿勢を正して微笑むティフォンにひらひらと手を振る。
そのまま部屋を出ていく背中を見送ってティーカップを口元へ運ぶ。
今日は疲れが取れるハーブティーだな、と香りで判断してひとくち飲む。
使用人を付けるって話は正直口から出まかせのようなものだった。強がって発言をしてしまって今となっては後悔しかない。ティフォンと過ごす時間を減らしたくないのになぜか真逆のことを言ってしまうこの口を今すぐ縫いたい気分だ。
『はぁぁー……。ティフォンが私以外の執事になるなんて考えたくない…』
頭を振って変な妄想をする思考をかき消す。
次に浮かぶのは歴史書に描かれていた絵だった。身分差婚の末に不幸になったと書かれたふたり。
最悪の場合は、ティフォンとあのふたりを再現するしかないな、と考えながら紅茶を飲み干した。
コンコンッ
『ティフォンかな、入って』
開かれた扉の方を見やる。
だがそこには想像していた人物は立っていなかった。
煌びやかな軍事服を身に纏った生きてきた中で公の場でしか挨拶すらも交わしたことのない人物。
『…ヴァスカル王太子様…』
「ふんっそんなよそよそしい呼び名ではなく昔のようにお兄様とでも呼んだらどうだ?第三王女様?」
『…ご挨拶申し上げます母なる国ティア王国の瞬く若き太陽ヴァスカル王太子様』
スカートを手でつまみ上げて挨拶をする。
ヴァスカル王太子。つまり私の兄だ。私に兄弟で男児はヴァスカル王太子のみ。つまり次期国王と言っても過言ではない。
そんな人物が今まで第三王女の私を訪ねたことも挨拶すら返してこなかったのになんのつもりで今日ここに来たのか見当もつかない。
『申し訳ありませんが今執事が席を外しており、恐縮ですが私しが紅茶をお淹れします。どうおお席でおくつろぎください』
「ふん、ろくに淹れたこともないやつの茶など要らん。用件だけ済ませたら帰る。さっさと座れ」
『…失礼します』
本当誰に似てこんな憎たらしく育ったのかしら。親の顔が見てみたいわ。
表情に出ないように気を付けて王太子の対面の席に腰を掛ける。
私が座ったことを確認すると王太子はふてぶてしく話し始めた。
「第三王女、お前はいくつになったんだっけか」
『はい。15になります』
「もうそんなでけぇのか。じゃあもう結婚のことを考え始めてもいいころだな」
『まだまだ未熟者でございます』
「お前がどこに嫁ぐかは俺が決めてやる。貿易に有効な国か、王族の勢力を高める貴族に売り飛ばすのもありだと思ってるんだ。これ以上お前が王族の名誉に泥を塗るようなことをしてほしくないのでな」
私の噂を知っているのだろう。執事しかいないのは私のせいではないのに噂が立てば私のせいとなる。
反応を悟られてはいけない。何も王太子に見せてはいけない。たったひとつのボロが私の立場をさらに悪くさせることはわかっている。
私は落ち着いた動作で紅茶を飲んだ。手は震えていない。所作に問題はない。表情も崩れていない。紅茶の味はしない。なんならもう冷めている。
せっかくティフォンが愛情込めて淹れてくれた紅茶がぁ…。
『王太子様。未熟な私しのためのお気遣いありがとうございます。ありがたく頂戴します』
「ふんっ光栄に思え。そして国のために尽くすんだな。決まり次第側近に報告させに行く。デビュタントに出たら速攻で嫁入りだ。覚えとけよ」
『わかりましたわ。ヴァスカル王太子様』
私の反応が気に食わないのか腹立たしそうに背中を向けて歩き出す王太子。
その背中に刺さるように視線を向ける。
扉が閉まる、その瞬間まで。
.