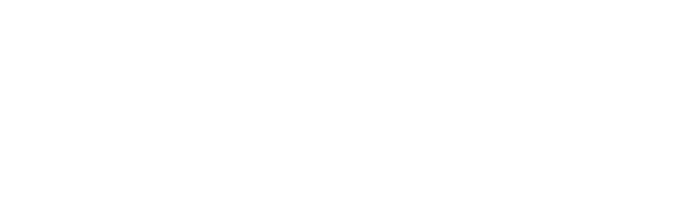第二章
『ねぇティフォン』
馬車の中で対面に座るティフォンに話しかける。なんとなく、いつものように顔を見て話したら泣いてしまいそうなので頬杖をついて外を見る。
学園への通学途中にある綺麗な花畑をちょうど通過するところだった。
今の心境にはこのきれいな花畑を見ても心に響かなかった。入学当初は興奮してティフォンに伝えていた時もあった気がする。
「いかがなさいました?お嬢様」
『私がお嫁に行くとき、ついてきてくれる?』
「…お嬢様。申し訳ありません。それはお嬢様の幸せのためにはならないのです。私はいつまでもお嬢様に幸せでいてほしいのです」
『私は…!!』
ティフォンの言葉に咄嗟に身体が動いた。
バッとティフォンの方を向いて彼の表情を見て言葉が止まった。いつもと変わらぬ微笑みを浮かべている。
行き場を失った言葉と勢いは無理矢理喉の奥に突っ込んで目を反らした。
『…私、使用人を雇うわ』
「…え?」
『いつまでもティフォンに甘えてばかりもよくないわ。使用人を雇えばティフォンにも今まで上げられなかった休暇もあげられるようになる。たまには実家に帰るなり行きたいところへ旅行へ行けるわ』
「…私はいつでもお嬢様のことしか考えておりませんよ。お嬢様が
なさることに私は意見など言いません」
『ふんっ…口ばかり上手くなるのね、ティフォンは』
目頭が熱くなるのを必死に抑えながら今できる精いっぱいの皮肉を言う。本当はもっとティフォンを困らせることを言いたくて言いたくてたまらないのに。
なんなら結婚でも申し込みたい。
『…』
「お嬢様、お嬢様はどうしたいのですか?」
『…なにがよ?』
「失礼ながら申し上げます。ご結婚願望はおありなのですか?」
『…ないわよ。今までそんなもの考えたこともないわ』
妄想の中でならティフォンと50回は挙式したことあるけど、と心の中でつぶやく。
「そうですか、出過ぎたことを申し上げてしまい申し訳ありません」
『…ティフォンは、どうするつもり?』
「フフッ私はお嬢様がご結婚をされたのを見届けてから考えてみます」
口元に手を添えて笑うティフォンがかわいらしくて仕方ない。
私が結婚しなければティフォンも結婚するつもりがない、ということで少しは安心している自分がいる。
馬車が止まり馬が鳴く声がした。どうやらもう家に着いたようだ。
ティフォンが先に降りて足場を作ってこちらに手を差し伸べる。
このティフォンの上を見上げる表情が一番好きかもしれない。
そんなことを考えながら足場に足を着いてティフォンの手に自分の手を重ねて馬車から降りる。
ふぅ、と息を吐いて玄関までの間にある庭をティフォンと歩く。
.