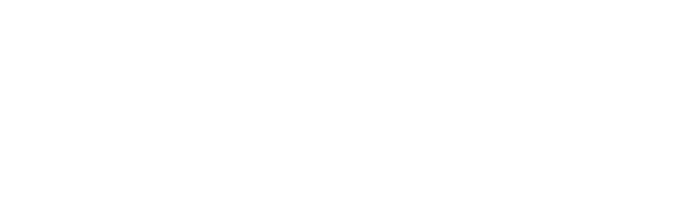第二章
図書館での勉強を終えた帰り道。
馬車で学園前まで迎えに来ていたティフォンと合流をしようとしていた。
遠くから見慣れた執事服を見かけて駆け寄ろうとしたそのとき、近くにいた令嬢たちの会話が耳に入ってきた。
「あの方……私し達よりも1つ上の王族の…」
「ああ…あの三番目の男の使用人しかいないっていう…」
「ディーテ様やラシル様は時期王妃として立派になられてますのに…執事と仲睦まじいと聞きましてよ」
「王族として恥じらいはないのかしら…」
いつもならきっと気にも留めなかった。だって私の目にはティフォンしか映らなかったし、周りの目なんか気にしていたら私は私らしく振舞えない。
不愉快極まりない内容をわざときこえるように話している。
ここまでは耐えられた。次の内容を聞くまでは。
「でも執事の顔はよろしいらしくてよ?私、第三王女が嫁いだらその執事を買おうかと検討しておりますの。私しのお父様もきっと快く了承してくださるはずだわ」
「まぁ!それはぜひ私しも見てみたいですわ」
「ふふっ…顔が好みであれば夜のお相手もしてもらおうかしら」
ブツッ
私の脳内にはっきりとその音が聞こえた。
ヒールの踵をカツンッと甲高く鳴らす。その音に驚く令嬢ふたりの元へと歩み寄る。
正直感情的になりすぎてこの時のことは覚えていない。
すごい形相でまくしたてたような気がする。
『あなたたち、どこのご令嬢か存じ上げませんけど私のことを知っていてその口がきけているのでしょうか。私は母なる国ティア王国の第三王女、ベラ・ローダンディ。あなたたちは私よりも上のご身分でしょうか。発言を許可しますのでお答えいただけますでしょうか』
「…も、申し訳ありません…母なる国ティア王国の瞬く三ツ星ベラ王女様……」
「どうかお許しください…母なる国ティア王国の瞬く三ツ星ベラ王女様…」
『なぜ反撃を食らうとすぐ謝るのにあのような発言をしたのか気になりますね。心の内ではまだあざ笑っておられるのでは?私の冒涜は私のお父様、お母様への冒涜。おふたりへの冒涜は母なる国ティア王国への冒涜と同等ですわ』
「た、大変申し訳ございません…!」
「ベラさん、何をしておられるのですか」
怒りで我を忘れていると、エリザが通りかかった。青ざめた顔をした令嬢が深く頭を下げているのを見て状況を理解したのか深くため息を吐いた。
「王族に喧嘩を売るなんてとんだ令嬢もいるものですわね、学園内で身分差関係なく入れるとしても常識も身につけなくては首が閉まるのはあなた方のご両親ではなくて?」
「は…っ…あ、アロンダード王国の華に挨拶申し上げます…」
『エリザ…!この方たちがティフォンを…ティフォンを買うって…』
「お黙りなさい!ベラさん!…あとで話は聞きますわ。生徒会としてこのふたりに処分を下しますので私はこれで失礼いたしますわ」
『……お願いします』
いつもに増して覇気の強いエリザが口元の扇子を音を鳴らして閉じる。
カツカツと歩くエリザの後ろを泣きそうな顔をして令嬢が歩いて行った。
腑に落ちないこの怒りをぶつけるところもなく、ティフォンの元へと速足で向かった。
校門の近くまで来ると、ティフォンの話し声が聞こえてきた。
「ティフォンさん、いつもお疲れ様です」
「いえいえ、お嬢様のためですから。いつも馬車をきれいにしてくださってアイルくんもありがとうございます」
「これが俺の唯一の仕事ですから!お嬢様はそろそろ来ますかね」
「ええ、もう少しできますよきっと」
御者の男と話しているのかだいぶ砕けた話し方をしている。
この御者もまだ見習いの若い男の子。ベテランは姉2人の方へ付けられ私はこの見習いがいつも登下校を送ってくれている。
校門をくぐると、すぐにティフォンがこちらに気づいていつもの笑顔をこちらに向けてくれる。
私だけに向けてくれるこの笑顔。それがあんな令嬢に奪われるなんて想像しただけで吐き気がしてくる。
「お嬢様、ご気分が優れない様子ですね。馬車には乗れそうですか?」
『…え、あ、うん…大丈夫だと思う。ありがとうティフォン』
「あまり無理はしないでくださいね」
すぐに私の異変に気付いて手を差し伸べてくれる。その手に自分の手を乗せる。
片手で馬車の扉と足場を開く。ティフォンの手に体重をかけて足場を使って馬車に乗る。
無事馬車に乗り込んだのを見てティフォンが手を離す。なぜか、すごくそれが寂しく思えた。
.