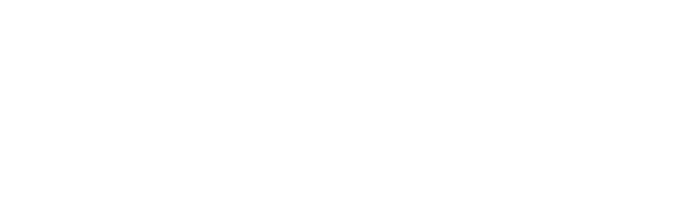第一章
「お嬢様」
『ん、ティフォン。どうしたの?』
「…先ほどは、ご友人様に不快な思いをさせてしまって申し訳ございません」
『…ティフォン、私はずっとティフォンと一緒にいたいな。へへ』
力なく笑う私を見るティフォンの表情はとても複雑な心境を表しているように見えた。
でも本当は今すぐにでも抱き着きたいし、もっともっと心の奥底にあるティフォンへの気持ちも伝えたい。普段から言っているような気もするけど。
「…何があっても私はお嬢様の味方です。私はなにがろうとお嬢様に命をささげる覚悟です」
『うーん、私たちの結婚を反対するお父様でも?』
「お、おじょうさま…あまりいじめないでくださいませ…」
困ったように眉を下げるこの表情がティフォンの一番好きな表情と言っても過言ではない。笑顔も好きだけどね!!!!!
なんで神様はこんなにもかっこいいティフォンを執事として生を授けたのか憎いとさえ感じる。
ティフォンの顔を見つめる私の視線に気づいたのか顔を反らしていたティフォンがこちらを見た。
「ふふ、お嬢さまと過ごす時間は楽しいです。私にとって大切な時間です。これまでも、きっとこれからも」
『そんなこと言うと私お嫁に行かなくなるよ?』
「お嬢様の幸せが私の幸せです。お嬢様の人生、お嬢様の幸せだと思う道を進むべきだと思います」
『どうして私の執事はこんなに尊いの…!』
微笑みながら愛おしそうにこちらを見るティフォンの視線にとろけてしまいそうな感覚に陥る。
幸せを噛みしめながらティフォンを連れて玄関ホールから自室へと移動する。
すれ違う使用人たちは立ち止まって私が通り過ぎるまで頭を下げる。いつまでも異性の執事しか連れていない私を見る使用人たちからの視線からはあまり好ましい印象は感じない。
もう慣れたことだが、あの話を聞いた後だと本当に今の状況が本来ありえないことなんだと突きつけられているような感覚。
『…ティフォンはさ』
「なんでしょう?」
『私の執事をやめたい、と思ったことはある?』
「いいえ。私のお嬢様はお嬢様だけですので」
『…それは辞められないからってこと?』
「ふふ、お嬢様だから仕えたいってことですよ」
口をとがらせながら振り返る私にいつものように微笑んでそういうティフォン。本当にかっこいい、ずるい。
振り向かせていた顔を前に戻して廊下をずんずんと進む。
自室の前に着くとティフォンが扉を開いて道を開ける。ようやく自分の安らぎの場所へとたどり着いた安堵感に脱力しながらソファへと品など気にせずドカッと座る。
大きく息を吐いてティフォンの持ってきた水を口に含んでゆっくり飲み込んだ。
「お嬢様、先にお風呂にいたしますか?お食事にしますか?」
『うーん……なにか軽いものが欲しいわ』
「では、疲れの取れる甘いものをお持ちします。少々お待ちください」
ニコッと笑って部屋を出るティフォン。ひとりになった静かな部屋で先ほどエリザから言われた言葉を思い出す。
第三王女なんて自由気ままに生きられるものだとばかり思っていた。王族の役割として国のために生きるのことはうっすらとわかっていたがそれが他国との協定のためや貿易のために嫁ぐことなんて考えたこともなかった。
政略結婚。そこに愛がなくとも知らぬ男と婚姻が結ばれる。
私がティフォンのことを好きだろうと関係がない。
『お父様は、私にそんなことさせるのかな…』
昔から私には不干渉の両親。使用人がいれば私はしぬことはないと思っているのか姉2人の教育に熱を入れて私には最低限の躾、教育を施してきた。使用人も私に価値を見出さなくなったのかティフォンが来てからは面倒さえも見てくれなくなり、私にはティフォンしかいなくなったわけだが。
結果的には私はティフォンといられる時間が増えて万々歳だが、この先一緒にいられなくなるとなれば話が変わってきてしまう。
『…本当にティフォンを嫁ぎ先に連れていくことはできないのかな』
色々考えてみるもどれも現実味を帯びないものばかりが出てくる。
コンコンッと扉がノックされる。返事をすると、扉が開かれて軽食をカートにのせてティフォンが入ってきた。
いつも扉が開かれてティフォンの顔が見えると無意識に安心する。
ゆっくりとカートを机の近くまで運び運んできたものを私の前に置いた。
甘い香りの漂うショートケーキだ。昔から私の大好物。嫌な日があったときにティフォンがいつも用意してくれるショートケーキは私に元気をくれる。
『私、元気ないと思った?』
「本日は大好物が食べたい日ではないかと思いまして」
『…私のすべてを見透かせるティフォン以外に私の旦那様になれる男なんていないのにね、変な国よね』
ショートケーキの皿をもってフォークで一口サイズに切る。
私の言葉にティフォンは何も言わなかった。私もティフォンの表情をみなかった。
ティフォンの淹れる紅茶の香りと一緒に私の言葉も消えていった。
.