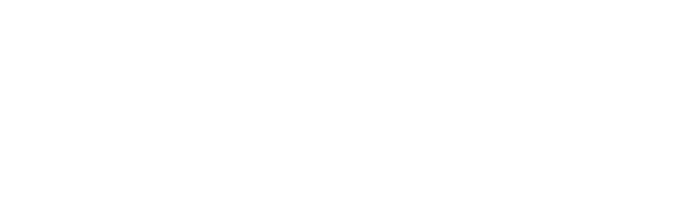第四章
暗闇の中で耳を塞いでいる自分の手に誰かの手が重ねられた。思わず体が震えてあの男の手の感触を思い出してしまう。
「お嬢様」
ティフォンの声がかすかに聞こえて目をゆっくりと開く。
視界に、ティフォンの柔らかな微笑みが見えて自分の身体から力が抜けた。その体はそのままティフォンの方へ倒れてティフォンに受け止められる。
私の身体を受け止めたティフォンがそのまま私を姫抱きして歩き出す。気づかないふりをしていたが、この場に鉄のにおいが広がっていた。そしてティフォンの手袋が外されているのと袖に赤い染みがついていることにも。
ティフォンの首元に抱き着く。
「お嬢様、不在にしてしまって申し訳ありませんでした。すぐに帰ってくるつもりだったのですが。思ったよりも手間取ってしまい…」
『…ううん、助けてくれてありがとう…多分家の中にも貴族の人と何人かいると思う…』
「そちらの対応は私にお任せください。お嬢様はお部屋でお休みください。後ほど救急キットと紅茶をお持ちします」
そう話すティフォンの声はいつもと変わらぬ優しい声なのに、ティフォンの目には明らかな怒りと殺気が込められていた。
こんなティフォンは初めてだった。
でもいまはそんなティフォンが心強くて、安心できた。
「では、少々お待ちください。部屋からは出ないように」
『気を付けてね…ティフォン…』
部屋を出ていくティフォンを見送って布団の中にもぐりこむ。
目を閉じるとあの男のことを思い出してしまう。身体の震えがまた戻ってくる。
あのままティフォンが助けに来なかったら…と思うと、吐き気がする。
必死にティフォンの抱きしめてくれた感触を思い出す。
それからどれほどの時間が経ったのだろう。
布団の中にもぐりこんだまま少し意識が飛んでいたようだ。
窓の外が騒がしい…。ティフォンに何かあったんじゃないかと窓に駆け寄ると、小さな人だかりができていた。
『あの格好は…王室で見た…警備隊の人たち…』
どうやらここに侵入した貴族たちは王室直属の警備隊に引き渡されたらしい。第三王女と言えど王族の邸宅に侵入し危害を加えようとした罪は重いだろう。
もう2度と前に現れないことを祈ろう…。
1段落ついたことにホッと息を吐いて部屋の入り口の扉まで歩く。
扉をそっと開けて廊下を見渡す。
屋敷の中から誰もいなくなったのか朝と同じく静まり返っている。同じ情景に恐怖心がぶり返す。
『てぃ……ティフォン……!』
廊下の先に呼びかける。
返ってきたのは静寂だった。怖くなって部屋の中に戻った。ティフォンがまたこの部屋にノックをして微笑みながら入ってくるのを待つ。
.