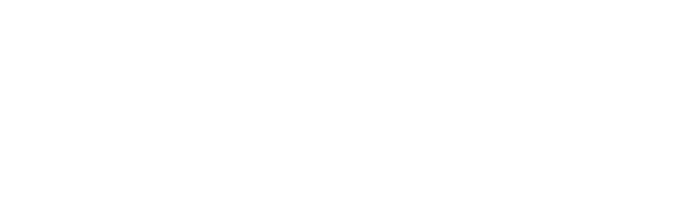第三章
一時間ほど経過してようやく馬車が動き出した。
家までもう少し。疲れもあって眠気が襲ってきてウトウトしながら馬車の壁にもたれかかっていると、隣に気配を感じた。
そちらに視線を向けると、ティフォンがなぜか私の隣に腰かけている。
『ティフォン…?』
「お隣に座ってしまい申し訳ありません。お嬢様、眠られるのでしたら私に寄りかかってください。そんなところでは馬車の揺れで頭をぶつけてしまいます」
『…ん』
ティフォンの優しくささやく声に素直にティフォンの肩に寄りかかる。頭が乗りやすいようにか、少し身体を傾けているのがわかった。
ティフォンの良い香りが心地いい。そのまま私は夢の中へといざなわれた。
『んぅ……』
目が覚めた時、私は見慣れたベッドで寝かされていた。
服も王宮に行くための着飾った格好ではなく寝間着に着替えており、髪も装飾品がとられている。
ベッドから起き上がって覚醒していない頭で周りを見渡す。
ティフォンの姿が見当たらない。
あくびをひとつしてからベッドから出る。
ドレスの上から羽織るブランケットを肩にかけて部屋をでると、どうやらこの邸宅には誰もいなさそうだった。
廊下の明かりはついておらず、外で作業をするものの気配も感じられない。
『…ティフォンも出かけたのかな…』
廊下を進み、キッチンの方へと向かう。
もちろん調理人なんかいないこの邸宅のキッチンは無人だった。
ティフォンがきれいに使ってくれているおかげで食べ物は新鮮なまま保存されている。
冷蔵庫を開けるとティフォンが作り置きしたであろうデザートが置いてあった。
ひとつ拝借をして、シンクにあったフォークを手に取る。
『ティフォンの紅茶が欲しくなるなぁ…』
ぽつりとつぶやいて食べ進めるとあっという間にお皿が空になった。
だがまだ自分の胃が食べ物を欲している。
まだ何かないかと冷蔵庫を物色したが、これといって食べれそうなものはなかった。いや、食べ物はあるが調理済みのものがなかった。
王族は基本料理をしない。調理人が雇われるからだ。だから私も料理というものは学んでいないし自分からしようとも思ったことがない。なんて言ったってティフォンの作る料理がおいしすぎるがゆえだ。
幼少期はちゃんと調理人はいた。かなりのおじいさんだったが気さくで優しく、この邸宅を出ていくこともしなかった。
だが、年齢には逆らえずに私が淑女教育を受けている最中に倒れてしまいそのまま領地へ帰って亡くなったらしい。
それ以来はティフォンが調理人としての仕事もし始めた。
自分はなにもできない上にティフォンに甘えすぎてるな、と少し反省をする。
はぁ、と息を吐いてキッチンの椅子に腰をかける。使用人用の椅子はとても座り心地が悪く、薄い寝間着では肌に直接椅子の感触が伝わってくるように気持ち悪い。
『ティフォンどこ行っちゃったの』
.