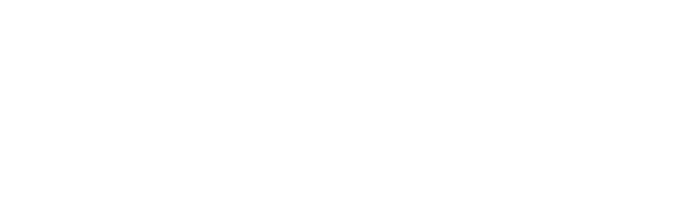君の名前をもう一度。
璃子が寝付いたのを確認して、大輝はその璃子の寝顔を見つめる。
最初に見た時よりかは安らかな顔をして寝息を立てている。
「もうこんな時間か……」
携帯で時刻を確認するともう18時を過ぎていた。
日が暮れるのが早くなっていたためにもう外は暗くなってきていた。
病院の受付時間も過ぎている。
璃子の母親ともまた顔を合わせるのは少し気まずい。
今日のところは帰ってまた休日に出直そう。
そう思い立ち上がって璃子の頭を撫でて家を出た。
帰り道ー…
とぼとぼとひとり歩く大輝。
夏が終わったと涼しい秋風が身体を縫うように吹いた。
『梨子のこと…どうすっかな』
就活はとりあえず結果が出るまではいったん置いておいてもいい。
落ちた時は地獄を見るだろうがとりあえずは終わったことにする。
璃子も体調がよくなれば梨子の見舞いに行けるだろう。
今までは意識のない梨子への見舞いだったが、これからは小学生の中身の梨子への見舞いになる。
『俺…今まで梨子のどこがきらいだったんだっけな…』
ふとそんなことが疑問として出てきた。
言い合いはあった。そんなやり取りに嫌気もさしていた。
笑顔なんて初対面以来見せてこなかったからかわいいと思ったこともなかった。
だが、今は梨子のことを思い浮かべるとこちらに悪意など一切ない笑顔を向ける梨子の姿。
そんな姿しか思い浮かばないのだ。そして決まってその姿にドキドキする自分。
璃子以外にこんな感情が出てくるなんて思わなかった。それもクラスメイトで一番言い争っていた相手に。
感情の変化に大輝自身も追いつけていないが、その事実だけは確実だった。
道端に咲いている花を花だと認識はしていてもその美しさに気づかなかった時のように、気づいた時にはその美しさにくぎ付けになってしまっていた。
『手…柔らかかったな』
自分の手のひらを見ながら、梨子の手を握ったときのことを思い出す。事故で擦り切れてたりしているものの璃子よりも柔らかく、片手で包み込めてしまうほど細く小さい梨子の手。
無意識やとっさのことだったが梨子に触れた肌をいまだに覚えている。
そんなことを考えながら歩いていると、いつの間にか自分の家の前にたどり着いていた。
玄関の扉を開いて靴を脱ぐ。
扉の音に気付いたのかリビングから覗く人影が視界の端に見える。
「おかえりぃ大輝。お母さんから聞いたよ。璃子さんは大丈夫そう?」
『ただいま父さん。うん。熱もだいぶ下がってだいぶ顔色もよくなってたよ』
「それはよかった。手洗いうがいしてご飯にしよう」
そういいながら父親は覗かせていた顔を引っ込ませた。
奥から母親が料理しているであろう生活音が聞こえる。
父親に言われたように手洗いうがいを済ませて自室に財布などを置いてリビングへと向かう。ふんわりとおいしそうな匂いがする。
「おかえり大輝」
『ただいま』
リビングへ入ると夕ご飯をテーブルに並べている母親が声をかけてくる。今日は母親といろいろと過ごしたためになんだか照れくさい。
大輝は自分の椅子に腰かけるとテーブルに並べられた料理を見る。
いつもよりなんだか豪華な気がする。そこそこな大きさの骨付き肉なんかもある。
『今日なんかイベントあったっけ』
「お母さん、結婚記念日って今日だっけ」
「お父さん、ボケるのはまだ早いわよ。今日は大輝の大舞台だったからその慰労をかねてよ」
『俺?』
「あっ。今日は大輝の就活の面接の日だったね。手ごたえはあったかい?」
父親が思い出して振った話題でようやく自分も思い出した。璃子と梨子のことで頭がいっぱいで今日の面接のことをすっかり忘れていた。
どんな様子だったか思い出して口を開く。
『志望動機で…璃子を支えたいことを言ったら担当の面接官の人に食いつかれたくらい』
「まぁ、そんな不純な動機なんか話したの?」
『不純じゃねぇよ』
母親からの軽蔑なまなざしにツッコみながら顔を赤らめると父親があっはっはと大笑いをした。
骨付き肉を掴むと勢いよくかぶりつきご飯をかきこんだ。
父親と母親もそれに続いて食事を始めてそのあとは和やかな談笑が始まった。
おかずも減り、夕ご飯が終わりかけになった頃に母親が口を開いた。
「そうだわ、お父さん」
「ん?どうした?」
「璃子さんのことだけれどね、まだ本調子じゃないから治るまでの間、璃子さんの看病と家事とお母様の様子を私が見に行こうと思うの」
「おお、良いんじゃないか?」
『それ本気だったのかよ』
母親の提案に父親は笑顔で了承をしている。
息子の彼女といえどふたりにとっては他人も同然だし、踏み込みすぎといっても過言ではない。
大輝はそう思う反面、璃子のためになるというエゴも捨てきれない。
今の璃子の状態では璃子の母親がまた不安定になったときにどうしようもできない。
だからと言って大輝の母親がどうにかできるとも思えないが、病院に連絡を入れるように言えばいいだろう。
そう思いながらもやはり母親に任せるのは迷惑になりかねないとも思ってしまう。
「璃子さんにも一応伝えてはいるのだけど、大丈夫かしら」
「ご迷惑にならない程度に必ず璃子さんに声掛けすれば大丈夫じゃないか?大輝の話を聞くに1日2日で元気にはなるだろうし」
『でも他人の家に勝手に出入りするのはダメだろ』
「他人だなんて、大輝が一番言っちゃだめでしょう。こういう助け合いは必要なことじゃない」
「見て見ぬ振りもできないだろう。こういうときに璃子さんから頼られるようにもっと彼氏として頑張らないとな」
『うぐ…。』
父親にごもっともなことを言われ何も言えなくなる。
何も連絡をもらえなかったのは確かだし、あの時に璃子の家に行かなければ知らないままだっただろう。
頼ってくれない璃子の性格はわかりきっているし、その心を変えられるようには努力はしたい。
そうふたりの会話を聞きながら決意を固める。
「お父さんなんか、何かあるたびに心折れて私に泣きついていたのにねぇ」
「お母さん…あまり掘り返さないでくれよぅ」
過去に何かあったのだろう、呆れて笑う母親と眉を八の字にして慌てふためく父親。そのまま大輝を置き去りにふたりの世界へと入っていく。
黙々と残ったおかずをすべて平らげて皿を重ねて席を立つ。
そのタイミングでふたりはこっちに帰ってくると、母親も2人分の皿を重ねて大輝の後に続いてキッチンへと来た。
父親はふきんでテーブルを拭いている。
「大輝も私か、言いづらかったらお父さんにちゃんというのよ。なんでもいいから」
『え?…ぁあ、うん。わかった』
持ってきた皿をシンクの中に置いていると、後ろについてきた母親がこっちを見ずにそういった。
何を言いたいかはなんとなく察した。
両親も、両親らしく息子のために動きたいのだろう。
.