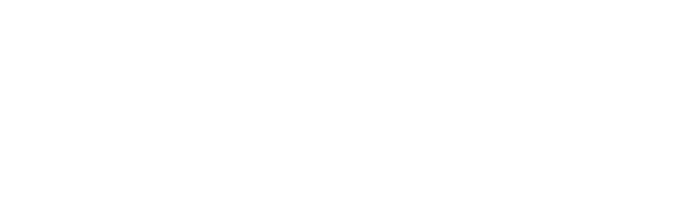君の名前をもう一度。
プルルルルル…
「………もしもし?璃心?」
『あ、お母さん。体調は大丈夫?』
「どうもこうもないわ!!!!信じられないわ私!!!」
母の怒声に耳の奥がキーンと鳴った。
船越と別れてから帰り道、梨心の様子を早く知りたかった璃心は母へ電話をかけていた。
だが、電話に出た母は何かのきっかけで興奮状態らしく璃心に向かって吐き捨てるように言葉を連ねていた。璃心は母のこの状態でひとりで家にいるのはいけないと思い少し駆け足で帰る。
その間も母をなだめるように話しかけるも母の様子は収まらずに耳が怒声で少しおかしくなってきていた。
『お母さん、事情を聞くから落ち着いて?』
「これが落ち着いていられますか!!!梨心が…梨心がまだ意識戻らないっていうのに…」
どうやら母の今の状態の原因に梨心が関係しているらしい。
母からすべての事情を聞けるかは不安だったが、梨心が関わっているからには自分も事情を知っておかなくてはならない。母にどう聞こう、と考える。
青信号の横断歩道を確認して渡る。家はまだ遠い。
家に帰る頃には母に落ち着いていてもらいたい。できる限り口調を優しくなだめるように話しかける。
『お母さん、梨心はまだ意識戻ってない?』
「そうよ!!!あの子はまだ目が覚めないっていうのに…なんであの子をこんな目に合わせた奴が…!!!」
『…!お母さん、今日誰かと会ったの?』
「誰かって!!!あいつよ!!!!梨心をこんな傷だらけにしたやつ!!!!あいつの両親ってやつと、警察が!!!」
母の言葉に璃心の心臓が跳ねた。
母の言うあいつって言うのは梨心の事故の原因、大型トラックに乗りながら居眠り運転をした男性のことだろう。その両親と警察が付き添いに行っていた母の元、いや入院している梨心のもとへ来たという。
今更になって見舞いにでも来たのだろうか。なぜ今だったのだろうか。
ふと璃心は先程母が梨心が意識を戻らないことを嘆いていたことを思い出した。そのことを嘆くということはもしや、事故の原因の男性が、
『相手方の人が…意識を戻した…?』
「そうよ…そうなの…梨心が……梨心が今も眠っているのに………あいつは目を覚ましたって…ぐすっ……事情を聞いたら記憶にない、何も覚えてないなんて言っていたみたいよ……なんて人達なの……梨心が…梨心が…!うあぁぁぁ……!」
怒声を上げていた母が電話の向こうで泣き始めた。
すべて事情を話し終えたであろう母はその後は泣くばかりで会話にならなかった。走りながら話していたため息を切らした璃心はようやく家が見えるところまでたどり着き、最後の追い上げに駆け出した。
記憶にないと言う加害者のこと、その両親と警察が揃って見舞いに来たこと、母の精神不安定の再発、意識の戻らない梨心。
思ったよりも事態が深刻化していることに泣きそうになりながらも走り続ける。仕事用のヒールで走っていることで足が悲鳴をあげようと、汗でシャツが汚れようと、振り乱してしまった髪も何もかも気にせずにただ、家へ向かって走る。
ガシャーンッッ
家の前へ来たときにその家の中から大きな音が鳴り響いた。
おそらく母が中で物を壊しながら取り乱している音だ。
その音に顔を青ざめながら鞄から乱暴に鍵を取り出して震える手で鍵を開ける。玄関へと雪崩れるように入ると靴を揃えるのも忘れて脱ぎ捨ててリビングへ向かう。その間も泣きじゃくる母の叫び声と物を倒す音、落とす音、母の体が何かを蹴る音、雑多な音が聞こえていた。
リビングの扉を開けた璃心の目の前にはいつもは綺麗に整えられていたシンプルな部屋に物が散乱して、壊れ、叩きつけられたであろう光景が広がっていた。
その部屋の隅で梨心の名前を呼びながら座り込んで丸くなった母の背中が見えた。
父のことを立ち直った母にはやはり梨心のことは受けとめきれなかったのだろうか、母に駆け寄った璃心は落ち着かせるように母の背中をさすった。
『お母さん!そんなに泣かなくて良いんだよ、私がちゃんと相手方の人に謝罪してもらうから』
「璃心………。璃心、どうして梨心は目を覚まさないの…?」
『……梨心は今必死に身体を治してるのよ…まだ起きたら痛いから…だから…』
「……そうよ、そうだわ」
『………お母さん…?』
泣きはらした目で璃心を見ていた母が何か違うものを捉えてつり上がった目でつぶやいた。
その母の異変に璃心の心に不安が広がる。母の肩を掴んだ手が震えだす。それでも母は璃心の方を見ているが焦点は璃心に向いてはいなかった。
母が立ち上がる。
ふらふらとした足取りで立ち上がった。璃心は力の抜けた腕をおろして顔だけ母の方を向いた。
「あいつが起きたから、梨心が起きないんだわ……あいつがもう一度寝たらきっと梨心は目が覚めるわ……」
『…?!や、やめてよお母さん!!そんなことあるわけないじゃない!!』
「璃心、やめなさい。お母さんにもう任せてくれていいのよ。璃心は今までよく頑張ってくれたわ……」
ぽつりぽつりと母が小さくつぶやく。
ふらふらしながらリビングを出ていく母の姿を追う璃心。今までとはまた違った母の姿に恐怖を抑えきれない。
次はどうやったら母は落ち着くのか必死に考えながらリビングを出た母を引き止める。
母の細い腕を掴むもそれを無視して母はそのまま玄関へと向かう。
『お母さん!!1回落ち着いて!!』
「私は落ち着いてるわ」
『ダメだよどこへ行こうって言うのよ!!』
「担当の警察の人の名前を聞いてるのよ!そいつからあいつらのことを聞き出すのよ!!!」
璃心が必死に母を止めるも母は思いっきり振り払い、璃心は床へと倒れ込んだ。
尻餅をついた璃心はすかさず母に抱きついて止めようとする。
乱暴に足を前へ出そうとする母にしがみついて母を止める言葉を必死に叫ぶ。
母に届かない璃心の想い。
それが悲しくて悔しくていつしか璃心も涙を流していた。
それでも母を離すまいと腕に力を込めてしがみつく。
『お母さん…!お願いだから…!お願い…もうやめて…!』
「離しなさい、璃心!!!」
もうどうしたらいいかわからなくて泣きじゃくる璃心。
その時璃心のスーツのポケットに入れていた携帯が鳴った。それに気付いて片手をポケットに突っ込んで携帯を開くと、画面には大輝の名前が表示されていた。反射的に応答ボタンを押すと璃心は叫んだ。
『た、大輝くん!!助けて!!』
「?!璃心?!大丈夫か?!」
電話に応答する間だけなら片手で母にしがみつくことはできたが、それも長くは持たず、携帯を近くに放り投げて両手でまた母にしがみついた。
母は大輝に電話が繋がっていることも気に留めずに変わらず璃心を引き剥がそうとしている。
大輝が何か通話越しに叫んでいるのはわかるが今はそれに答えられない。
『大輝くん!!家まで来て!!』
「いい加減になさい!!!!!」
涙と鼻水でグズグズになりながら叫ぶと、痺れを切らした母が璃心の頬を引っぱたいた。不意打ちに璃心の腕の力が抜けて母は璃心の腕から開放された。
姿勢を崩して膝をつく母だが、璃心よりも早く立ち上がって玄関扉へと手をかけた。
我に返った璃心も慌ててあとを追いかけるも母は玄関扉を開けて外へと出ていってしまった。
その後ろ姿を見ながら涙が溢れて力が抜けてしまう。
『あああぁぁ……お母さん………』
膝から崩れ落ちてただただ涙を流した。
せっかく立ち直れた母がまた不安定になってしまった。また一からスタートなのだろうか。また毎日泣いては暴れだすを繰り返すの?梨心が意識を取り戻したら戻るのだろうか。戻らなかったら?梨心の付き添いをしながら母の付き添いもできるだろうか。私にまたできるの?
自問自答が止まらない。どんどん思考がネガティブになってしまう。もうだめだ、もう頑張りたくない、もう自分にはできない。
泣き崩れながら床に蹲る。
母に叩かれた頬が痛む。叩かれた反動で口の中を切ってしまったようで今になって口の中に血の味が広がっていることに気付いた。
でももう璃心にはそんなことも気にしたくないくらいに世の中のすべてが嫌になってしまっていた。
そんな璃心の耳に遠くから自分を呼ぶ声が聞こえた。
「………!!……こ!!……璃心!!!」
『た…いき……くん…』
先程放り投げていた携帯から大輝の声が聞こえた。
まだ電話が繋がっていたらしい。
手を伸ばして携帯を手に取る。
泣きじゃくりながら携帯を耳に当てると必死に大輝が璃心を呼びかけていた。
大輝の声に少し気持ちが落ち着く、ずずっと鼻をすすって涙を拭った。
「璃心!今璃心の家に向かうところで裸足でふらふらしてる璃心のお母さんを見かけたから話しかけたんだよ。そしたら警察に連れて行ってくれって言われたから…タクシーに乗ってんだけど」
『…!お母さんがいるの…?』
「う、うん。だいぶまた不安定そうだけど…璃心でも対応しきれなかったんだよね?だからこのまま病院に行ったほうがいいのかなって…」
『……うん、ありがとう…私も向かうよ…』
「……無理してこなくても大丈夫だよ、本当にしんどいときは1回落ち着いてゆっくり寝ていいんだよ」
大輝の言葉にまた涙が溢れてそのあとは会話ができなかった。わんわん大声上げて泣く璃心に大輝は一生懸命「大丈夫、安心して」と声をかけ続けた。
涙を止めたくても頭の中が今まで我慢してきたいろんな感情が涙と一緒に溢れ出て止まらなくてただただ怪我をしたときの子供のように泣くことしかできなかった。
.