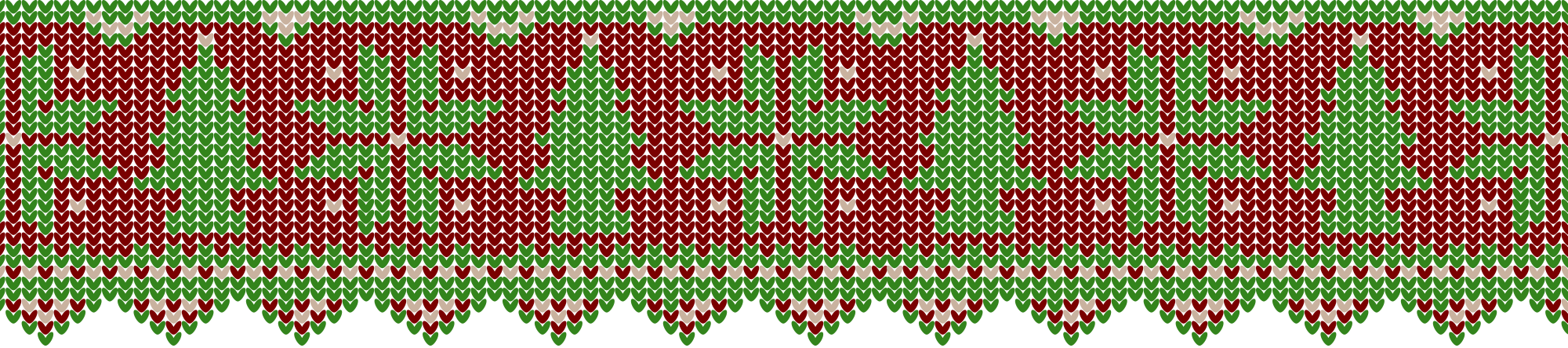レグリ小話
今日はここらへんで一番大きな広場で、アローラ伝統の祝祭が開かれていた。ツリーも休業し、家々も色とりどりに飾り付けられ出会う人皆がお祭りムードだ。
小銭だけポケットに突っ込み、グリーンと共にワインやビール、伝統の菓子なんかを売っている出店を夕方からまわった。ここの人達は皆陽気な性質をしていて、あちこちで楽器に合わせて踊る人を見かけた。日も落ちる頃にはグリーンは軽く足元をふらつかせていた気がする。僕より酒に弱いくせに勧められるままに飲むものだから、もう目が据わっていた。
あたりはすっかり暗くなっている。まだ左手に持ったワインをちびちびと飲んでいるグリーンの右手を引き、広場を見渡せる石造りの階段に二人並んで腰を下ろした。手を離す瞬間に少しだけグリーンの指が絡んできた気がする。グリーンは僕の右側に座り、左手に持っていたプラスチックのグラスは彼の右側に置いた。
広場には煌々と燃える松明やオレンジ色の灯りがあちこちにともり、楽器隊の鳴らす陽気な音楽に男性も女性も手を取りあい楽しそうにステップを踏んでいる。隣のグリーンも気持ちよさそうに音楽に合わせ鼻歌を歌っていた。すごく音痴だ。思わず笑ったら、目敏く気づかれ右腕を肘で小突かれる。
「いて」
べつに痛くはなかった。グリーンの鼻歌がやんだので何気なく彼の方を見ると、灯りに灯され橙色に輝く瞳で、ついさっき小突いた僕の右腕をぼんやりと見ていた。見つめていた、と言ってもいいかもしれなかった。
「飲み過ぎだよ」
「そんな酔ってねーよ」
「目潤んでる」
「…………」
あ、拗ねた顔。そんな顔をしてもこいつの顔は整っている、たぶん。暗い中、祭の灯りに照らされてなんだかいつもよりかっこいい気がする。
グリーンは右脇に置いたグラスを掴んで残った中身を一気に煽ると、口元から一筋垂れたワインの赤を、綺麗な顎の輪郭から滴り落ちる寸前に手の甲で拭った。
そのあいだずっとこの親友の顔を見ていた僕はなんだかたまらない気持ちになって、このなんとも形容できない気持ちを感じているのが僕だけじゃなければいいのに、と、なんとなく悔しいような気持ちになった。すぐにグリーンから目を逸らし前方で楽しそうに踊り続ける人達を見ていると、ワインを拭ったグリーンの左手の小指が、地面に置いた僕の右手の小指に重なったことに気づく。陽気な音楽はまだ続いている。なんだか暑い。顔が赤くなっていないか心配だけど、酒に酔っただけだと言い訳すればいい。
「………」
「………」
さっきからグリーンは寡黙だった。「酔ってんのか?」とか聞けよ。いつもうるさいくせに。動かない口の代わりに、グリーンの細くて綺麗な小指は僕のごつごつとした小指をきゅうと掴んだ。僕は前に彼の手が綺麗な女性みたいに滑らかで好きだと言ったが、彼は別に嬉しくないとこたえた。
どうしよう、これって友達同士なら普通にある接触だろうか。なんでもないように手を持ち上げて離れればいいのか?グリーン以外にグリーンほど親しい友達のいない僕には検討もつかなかった。
僕とグリーンの周りだけ、音がなくなったみたいだ。グリーンが静かに呼吸をする音だけが、やけにハッキリと聞こえた。皆の楽しそうな笑い声と音楽がずっと遠くに響いている。そういえばいつのまにか音楽が変わった気がするけど、相変わらず広場は楽しそうな雰囲気だ。特に理由もなくさっきからずっと凝視していたカップルが、踊りながら笑顔でキスをしているところを見てしまう。多分、グリーンも同じものを見ていた。そんな気がした。
小指ってこんなにでかかったっけ?僕の右手はとっくに小指の感覚しかない。グリーンも同じことを考えているのかな?グリーンのちいさな小指を振り払って、僕の手を重ねてもいいかな?僕ももっと酒を飲んでおけば良かったと思った。
「俺達も踊るか?」
僕の葛藤が決着する前に、熱い小指は離れていった。グリーンは立ち上がり少しふらついたが、階段を数段降りて少し腰を屈め、僕を上目遣いで見つめた。そして昔から変わらない、片目を細めた悪戯っぽい笑みで言った。見ると、右手を差し出している。
「お手をどうぞ、姫」
なんだそれ。くそ、むかつく。かっこいい。まるでおとぎ話の王子様みたいなポージングが完全に様になってしまっているこの酔っぱらいは、しかし酒のせいか顔が真っ赤に染まってしまっていた。そういうところはかわいい。詰めが甘いんだ。
「……く、はは、なーんてな!にしてもあちーな、ちょっと頭冷やしてくるわ」
「待って」
常に冗談めかして予防線を張り、失敗すると安全なところに逃げるのはこいつのよくやる手法だ。グリーンが足を止めて僕を不思議そうに見上げる視線を無視して、階段を降りて広場の砂の上に立った。
「よろしければ」
「…………!」
左手を胸に当てて右手を差し出した。多分なんかこんな感じで合っていると思う。グリーンは「はっ」とか「おっ」とか意味不明な音を吐いて相当動揺しているように見えた。相変わらずだが顔は真っ赤だ。少し得意な気持ちになって自然と右の口角が上がった。
どちらから手を取ったかは覚えていない。僕らは付き合いたてのティーンのようにぎこちなく手を繋いで、広場の真ん中まで出ていった。途中でビールを売る女性に声をかけられたので、グリーンの分は断って僕はハーフパイントを一気に飲み干した。僕の右手を掴んだままのグリーンは「おわー」なんて声をあげていた。
「はは、うわ…な…ちょっと恥ずかしくねえ?」
「そう?」
踊る人達の端に紛れ込んでグリーンの両手を取ると、彼は少し饒舌になった。
「誰も僕達のことなんて気にしてない」
「………ん…たしか、に…」
本当にそうだ。ここにいる人達は皆手を取ったパートナーのことしか見ていない。ほとんどがカップルと思われる異性同士だったが、酔っ払った男性数人で手を取って楽しそうにじゃれあう若者もいたし、女性同士抱き合って笑いただ音楽にゆらゆらと揺れている人達もいた。
「俺わかんねーよダンスとか」
「みんなわかってないよ」
「……ふ、たしかに」
グリーンの顔に笑顔が戻って来る。かわいいと思った。少しの酔いも手伝って、溢れる気持ちを抑えずにグリーンの顔を見つめることができた。グリーンは僕の顔を見て笑顔を一瞬ふっと潜めたが、すぐに目を逸らしはにかんで僕の背中に手を回した。
「こうだろ?」
「はは、多分」
二人でぎこちないステップを踏んで、どこかで見た映画の真似事をする。すごく不格好だったと思うけど、グリーンはとても楽しそうだった。広場は男女の笑い声と歌声に溢れ、幸せな雰囲気に包まれていた。自然に彼の背中に回していた手は、グリーンの細い背骨の凹凸をなぞるように感じていた。
「あれやりたい、くるくるって回るヤツ」
僕が言うと彼は声をあげて笑っていた。幼馴染は「くるくるって回るヤツ」を完全に理解して、その背中から手を離すと僕の左手を軸に軽やかにくるくると回って見せた。苦しそうになるくらい笑っている。僕も多分ここ最近で一番おかしく笑っていた。
あ、しまった、と思った瞬間には、その酔っ払いは再びくるくると回り僕の腕の中に背中を向けてすっぽりと収まってしまった。ただの幼馴染で親友でライバルである彼の体は、まるで元から一つだったみたいに、かっちりと僕の体にはまってしまった。
「………」
「………」
すぐ目の前に見えるグリーンの耳が酷く熱そうで、同時に熱を孕んだ甘い香りが漂った気がした。
この時、信じられないほど絶好の(「最悪の」ともいう)タイミングで音楽が終わった。周りが歓声と疎らな拍手で盛り上がる。酔っ払って楽しくふざけていた僕も、グリーンもきっと、歓声に一瞬で頭が覚めた心地がしただろう。グリーンは絡み合っていた左手をほどいてパッと僕の腕から離れると俯いて右足の爪先でトントンと砂地を叩いていた。僕はそれが彼の気まずい時にやる癖だと知っていたので、つられて少し気まずい気持ちになる。
「……あー!ははは!楽しかった!」
「……うん」
グリーンは顔を上げて僕の肩に肘を置いて体重をかけると(昔からよくやるポーズだけど今は身長差のせいで少し辛そうだ)、周りで手を叩いて口笛を吹いている人達にいつもの調子で「サンキュー!」なんて言っている。…別に僕達を称賛しているわけではないと思うんだけど。
今更少し恥ずかしさを感じながら、棒立ちでグリーンの体重を受け止めていると、すぐにさっきまでとは違うしっとりと落ち着いた曲が流れ始めた。賑やかだった広場が波の引くように静かになる。
「…もう一杯くらい飲んで帰るか?」
僕の肩から離れ、さっきグラスを置いてきた階段の方に歩き出すグリーンの顔は見えなかった。
「もう一曲踊ってこう」
黙って頷いて後を追おうと思っていたのに、グリーンの真っ赤な耳に短い髪をかける仕草を見ていたと思った瞬間には、彼の手を引いてふらついた頼りない腰を抱き寄せていた。
「は、?おまえ…その、…この曲で?…なんつーか…カップル向け?じゃん」
グリーンは酔いもほとんど冷めてしまったのか、ぐっと距離の縮まった僕の目を見ず気まずそうにちらちらと周りを見回した。僕の腕の中から逃れようと腰を捩っている。たしかに、先程までとは違って明らかに恋人同士と見られる人達が落ち着いたピアノの旋律にのって手を取り合い揺れていた。夜も遅い時間で、まだ疎らに姿のあった子供たちはいつのまにか姿を消し、これからは恋人同士の時間という雰囲気だ。
「……問題ある?」
「は……」
僕はまだ少し酔っ払っているみたいだった。右手はグリーンの手を握りしめ左手はまだしっかりとグリーンの腰に触れていた。グリーンは身体を硬直させ今度はまっすぐ僕の顔を見ていた。
「ねえ…けど」
ぱちぱちと瞬きを3回くらいして、グリーンも僕の腰に手を回した。音楽に合わせて、ただからだをゆっくりと揺らす。男同士でこんなことをしていても、誰も茶化す人はいなかった。僕はこの土地のそんなところが好きだった。
握りあった手が汗ばんでいるのが気になったが、それは僕だけではないみたいで、彼の手は落ち着きなくもぞもぞと僕の手の中で動いている。
「顔、近い」
「……そうだね」
「……」
「……」
「……」
また黙ってしまったようだ。グリーンはずっと俯いていた。さっきからグリーンが面白いくらい動揺を見せるので、逆に僕の頭は少し冷静になっていた。伏せた睫毛がふるふると揺れているのをじっと見つめていると、見上げたオレンジの瞳と視線がかち合う。
「……なんか、笑えるな…」
「……」
「……あー、酒飲みすぎたな」
僕達のからだはほとんど密着していた。彼は今度は恥ずかしさをごまかすようによく喋る。その唇が開くたびに彼の息が僕の唇に触れて熱く溶ける。ちゃんと音楽にのれている自信が無い。彼に触れているからだの箇所全てが燃えるように熱くて、五感が彼のことしか感じることができなかった。
彼に恋をしていると思った。
グリーンも同じことを思っているだろうか。
今まで何度も心に浮かんだ疑問は、今日も答えを聞くことなく奥にしまいこまれていった。でも、灯りを反射してゆらゆらと揺れる目の前の瞳を見ていると、答えを聞く必要はないんじゃないかとも思えた。
「……レッド…」
グリーンは色々な感情の浮かんだ目で僕の目を見つめたままぽつりと僕の名前を呼び、僕の肩口に顔を埋める。多分キラキラと潤んだ瞳を見られたくなかったんだろう。僕は今どんな顔をしてるんだろうか。
向こうのカップルが足を止め唇を交わしたのがグリーンの背中越しに見えた。僕達の両手は互いの背中にまわり、二人揃ってうるさく鼓動する胸のあたりはぴったりとくっついてもう二度と離れないような気がした。
「……お前、心臓うるせーよ」
「……お前もだろ」
「……」
「……」
「……なんか、はは、接着剤で、くっついたみてー…」
「…!」
グリーンの顔を埋めた肩が熱い。僕のさっき考えていたバカみたいな妄想を彼は口に出した。なんだか少し泣きそうになって、顔を見られたくなかったので彼の背中をぎゅうと強く抱きしめたら、同じくらいの強さで抱き返される。綺麗な両手の思わぬ力強さに一層心臓がうるさく鳴った。僕の肩が少し濡れている気がする。グリーンは昔から、感情が昂るとすぐ涙が溢れてくるみたいだった。ゆっくりとステップを踏んでいた足はいつのまにか止まっていて、ただお互いに強く抱きしめあって突っ立っていた。
「………部屋帰ろうか」
「……うん」
向こうのカップルはいつの間にかいなくなっていた。二度と離れないように思えた僕達のからだは簡単に離れたけれど、繋いだ手は少なくとも朝がくるまで離したくない、なんて浮かれたことを思いながら、まずは階段に置いてきた空のグラスを回収しに歩き出した。
小銭だけポケットに突っ込み、グリーンと共にワインやビール、伝統の菓子なんかを売っている出店を夕方からまわった。ここの人達は皆陽気な性質をしていて、あちこちで楽器に合わせて踊る人を見かけた。日も落ちる頃にはグリーンは軽く足元をふらつかせていた気がする。僕より酒に弱いくせに勧められるままに飲むものだから、もう目が据わっていた。
あたりはすっかり暗くなっている。まだ左手に持ったワインをちびちびと飲んでいるグリーンの右手を引き、広場を見渡せる石造りの階段に二人並んで腰を下ろした。手を離す瞬間に少しだけグリーンの指が絡んできた気がする。グリーンは僕の右側に座り、左手に持っていたプラスチックのグラスは彼の右側に置いた。
広場には煌々と燃える松明やオレンジ色の灯りがあちこちにともり、楽器隊の鳴らす陽気な音楽に男性も女性も手を取りあい楽しそうにステップを踏んでいる。隣のグリーンも気持ちよさそうに音楽に合わせ鼻歌を歌っていた。すごく音痴だ。思わず笑ったら、目敏く気づかれ右腕を肘で小突かれる。
「いて」
べつに痛くはなかった。グリーンの鼻歌がやんだので何気なく彼の方を見ると、灯りに灯され橙色に輝く瞳で、ついさっき小突いた僕の右腕をぼんやりと見ていた。見つめていた、と言ってもいいかもしれなかった。
「飲み過ぎだよ」
「そんな酔ってねーよ」
「目潤んでる」
「…………」
あ、拗ねた顔。そんな顔をしてもこいつの顔は整っている、たぶん。暗い中、祭の灯りに照らされてなんだかいつもよりかっこいい気がする。
グリーンは右脇に置いたグラスを掴んで残った中身を一気に煽ると、口元から一筋垂れたワインの赤を、綺麗な顎の輪郭から滴り落ちる寸前に手の甲で拭った。
そのあいだずっとこの親友の顔を見ていた僕はなんだかたまらない気持ちになって、このなんとも形容できない気持ちを感じているのが僕だけじゃなければいいのに、と、なんとなく悔しいような気持ちになった。すぐにグリーンから目を逸らし前方で楽しそうに踊り続ける人達を見ていると、ワインを拭ったグリーンの左手の小指が、地面に置いた僕の右手の小指に重なったことに気づく。陽気な音楽はまだ続いている。なんだか暑い。顔が赤くなっていないか心配だけど、酒に酔っただけだと言い訳すればいい。
「………」
「………」
さっきからグリーンは寡黙だった。「酔ってんのか?」とか聞けよ。いつもうるさいくせに。動かない口の代わりに、グリーンの細くて綺麗な小指は僕のごつごつとした小指をきゅうと掴んだ。僕は前に彼の手が綺麗な女性みたいに滑らかで好きだと言ったが、彼は別に嬉しくないとこたえた。
どうしよう、これって友達同士なら普通にある接触だろうか。なんでもないように手を持ち上げて離れればいいのか?グリーン以外にグリーンほど親しい友達のいない僕には検討もつかなかった。
僕とグリーンの周りだけ、音がなくなったみたいだ。グリーンが静かに呼吸をする音だけが、やけにハッキリと聞こえた。皆の楽しそうな笑い声と音楽がずっと遠くに響いている。そういえばいつのまにか音楽が変わった気がするけど、相変わらず広場は楽しそうな雰囲気だ。特に理由もなくさっきからずっと凝視していたカップルが、踊りながら笑顔でキスをしているところを見てしまう。多分、グリーンも同じものを見ていた。そんな気がした。
小指ってこんなにでかかったっけ?僕の右手はとっくに小指の感覚しかない。グリーンも同じことを考えているのかな?グリーンのちいさな小指を振り払って、僕の手を重ねてもいいかな?僕ももっと酒を飲んでおけば良かったと思った。
「俺達も踊るか?」
僕の葛藤が決着する前に、熱い小指は離れていった。グリーンは立ち上がり少しふらついたが、階段を数段降りて少し腰を屈め、僕を上目遣いで見つめた。そして昔から変わらない、片目を細めた悪戯っぽい笑みで言った。見ると、右手を差し出している。
「お手をどうぞ、姫」
なんだそれ。くそ、むかつく。かっこいい。まるでおとぎ話の王子様みたいなポージングが完全に様になってしまっているこの酔っぱらいは、しかし酒のせいか顔が真っ赤に染まってしまっていた。そういうところはかわいい。詰めが甘いんだ。
「……く、はは、なーんてな!にしてもあちーな、ちょっと頭冷やしてくるわ」
「待って」
常に冗談めかして予防線を張り、失敗すると安全なところに逃げるのはこいつのよくやる手法だ。グリーンが足を止めて僕を不思議そうに見上げる視線を無視して、階段を降りて広場の砂の上に立った。
「よろしければ」
「…………!」
左手を胸に当てて右手を差し出した。多分なんかこんな感じで合っていると思う。グリーンは「はっ」とか「おっ」とか意味不明な音を吐いて相当動揺しているように見えた。相変わらずだが顔は真っ赤だ。少し得意な気持ちになって自然と右の口角が上がった。
どちらから手を取ったかは覚えていない。僕らは付き合いたてのティーンのようにぎこちなく手を繋いで、広場の真ん中まで出ていった。途中でビールを売る女性に声をかけられたので、グリーンの分は断って僕はハーフパイントを一気に飲み干した。僕の右手を掴んだままのグリーンは「おわー」なんて声をあげていた。
「はは、うわ…な…ちょっと恥ずかしくねえ?」
「そう?」
踊る人達の端に紛れ込んでグリーンの両手を取ると、彼は少し饒舌になった。
「誰も僕達のことなんて気にしてない」
「………ん…たしか、に…」
本当にそうだ。ここにいる人達は皆手を取ったパートナーのことしか見ていない。ほとんどがカップルと思われる異性同士だったが、酔っ払った男性数人で手を取って楽しそうにじゃれあう若者もいたし、女性同士抱き合って笑いただ音楽にゆらゆらと揺れている人達もいた。
「俺わかんねーよダンスとか」
「みんなわかってないよ」
「……ふ、たしかに」
グリーンの顔に笑顔が戻って来る。かわいいと思った。少しの酔いも手伝って、溢れる気持ちを抑えずにグリーンの顔を見つめることができた。グリーンは僕の顔を見て笑顔を一瞬ふっと潜めたが、すぐに目を逸らしはにかんで僕の背中に手を回した。
「こうだろ?」
「はは、多分」
二人でぎこちないステップを踏んで、どこかで見た映画の真似事をする。すごく不格好だったと思うけど、グリーンはとても楽しそうだった。広場は男女の笑い声と歌声に溢れ、幸せな雰囲気に包まれていた。自然に彼の背中に回していた手は、グリーンの細い背骨の凹凸をなぞるように感じていた。
「あれやりたい、くるくるって回るヤツ」
僕が言うと彼は声をあげて笑っていた。幼馴染は「くるくるって回るヤツ」を完全に理解して、その背中から手を離すと僕の左手を軸に軽やかにくるくると回って見せた。苦しそうになるくらい笑っている。僕も多分ここ最近で一番おかしく笑っていた。
あ、しまった、と思った瞬間には、その酔っ払いは再びくるくると回り僕の腕の中に背中を向けてすっぽりと収まってしまった。ただの幼馴染で親友でライバルである彼の体は、まるで元から一つだったみたいに、かっちりと僕の体にはまってしまった。
「………」
「………」
すぐ目の前に見えるグリーンの耳が酷く熱そうで、同時に熱を孕んだ甘い香りが漂った気がした。
この時、信じられないほど絶好の(「最悪の」ともいう)タイミングで音楽が終わった。周りが歓声と疎らな拍手で盛り上がる。酔っ払って楽しくふざけていた僕も、グリーンもきっと、歓声に一瞬で頭が覚めた心地がしただろう。グリーンは絡み合っていた左手をほどいてパッと僕の腕から離れると俯いて右足の爪先でトントンと砂地を叩いていた。僕はそれが彼の気まずい時にやる癖だと知っていたので、つられて少し気まずい気持ちになる。
「……あー!ははは!楽しかった!」
「……うん」
グリーンは顔を上げて僕の肩に肘を置いて体重をかけると(昔からよくやるポーズだけど今は身長差のせいで少し辛そうだ)、周りで手を叩いて口笛を吹いている人達にいつもの調子で「サンキュー!」なんて言っている。…別に僕達を称賛しているわけではないと思うんだけど。
今更少し恥ずかしさを感じながら、棒立ちでグリーンの体重を受け止めていると、すぐにさっきまでとは違うしっとりと落ち着いた曲が流れ始めた。賑やかだった広場が波の引くように静かになる。
「…もう一杯くらい飲んで帰るか?」
僕の肩から離れ、さっきグラスを置いてきた階段の方に歩き出すグリーンの顔は見えなかった。
「もう一曲踊ってこう」
黙って頷いて後を追おうと思っていたのに、グリーンの真っ赤な耳に短い髪をかける仕草を見ていたと思った瞬間には、彼の手を引いてふらついた頼りない腰を抱き寄せていた。
「は、?おまえ…その、…この曲で?…なんつーか…カップル向け?じゃん」
グリーンは酔いもほとんど冷めてしまったのか、ぐっと距離の縮まった僕の目を見ず気まずそうにちらちらと周りを見回した。僕の腕の中から逃れようと腰を捩っている。たしかに、先程までとは違って明らかに恋人同士と見られる人達が落ち着いたピアノの旋律にのって手を取り合い揺れていた。夜も遅い時間で、まだ疎らに姿のあった子供たちはいつのまにか姿を消し、これからは恋人同士の時間という雰囲気だ。
「……問題ある?」
「は……」
僕はまだ少し酔っ払っているみたいだった。右手はグリーンの手を握りしめ左手はまだしっかりとグリーンの腰に触れていた。グリーンは身体を硬直させ今度はまっすぐ僕の顔を見ていた。
「ねえ…けど」
ぱちぱちと瞬きを3回くらいして、グリーンも僕の腰に手を回した。音楽に合わせて、ただからだをゆっくりと揺らす。男同士でこんなことをしていても、誰も茶化す人はいなかった。僕はこの土地のそんなところが好きだった。
握りあった手が汗ばんでいるのが気になったが、それは僕だけではないみたいで、彼の手は落ち着きなくもぞもぞと僕の手の中で動いている。
「顔、近い」
「……そうだね」
「……」
「……」
「……」
また黙ってしまったようだ。グリーンはずっと俯いていた。さっきからグリーンが面白いくらい動揺を見せるので、逆に僕の頭は少し冷静になっていた。伏せた睫毛がふるふると揺れているのをじっと見つめていると、見上げたオレンジの瞳と視線がかち合う。
「……なんか、笑えるな…」
「……」
「……あー、酒飲みすぎたな」
僕達のからだはほとんど密着していた。彼は今度は恥ずかしさをごまかすようによく喋る。その唇が開くたびに彼の息が僕の唇に触れて熱く溶ける。ちゃんと音楽にのれている自信が無い。彼に触れているからだの箇所全てが燃えるように熱くて、五感が彼のことしか感じることができなかった。
彼に恋をしていると思った。
グリーンも同じことを思っているだろうか。
今まで何度も心に浮かんだ疑問は、今日も答えを聞くことなく奥にしまいこまれていった。でも、灯りを反射してゆらゆらと揺れる目の前の瞳を見ていると、答えを聞く必要はないんじゃないかとも思えた。
「……レッド…」
グリーンは色々な感情の浮かんだ目で僕の目を見つめたままぽつりと僕の名前を呼び、僕の肩口に顔を埋める。多分キラキラと潤んだ瞳を見られたくなかったんだろう。僕は今どんな顔をしてるんだろうか。
向こうのカップルが足を止め唇を交わしたのがグリーンの背中越しに見えた。僕達の両手は互いの背中にまわり、二人揃ってうるさく鼓動する胸のあたりはぴったりとくっついてもう二度と離れないような気がした。
「……お前、心臓うるせーよ」
「……お前もだろ」
「……」
「……」
「……なんか、はは、接着剤で、くっついたみてー…」
「…!」
グリーンの顔を埋めた肩が熱い。僕のさっき考えていたバカみたいな妄想を彼は口に出した。なんだか少し泣きそうになって、顔を見られたくなかったので彼の背中をぎゅうと強く抱きしめたら、同じくらいの強さで抱き返される。綺麗な両手の思わぬ力強さに一層心臓がうるさく鳴った。僕の肩が少し濡れている気がする。グリーンは昔から、感情が昂るとすぐ涙が溢れてくるみたいだった。ゆっくりとステップを踏んでいた足はいつのまにか止まっていて、ただお互いに強く抱きしめあって突っ立っていた。
「………部屋帰ろうか」
「……うん」
向こうのカップルはいつの間にかいなくなっていた。二度と離れないように思えた僕達のからだは簡単に離れたけれど、繋いだ手は少なくとも朝がくるまで離したくない、なんて浮かれたことを思いながら、まずは階段に置いてきた空のグラスを回収しに歩き出した。
1/1ページ