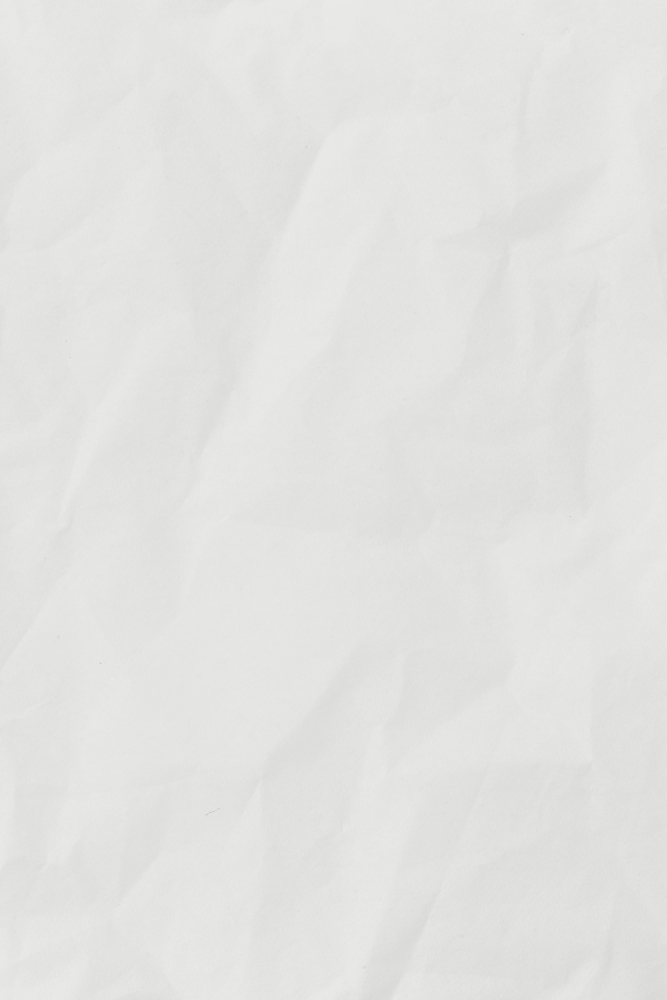共に智たれウォーターフォールスター
コンコンコンという扉をノックする音で、ブーディカは泊っている部屋のベッドから立ち上がる。
扉に近付いて行くその身には、変装の服ではなく普段通りの霊衣がまとわれていた。
小屋でのひと悶着から夜が明け、時刻は午前9時。
著者の自宅からほど近い古民家の宿で、報告会は行われた。
「結果から言うと、あの赤い本の中身は出版予定の物ではなかったよ。後日必ず、本来書く予定だったブーディカに関する研究本を出版すると約束を取り付けて来たから安心したまえ」
談話室の様な小さなスペースに取り付けられた4人用の席に、ホームズ以外が座ってその報告を聞く。
あの小屋にホームズと共に残っていたモリアーティからすれば聞く必要は無いのだが、別段他にしなければならないことも無いので同席している。
「どうやら彼はあの女性と一緒になりたかったらしいんだが、プロポーズ目前で他の男に連れ去られそうになったらしくてね」
「あ、あー…」
「匿うのと、連れ去ろうとした相手への牽制でああなったと…マネージャーはどうやら著者の親友だ。まぁ、自分に置き換えて想像したら協力せずにはいられなかったという友情さ」
「それではこの超微小特異点の原因は…」
「彼女が連れ去られそうになった、だな」
すんなりと解かれてしまったこれまでの経緯に、ホームズは愉快そうな笑いを浮かべてはいるが不完全燃焼であることは察するに余りある。
だがそこに切り込めるくらいに、マスターの疑問はまだあった。
「じゃあ赤い本の千切られた本当の中身は?」
彼女の挙手からの質問に、マシュも思い出したかのように続く。
だが、それはモリアーティに切り返された。
「書斎の引き出しに置いてあるんだって言ってたヨ。スウェーデンの「ホースの赤い馬」って知ってるかい?どうやらそれを旅商人から買ったことでアイデアが湧いたから創作をしてみたらしいんだが…彼は研究家であって作家ではなかったらしくてね。製本までしてみたはいいものの売り物には出来なかったらしい。読ませたのも彼女だけだと言っていたが…黒歴史ってやつだネ。千切っちゃったのは」
あまりにもあっさりとした顛末に、マスターは気が抜けたのか「引き出し見たけど読めないから分かるわけないよ~!」と嘆いた。
そんな彼女を慰めながら、ブーディカは書斎の部屋を思い出し、馬の木彫り人形は自分へのリスペクトではなかったのかと少し恥ずかしいやら悲しいやらと笑うのであった。
「ま、でもハッピーエンドだネ。彼らからすればブーディカの歴史に関わることで幸せを掴んだんだから、幸せを呼んだ女王ってとこかナ?」
「あたしが?全然幸せ呼んでないよ?」
「いやいや、ちゃんと呼んでいるとも。何しろ彼は君の研究をしていたからあの小屋で彼女と出会い、そして彼は彼女にだけ赤い馬の本を読ませた。彼女は君という女王に興味を抱き、そして彼が書き描いた世界を気に入った。だからこそ、学べるあの箱を2人で分かち合おうとしたんじゃないか」
「ほとんど偶然みたいなものだね?」
「ハッハッハッ!そうかもしれない!が、だからこそ尊い…幸せと呼ぶに相応しいのさ」
随分と優しさを感じさせるモリアーティからの言葉に、昨日の夫婦役が抜けきっていないからか、ブーディカも嬉しそうにはにかんで応える。
素性を知っているだけに素直に受け取っていいものかとも思うが、今だけは仮初の夫婦を信じてみようではないかとブーディカが席を立ちあがると、視線の高さが近くなったことでホームズからの冷めきった視線を受けることとなった。
またしてもしなくていい後悔を感じてしまい、少し…眉間にしわを寄せながら眉を下げる。
ブーディカが立ち上がったことでマスターとマシュも立ち上がり、あとどれだけここに滞在できるのかをダ・ヴィンチに確認しようとしたところで、ホームズに3日程の自由があることを伝えられた。
それならばとマスターはマシュとブーディカの腕を絡め取り、談話室から2人をさらい出す。
「ねぇマシュ。わたし昨日のブーディカ綺麗だなって思ってさ」
「え!?」
「わかります!」
「ちょっと一緒に着てみようよ」
キャッキャッとさえずるように楽しみを歌う彼女達の背を、いってらっしゃいという様に見送るホームズとモリアーティ。
3人が宿を後にしたのを確認すると、空いた席にホームズが腰掛け、モリアーティの隣に並ぶ形から会話を始める。
「昨日はさすがの対処法だったな」
「まぁ人さらいの対処なんて彼女の買取が一番だとしか言えないでショ」
「それもそうだな。あの著者は後手に回らない努力をすべきだとは思うがね」
「律儀そうだし娼館に提示された金額出すつもりなんじゃない?踏み倒せるだろうに…」
「ほぼ黒の様な金の稼ぎ方を教えておいてよく言う。見返りも無いのにどうしたんだ?」
「別に。さっき言っただろう。幸せと呼ぶに相応しいと思ったまでさ」
感情などこもってもいない言葉のラリーが止まると、モリアーティは宿の店主にドリンクを注文した。
それに続く形で灰皿を頼もうとしたホームズだったが「吸うならドリンクを君に譲って私も外に出る」というモリアーティからの当然そうに放たれた一言で、ドリンクに切り替える。
ゴトンと分厚いマグカップに注がれた紅茶がふたつ届くと、会話は再開された。
「折り入って教授に相談があるんだが」
「ろくなことじゃないな」
「………………そうだな…」
「…マジなやつかネ?」
「私に金を渡すか、付いて来るか…どちらが良い?」
「どっちも断るし相談じゃないぞ、それ」
深い溜め息をつき、届いた紅茶を口に運ぶモリアーティに、ホームズは本気で困った顔を向ける。
まさかそんな表情をされるとは思ってもいなかったために、知らぬ存ぜぬを通したかったモリアーティも少しの動揺を見せた。
「……教授、出来ればでいいんだ」
「な、なに…」
「金を渡してほしいし付いて来てもほしい」
「いい加減にしろヨおまえ」
少しでも本当に困っているんじゃないかと心配した自分が馬鹿だったと落胆するモリアーティを他所に、ホームズはドリンクを彼から取り上げそのまま無理やり拘束すると、勢いに任せて宿を飛び出す。
とても渋く魅力的でありながら悲壮感漂う叫び声が市中に響き渡ったことは、説明するまでもないだろう。
◆
場所は変わり娼館。
あの少女との約束を守るため、ホームズはモリアーティという金を引き連れてその扉を開けた。
初老の男性の首根っこを掴む形で来訪したホームズに、たまたま広場で受付まがいの務めをしていた少女は恐怖と驚きで後退った。
「あ、あ、あんた!」
「あぁ、ちょうど良かった。約束のチップと「お相手」だ」
チップを少女に投げる動作と同じように放り投げられ差し出されたモリアーティは、何の説明も無いままに娼婦の目の前に立たされた挙句「お相手」という表現に腸が煮え繰り返る想いでホームズを睨む。
だがそれでも一向に説明をしようとしないホームズに、額に浮かべた青筋を隠すこともなくそのまま踵を返した。
しかしその歩みは、娼婦である少女の一言で止められる。
「あんた、この人に捨てられるの?」
肩をぶつけそうなくらい近くで交差しようとしていたモリアーティと、ぶつけられても構わないとすまし顔で身構えていたホームズ。
そんな2人を困惑した目で見上げながら、そう少女は訊ねずにはいられなかった。
捨てられるとはどういうことなのか。
モリアーティが答えを求めるようにホームズへ視線を向けても、彼は頑なにそれに応えようとしない。
気まずい空気が場を支配する。
だが少女には、もうひとつ確認することがあった。
「チップ、持ってきたってことは…解決したんだな?」
「したとも。彼女はちゃんとここに帰ってくるが、それでもすぐ…別れることになる」
「――……それって…」
「ああ、先生とあの箱を手に入れたとだけ、伝えておこう」
微笑むホームズからの言葉に、彼女は静かに涙を流す。
そうかと小さく何度も呟き、投げ渡されたチップの入った麻袋を強く握りしめながら、その場にしゃがみこんだ。
ここで、背後で少女が泣いていることは分かってもどういった理由で連れてこられたかは結局分からないままでいるモリアーティは、ホームズの無礼さよりも状況の不透明さに苛つきだす。
そして、色々と言いたい文句が降り積もって雪崩そうだと思い、もう待つ必要も無いと割り切りがつきかけたその時。
「それでは私は彼と帰るよ」
「は?」
唐突に。
今度は腰に腕を回され、小脇に抱えられるような形で扉から外へ連れ去られる。
2人が少女の目の前に現れて数分。
来るのも突然、去るのも突然。
遠くになっていく初老の「ホーーーーームズ!!」という怒声に、静かに泣いていた少女は鼻水を噴き出して破顔した。
「確かに……それ以前だけど、お似合いじゃないか。ホームズ」
そもそも男だし、髭あったけど…と内心付け加えながら、それでも少女の瞼の裏には精一杯取り繕っていたすまし顔の彼がいる。
顔も良くてスタイルだって良い。
金だって持っていそうだと思えるほど、良い服を身に着けている。
そんな男の悲しい告白が、まさか真実なのだとは思いもしなかった。
「今度はあんたが、その人と分かち合えたらいいね」
.
扉に近付いて行くその身には、変装の服ではなく普段通りの霊衣がまとわれていた。
小屋でのひと悶着から夜が明け、時刻は午前9時。
著者の自宅からほど近い古民家の宿で、報告会は行われた。
「結果から言うと、あの赤い本の中身は出版予定の物ではなかったよ。後日必ず、本来書く予定だったブーディカに関する研究本を出版すると約束を取り付けて来たから安心したまえ」
談話室の様な小さなスペースに取り付けられた4人用の席に、ホームズ以外が座ってその報告を聞く。
あの小屋にホームズと共に残っていたモリアーティからすれば聞く必要は無いのだが、別段他にしなければならないことも無いので同席している。
「どうやら彼はあの女性と一緒になりたかったらしいんだが、プロポーズ目前で他の男に連れ去られそうになったらしくてね」
「あ、あー…」
「匿うのと、連れ去ろうとした相手への牽制でああなったと…マネージャーはどうやら著者の親友だ。まぁ、自分に置き換えて想像したら協力せずにはいられなかったという友情さ」
「それではこの超微小特異点の原因は…」
「彼女が連れ去られそうになった、だな」
すんなりと解かれてしまったこれまでの経緯に、ホームズは愉快そうな笑いを浮かべてはいるが不完全燃焼であることは察するに余りある。
だがそこに切り込めるくらいに、マスターの疑問はまだあった。
「じゃあ赤い本の千切られた本当の中身は?」
彼女の挙手からの質問に、マシュも思い出したかのように続く。
だが、それはモリアーティに切り返された。
「書斎の引き出しに置いてあるんだって言ってたヨ。スウェーデンの「ホースの赤い馬」って知ってるかい?どうやらそれを旅商人から買ったことでアイデアが湧いたから創作をしてみたらしいんだが…彼は研究家であって作家ではなかったらしくてね。製本までしてみたはいいものの売り物には出来なかったらしい。読ませたのも彼女だけだと言っていたが…黒歴史ってやつだネ。千切っちゃったのは」
あまりにもあっさりとした顛末に、マスターは気が抜けたのか「引き出し見たけど読めないから分かるわけないよ~!」と嘆いた。
そんな彼女を慰めながら、ブーディカは書斎の部屋を思い出し、馬の木彫り人形は自分へのリスペクトではなかったのかと少し恥ずかしいやら悲しいやらと笑うのであった。
「ま、でもハッピーエンドだネ。彼らからすればブーディカの歴史に関わることで幸せを掴んだんだから、幸せを呼んだ女王ってとこかナ?」
「あたしが?全然幸せ呼んでないよ?」
「いやいや、ちゃんと呼んでいるとも。何しろ彼は君の研究をしていたからあの小屋で彼女と出会い、そして彼は彼女にだけ赤い馬の本を読ませた。彼女は君という女王に興味を抱き、そして彼が書き描いた世界を気に入った。だからこそ、学べるあの箱を2人で分かち合おうとしたんじゃないか」
「ほとんど偶然みたいなものだね?」
「ハッハッハッ!そうかもしれない!が、だからこそ尊い…幸せと呼ぶに相応しいのさ」
随分と優しさを感じさせるモリアーティからの言葉に、昨日の夫婦役が抜けきっていないからか、ブーディカも嬉しそうにはにかんで応える。
素性を知っているだけに素直に受け取っていいものかとも思うが、今だけは仮初の夫婦を信じてみようではないかとブーディカが席を立ちあがると、視線の高さが近くなったことでホームズからの冷めきった視線を受けることとなった。
またしてもしなくていい後悔を感じてしまい、少し…眉間にしわを寄せながら眉を下げる。
ブーディカが立ち上がったことでマスターとマシュも立ち上がり、あとどれだけここに滞在できるのかをダ・ヴィンチに確認しようとしたところで、ホームズに3日程の自由があることを伝えられた。
それならばとマスターはマシュとブーディカの腕を絡め取り、談話室から2人をさらい出す。
「ねぇマシュ。わたし昨日のブーディカ綺麗だなって思ってさ」
「え!?」
「わかります!」
「ちょっと一緒に着てみようよ」
キャッキャッとさえずるように楽しみを歌う彼女達の背を、いってらっしゃいという様に見送るホームズとモリアーティ。
3人が宿を後にしたのを確認すると、空いた席にホームズが腰掛け、モリアーティの隣に並ぶ形から会話を始める。
「昨日はさすがの対処法だったな」
「まぁ人さらいの対処なんて彼女の買取が一番だとしか言えないでショ」
「それもそうだな。あの著者は後手に回らない努力をすべきだとは思うがね」
「律儀そうだし娼館に提示された金額出すつもりなんじゃない?踏み倒せるだろうに…」
「ほぼ黒の様な金の稼ぎ方を教えておいてよく言う。見返りも無いのにどうしたんだ?」
「別に。さっき言っただろう。幸せと呼ぶに相応しいと思ったまでさ」
感情などこもってもいない言葉のラリーが止まると、モリアーティは宿の店主にドリンクを注文した。
それに続く形で灰皿を頼もうとしたホームズだったが「吸うならドリンクを君に譲って私も外に出る」というモリアーティからの当然そうに放たれた一言で、ドリンクに切り替える。
ゴトンと分厚いマグカップに注がれた紅茶がふたつ届くと、会話は再開された。
「折り入って教授に相談があるんだが」
「ろくなことじゃないな」
「………………そうだな…」
「…マジなやつかネ?」
「私に金を渡すか、付いて来るか…どちらが良い?」
「どっちも断るし相談じゃないぞ、それ」
深い溜め息をつき、届いた紅茶を口に運ぶモリアーティに、ホームズは本気で困った顔を向ける。
まさかそんな表情をされるとは思ってもいなかったために、知らぬ存ぜぬを通したかったモリアーティも少しの動揺を見せた。
「……教授、出来ればでいいんだ」
「な、なに…」
「金を渡してほしいし付いて来てもほしい」
「いい加減にしろヨおまえ」
少しでも本当に困っているんじゃないかと心配した自分が馬鹿だったと落胆するモリアーティを他所に、ホームズはドリンクを彼から取り上げそのまま無理やり拘束すると、勢いに任せて宿を飛び出す。
とても渋く魅力的でありながら悲壮感漂う叫び声が市中に響き渡ったことは、説明するまでもないだろう。
◆
場所は変わり娼館。
あの少女との約束を守るため、ホームズはモリアーティという金を引き連れてその扉を開けた。
初老の男性の首根っこを掴む形で来訪したホームズに、たまたま広場で受付まがいの務めをしていた少女は恐怖と驚きで後退った。
「あ、あ、あんた!」
「あぁ、ちょうど良かった。約束のチップと「お相手」だ」
チップを少女に投げる動作と同じように放り投げられ差し出されたモリアーティは、何の説明も無いままに娼婦の目の前に立たされた挙句「お相手」という表現に腸が煮え繰り返る想いでホームズを睨む。
だがそれでも一向に説明をしようとしないホームズに、額に浮かべた青筋を隠すこともなくそのまま踵を返した。
しかしその歩みは、娼婦である少女の一言で止められる。
「あんた、この人に捨てられるの?」
肩をぶつけそうなくらい近くで交差しようとしていたモリアーティと、ぶつけられても構わないとすまし顔で身構えていたホームズ。
そんな2人を困惑した目で見上げながら、そう少女は訊ねずにはいられなかった。
捨てられるとはどういうことなのか。
モリアーティが答えを求めるようにホームズへ視線を向けても、彼は頑なにそれに応えようとしない。
気まずい空気が場を支配する。
だが少女には、もうひとつ確認することがあった。
「チップ、持ってきたってことは…解決したんだな?」
「したとも。彼女はちゃんとここに帰ってくるが、それでもすぐ…別れることになる」
「――……それって…」
「ああ、先生とあの箱を手に入れたとだけ、伝えておこう」
微笑むホームズからの言葉に、彼女は静かに涙を流す。
そうかと小さく何度も呟き、投げ渡されたチップの入った麻袋を強く握りしめながら、その場にしゃがみこんだ。
ここで、背後で少女が泣いていることは分かってもどういった理由で連れてこられたかは結局分からないままでいるモリアーティは、ホームズの無礼さよりも状況の不透明さに苛つきだす。
そして、色々と言いたい文句が降り積もって雪崩そうだと思い、もう待つ必要も無いと割り切りがつきかけたその時。
「それでは私は彼と帰るよ」
「は?」
唐突に。
今度は腰に腕を回され、小脇に抱えられるような形で扉から外へ連れ去られる。
2人が少女の目の前に現れて数分。
来るのも突然、去るのも突然。
遠くになっていく初老の「ホーーーーームズ!!」という怒声に、静かに泣いていた少女は鼻水を噴き出して破顔した。
「確かに……それ以前だけど、お似合いじゃないか。ホームズ」
そもそも男だし、髭あったけど…と内心付け加えながら、それでも少女の瞼の裏には精一杯取り繕っていたすまし顔の彼がいる。
顔も良くてスタイルだって良い。
金だって持っていそうだと思えるほど、良い服を身に着けている。
そんな男の悲しい告白が、まさか真実なのだとは思いもしなかった。
「今度はあんたが、その人と分かち合えたらいいね」
.