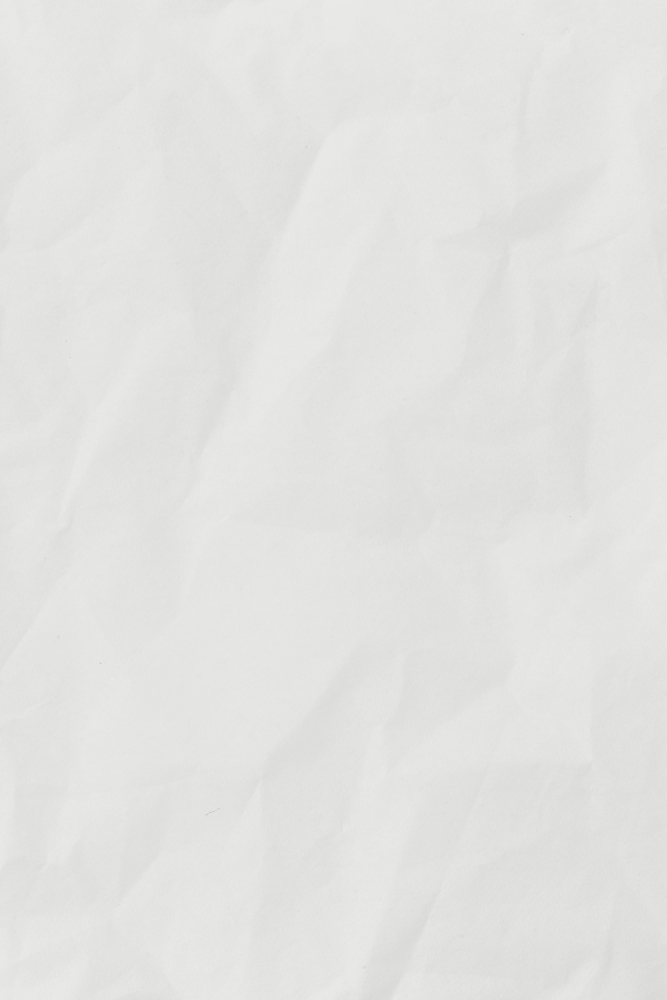届かず距離スメル
あの日の話をしよう。
あなたが空に手を伸ばした時さ。
私にはただ伸ばしている様に見えたんだが、もしかしたらあなたは何かに添えようとしていたのかな。
今更その真意を話せなんて言わないさ。
ただ少し、そうだったら良いのになと、私が勝手に思っているだけさ。
だからあの日の話をしよう。
あなたを滝底に落とし、私が勝ったあの日の話をしよう。
◆
ただ書物のように、ただ映像のように、ただ風景のように。
そこは何も無い、印象と心象の世界。
世界が作った「ジェームズ・モリアーティ」の箱。
「ジェームズ・モリアーティ」たらしめるものだけが有り、その存在性を否定したり変えてしまうようなものは無い。
それだけ英霊、キャラクターというものは、己の考えが作り出すよりも遥かに、他者からの評価で枠に嵌められるものなのだろう。
生みの親であるその作家は、まるで生きているかのような扱いを受けたその男の現実に嫌悪を抱き、作中で男を滝に落としたほどだ。
そしてこの世界に佇むひとりの男も、また男を滝に落とした者だ。
(いやはや、自分で自分を英霊なんぞにして主人公になる為の無理で終わるかと思ったら、まさか外部からも斡旋 されるとは…)
決して厚くはない小さな書物は、老齢と謳われたジェームズ・モリアーティの手で開かれ捲られていく。
そこに記されている内容は、とある剪定事象で若き己が宿敵であるシャーロック・ホームズを滝に落とす物語。
別側面の影でしかない自分という者の時間は、オリジナルであるモリアーティにはどうしても他人事でしかない。
淡々としたものだ。
だがひとつだけ、気になった。
(……手を伸ばしながら落ちた。フム、何故ここだけホームズの情景を記録している?)
ただの事実が引っ掛かる。
自分のことだ、いくら別の個体とはいえ本質は変わらない……そう考えれば考えるほど、沼となった。
どの剪定事象でも悪の何たるかを体現した個体達は、主観でしか語らなかった。
(落とした…その結果負けたという記録ならわかる。だがこれだけ、どうしてホームズの動作を書いている?)
気にすることではないだろう…と、モリアーティからすれば余計な情報でしかないのだから。
宿敵の落ち様なんぞ、記したところで意味は無い。
だからこそ、気になった。
ここは何も無い、印象と心象の世界。
世界が作った「ジェームズ・モリアーティ」の箱。
座と呼称される英霊のソフトウェアのようなもの。
やることも定められたことも、これから召喚される先で本質が変わることも無い。
ただ、知ってみたいと思ったのだ。
(若き私は一体…何を見たのだろうか)
◆
ザクザクと響く芝生 を踏みながら進む音。
辺り一面美しく広がる平原は、質素で幻想的で美しく、どこまでも広がる青空は太陽が見当たらないだけで澄み切ったものだ。
小さな書物を携えて、モリアーティは歩く。
目的地は宿敵の箱。
どこかにあるだろうと当ても無く歩いているだけの老体は、未だ結論が出ない気持ちに眉を顰 めた。
(手を伸ばしながら落ちたのはわかるけど、どういう風に?それこそB級映画みたいな感じだったなら滑稽だけど、あの男は助けを乞うタイプでもないしな)
美しい青の中をうんうんと唸りながら歩くモリアーティの後ろ姿に、ひとりの黒い男が近寄る。
明らかに増えているはずの足音に一向に気付かない…もしくは気付かないフリをしているモリアーティに数分程の時間付きまとい、男は痺れを切らせて声を掛けた。
「モリアーティ教授」
いささか不機嫌なその声に、モリアーティは振り向きながら素っ頓狂な返事をする。
「いつの間に」
「いくら何も無い所とはいえ気が緩みすぎだろう」
「何も無いから仕方ないでしょ」
「ヴァルハラ辺りに送ってもらうかね?」
「あそこは戦士の場所なんだから、私達みたいなのは申請前に返されるヨ」
「何故私まで一緒に行くていなんだ…」
「好奇心で覗くくらいするかと思ってネ。ま、ちょうどいい。おまえを探してたんだヨ」
携えた小さな書籍を気怠 げに持ち上げ、モリアーティはホームズの持つ厚い書籍を指差す。
お見通しと言わんばかりのそれに、ホームズは先程気が緩んでいるとした言葉は心の内で訂正した。
「……実は私も」
目を伏せ、相手を真似るように少々重い書籍を持ち上げる。
内容は言うまでもない。
「座というのはもっと有意義だと思っていたんだが…いやはや予想に反してブラックな事件もジョークも無くてね」
「この芝生とか燃やしたところで意味無さそうだもんネ」
「花くらい咲いていたら生物的観点も得られるんだが、どうも無機物に人工的な自然を埋め込むのが上手いようだ。人理というものは」
「耳が痛くなるご指摘だ」
「我々も含めた嫌味だとも」
口角を緩く上げた会話を楽しみ、ふたりは芝生に腰を落とす。
身嗜 みを整えた英国の老紳士と、見かけこそ若くされてはいるが中身はそこそこ老いている紳士がする三角座りは、どこか穏やかだった。
実際、この座というものが何なのかは登録された英霊にもよくわからない。
与えられた世界の領域で、分身が果たした内容を校正された物語として読む場所だ。
過不足もあれば摩訶不思議もあるのに、面白さは感じない。
「そういった人生の一部を自分ではない自分が経験した」だけなのだ。
だが、だからこそ疑問もあれば答えもある。
「おまえ、カルデアでの剪定事象でライヘンバッハに落ちて死んだ時、なんて思ってた?」
「……それがわかっていればここには居ないな」
「なんだ、書いてなかったのか」
「知っているだろうに。これには事実しかない……感情は、分身にしかわからないものじゃないか」
「情景くらい書いてなかったのか?」
「書いていたよ、珍しくね。だがそれは本当に……些末 なものというか、実にくだらなくてね」
「で?」
「…空に手を添えて落ちた……とだけ」
随分と詩的なそれに、モリアーティは目を丸くする。
「笑ってくれて構わないよ。そもそも書き物なんて出来やしないのに何を記録しているんだろうね、この僕は」
折り曲げた長い脚の間に顔を沈め、ホームズは深い溜め息を吐 く。
「あー…ワトソン君が書いてくれてたらいいのに。そしたらきっと座でも大ヒットだ。ワトソン君が作家として召喚されるんだきっと」
「ハイハイうるさいヨ全く。そもそも私くらいハングリー精神持ってるのかネ、彼」
「……持っているはずだ」
「それ多分おまえにだけだヨ。ハイ、終わり。で、私の方なんだけど」
羞恥心で俯くホームズを軽くあしらい、モリアーティは淡々と話を進めていった。
決して厚くはない書籍の終わり近くを開き、字列に指を這わせる。
「これにはね、おまえが手を伸ばしながら落ちたと書いてるんだ」
ホームズとは逆で背を反らし腕に体重をかけて空を見上げ始めたモリアーティが、今度は深い溜め息を吐いた。
いっそこのまま寝転がってしまおうかと思った矢先、ホームズが頭を上げる。
「若い君 は、私が手を伸ばしているように見えたんだな」
「みたいだネ〜…憐んでたのかやってやったって思ったのか……ただネー、何かしら私の存在性に関わることだから記録されてるんだと思うんだけど…思いつかん」
「おいおい、だったら私にも思い付かないようなものだ。しっかり考えたまえ」
「おまえも考えるんだヨ!」
澄み渡る青い中で、モリアーティのキレがある張った声が響いた。
.
あなたが空に手を伸ばした時さ。
私にはただ伸ばしている様に見えたんだが、もしかしたらあなたは何かに添えようとしていたのかな。
今更その真意を話せなんて言わないさ。
ただ少し、そうだったら良いのになと、私が勝手に思っているだけさ。
だからあの日の話をしよう。
あなたを滝底に落とし、私が勝ったあの日の話をしよう。
◆
ただ書物のように、ただ映像のように、ただ風景のように。
そこは何も無い、印象と心象の世界。
世界が作った「ジェームズ・モリアーティ」の箱。
「ジェームズ・モリアーティ」たらしめるものだけが有り、その存在性を否定したり変えてしまうようなものは無い。
それだけ英霊、キャラクターというものは、己の考えが作り出すよりも遥かに、他者からの評価で枠に嵌められるものなのだろう。
生みの親であるその作家は、まるで生きているかのような扱いを受けたその男の現実に嫌悪を抱き、作中で男を滝に落としたほどだ。
そしてこの世界に佇むひとりの男も、また男を滝に落とした者だ。
(いやはや、自分で自分を英霊なんぞにして主人公になる為の無理で終わるかと思ったら、まさか外部からも
決して厚くはない小さな書物は、老齢と謳われたジェームズ・モリアーティの手で開かれ捲られていく。
そこに記されている内容は、とある剪定事象で若き己が宿敵であるシャーロック・ホームズを滝に落とす物語。
別側面の影でしかない自分という者の時間は、オリジナルであるモリアーティにはどうしても他人事でしかない。
淡々としたものだ。
だがひとつだけ、気になった。
(……手を伸ばしながら落ちた。フム、何故ここだけホームズの情景を記録している?)
ただの事実が引っ掛かる。
自分のことだ、いくら別の個体とはいえ本質は変わらない……そう考えれば考えるほど、沼となった。
どの剪定事象でも悪の何たるかを体現した個体達は、主観でしか語らなかった。
(落とした…その結果負けたという記録ならわかる。だがこれだけ、どうしてホームズの動作を書いている?)
気にすることではないだろう…と、モリアーティからすれば余計な情報でしかないのだから。
宿敵の落ち様なんぞ、記したところで意味は無い。
だからこそ、気になった。
ここは何も無い、印象と心象の世界。
世界が作った「ジェームズ・モリアーティ」の箱。
座と呼称される英霊のソフトウェアのようなもの。
やることも定められたことも、これから召喚される先で本質が変わることも無い。
ただ、知ってみたいと思ったのだ。
(若き私は一体…何を見たのだろうか)
◆
ザクザクと響く
辺り一面美しく広がる平原は、質素で幻想的で美しく、どこまでも広がる青空は太陽が見当たらないだけで澄み切ったものだ。
小さな書物を携えて、モリアーティは歩く。
目的地は宿敵の箱。
どこかにあるだろうと当ても無く歩いているだけの老体は、未だ結論が出ない気持ちに眉を
(手を伸ばしながら落ちたのはわかるけど、どういう風に?それこそB級映画みたいな感じだったなら滑稽だけど、あの男は助けを乞うタイプでもないしな)
美しい青の中をうんうんと唸りながら歩くモリアーティの後ろ姿に、ひとりの黒い男が近寄る。
明らかに増えているはずの足音に一向に気付かない…もしくは気付かないフリをしているモリアーティに数分程の時間付きまとい、男は痺れを切らせて声を掛けた。
「モリアーティ教授」
いささか不機嫌なその声に、モリアーティは振り向きながら素っ頓狂な返事をする。
「いつの間に」
「いくら何も無い所とはいえ気が緩みすぎだろう」
「何も無いから仕方ないでしょ」
「ヴァルハラ辺りに送ってもらうかね?」
「あそこは戦士の場所なんだから、私達みたいなのは申請前に返されるヨ」
「何故私まで一緒に行くていなんだ…」
「好奇心で覗くくらいするかと思ってネ。ま、ちょうどいい。おまえを探してたんだヨ」
携えた小さな書籍を
お見通しと言わんばかりのそれに、ホームズは先程気が緩んでいるとした言葉は心の内で訂正した。
「……実は私も」
目を伏せ、相手を真似るように少々重い書籍を持ち上げる。
内容は言うまでもない。
「座というのはもっと有意義だと思っていたんだが…いやはや予想に反してブラックな事件もジョークも無くてね」
「この芝生とか燃やしたところで意味無さそうだもんネ」
「花くらい咲いていたら生物的観点も得られるんだが、どうも無機物に人工的な自然を埋め込むのが上手いようだ。人理というものは」
「耳が痛くなるご指摘だ」
「我々も含めた嫌味だとも」
口角を緩く上げた会話を楽しみ、ふたりは芝生に腰を落とす。
実際、この座というものが何なのかは登録された英霊にもよくわからない。
与えられた世界の領域で、分身が果たした内容を校正された物語として読む場所だ。
過不足もあれば摩訶不思議もあるのに、面白さは感じない。
「そういった人生の一部を自分ではない自分が経験した」だけなのだ。
だが、だからこそ疑問もあれば答えもある。
「おまえ、カルデアでの剪定事象でライヘンバッハに落ちて死んだ時、なんて思ってた?」
「……それがわかっていればここには居ないな」
「なんだ、書いてなかったのか」
「知っているだろうに。これには事実しかない……感情は、分身にしかわからないものじゃないか」
「情景くらい書いてなかったのか?」
「書いていたよ、珍しくね。だがそれは本当に……
「で?」
「…空に手を添えて落ちた……とだけ」
随分と詩的なそれに、モリアーティは目を丸くする。
「笑ってくれて構わないよ。そもそも書き物なんて出来やしないのに何を記録しているんだろうね、この僕は」
折り曲げた長い脚の間に顔を沈め、ホームズは深い溜め息を
「あー…ワトソン君が書いてくれてたらいいのに。そしたらきっと座でも大ヒットだ。ワトソン君が作家として召喚されるんだきっと」
「ハイハイうるさいヨ全く。そもそも私くらいハングリー精神持ってるのかネ、彼」
「……持っているはずだ」
「それ多分おまえにだけだヨ。ハイ、終わり。で、私の方なんだけど」
羞恥心で俯くホームズを軽くあしらい、モリアーティは淡々と話を進めていった。
決して厚くはない書籍の終わり近くを開き、字列に指を這わせる。
「これにはね、おまえが手を伸ばしながら落ちたと書いてるんだ」
ホームズとは逆で背を反らし腕に体重をかけて空を見上げ始めたモリアーティが、今度は深い溜め息を吐いた。
いっそこのまま寝転がってしまおうかと思った矢先、ホームズが頭を上げる。
「若い
「みたいだネ〜…憐んでたのかやってやったって思ったのか……ただネー、何かしら私の存在性に関わることだから記録されてるんだと思うんだけど…思いつかん」
「おいおい、だったら私にも思い付かないようなものだ。しっかり考えたまえ」
「おまえも考えるんだヨ!」
澄み渡る青い中で、モリアーティのキレがある張った声が響いた。
.